十三夜
乙姫 静香
蒼い月が冴える夜、声が聞こえる十三夜。

「入るよ」
小さく言うと、俺は板を軋ませながら建てつけの悪い戸を開けた。昼からこのあばら屋に移された彼は、眠っていたのか小さく身じろぐと、ゆっくりと起き上がり俺を見た。
とはいえ、もう目も余り見えてない筈だ。それでも目が見えているように振る舞う姿が、胸を突いた。
「健祐さん?」
彼の声が弱々しく響く。俺は一瞬答えに困ったが、それでも努めて平静を装って返した。
「いや、宗祐だよ。健祐は・・・弟は、仕事が忙しくてこれないんだ。健祐も、由宇さんのこと気にしてたけど・・・」
 着物の裾を整えながら、由宇(ゆう)さんの脇に腰を下ろす。薄っぺらで粗末な布団が、彼に対する周囲の意識を物語っているようで、俺は布団に触れた手を静かに引っ込めた。
着物の裾を整えながら、由宇(ゆう)さんの脇に腰を下ろす。薄っぺらで粗末な布団が、彼に対する周囲の意識を物語っているようで、俺は布団に触れた手を静かに引っ込めた。
双子の弟が場末の男娼にはまったのが一年前、家を勘当されたのが半年前。さらにその男娼を捨てて、他の女と駆け落ちしたのが2ヶ月前。そして一週間前、俺は病でぼろぼろになりながらも、不実な弟を待ち続ける彼を見つけた。
おそらく花街でつけられたであろう由宇と名乗る少年は、俺の嘘を見透かすような瞳で俺をじっと見つめたが、見えないことを悟られたくないのか、それとも見つめることを失礼と思ったのか、その言葉に何を言うでもなく、視線を逸らした。
「ほっ・・本当だよ。あいつ、家に連れ戻されて、それで、今まで放蕩してた分も働かなくちゃいけないから」
見え透いた嘘で慌てて繕いながら、俺は由宇さんを見つめる。年下であろうことは分かっていたが、それでも何故か由宇さんと呼びたい気に、彼はさせた。
「そうですね。私が、健祐さんの道を踏み外させてしまったのですものね。それなのに、住む場所までいただいてしまって・・・」
痛む身体を惜して、由宇さんが手をつこうとする。俺はそんな彼を手で押しとどめると、薄い浴衣の肩に持ってきた自分の羽織をかけた。
「そんなこと、気にしなくていいんだよ。由宇さんは自分の身体をなおすことだけ考えなくちゃ。健祐があんな場所にほっておかなけりゃ、こんなに悪くなることもなかったろうに」
俺の言葉に黙って耳を傾ける。細い首をかしげたまま、黒目がちな瞳が俺の顔を追った。
初めて由宇さんを見た時、そこに人が居るとは到底思えなかった。
父に頼まれた健祐の捜索もままならず、男娼と住んでいたという川近くの掘立て小屋に近づいた俺の目にとまったのは、月の光に半分透けたような蒼白い肌をした彼だった。ひとつに束ねた髪がさらさらと風に揺れ、はだけだ着物の裾からは、しなやかに伸びたふくらはぎが覗く。声をかけることも忘れて、俺は立ち尽くした。
そう、あの時も彼は、この形のいい口唇をゆっくりと動かして言った。
「健祐さん?」
・・・と。
その時、親戚一同から「金目当ての薄汚い男娼が」とののしられていた本人が、こんなにもはかなげな少年だということを初めて知った。そして、彼がもう治ることはないであろう病に冒されていることも。
カタカタと、明かり取りから入り込む風が反対側の戸を揺らす。由宇さんは俺のかけた羽織に白く長い指を伸ばすと、それをゆっくりとつかんで呟いた。
「羽織・・・」
「俺の、ちょっと小さくなっちまった奴で悪いんだけど、めぼしいもんが見つかんなかったんでな。寒かったら着てくれ。使わなかったら、そこら辺に置いといてくれればいいから・・・」
無骨な指で自分の頭をかく自分とは全く違う細い肩。俺には小さすぎた羽織も、由宇さんには少し大きいようだった。
由宇さんを身近に置くと俺が言い出した時、家族はこぞって反対した。だが、健祐に捨てられてそのまま放置しておくのなら、せめて最期くらい引き取った方が体面上良いと、俺は半ば強引に由宇さんをここに呼んだ。だからもちろん、家族の人間はほとんどここには寄り付かない。定期的に食事や薬を運ぶ以外、誰も気を配ろうとはしなかった。当然ながら、両親は俺がここに近づくことも嫌がった。健祐の二の舞いになることを、恐れたに違いなかった。
「こんな立派なもの・・・」
指先で確かめるように、由宇さんが生地の表面を撫でる。本当ならもっと気の利いたものでもと思っていただけに、彼が感嘆するほどに、申し訳なさが増した。
「でも、俺のお古だから。もっとちゃんとしたもの、用意できれば良かったんだけど」
「そんなことないです。この手触り・・・ずいぶんと仕立ての良いものですねぇ」
高すぎも低すぎもしないやわらかな声で、彼が言う。
「健の奴と、そろいで作ったんだ。もうどっちにも小さくなっちまったけどな」
「健祐さんと、同じ物?」
「あぁ」
その瞬間、彼は心の底から嬉しそうに、口の両端を形良く引き上げた。こぼれそうな瞳は三日月型に変わる。俺の胸が、ちりっと焼けた。
*****
それからは、敷地のはずれにあるあばら屋に日参する日々が続いた。初日の一言以降、彼は健祐の様子を伺うような言葉は一切、口にしなかった。ただ時折、親でも健祐と間違う俺のことを黙って見つめることはあったが。
健祐の行方はまったくつかめない。というより、家族の誰もが、もはや健祐ははじめからいなかったものとして生活をしていた。だからこそ、由宇さんの存在は忘れていた傷を思い出させるような、具合の悪いものとして捉えられた。おそらく、わざと食事を抜かされたりすることもあったのだろう。けれども彼はそれを俺にもらすこともなく、そこに植えられた木のように、黙って俺のくだらない話に細い首を傾けた。
「宗祐さんは、本当にお話が上手ですね」
ある時、そう言って彼は俺に微笑んだ。
「そんなこと・・・由宇さんしか言わないよ」
「そんなことないですよ。宗祐さんのお話はとても面白いです」
床の上で半身を起こしたまま、由宇さんはそう言って小さく肯く。
「健祐の方が、話し上手だし、女の扱いだって上手い。俺はそういうの、からっきし駄目だから・・・」
俺は恥ずかしさからそんなことを口走り、そしてしまったと思う。健祐はその結果、他の女と逃げたのだ。
「・・・ごめん」
困って頭を掻く。すると、彼は紅を引いたように赤い口唇を動かした。
「宗祐さんはなにも悪くないじゃないですか。どうして謝るんですか?」
「いや・・・だって、無神経なこと・・・。俺、由宇さんのこと考えなかったから・・」「でも、私のことを考えてくれたから、謝るのでしょう?」
「いや、それは・・」
「宗祐さんは、優しいですよ」
俺は由宇さんの言葉の意味を一瞬飲み込めずに、彼の顔を見返した。
「宗祐さんは、優しい人です。少なくとも私は、そう思います」
由宇さんが、白く長い指で俺のごつく骨張った手を取る。由宇さんが初めて自分から俺に触れた時だと気付いたのは、それから少ししてだった。
*****
その夜、俺は庭で、由宇さんに触れられた手をじっと見つめた。月の光は暗く、切り取られた爪のような三日月が、そこだけ妙に白かった。
こんな俺の手とは比べ物にならない由宇さんの白い手。触れられた手は冷たかったのに、その余韻はこんなにも暖かく感じる。俺は自分の手をもう片方の手で握ると、胸にそっと押し当てた。
なぜ、健祐は由宇さんを捨てて出ていったのだろう。俺なら、絶対にそんなことはしないのに。
俺なら?
俺は一体何を考えてるというのだ。そんなこと、ありえないのに。由宇さんが待っているのは、健祐なのに。
そう、由宇さんの心にいるのは、健祐なのだから・・・。
*****
次の日、俺は街に出かけた後に、花を持って由宇さんの小屋へと急いだ。
「由宇さん」
声をかけながら、戸を開ける。すると、俺はそこに由宇さんの白い背中を見て、慌てて戸を閉めた。
「宗祐さんっ」
「ごっごめんっ」
由宇さんは着物を脱いで身体を拭いていた。由宇さんも慌てて、はだけていた着物に袖を通す。肉のついていない、細い身体。
「もう、いいですよ」
声がして振り返ると、由宇さんがいつものように半身を起こして座っている。
「本当に、ごめん」
「いえ、私の方も。宗祐さんの足音だと分かってたんですけど・・・」
恥ずかしそうに、由宇さんがうつむく。おそらく、急いで片づけようとしたのだろう。木桶の水が、少しこぼれていた。
「あの、これ。好きだったら・・・いいんだけど」
適当に摘んできた名も知らない花を差し出す。すると、由宇さんはその花を見つめて嬉しそうに呟いた。
「水仙・・・ですね」
花の名前など桜くらいしか分からない。すっと伸びた茎が、由宇さんを思わせるなと勝手に摘んできたのだ。
「きれいですね。ありがとうございます」
細い指が、水仙を手にする。指先でくるくるとまわすと、彼は木桶の中に茎の先をそっと入れた。
そのまま、お互いに何も言わないまま時間だけが過ぎる。俺は沈黙に堪え兼ねて、口を開いた。
「由宇さん・・・」
「はい」
首をかしげて、微笑みながら彼が返す。
「もし、良かったらだけど・・・俺が身体、拭こうか?背中とか・・・」
途端に、由宇さんが顔まで真っ赤にする。俺はそこまで恥ずかしがられると思ってなかったので、少し驚いて、両手を目の前で振った。
「い・・いや、嫌ならもちろん構わないんだけど。もし、不自由があるならと思って・・」
言えば言うほど、何か言い訳めいたものを自分の中に感じる。俺も彼につられて顔を赤くすると、膝の上で両の拳をぎゅっと握った。
「お気遣い・・・ありがとうございます」
絞り出すように、由宇さんが言う。由宇さんの手も、ぎゅっと握られていた。
「でも、そんなに甘えてしまったら、罰が当たりますから」
甘えてくれてもいいのに、と言いかけてやめる。いくら顔が同じでも、恋人の兄にそこまでされるのは嫌なのかもしれない。毎日ここに来過ぎて、俺が恋人のような錯覚を、自分で勝手に持ってしまったような気がした。
「・・・・・・ごめん」
「どうして、謝るんですか?」
即座に、彼が顔を上げる。あまりにはっきりと聞き返されたので、俺も驚いて顔を上げた。
「いや・・・俺は、人の気持ちが読めないから。よかれと思ったことも、よく・・・裏目に出るから。本当は、由宇さんのこと、喜ばせてあげたいとか思っても、どうしていいか分からなくて・・・。だから、ごめん」
たどたどしい俺の言葉を、由宇さんがじっと聞いている。俺が口を閉じると、彼が微笑んで静かに言った。
「健祐さんとは、まるで反対ですね」
由宇さんの言葉が、切るように響いた。それは長年抱き続けた俺の劣等感を、象徴する言葉だったから。
「健祐さんは、人を喜ばせるのが上手い、人付き合いの上手い人でしたからねぇ」
「あぁ。そうだな・・・」
目を背けるように、木桶の水仙を見る。由宇さんは俺の様子に気がついているのかいないのか、そのまま話し続けた。
「でも、健祐さんと同じでなければいけないんでしょうか?」
「え?」
遠くで鳥の泣く声が聞こえる。空を飛び、ねぐらへ帰る、鳥の群れ。
「宗祐さんは宗祐さんだから、健祐さんである必要はないんじゃないですか?」
おぼろげにしか見えてない目で、由宇さんが俺を見る。俺は膝の上で握った手に、痛いほどに力を込めた。
返す言葉もなく、口唇を震わせる。
熱いものが、頬を伝った。
俺は最初、自分が泣いていることに気がつかなかった。ぽたぽたと、床に落ちる大きな粒が音をたててはじけた。
「宗祐さん・・・?」
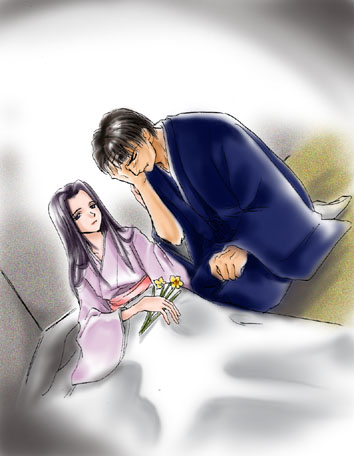 大きく鼻をすすった音に、由宇さんが声をかける。そんな優しい響きの向こうで、俺は小さい頃から親の繰り返す「兄弟の順番が逆だったら、要領のいい方が長男になったのに」という台詞を思い出していた。
大きく鼻をすすった音に、由宇さんが声をかける。そんな優しい響きの向こうで、俺は小さい頃から親の繰り返す「兄弟の順番が逆だったら、要領のいい方が長男になったのに」という台詞を思い出していた。
「何か、失礼なことを言ったでしょうか?宗祐さん・・・どうしたんですか?」
由宇さんが、身を乗り出して俺の顔に手をかける。濡れた頬に由宇さんの指がかかると、彼が驚いたように一度手を離し、それからゆっくりと、もう一度確かめるように俺の頬に触れた。
「宗祐さん・・・。私は、宗祐さんには、そのままでいて欲しいって・・・そういう意味で言ったんですが・・・」
「う・・うん。わかってる・・・わかってるよ、由宇さん」
白い指先が、俺の涙をぬぐおうと頬をなでる。でも由宇さんがそうしようとすればするほど、俺の涙は溢れてこぼれた。
「なら、どうして?」
「・・・いや、なんでもないよ。由宇さんは何も悪くないから・・・」
「でも、宗祐さん・・・」
「嬉しかった・・・だけだから・・・」
大きな手のひらで、顔をぬぐう。由宇さんはそんな俺を見上げると、とても悲しそうな瞳をして言った。
「私も・・・宗祐さんのことを喜ばせてあげたいと・・・そう言ったら、失礼にあたるのでしょうか?」
「え?」
彼の言葉に、一瞬、息が止まった。
目を見つめたまま、由宇さんの濡れた指先を手に取る。俺が着物の袂で由宇さんの手を拭くと、彼が続けた。
「どうしたらいいか分からないのは、私も同じなんです・・・」
見えてない瞳で俺を見る。健祐にそっくりな俺の顔、俺の声。由宇さんの待つ、健祐に。
触れた指先が、燃えるように熱い。俺はそのままどうにかしそうになる自分を押さえようと、由宇さんの手を離して立ち上がった。
「由宇さんは、身体をなおすことだけ考えてくれればいいんだよ。それだけで、充分なんだから」
布団の上で、彼が正座をしたまま動かない。俺は明かり取りの窓から外を見ると、暮れていく夕日を見つめた。
「本当に、それだけで・・・」
*****
→次の頁へ
→「十三夜」メニューへ
→隠し部屋メニューへ
着物の裾を整えながら、由宇(ゆう)さんの脇に腰を下ろす。薄っぺらで粗末な布団が、彼に対する周囲の意識を物語っているようで、俺は布団に触れた手を静かに引っ込めた。
大きく鼻をすすった音に、由宇さんが声をかける。そんな優しい響きの向こうで、俺は小さい頃から親の繰り返す「兄弟の順番が逆だったら、要領のいい方が長男になったのに」という台詞を思い出していた。
