Tri-Ex社 Model LM470D
|
 風杯型風力計の設置 大田計器製作所製 SP−26 風杯型風力計の設置 大田計器製作所製 SP−26
|

|


|
LM470D クランクアップタワーに風杯型風速計を取り付けしました。
取り付けの理由は、タワー建塔当時オプションで風速計感知型昇降機能付きのコントローラーがあったのだが、高価だったため注文しなかったためで、ずーっと後悔していたのですが、それでも高価で購入することが出来なかったからなんです。
結局は、天気図で風を予想してあらかじめタワーを縮塔しておくか、風が吹いてきたら風の状態を判断して手動で縮めていたのですが、数値的な風の強さを知りたかったし、一番は突然の突風に対応できれば安心なので設置することにいたしました。
この趣味は、万が一タワーが倒れたり折れたりした時には、重大事故になってしまいますし、何といっても安心感を持てることいは、精神衛生的に重要ですからね。
|
 |


|
3年ほど前に、風杯型風速計のみを入手しましたが、受信部がなかったのでシャックのお飾り状態になっていました。
受信部の新品を購入しようかと大田計器製作所にも問い合わせをしましたが、6万円以上と高価だったので、あきらめていました。
ところが、オークションで、手持ちの風杯型風速計26−SP型用の受信部が出ていたので早々に購入し、タワーに取り付けることとなりました。
、 |
風杯型風速計と受信部(計測部)
|
|
|
 |


|
風速計の風杯部分の塗装が剥げて、銅の地肌が出ていたので、塗装しました。
この風杯型測定器の仕組みは1回転で12パルスを発生するタイプ(パルス型)で、気象庁の認定も取得できる精度の高いものだそうだ。
しかし、相当古いのでそこまでは正確ではないとは思うが、ケースはアルミ鋳造だし風杯部分も銅製で屋外の風雨に曝されても早々簡単には壊れそうもない構造です。
|
風杯型測定部
|
|
|

|



|
タワーへの取り付けは、5mm厚のアルミ板をベンダーで曲げ加工しタワーにステンレスバンドで固定しました。
風速計から受信部までは。0.5sqの2芯線で接続してあります。
この風速計には鉄製の台座が付属していて、元々はクレーン車に付けられていたものらしく取り付け台座部分のボルトには貫通の穴があいていて、風杯型風速計からのパルス信号ケーブルが通せるようになっていましたので、そのまま使用することとしました。
この貫通ボルトは、クレーン車に付けられていたため、クレーンアームの角度が変わっても常に風杯型風速計は、水平に保たれるように貫通部分にベアリングが使用されていて、風杯型風速計取付け土台座は常に水平状態様を保ちます。
クレーン程ではありませんが、クランクアップタワーは多少は傾きが生じますので、折角ですからこの機構をそのまま使うことにしました。
|
| |
|
|
 |


|
受信部は風速40m/sec までの表示があるが、風杯型風速計の測定範囲は30m/sec までのようだ。気象観測するわけではないので問題ない。
もっとも、風速30m/sec の風なんて、よほどでかい台風の直撃がない限り記録することもないですからね。
受信部には、リアルタイムの風速表示と、平均風速表示を切り替えることが出来ます。また、警報音を鳴動させる風速をプリセットするダイアルが付いていて、風速
0〜30m/s間を設定できます。
設定した風速になった途端に内蔵のアラーム(警報音)が鳴り出します。 |
受信部の表示
|
|
|
 |

|
受信部の背面には、外部警報用の無電圧トランスファ接点で、警報接点容量:AC250V・5AまたはDC30V・5A(抵抗負荷)が装備されいているので、私の制作したタワー制御回路のDOWNのスイッチにカスケード接続しました。
実際に10m/secに設定してみたところうまく動作してくれたので、これで安心できます。
安全装置完成までに10年以上も掛かってしまいました。(苦笑 |
受信部の背面端子
|
|
警報1または2にタワー制御回路へ接続 |
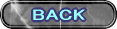 |

