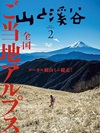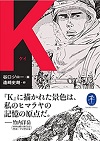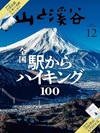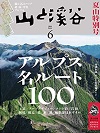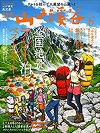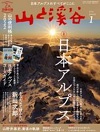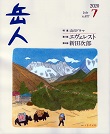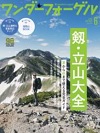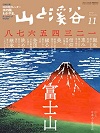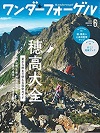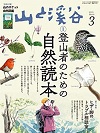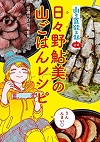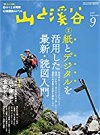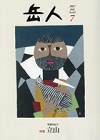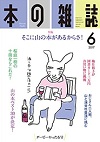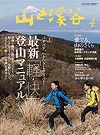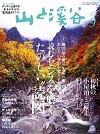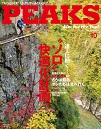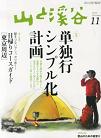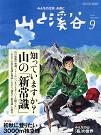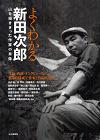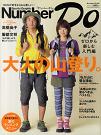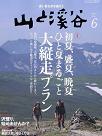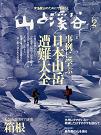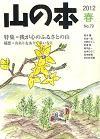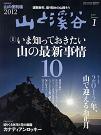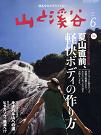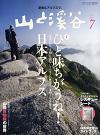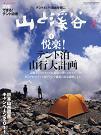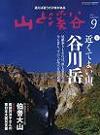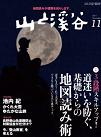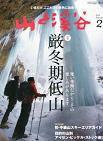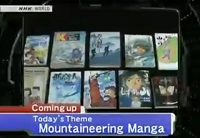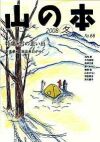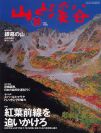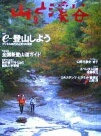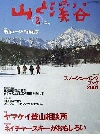|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る
この頁のトップに戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||