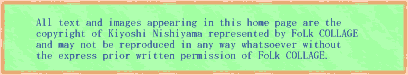余呉湖を訪ねる −天女伝説の湖−
西山喜代司
ラムサール条約に登録されている琵琶湖から少し離れた北東に小さな湖(みずうみ)があります。余呉湖です、「余る」という字を当てるので、琵琶湖を神様がお作りになられるとき、この湖をつなぎ忘れたために「余呉湖」と名付けられたのでしょうか。この湖を訪れると、何かそのような神々しさを感じます。そして、この印象に似つかわしい伝説を持っています。余呉湖にちなんだお話を紹介しながら、四季に彩られた余呉湖の魅力をお見せしましょう。
周囲約六キロメートルの余呉湖は余呉駅から川並集落のある北方を除いて、三方は岸まで山が迫ってきています。その一つ、南岸にそそり立つ標高421mの賎ヶ岳は、400年前の柴田勝家と羽柴秀吉との、「賎ヶ岳の合戦」でよく知られたところで、余呉湖は血の色に染まったといいます。中でも特に激しかった戦いは、勝家の先鋒佐久間盛正との、湖岸にある国民宿舎と川並にかけてで、世に言う「賎ヶ岳の七本槍」(実際は七人ではなく九人である、七本は後の人がつけた名称)としてよく知られています。湖の最も深いところは南にある国民宿舎よりの約十三メートル。余呉湖の湖周道路は、切り立った山を切り開いてできたため、狭い道幅ですが、自転車で湖周を走るにはむしろ適しています。余呉湖の玄関口JR余呉駅を出てしばらくの三叉路を右にとると、静かな湖がひろがります。左右にひろがる田園をしばらく歩くと、湖の辺に大きく枝葉を広げたこんもりと繁るアカメヤナギに出会う。天女伝説の柳です。「衣掛柳」の側に佇み、背後にひろがる小さな漣を立てている湖に目をやると、今も天女が水浴びをしているかのようです。
「近江の国伊香の郡にある余呉の湖に天の八女(やおとめ)、ともに白鳥(しらとり)となって天より降り、湖辺で水浴をせし。この時、伊香刀美、西の山でこの白鳥を見て、この形もしや神人と疑い、浜辺に往って見るに、真にこれ神人なりき。伊香刀美、感愛を生こし、白き犬に妹の天の羽衣を盗ませし。姉の七人の天女は天上に帰りしが、妹は羽衣無く天上に帰れず。伊香刀美、この天女と夫婦となり、男女二人ずつをもうけし。兄の名は意美志留(おみしる)、弟、那志等美(なしとみ)、姉、伊是理媛(いせりひめ)、妹、奈是理媛(なせりひめ)。これは伊香連(いかごのむらじ)等の先祖でなりき。後に天女、羽衣を探し当て、天井へと帰りし。伊香刀美は一人空しく床を守り嘆くことしきりなし。」
これは、『近江国風土記逸文』が伝える「羽衣伝説」です。この話しは、天女が羽衣を奪われ、人間の女房となったことから「天人女房」の説話とか、神女が白鳥となって人間界を訪れて結婚し、再び天に戻ることから「白鳥処女説話」ともいわれます。余呉湖の「天女伝説」は三大天女伝説の一つにあげられています。ちなみに他は、京都府中郡峰山町の丹後型天女伝説と静岡県清水市の三保型天女伝説で、それぞれに特徴があるため、その土地の名をとって、「余呉型」「丹後型」「三保型」といいます。それぞれは、天女が水浴びをしている間に天羽衣を隠されるところまでは同じです。「丹後型」の天女は老夫婦の養女となり、良酒を作ることによって、老夫婦は裕福になります。富者になると、この老夫婦は天女を家から追い出してしまいました。天羽衣がないため、天女は天に帰ることも出来ず、奈具村に留まり在地の神となります。今、峰山町で語られている「天女伝説」は、かなり書きかえられ、若者との恋物語になっています。「三保型」は、漁人と夫婦になった天女はある日、隠してあった羽衣を探し、天に帰ってしまいます。それを知ると、漁人も天へと登っていくという、いわば、追っかけ型。もう一つ、面白いのは羽衣を掛けた木で、余呉型では「柳」ですが、今紹介した二つ以外の日本に伝わる天女伝説はすべて松です。松は門松にするように古くから神の依り代とする木で、天女には似つかわしい木といえます。が、鏡湖といわれた静かな余呉湖には、春に芽吹き、夏には青々とし、秋には色褪せて落葉し、冬は次の新芽を育てる柳のほうが似つかわしいからでしょうか。衣掛柳は、よく川の側で見かける、葉が細長く、枝の垂れ下がっている種類ではなく、マルバヤナギともいい、丸葉で普通のこんもりとした柳です。
余呉湖の天女伝説は、『近江国風土記逸文』のなかに見られ、これは『帝王編年記』に収められていたものです。『帝王編年記』は鎌倉時代に記されたものですが、この中に収められている諸国の風土、伝説、風俗は、奈良時代に成った『風土記』からの引用とみなされており、古くからの地方に伝わる伝説や歌謡を知ることができます。天女の羽衣を隠した伊香刀美はこの地方を治めた伊香連の祖先とされています。『新撰姓氏録』によると、伊香連は「大中臣同祖 天児屋根命七世孫 臣知人命の後なり」とあり、臣知人命は天女と伊香刀美の間に生まれた意美志留と同一人です。余呉町に隣接する木之本町大音にある伊香具神社は白鳳時代(七世紀後半から八世紀前半)に建立された神社で祭神は伊香津臣命で、伊香連を意味します。中臣氏は大和朝廷での神事祭祀を司った氏族で、その同祖とする伊香津臣命も同じようにこの地方を神事祭祀によって治めたのでしょう。伊香連が天人女房の血をその系図の中に組み入れたのは、神と人との中を取り次ぐ役を表すためではないでしょうか。
余呉湖近くにある乎弥(おみ)神社の祭神は臣知人命と梨迹臣命で、この二神は天女伝説のなかの意美志留、那志等美です。また、伊香郡高月町雨森の雨川命神社には三神、伊香刀美・臣知人命・梨迹臣命、伊香郡木之本町木之本の意冨布良神社には梨迹臣命が祀られ、天女伝説がこの地方に広く流布していたことが知られます。伊香郡木之本町杉野の本宮横山神社には伊香津臣命が合祀されています。このように天女伝説の中の人物が伊香郡の神社に祭られていることから、伊香郡に大きな勢力を持っていたのでしょう。もしかすると、大和朝廷に匹敵するほどの力を持っていたのではないでしょうか。だからこそ、後ほど述べる、菅原道真伝説も生まれたのではないでしょうか。
川並集落は余呉湖に面してあるただ一つの集落です。山がせまる湖との狭隘な土地を利用して人々が開拓し、天女伝説に登場する桐畑太夫の住んでいたところと言い伝えられています。今は川並の北野神社に合祀されている新羅崎(しらぎ)神社は、天日槍(あめのひぼこ)を祭神とし、新羅崎神社縁起に「菊石姫伝説」があります。天日槍は記紀の中に出てくる新羅の皇子で、古代に日本へ渡来してきたと伝えられています。日本の各地に天日槍は足跡を残していますが、ここ余呉町中之郷にも日槍塚という古墳があり、多くの渡来人が住みつき、農耕などの優れた技術をもたらした、といわれています。この地方に盛んだった養蚕の技術も渡来人がもたらしたものでしょう。
「都からの落人(わけあって都から住み着いた)桐畑太夫は、この二町余り西の桐畑池の口に屋敷を構え、居住していた。太夫は諸事に長け、村長として村民に慕われていた。桐畑太夫に最愛の一人娘が誕生し、菊石姫と名付けられ、美しく心優しい娘であった。ある旱魃の年、村人が苦しんでいるのを見た菊石姫は、湖の生け贄となり、蛇身となって雨を降らそうと決意し、湖に身を投げた。すると、一天にわかにかき曇り、大雨が降ったと言う。」(新羅崎神社縁起「菊石姫伝説」から)
旱魃の時、娘が水に身を投げて雨を降らせる伝説は、全国の池や沼に伝わり、菊石姫の伝説もその系統に属するものです。川並では昭和初期まで旱魃の年には湖畔にある菊石姫に縁のある、蛇の枕石を新羅崎神社境内にあげ、これを菊石姫として雨乞いをしていました。
川並の桐畑家には『桐畠太夫縁起』が代々伝わっており、この中にも「菊石姫伝説」が語られていますが、先の『新羅崎神社縁起』とは内容を異にしています。
「桐畑家に生まれた菊石姫は徐々に蛇体となり、このままでは太夫の家において置けなく、屋敷から一丁余り東北の屋賀原に仮屋を建て、そこへ捨て置いた。姫を守していた下女は深く哀れみ、自らの食物を分け与えて養育した。姫が十八になったとき、姫は湖水へと入っていった。龍となった姫はこの時、長く養育してもらった下女にお礼として、自らの片目を与えた。不思議な力を持った龍の目の話しが、お上にまで聞こえ、両目を差し出せとの命が下った。片目しか持たない下女は、菊石姫を湖より呼び、もう片方の目を貰った。が、両目ともなくした龍には、時刻を知ることが出来ないため、鐘を撞く事を約し、もう片方の目を、湖の辺にあった石に投げつけた。このときの跡が石に残っている。この石を「目玉石」と呼び、新羅崎神社跡近くの湖岸に祀られている。」(『桐畠太夫縁起』から)
化身した龍の両目を差し出すところなどは、大津市三井寺にちなんだ「三井の晩鐘」を彷彿とさせます。そして、『桐畠太夫縁起』では、「菊石姫伝説」に続いて「余呉の天女伝説」が形をかえ語られており、天女と桐畑太夫との間にできた子供を菅原道真としています。この菅原道真の生誕は信憑性には乏しいですが、道真が余呉湖東方の大箕山にある菅山寺を寛平元年(889)と寛平七年に訪れたことは「興福寺の官務牒疏」に記されており、史実です。寛平七年正月に訪れた際には、今までの龍頭山大箕寺を、自ら山門の扁額を認め、「大箕山菅山寺」と改めました。鎌倉時代に鋳造され、現在国の重文に指定されている銅鐘の銘にもこのことが刻まれています。菅山寺山門の両脇には、菅公お手植えの欅が、今も千年の月日を経て訪れる人を迎えてくれます。瘤やいびつな格好をした、幹周囲約六メートルになる老木です。道真公は余呉湖から少し南へ下がった木之本町にある伊香具神社に自らの法華経、金光明経を書写して宝殿に納め、この地域とは縁が深かったのです。
道真が延喜三年(903)大宰府にて死去すると、都では道真公の怨霊に脅かされ、天神御霊となった。菅山寺では天暦九年(955)境内に近江天満宮を建立し、道真公自ら刻まれたという像を御神体として祭りました。今でも、四月二十五日に春の大祭、九月二十五日に秋の大祭があり、多くの人が参拝します。
また、「天女伝説」では、「天女との間にできた三歳になる子を岩の上において、太夫は天女を追いかけて天に登ってしまった。岩に置き去りにされた子の泣き声が経文の響きを持っていたため、菅山寺僧尊元和尚の耳に届き、この子を菅山寺へと連れて帰った。」泣いていた岩を「夜泣き岩」と呼び、西天神宮そばの梅林の傍らにあります。日に日に非凡さを見せる童子を、菅山寺に訪れていた菅原是善卿の目に留め、養子として京へ連れて帰った。この童子が後の道真公である、としています。
菅山寺参道入口にあたる余呉町坂口で、飴屋市助が飴を作っていました。この飴は坂口飴と呼ばれ、坂口は北国街道が通っており、街道を通る領主の土産物として重宝されていました。『西浅井むかし話』にはこの坂口飴と道真公とのことが語られています。
「‐‐‐‐歌たその子供を残してあの天人が衣を着て、天へ帰ってしもうた。そしたところがほの子供は、ひとりであるけど、ほの親父(おや)っさんが、そんな子供やさかい、ひとりの子供やけれど、父親で乳も出ないし、その湖辺捨てた。そうしたところが、それのずっと東の方の山の上に、菅山寺言(ちう)うお寺があった。そしたら「勤めをしていたら、どうしても法華経を読む声が聞こえてくる」言うので、弟子に見せにやったところが、赤子は岩の上にひとりで寝ていた。それをほんで連れて戻って、その坊さんが育てた。その育てたのは、その裾にある、坂口飴言う、今でも坂口飴言うてありますが、その飴で育てはったらしいんですわ。それが菅原道真公であったと。‐‐‐‐」(『西浅井むかし話』)
カラフルで色々な形の日常親しんでいる固い飴は江戸時代に入ってから登場してきたもの。本来の飴は液状の水飴で、平安時代には食されていました。坂口飴は菊水飴と名を変え、今もここ坂口で作られています。
川並にある北野神社は、安和の変(安和二年、969)により都を逃れた村上播磨守(62代村上天皇の皇子・為平親王)が、天禄3年(972)この地に来住し、菅山寺の守護神天満宮の分霊を勧請して、山麓に祭ったのが始まりとされています。祭神はもちろん菅原道真。北野神社は毎年二月二十五日に天神講の祭典があります。川並集落の中で決められた当番が六升の餅米を鏡餅にし、これを当番の家の者が背負って、北野神社に奉納し、その年の村内安全、五穀豊饒を祈ります。北野神社梵鐘には天女の姿が鋳込まれています。この地域では、天神信仰が盛んで、菅山寺の近江天満宮でも春と秋に大祭が催され、多くの人が参拝されます。余呉湖から一キロほど北へ離れた中之郷の明三寺本堂天上には、天女が鞨鼓(かっこ、鼓の一種で両側から叩く)や笙を持ち、楽を奏でる天女の姿が描かれています。この絵は、本堂が再建された延享四年(1747)の頃の作とされています。数十年前、屋根葺き替えの際に、雨漏りで天女の顔付近が黒ずんでしまったことが惜しまれます。
余呉湖の南岸に切り立つように聳えるのが賎ヶ岳で、余呉湖は賎ヶ岳北麓の断層盆地によって作られたものです。琵琶湖よりも水位が約五十センチ高く、もし賎ヶ岳にトンネルを掘ったなら、余呉湖の水は琵琶湖に流れ込むことになります。また余呉湖は周囲の山々の渓流や伏流水の水によってできた湖で、大きな河川の流入や放出がなく、完全な閉塞湖でした。そのため湖面は穏やかで鏡のように周囲の景色を湖面に映すほど穏やかな湖だったことから鏡湖と古くからいわれていました。
楽浪(さざなき)や比良の高嶺に雲消えて
余呉の入江に澄める月かげ (源師光 「万代和歌集」 )
しかし、大きな流水口がないことから洪水の被害を受け、常にその脅威にさらされていました。昭和三十一年から大規模な治水事業「余呉川総合開発事業」が実施され、余呉湖導水路と余呉湖放水隧道が完成し、今はその心配もなくなりました。賎ヶ岳越しに琵琶湖の水を揚水し余呉湖へ供給し、余呉湖の水は余呉湖放水トンネルから流出し、余呉川周辺地域への水田用水として利用されています。余呉湖は人工的に調節されるダム湖となったわけです。閉塞湖ではなくなったためか、私は、何度か余呉湖の岸に立ち湖を眺めましたが、一度も漣一つない鏡湖には出会えなかったのです。四季を通じて何度か足を運んだ大きな理由の一つに鏡湖を確かめてみることにあったののですが。
長年透明な美しい水を保ってきた余呉湖も最近では透明度も悪化しています。昭和三十三年から昭和四十年にかけての国鉄(今のJR)北陸線のトンネル工事による地下水の経路が変更になってしまったためとも、導水路工事による余呉湖北方の地下にある湧水の水路が変わってしまったためではないかとも言われています。
余呉湖北部の湖底から縄文晩期の土器が発見されており、縄文時代から人々が住んでいたことが分かります。土器と同時にクルミやトチ実も発見されており、湖から切り立った山の木の実や動物や余呉湖の魚貝類とあわせて、この辺りは自然の恵みの多いところでした。余呉湖が古代の情報を我々に残してくれたものがあります。「余呉湖埋没林」と呼ばれ、昭和四十五年に工事のため湖水を放水した時、鏡丘中学校科学クラブ員が見つけました。約二千年前の乾期に繁っていた森林跡です。この後、調査が進められ、6500年前、8200年前の埋没林が発見されました。この発見は、地球の乾期と雨期を知れる古気象学上貴重な情報で、世界に注目されました。これにより地球は2000年から3000年を周期として、乾期と雨期を繰り返してきたことが分かりました。いま発見された埋没林は湖水が引かれ再び湖の中で眠っています。
余呉湖と賎ヶ岳をはじめとする湖に面している山々は、余呉湖に四季を知らせます。天女のアカメヤナギは、今も初夏には青々とした新緑の衣に身を包みます。夜の静寂に包まれたころ、アカメヤナギの葉と葉の囁きは、古の物語を織っているかのようです。東の空が白み始め、空の色が紺青から赤紫に染まるころ、天女の柳に山から顔を出した日が射し、新緑の瑞々しい葉はその日の新しい光を照り返す。一日という時間の流れの中で呉湖はいろいろな姿を見せてくれます。朝陽が顔を見せるその日の始まりから、うたた寝をもよおす昼下がり、そして、夕暮れは細部を塗りつぶし、全てを同一平面に化そうとし、ついには闇に包まれるまで、余呉湖の姿を追っていっても飽きないでしょう。辺りが暮色に染まる頃、対岸の照明と列車からの車窓の灯りを一筋の流れとして湖面に照り返す。静止している灯りと、スーと走っていく灯りは闇の色に変わった湖に照り返されていた。湖が民家や街路の灯火だけを映す夜のしじまに、規則的で低く疎く響く音とともに流線型の灯りが走る。列車の車窓の灯りの行進は、寝静まった湖をふと目覚めさせます。
春、柔らかい風が湖の面をなでると、眠そうな湖面の水は上下に緩慢な起伏運動をします。柔らかい風 は湖辺の木々の芽を誘い出します。
月に照らされた湖面は深く沈んだ湖を月の落子達がせわしなく駈け回り、湖面に生まれる細波は月光の 波長を増幅させるかのようです。
晩秋の頃、ミルク色のベールに包まれた湖岸の民家や街路の灯火は光芒を、にじんだスポットライトの ようだ。霧の間から朝の陽光が見え始め、やがて湖との区別ができる頃、霧はスーと晴れていく、ドラマ チックな演出をするかのように。
賎ヶ岳から舞い降りる雪は余呉湖が冬の装いに変わることを告げます。湖に吸い取られる雪。周囲の景 色を白に変えていく雪、でも、湖は雪を吸い取っていきます。
運命に翻弄された若い男女の哀話を余呉湖が暖かく包み込む、という水上勉の『湖の琴』も、余呉湖が語る話です。『湖の琴』のストーリーの粗筋です。
関西長唄界の巨匠、桐屋紋左エ門は木之本町西山へ、三味線糸の作業場を見学に訪れた。その折に、糸繰り工の栂尾さくに見惚れた。それは、立ち寄った高月町渡岸寺でみた十一面観音の生まれ変わりの、夕顔の花のようであった。さくには、将来を誓い合った同じ作業場の松宮宇吉がいた。権力を傘に、紋左エ門の元へ呼び寄せられたさくは、強引に体を奪われた。逃げるように帰ったさくは以前の百瀬家で宇吉らと一緒に働いたが、ある日、体の異変を感じた。妊娠していたのだ。誰にも話せず、悩んださくは忽然と姿を消した。さくが姿を消した日、宇吉の姿も見なくなった。
さくを捜していた宇吉は、以前一緒に働いた桑畑にある小舎で首をつったさくを見つけた。一人での死への旅立ちを哀れと思った卯吉は、いとおしいさくと一緒に余呉湖へ沈んでいった。行方不明となったさくと宇吉の消息を、余呉の湖の湖底から響いてくる琴の音が語る。誰ということなく、さくと宇吉のことが語り継がれている。
悲しくも哀れなさくの生涯を水上勉は『湖の琴』で描いています。時代が今なら、さしずめ、これをネタに桐屋紋左エ門が締め上げられるところでしょう。水上勉は、さくと宇吉との純真で切ない恋心を、余呉湖の持つ神秘的な情景を背景にしてストーリーを展開しています。物語のラストで、湖の底で一緒になろうとする宇吉を余呉湖に映える月との情景を重ね合わせて印象深く綴られています。
「とみるまに、空にたれこめていた黒雲が割れふたたび月光がさしてきた。宇吉は空を仰いで拝んだ。月は、さくの冥府への旅立ちに、明かりをそえてくれようと、わざわざ、広い余呉の湖の竜神の岸にだけ 、ぽっかりと明かりの輪をくれたのだった。」(『湖の琴』)
余呉湖に惹かれて何度私は足を運んだことでしょう。書斎にいて、窓の外のひっきりなしに降る雪を見ると、私の脳裏には、雪のもたらす情景を静かに受け入れていく余呉湖が目の前に浮かびます。と同時に、私は車を琵琶湖の北へと走らせています。春の空気の流れが完全に止まってしまっているような眠りを誘う日、この日こそ鏡のような余呉湖が湖の春眠を映しているだろうと、余呉湖を訪れたことも何回あったでしょう。夏の真上の太陽を照り返す余呉湖の表面から醸し出される蜃気楼は天女の姿かと錯覚します。晩秋の早朝に訪れた日のミルク色の濃い靄に包まれた余呉湖。陽が上る頃になって次第に辺りの景色がぼんやりと認められるようになっていく、時間の移ろいを体験した日のことは忘れることができません。
ひっそりと静まり返った余呉湖のそっと大切に仕舞い込んだ、切なくも哀しい話を聞きたくなったなら、ここ余呉湖の辺に佇み、そっと、湖の声に耳を傾けて下さい。湖と周囲の景色が織りなすスクリーンに湖の話をつづってくれることでしょう。忘れてしまった自然の優しい心を思い出させてくれます。