【スバルのダウンサイジング・ターボについて】
詳細は専門家に任せるとして、VM4を例にとって簡単に言うと、
『従来の2.5リッタークラスのエンジンで発揮されるパワー&トルクを、
1.6リッターのエンジンで達成しよう』というのがコンセプトだ。
レヴォーグの場合、車重は1.5トン強。この1.5トンという重さは、
一般的なワゴン車としては特に重量級というほどではないが、
筆者の主観では自然吸気エンジンなら2リッターでトルク20kgm、
2.5リッターなら25kgmは欲しい。
また、ストップ&ゴーの多い街中を走るなら低回転からのトルクも、
高速道路を走るならそれに加えて高回転での伸びも欲しい。
しかしこのご時勢、大排気量でぶっ飛ばすタイプのクルマは
消費者に対する訴求内容としては不利な状況にある。
排気量が大きくなると燃費が悪くなる傾向にあるし、
環境アセスメントや税制から見ても、CO2やNOx排出量の
少ないクルマが好まれるからだ。
そこで、「従来エンジンと同等の動力性能を確保したまま、
排気量を小さくして、巡航時の燃費を向上させてみよう。
必要なトルクはターボ(過給器)で補えばいいだろう。」
という考えが生まれたわけだ。
ターボといえば軽自動車だが、軽の場合、660cc(以前は550cc)
という排気量の縛りがある。どちらかというと燃費の向上よりも、
与えられた排気量の範囲内でパワーアップを狙った経緯があり、
ここではダウンサイジングと同列に扱うことは避けておく。
過給器の代わりにモーターを利用するのがハイブリッドカーだが、
アプローチの方法が違うだけで、燃費向上の目的は変わらない。
VM4はステーションワゴンとして大きな積載能力を持ち、しかも
パワー&トルクは並みの2リッターセダンを凌駕し、そのうえAWD。
おまけに小排気量でガソリンはレギュラー仕様。
お財布にも優しいクルマ、ということになる。
果たしてそのような旨い話があるのだろうか?
前置きが長くなったが、走行性能のレビューに移ろう。
★★★走行性能レビュー★★★
☆☆エンジン☆☆
 |
VM4に搭載されるエンジンはFB16。
水平対向4気筒、1.6リッター、直噴DOHCターボである。
FB系は自然吸気専用エンジンとして開発され、2011年式の
インプレッサに搭載されていた。
VM4では直噴ターボになるため、クランク以外の部品が再設計され、
アイドリングストップにも対応している。
水平対向エンジンの詳細については専門家に譲るとして、
乗ってみた印象では他メーカーの同クラスのエンジンと比較して
車内エンジン音は静かであり、振動も抑えられていると感じる。
エンジンスタート後30秒ほどで音は落ち着いてくる。
車外へ出て、ボンネットの傍に立ってアイドリング音を聴くと、
マークⅡ2.5リッター直6の音に比べて素朴な音がする。
噂に聞くほどのドコドコした騒音ではないが、お世辞にも
官能的とは言いがたい。
(アイドリングストップ)
アイドリングストップは欧州車に見られるON/OFFの素っ気無さに
比べるとジェントリーだ。車内にエンジン音があまり伝わらないので、
ストップした瞬間の静謐さとの落差が小さいからだろう。
ただし生業として機械を操作する筆者としては、「唐突に機械が停止
する」という状況はかなり精神的なストレスになる。
街中を走っていると頻繁なエンジンのON/OFFが煩わしくなる。
アイスト機能がバッテリー寿命に及ぼす悪影響についても常々
懸念を抱いていたのと、走行開始直後はなるべく早いうちに油温を
上げたいことから、最近は乗車時にアイストをOFFにしている。
燃費向上・CO2排出量低減の目的でつけられたそうだが、可能なら
機能を解除したい(ディーラーでは解除不可とのこと)。
(使用燃料)
レギュラー仕様だが、スバルテクニカルサポートに問い合わせたところ、
ハイオクを入れても問題ないそうだ。
レギュラーだとエンジンの振動がわずかに大きく、ハイオクのほうが
発進加速もスムーズに感じる。
燃費よりもストレス軽減を優先させ、今はハイオクを入れている。
財布への優しさとは相反するが、このストレス軽減は危険回避に
繋がるかも知れない。
☆☆CVT☆☆
(リニアトロニック)
レヴォーグのトランスミッションは「リニアトロニック」という無段変速機。
5代目レガシィで採用された。従来のCVTよりもエネルギーの
伝達効率を高め、大容量トルクにも対応できるようになった。
この新しいCVTの開発に当っては相当の時間と労力がかけられ、
完成したときの達成感と感動は並々ならぬものであったらしい。
そこでスバル開発陣の皆さんが「従来のCVTという枠に囚われない、
まったく新しいトランスミッションだ」との自負をもって名づけたそうだが、
ようはCVTである。
同時期に乗り比べた他社のAT車に比べても非常にスムーズな変速だ。
これに慣れてしまうと、「アクセルを踏んで3,000近辺まで回して次の
ステップに移る」という段つき変速(AT)が煩く感じられるようになる。
スバル開発陣に脱帽。
(パドルシフト)
パドルシフトが付いている。シフトレバーをマニュアルモードに入れて
操作するが、D(ドライブ)レンジのまま操作しても、一時的にマニュアル
モードに切り替わり、パドルでの変速が可能。状況に応じて使い分ける。
坂道やスロープではDレンジのまま1速に入れたりする。パドル操作から
しばらく経つとATモードへ自動で戻る。
2~3日クルマを動かさなかった後で、街中を3000rpm前後で走らせたい
状況では主にマニュアルモードで走行するため、パドルを多用する。
しかし、身体がAT車に慣れ切ってしまっているせいか、変速し忘れて
ブーストばかり上がって車速がついて来ない時がたまにある。
(ラバーバンドフィール)
VM4のゼロ発進加速時のモッサリ感がCVTのラバーバンドフィール
から来るものだという説がネット上で散見されるが、原因がCVTの
変速ラグなのか、ターボラグなのか、はたまたECUの調律にあるのか
立証したわけではないので、言及は避ける。
(エンジンブレーキ)
エンジンブレーキはマークⅡ2.5や他車ATに比べて効きが弱い。
Dレンジのままだと、急な下り坂やビル内の急なスロープでは、1速に
入れてもややスピードが出すぎるため、ブレーキをかける場合が多い。
ただしマニュアルモードであれば、エンブレは効きやすい。
☆☆脚まわり☆☆
 |
VM4にはGTとGT-Sのラインナップがあった。
GT :17インチ+カヤバ・・・柔らかい乗り心地
GT-S:18インチ+ビルシュタイン・・・硬い乗り心地
マークⅡの柔らかな脚に近い感覚はGTだったが、
筆者はネームバリューに押されてマークⅡの脚については
柔らか過ぎると感じていたので、ビルシュタのGT-Sを選んだ。
はじめはローラーに乗っかっているような違和感を覚えたが、
ロールしにくく、舗装の行き届いた路面なら滑るように走る。
速度が乗ってからの安定性もいい。よく曲がり、よく止まる。
筆者は制動時、カックンがないようにブレーキを踏むことを
心がけているが、多少速度が乗ってからの制動であっても、
ノーズが突っ込みにくい。前輪と後輪がほぼ同時に止まる。
ただし段差から降りる時には車体が塊となって落ちる感覚が
あったり、やや路面の古い道路ではロードノイズが大きい。
硬い脚回りなので路面凹凸への追従性は悪いかと思ったが、
いつも検証に使うトンネル内の段差舗装は問題なかった。
マークⅡに比べても収束が早いと感じた。大きな坂道のカーブでも
車体はあまり傾くことなくスムーズに降りる。
高速道路での走行、右左折やカーブへの適応は、8jホイールと
235のタイヤを組み合わせたときにもっとも良好だった。
大橋ジャンクションの長いループはマークⅡよりも安定して
走ることができた。
その代わり低音域のロードノイズが増加し、街乗りでの軽快さは
減少した。
(スタッドレスタイヤ)
純正7.5jのホイールに225のスタッドレス(DUNLOPのWinterMaxx02)
を履かせる組み合わせが意外に良かった、と感じたが、
蹴り出しがしっかりして、操舵反応がクイックになり、しかも
ロードノイズが減少する。いかんせんスタッドレスなので柔らかすぎ、
常用とまでは行かないものの、カーオーディオの音や同乗者の声が
聴き取りやすくなる。
空気圧をこまめにメンテナンスしないと乗り心地を良い状態に保てない。
ゴーっという低音ノイズは減るものの、サーっというパターンノイズは
逆に増える。雨天ではなぜかロードノイズ、パターンノイズともに
抑えられ、車内が静かに感じられる。
タイヤ幅が細くなるせいか街中・低速域での取り回しはやや楽だが、
郊外・高速域では操舵反応が柔らかすぎて不安になる。
本来、降雪時で真価を発揮するタイヤなので雪上や路面凍結下での
レビューを書ければ良いのだろうが、東京ではなかなか雪は降らず、
書く機会はまだ先の話になりそうだ。
(画像は純正ホイール+WinterMaxx02)
 |
☆☆発進加速☆☆
信号待ち停止状態から発進する際、アクセルを踏み込んで回転数を
2,000rpmに抑えつつ発進するとき、5秒でだいたい20km/h近辺に
達する。
この5秒20km/hは、東京都環境局から発表されている「eスタート」
の目安と同じ。ただ、乗り始めの頃はゼロ発進時や徐行からの
再加速時のモッサリ感が気になった。
高速巡航の多いユーザーはあまり気にならないかも知れないが、
街乗りの多い環境下ではHVやEVに比べて不利であろう。
とくに対向車の間隙をうかがって右折する際はレスポンスが遅く、
(あくまでもマークⅡ時代と比較してだが)イマイチだと感じた。
良く言えば穏やかな加速だが、自分の意図した加速ではなく、
「踏んで1~2拍遅れて加速が始まる」といったほうが正しい。
カスタマイズを重ねるうちに、最近では2,000rpmで5秒25km/hと
なるケースも見られるようになっており、これぐらいの発進加速性能
があれば充分である。
なお、冬場は空気密度が濃いためか、夏場に比べて加速性能が良い。
☆☆S/Iドライブ☆☆
VM4は2つの走行モードを選ぶことができる。
Iモード(インテリジェントモード):出力特性が穏やか。市街地用。
Sモード(スポーツモード):ダイレクトな反応。高速道路・郊外用。
乗車した時点ではIモードになっている。
よりダイレクトな加速が欲しい時は、走行モードをSモードにする。
モードの切り替えはステアリングに付属のスイッチで行う。
インプレッサやXV、フォレスターなどでも採用されている、スバルの
定番機能だ。
Sモードは飛び道具的な機能ではない。エンジンの持つポテンシャル
をどこでどれだけ引き出すかの違いであり、どちらのモードでも
最大馬力・最大トルクは変わらない。
Sモードにすると、1,500~2,000rpm付近で引き出される馬力とトルクが
Iモードよりも大きくなる。これが出足のリニアな加速感や高速巡航時の
メリハリとなって現れる。
前述のようにゼロ発進時におけるモッサリ感のため、カスタマイズ
する以前は右折時にSモードへ切り替えることが多かった。
カスタマイズ後は通常の街乗りであればSモードの加速は過剰であり、
IモードとSモードの差が縮まったように感じられたため、
Iモードだけでおおむねこと足りるようになった。
代車で借りたアベンシス(直4、2.4L)、試乗したV40(直4、1.6Lターボ)
よりも発進加速がスムーズに行えることが確認できた。
最近、運転免許を取った甥っ子が義兄のプリウスαに乗って遊びに
きた際、VM4を試しに運転してもらったことがある。Iモードのみで
運転したところ、発進から『うわ、すっげースムーズ!」と声を上げて
いたので、低回転域からのトルクは確実に厚くなったようだ。
☆☆後退速度☆☆
後退時の速度は遅い。これは速度制限リミッターがついているため。
バックビューがついているからといって、後方視界は咄嗟の飛び出し
に対して死角が多く、慢心できない。無いよりはあったほうがいい。
リミッターはアクセルを強く踏み込むことで解除される。
☆☆高速道路での走行☆☆
高速道路は、おもに首都高や東京⇔京都間の往復で検証した。
合流時はIモードのままでもすんなり入れることが多いのだが、
Sモードにすればストレスなく入れる。
クルマが増え、速度がそれほど必要ないときはIモード多用。
マークⅡのどこまでも伸ばしたくなる、というほどではないが、
ツーリングアシストを使いつつ80km/hぐらいの巡航をメインに
すれば快適なドライブになる、クルマを操る楽しさは減るが、
疲労と燃費を抑えることができる。
スポーツカーのように走らせたい、という人には勧めない。
実用的な範囲で楽しめる、ぐらいに考えてもらいたい。
☆☆アイサイト☆☆
 |
(プリクラッシュ・ブレーキ)
おもに先行車への追突回避を支援。
運転を邪魔しないため、かなりギリギリの状況で作動する。
ブレーキ操作はなるべくドライバー自身で行うもの、という
前提で設計されているそうだ。
(全車速追従機能付きクルーズコントロール)
高速道路や自動車専用道路で使用する前提で設計されている。
先行車の後を車間距離を保ちながら追従できる。
追従走行の対象にできるのは前方約90m以内の、自車と同じ
車線を走行する先行車。
先行車が急にいなくなったりすると、設定速度まで一気に増速
するので注意が必要。
先行車が減速停車するときの追従ブレーキングは、制動の
タイミングといい、完全停止の瞬間までの加減といい、まるで
人間が制動をかけているようで見事と言うほかない。
筆者のVM4はB型なので、最高速度設定は114km/hまで。
渋滞時には追突を未然に防ぐ強力な助っ人になる。
(車間設定)
車間距離を3段階に設定できるスイッチがあるが、高速道路では
「長」に設定しても、筆者個人としては先行車との距離はやや短いと
感じた。
(アクティブレーンキープ)
クルコンセット中に、車線の中央を走行するようステアリングホイール
の制御をサポートする。ドライバーによるハンドル操作が十分でないと
判断された時、「ハンドルを操作してください」と注意喚起する。
レーンが磨り減っていたりすると認識しないことがある。
(車線逸脱警報)
約40km/h以上で車線から逸脱しそうになると、警報と警告ランプで
知らせる。
(先行車発進お知らせ機能)
信号待ちから先行車が発進して3m離れた時点で自車が発進しない場合、
チャイムが鳴り、お知らせ表示が出る。なかなか親切な機能。
******************
これらの機能は、曲率の大きいカーブや、悪天候、強い逆光などの
悪環境下、先行車の急ブレーキには万全に対応できない場合がある。
状況に応じた危険回避は、やはりドライバーの咄嗟の判断が主であり、
クルーズコントロールは従であると考えるべきだろう。
☆☆操作系インプレッション☆☆
パワステなので軽いのは当然だが、ステアリングの応答性は滑らか。
マークⅡからそう違和感なく乗り換えられた。
ただ純正の本革巻きステアリングは滑りやすく、夏は熱いため、
合成スウェード巻きのステアリングに交換した。
シフトレバーは握りやすく、手にすぐ馴染んだ。
方向指示レバーの使い勝手が良い。スコンスコンと小気味よく入る。
ワンタッチレーンチェンジャーの反応も非常に良い。
欧州車が見習うべき部分だと思う。
ハザードスイッチが中央のエアコン吹き出し口の間にあったのだが、
遠すぎると感じたのでパーキングスイッチパネルをワンオフで製作
してもらい、マルチファンクションスイッチと共に移設した。
ハザードスイッチを撤去した跡の穴は、そのままにしておくわけにも
いかなかったので色々思案した結果、フロアライトアップ・スイッチを
取り付け、マルチファンクションスイッチの跡にはヘッドランプ光軸調整
スイッチを取り付けた。
 |
☆☆燃費☆☆
VM4の場合、カタログ燃費はJC08モードで16.0km/Lとされている。
オーナーの実燃費情報サイト『e燃費』によれば10.55km/L。
みんカラ情報では10.82km/L(レギュラー)10.11km/L(ハイオク)
となっている。
いずれもカタログ値の7掛け、とまでは行かないようだ。
筆者のVM4はトータルで6.2km/L。今のところお財布には厳しい。
ストップ&ゴーの多い街乗り中心の走行という要因もあるのだが、
実はゼロ発進加速時のモッサリ感のあった頃は7.4km/hほどあった。
ガソリンを食うようなカスタマイズを行っていることが主因だろう。
近所の百貨店へ出かけると、往復で5~6km/L程度。
幹線道路中心で近郊との往復だと8~10km/Lまで伸びることもある。
東京⇔京都の旅行では、京都市街での移動も含めて往復で15km/L
まで伸びたことがある。この時はアップダウンの少ない新東名を
中心に走行したので、高速だけなら19km/L程度だった。
マークⅡ時代は街乗りで約7km/L前後、高速に乗って14km/Lまで
伸びたときは「なんて燃費がいいんだ!」と喜んでいたことを思えば、
VM4は巡航が得意なクルマだと言えよう。
☆☆価格☆☆
燃費さえ気にしなければコスパに優れた車。
★★総評★★
荒削りだが色々楽しいスポーティーワゴン。
スバルのラインナップにおいて、技術面ではフラッグシップ
(2014年当時)と言っても過言ではない。
筆者はトヨタのマークⅡから乗り換えたが、はじめは様々な雑味に
戸惑うこともあった。しかしながら、0次安全を重視した設計思想と、
何よりも使いごたえのあるフィーリングに惚れ込んでいった。
新機軸の1.6DIT、安全支援システムのアイサイト、ボディサイズ
(開発陣には悪いが、アイスト機能は評価対象外としておく)、
そして日本の空を護った中島飛行機の流れを汲む富士重工という
開発企業の歴史と伝統、ドラマまでも含めると、これに競合する
他社のクルマは無い、という結論に達した。
脚がやや硬めなことや、ゼロ発進加速の問題はあったものの、
改良によって今は問題なく稼動している。
VM4と共にあること5年。街で見かける他社製のクルマを見ると、
所有欲よりもまず、そのクルマの性能や特徴、そしてそのクルマが
世に出されるに至った開発理念を知りたい欲求に駆られる。
近い将来、日本でもEV化の波が押し寄せることになるだろう。
この波は、高性能な日本車潰しという国際政治的なパワーも働く
一種の災厄なので、どう足掻いても避けられない。
2030年に内燃機関の自動車がどうなるのか、筆者は予測する術を
持たないが、自動運転技術の発達と密接に関係するはずだ。
自動運転と相性がいいのは、制御が容易で、かつ部品点数も少なく
保守点検が簡便なEVであろう。さまざまな利権構造があるにせよ、
交通環境は合理的な方向へ進むと思う。
EVは構造的に新規参入のハードルが低く、内燃機関方式の自動車
を生産することによって市場に君臨してきた既存の自動車メーカーは
絶対的な優位性を失うかも知れない。
スバルのアイデンティティとも言える水平対向エンジンも、EV化
という歴史の砂に埋もれ行く宿命なのかも知れないが、筆者の見解
では、ユーザーから必要とされることこそが最良の評価だ。
航空機の動力がレシプロエンジンからジェットエンジンに進化した
ように、自動車のパワートレインも、時代の要請に応じた進化を
遂げることで、また新たな市場競争の土俵に立つことができる。
仮にレヴォーグがEV化したとしても、快適なドライビングを実現
できれば、レガシィ時代から続く大いなる遺産も継承されるだろう。
新たに参入してくるであろう、EV用のパワートレイン開発技術を持つ
企業と共同開発する手もあるだろうし、さらに言えば航空・宇宙産業
に本腰を入れるのも面白い。
アメリカをはじめとする海外列強が保有する、いかなる航空機をも
凌駕する次世代戦闘機を開発するもよし、世界が驚嘆するような
宇宙戦闘機を開発するもよし。
中島飛行機の流れであるスバルには、時代の波に呑まれたり、
晒されたりするのではなく、波動そのものとなることを期待する。
まだ当分の間はガソリン車を楽しむ時代が続きそうだ。
VM4を駆って、安全運転の修行をしばらく続けることにする。
★★カスタマイズ★★
ゼロ発進加速時のモッサリ感を解決するにあたり、当時タキオンの
サポートメンバーとしてドラムスを担当してくれていたオガワさんに
相談した。オガワさんはメーカー出身で、自動車整備士の免許も
持つ。そのクルマ人としての見地から次のように具体的なアドバイスを
与えてくれた。
「まずエアクリーナーを交換してください。
次にエンジンオイル、いいやつを入れてください。
最後にハイオクを入れてください。
あとはアクセルを踏み込むだけです。」
幸か不幸かこのアドバイスが的確だったので、筆者は
カスタマイズに勤しむこととなった。
時機も得ていたのだろう、スバル車はアフターパーツを開発する
企業が多く、このレヴォーグもカスタムパーツのバリエーションが
実に豊富だった。
ただしスーパーオートバックス東雲店のスタッフさんの話では、
FB16エンジンはすでに完成されたエンジンであり、燃費重視で、
パワーアップの余地はあまり無いそうだ。
以下に挙げるカスタマイズの例は、いずれもVM4向けのものだが、
純正車がカスタマイズに対してどれだけ安全マージンを取っているか
の検証がなされたわけではないことを明記しておく。
また、その効果については筆者の主観的な評価がメインであり、
具体的な数値については、同一のカスタマイズを施工したからといって
必ずしも同一の結果となる保証は無いことをお断りしておく。
【吸気系】
(1.エアクリーナーエレメント交換)
オガワさんのアドバイスによるカスタマイズ着手の端緒。
STI製の通気抵抗の低いものに交換した。
(ケース継ぎ目から見える赤いフチがエアクリ)
(2.エアインダクション交換)
純正のエアインテーク、エアクリーナーロアケース、レゾネーターを
カーボンで一体成型したSyms製のものに交換した。
トルクが1~2kgmほどアップするらしい。
(3.インダクションホース交換)
純正のホースは蛇腹状なので、吸入抵抗を減らすためSAMCO製の
ものへ交換した。
(4.エアインテークパイプ交換)
ターボチャージャーとインタークーラーを繋ぐ純正インテークパイプは
スバル社内共用品のため途中に凹みがある。流入効率の良さそうな
アルミ製のものへ交換した。
(5.シュラウド交換)
熱されていない外気をなるべく多くインテークへ導くために、
ラムエアトレイ(5-1)とセット品のスマートフロウシュラウドへ交換した。
1 |
2 |
3-1  |
3-2  |
3-3 |
4 |
5-1 |
5-2 |
【排気系】
(6.マフラー交換)
常用・低速域でのトルクアップを目標としたので、排圧を適度につけながら
騒音を極力抑える必要があった。そこで、スバル直営店と取引があり、
トルクアップに定評のあるガナドールのチタンマフラーへ交換。
センターまで交換すると低速がスカスカになるため、リアピースのみ。
JQR認証製品。
2,700rpm付近でノーマルよりも8.5kgmトルクが太くなるらしい。
6-1 |
6-2 |
【冷却系】
(7.クーラントホース交換)
新車購入時からエンジンルーム内の熱の篭りが気になっていたので
クーラントホースを定評のあるSAMCO製に交換。効果を体感することは
困難かも知れないが、純正よりも耐久性に優れている安心感がある。
7-1 |
7-2 |
7-3 |
(8.フロントフェンダー・インナーカバー交換)
フロントフェンダー・インナーカバーをグリル穴のあるカーボン製の
エア・アウトレットダクトへ交換。ただしデッドニングのウレタンが
フェンダー内側に詰め込んであるので、効果のほどは疑問。
(8-2が交換前のインナーカバー)
8-1 |
8-2 |
【足回り・補強パーツ】
(9.リフトスプリング)
アルミホイールを8jのものへ交換した代償としてロードノイズや
突き上げが増えたため、硬さを損なわない程度で乗り心地を
改善させるためにPROVAのリフトスプリングへ交換。
効果は非常に高く、アイサイトにも影響はない。ただし車高が
わずかに高くなり、高速道路で横風の影響を受けやすくなった。
また、外観上はSUVっぽく見えてしまう。
9-1 |
9-2 |
(10.ボディダンパー)
突き上げやロードノイズの軽減を目的に装着。
ヤマハ発動機で開発されたものを欧州車向けパーツチューナーの
COXが車種別に専用設計し、Symsが販売している。
装着した当初は車体が真っ直ぐにすっ飛んでいくような感覚を
覚えたように思うが、これもタイヤの空気圧調整が手伝ってのこと
なのかも知れない。気になる揺り返しや微振動は減ったように感じる。
10-1 |
10-2 |
(11.フレキシブル・タワーバー)
リフトスプリングに交換した代償として柔らかくなり過ぎた操舵感を
戻し、コーナー終了後の不自然な揺り返しを軽減させる目的で
STI製のタワーバーを装着。下段の赤いSTI製バッテリーホルダーは
タワーバーとお揃いでつけてもらった。
(12.フレキシブル・ドロースティフナー)
揺り返しのさらなる軽減を目的に装着。操舵感は気持ち良くなった。
クロスメンバーの動きを抑制する働きがあるらしい。
11 |
12 |
 |
【その他エンジンルーム】
(13.カバー類の交換)
ドレスアップ効果が目的だが、エアインテイクやダクト類が
カーボン製になったので、統一感を出す目的でエンジンカバーや
ヒューズボックス、リレーボックスもドライカーボン製のものに交換した。
13-1 |
13-2 |
13-3 |
13-4 |
【アメニティ】
(14.フットレストバー装着)
オートクルーズ時に右足をブレーキに添え続ける姿勢が多いことから、
軸足の左足をシンメトリーにすることで疲労軽減を狙って装着。
素材はジュラルミンで、チタンコーティングが施されている。
(15.マットプロテクター装着)
フットレストバー装着に伴い、左足の収まりを良くする目的で同時に
装着。レヴォーグ専用ではないのでフィット感はイマイチだが、左足の
収まりは良くなった。ブラックアルマイトの材質に水圧転写でカーボン調に
してある。
14 |
15 |
【ECU】
スバル直営店からユーザーに対し、リプロを勧めることはほとんど
無いそうだが、こちらから申し出れば最新のデータへリプロしてくれる。
VM4の場合は法定6ヶ月点検の際、購入時のAJ992から993へ、
12ヶ月点検の際にはAJ996へ書き換えた。緩加速発進を改善する
リプロで、2,500rpm近辺ならほとんどの先行車に追随できるように
なった。
【音響】
 |
VM4に乗り始めて3ヶ月ほど経った頃だろうか。サポートメンバーの
オガワさんに「新車でカーオーディオをやってみようと思う」と話したら、
「シゲさん。カーオーディオは泥沼ですよ。」と諭された。
「何を言うか、あめいぬさんに師事し、実験君で鍛えた俺の耳で
最高のカーオーディオを一発で仕上げてやる」と内心意気込んだが、
先人の声には耳を傾けるものだ。
詳細は冗長になるため割愛する。
クルマのカーオーディオは、適切な方法を採ればどんどん音が
良くなるポテンシャルを秘めている。
ただ、やり過ぎて目的と合致しない方法を採った瞬間、音は
悪いほうへガラリと変わる。
音楽にはさまざまなジャンルがあり、曲にはさまざまな表情がある。
それらを一つのユニットで聴く以上、最大公約数的なセッティングに
する必要が出てくる。
そのセッティングをどの程度のレベルで妥協するかにもよるが、
求めすぎると果てしの無い試行錯誤の泥沼となるのだろう。
今思えば、純正スピーカーはどんなジャンルの音楽でもフラットに
聴かせる、公平なシステムだった。
(16.フロアデッドニング)
購入初期にアルミホイールを交換してからロードノイズが気になり、
静音化のために施工。一般道で平均2dBは減った。少し静かに
なったものの、音質は硬くなった。
(17.発泡ウレタン注入)
同じくロードノイズ対策。
ピラーおよびメインフレーム内部に発泡ウレタンを注入した。
頭付近で渦巻く邪魔な周波数帯域を抑制することができたが、
JBLの音の潤いが減った。
(18.タイヤハウスデッドニング)
低音ロードノイズの低減を狙ってショップで施工してもらった。
フェンダー外板内面(18-1)、フェンダーと車体の内部構造材との
クリアランスに難燃性ウレタン詰め込み(18-2)、フェンダーライナー
表面(18-3)、フェンダーライナーの内面にノイズ・レデューサーを
吹き付けた(18-4)。
高速道路でのロードノイズが多少減った。
(19.スピーカー交換)
スバル川口でソニックデザインのデモをやっていたので聴きに行ったが
中低域に迫力がなく、余計なアンビエンス感で期待したほどではなかっ
たので、カオデショップの店長さんに相談した。
サブウーファー無しでジャズヴォーカルも行ける音を、ということで
JBLの670GTiに交換した。青色LEDでライトアップ可能。
デッドニングが過剰になり、音の潤いが減った後でバイアンプ接続へ
変更した。
(20.サテライトスピーカー)
カロッツェリアのTS-STH700。無指向性で音場空間を作り出す、という
謳い文句に加えて、LEDイルミネーションに惹かれた。
これを単体で聴くと、シャカシャカした小さな音が鳴ってる、ぐらいにしか
感じないが、フロントスピーカーとのセットで聴くと、あるのと無いのとでは
かなり違う。
(21.アンプ)
デッドニングが過剰になったせいか音質が締まりすぎたので、ショップに
相談して選んでもらった。ナビヘッドユニットに見合うコンパクトなものを、
ということでMOSCONIのONE80.4にした。右側は670GTiのネットワーク。
デッドニングがドアだけなら必要なかった。
16 |
17 |
18-1 |
18-2 |
18-3 |
18-4 |
19 |
20 |
21 |
【パワーチェック】
2018年1月のことなので、やや古い情報になるが、スーパーオートバックス
東雲店でパワーチェックを行った。この東雲店はオートバックス旗艦店で、
スバル車を得意とする。インダクションホースやシュラウド交換前の状態だが
参考までにアップしておこう。
レヴォーグはAWDなので牽引フックは前後2本の準備が必要となる。
また、スタッドレスタイヤ装着車はチェックできない。ローラーからすっ飛ん
で大事故に繋がる恐れがあるそうだ。
Iモード、Sモードの両方をチェックした。誤差の範囲内かも知れないが、
最大馬力、最大トルクともにIモードで記録したのが興味深い。
 |
|
||||||
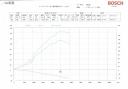 |
 |
 |
【性能諸元(LEVORG 1.6GT-S:DBA-VM4)】
(カッコ内は筆者カスタマイズ後の数値)
全長:4,695 ㎜
全幅:1,780 ㎜(1,796 ㎜)
全高:1,500 ㎜(1,515 ㎜)
ホイルベース:2,650 ㎜
最低地上高:130 ㎜(145 ㎜)
トランスミッション:CVT(リニアトロニック)
駆動方式:フルタイム4 WD
エンジン:水平対向4 気筒DOHC16 バルブ
直噴ターボ
総排気量:1,599 cc
最高出力:170 PS/4,800~5,600 rpm
(203.5 PS/5,060 rpm)
最大トルク:25.5 kgm/1,800 ~ 4,800 rpm
(31.2 kgm/3,860 rpm)
使用燃料:無鉛レギュラーガソリン(無鉛ハイオクガソリン)
燃料タンク容量:60 リットル
ステアリング形式:パワーアシスト付ラック&ピニオン
サスペンション形式(前):ストラット式独立懸架
サスペンション形式(後):ダブルウィッシュボーン式独立懸架
ブレーキ形式(前):ベンチレーテッドディスク
ブレーキ形式(後):ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前):225/45/R18(235/45/R18)
タイヤサイズ(後):225/45/R18(235/45/R18)
最小回転半径:5.5 m
車両重量:1,550 kg
乗車定員数:5 人
価格:3,056,400 円(2015年8月当時)
クルマのこと
INDEX



