

  |
●マイコンの波とテレビゲームの融合 |
1982 昭和57年 |
 78年にシャープが発売したMZ―80、79年にNECが発売したPC―8001。次代を担う商品と注目されていたパーソナル(個人的)なコンピュータの売れ行きは、80年代に入り、静かに、しかし着実に右肩上がりを続けていました。やがて、ソニー、東芝、富士通、松下と、日本の大手家電のほとんどすべてが業界に参入し、専門誌も多数創刊され、本格的な情報社会の到来を予感させていました。
78年にシャープが発売したMZ―80、79年にNECが発売したPC―8001。次代を担う商品と注目されていたパーソナル(個人的)なコンピュータの売れ行きは、80年代に入り、静かに、しかし着実に右肩上がりを続けていました。やがて、ソニー、東芝、富士通、松下と、日本の大手家電のほとんどすべてが業界に参入し、専門誌も多数創刊され、本格的な情報社会の到来を予感させていました。そしてテレビゲームもまた、メモリの量、キーボードの有無に違いこそあれ、その本流はまさにコンピュータそのものなのですから、この流れに無関係ではありませんでした。 82年は、このようなホビーコンピュータを意識したテレビゲーム、もしくはホビーコンピュータをゲームにも使おうというマシンが登場し始めたターニングポイントとでも言うべき年です。トミーのぴゅう太、技術のソードとタカラが組んだゲームパソコンm5、限りなくビデオゲームに近いコンセプトのパソコンである、コモドールジャパンのマックスマシーンなどです。 もう一つの流れとして、今までの純テレビゲーム路線にも変化が現れました。売れ筋の悪さはハードの弱さにあったと見たのか、海外から高性能ビデオゲームを輸入・販売するという流れです。強力な提携を結んだ米・マテル社からインテレビジョンを招いたのはバンダイ、ビデオパック規格という規格を採用したオデッセィ2を発売したのは河田、その他、香港製のエクセラなど、様々な高級機種が登場したのです。 マイコンブームの追い風と、カセットビジョンの好調さに続けとばかりに、この年から再びテレビゲーム市場が燃えてきました。第二次テレビゲームブームの幕開けです! ところで、当時の日本経済新聞(同右)は次のような興味深いレポートが載っていました。 「日本のテレビゲームがどう発展していくか―この点について、業界の見方は二つある。一つは『二、三万円のテレビゲームがまず中心となり、その後、パソコンゲームに消費者の目が向いていく』というテレビゲーム派で、もう一つは『単なるテレビゲームでは日本の消費者は飛びつかない。価格は高くても、パソコンとして使えなければダメ』とみるパソコンゲーム派で、タカラやトミーがこうした見方をとる。そんななかで問屋、小売店を含めて業界関係者が一様に強調しているのは。『結局は、ゲームソフトの開発が勝負のきめ手になる』という点だ。」 |
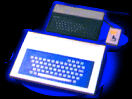 ぴゅう太/ゲームパソコン (トミー/ソード・タカラ) 第二次ブームの火蓋を切ったゲーム系パソコンの代表選手。少年少女のクリエィティブな感性を作品にするぴゅう太、10万円台パソコンすら凌駕する機能とナムコゲームをひっさげて登場したm5。続々と登場するクールなマシンに子供達の心は高鳴りました。  「大型新人」家庭用テレビゲーム パソコン機能で”実力”競う (日本経済新聞夕刊'83/2/5) 82年おもちゃショーで”ハットリくんも自在に描ける”とぴゅう太の前に人だかりができた現象を前口上。がん具業界の開発ブームの様子をレポートしています。 |