
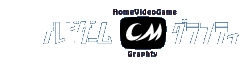
 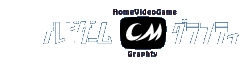 |
| ファミコンの普及により、世間に家庭用テレビゲームというものが認知されるようになり、HowToモノで一から説明する必要もなくなり始めた頃、任天堂CMはイメージ重視の演出へとコマを進めて行きます。所ジョージと間下このみを起用したゼルダの伝説、中山美穂のときめきハイスクールあたりから必然的に人気タレントを起用。ファミコンウォーズ&ファイヤーエンブレムといった、耳に残る印象CM。そして、話題になったスチャダラパーのヒップホップ:ゼルダの伝説(神々のトライフォース)、天下の糸井重里を起用したMOTHERなど、質も認知度も高い”名作”と呼ばれるCMを次々と生み出していきました。 各ソフト会社もCM制作に積極的に乗り出しました。何しろ、ファミコンソフトを発売するには巨大な契約料を任天堂に支払わなければいけませんでしたから、強力に売上を伸ばす手段としてTV-CMが盛んに用いられたのです。 87〜88年には、NEC-HEのPCエンジンやセガ・メガドライブが発売され、NECは主力商品である家電方向から、AVライクという切り口を示し、セガはタレントのいとうせいこうを起用するも、これまた過度にイメージに頼ることなく基本に忠実な路線を守るなど、それぞれが独自の方針でCMを制作しました。 90年代をまたぎ、市場が大きくなると、それにつれてCMの規模や本数も増えていき、さまざまな試みが打ち出されていくも、どれも基本的には今までの路線の延長上にあるものでした。そう、プレステが登場するまで・・・。  2003年の現在、SCE・プレステは冒頭にあげた独自路線を、任天堂ゲームキューブはどちらかと言えばベーシックなスタイルに戻ったような感じで展開されていますね(X-BOXはCM自体がめっきり減ってしまいました・・・)。やがてCMの舞台はテレビにとどまらず、ケータイなどにの別メディアなどに配信されていくようになるでしょう。また、新しいハードの登場にあわせて、プレステとは全く違う切り口のCMスタイルが、今後確立されていくと思われます。 2003年の現在、SCE・プレステは冒頭にあげた独自路線を、任天堂ゲームキューブはどちらかと言えばベーシックなスタイルに戻ったような感じで展開されていますね(X-BOXはCM自体がめっきり減ってしまいました・・・)。やがてCMの舞台はテレビにとどまらず、ケータイなどにの別メディアなどに配信されていくようになるでしょう。また、新しいハードの登場にあわせて、プレステとは全く違う切り口のCMスタイルが、今後確立されていくと思われます。しかし、CMの原点は 「この商品はこんなに優れているんですよ!」ということの伝達。ゲームなら「このゲームはこんなに楽しいんですよ!」というものが原点。これだけはいつまでたっても変わらないでしょう。ゲームがつまらなければCMだってきっとつまらないはず。そう、CM製作会社のスタッフの方々は、昔の方がそうしていたように、コピーライトよりもまずそのゲームソフトを徹底的にプレイし、魅力をたたきこんでから企画にとりくんでいただきたいものですね! |