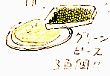青木タカオの「ちょっくら・おん・まい・でいず」 TOPに戻る
過去ログ「 ケララ・エピソード」'03.11月〜'04.2月vol.1「はじまり」11/18
・・走りながら、椰子の木に登る人。
2003年10月。ふと付けたテレビからの、ひとつの声が僕をとらえた。
「ここ南インドのケララ州コーチンでは、、」
(ああ、懐かしいなぁ、ケララ州コーチンじゃないか・・)。そこに僕は15年ほど前に、少しの間居たことがあるのだ。
緑豊かな村の道を走る人を、日本人のレポーターが一緒に追いかけていった。そして彼は一本の椰子の木にスルスルと登ってゆき、椰子の実をふたつみっつ地面に落とした。
「これは、俺の椰子の木なんだ。のどが乾くと、いつもここに来るんだよ!!」
そして切った椰子の実ジュースを美味しそうに飲み、わけてあげる彼。
また、別のシーンでは、船による漁業が映し出された。イワシの群を見つけたとたん、ひとり男が船から海に自分からおもいきり何度も飛び落ちていた。それはイルカから、イワシを守るために音でおどしているのだという。
バシャーン!!
船から大きく飛び、何度もそれを繰り返す彼がいた。
その姿は、なんとも嬉しそうにも見えた。
僕の中で、しばらく忘れかけていた、南インド・ケララ州でのいろんな出来事がよみがえってきた。僕が出会った旅と同じように、テレビのレポーターもまた、出会っているようだ。それはひとつの統一された、何か大きな話のような気がした。
『ケララ・エピソード』
僕はそのタイトルで、ひとつの作品を作ろうと決めた。僕の出会った南インドでの話を書こう。
そこには何かがあるにちがいない。それは何かは、まだわからないが。。
vol.2「バラナシのサシー・1」11/21
さあ、行こう。この話は、北インドのバラナシから始まる。
今は1987年11月。中国、チベット、ネパールと抜けて来て、国境越えのバスで、僕はやっと念願のインドに入った。
11月のインドはまだ暑いけれど、過ごしやすい季節だ。一泊200円前後のガンジス河沿いの宿に、僕は旅のリュックをおろした。小さな部屋の壁は白く、天井では大きなプロペラファンがゆっくりと回っている。僕は約ひと月、ここバラナシで過ごそうと決めていた。
一泊200円の宿と言っても、外見はしっかりしたビルであり、長期旅行者にはなかなかにのんびりとできるゲストハウスだった。どの宿でもそうだったけれど、一階はレストランになっており、僕の宿にも「EAST WEST RESTRANT 」と言う、まあ喫茶店、兼、食事処と言った感じのスペースがあった。
「ハロー」
香辛料の香り漂う中、僕もまたレストランを入ってゆくと、小さな机を前にして、褐色の肌のクルクルと髪のまるまった小柄な男性が、挨拶をしてくれ
た。
「ハロー、ジャパニ!! ホワッドゥユ・ウオント?」
人なつこそうな笑顔の彼は、どこか僕の小中学生時代の友人のようなイメージがあり、ひと目あったときから、なんだか他人のような気がしなかった。僕がそんな懐かしそうな目をしたせいもあるのだろう、なんだか一瞬にして友達になれた気がしたのだ。
いろんな国の旅行者たちが、テーブルでは食事をしていた。僕はフランスのお姉さんの瞳に吸い込まれそうな気持ちになりながら、たぶんフライドライスか何かを食べていただろう。
受付の彼が、厨房の方に行き何か話していた。その後、その中のひとりがわざわざ新しく来た僕の顔を見に来たのだった。そして言った。
「グッド・ジャパニーズ!!」
僕はいい顔をした旅行者との事だ。受付の彼と一緒に「グッド・グッド」とうなずきあっていた。どうやら気に入ってくれたらしい。
(ぼくも気にいったよ・・)
受付の彼の名前は「サシー」。南インドのケララ州の出身であることは、後で知ることとなる。
サシーは、なんとも最初から懐かしい男だった。
vol.3「バラナシのサシー・2」11/24
ホテル裏手にあるゴールデンテンプルの歌声で、毎朝起きていたインド・バラナシの日々。
ガンガー(ガンジス河)が沐浴でにぎわっている頃、僕はまたゆっくりと、ホテル一階の「EAST WEST RESTRANT」に向かう。
ルンギと呼ばれる、大きな布をいつも腰に巻いているサシーが、入口では待っている。
「ハロー、グッドモーニン」
「ハロー、ホワッドゥユ・ウオント?」
「チキンカリー、ヨーグルト、チャイ、・・フィニッシュ」
「オーケー、チキンカリー、ヨーグルト、チャイ、アンド、フィニッシュ!!」
仲良くなったサシーと、こんな小さなジョークが毎朝くりかえされた。まるで小学校時代の友達のようだ。
あるときのこと、僕がインドのガイドブックを持ってゆくと、サシーが本を見せて欲しいという。調理場の友達と一緒に写真を指さし眺めては、何やら嬉しそうだった。
折り込みのインドマップを広げて、サシーは、ひとつの場所を指さした。
「ヒア・リズ・グッド!! ケーララ、アイム・フロム・ケーララ」「リリー?」
「ユール・ゴ・トゥ・ケーララ、ベリベリグッド!!」
聞けば、サシーは数年に一度、故郷のケララ州に帰っているのだという。そしてここのホテルのマスター、ビンドー氏がケララ州出身なのだとも教えてくれた。
◇ サシーはいつも穏やかに笑っていて、鼻歌を歌いながら片付けをしたりしていた。
「♪ンーナパッカ・ンーナパッカ・・」
その響きはなんとも、はるばるとしたリズムとメロディーであり、心奪われるものだった。
「サシー、ホワッツ・ズィス・ソング? 」
「ズィスソング? マイ・カンリョーリーソング、ケーララ!!」
僕にはサシーの鼻歌の中に、揺れる椰子の木の群が見えるようだった。仲良くなったサシーと、鼻歌の中にあった響きを信じてみよう。
南インド・ケララ州。その言葉のカードは僕の胸の中に、しっかりとしまわれた。
vol.4「バラナシのサシー・3」11/27
ネパールから入ってきて、初めてのインドでの場所であるバラナシに来てから、もうすぐ三週間になろうとしていた。
ここで充分に生活や習慣に慣れてから、インド中を巡ろうと思ったのだ。
泊まっている小さなホテルのみんなとも、とても仲よくなった。レストラン受付のサシー、そしてマスターのビンドー氏。ヒンドー氏は背が高く、四角
いセルロンドのメガネをかけ、白髪まじりの初老のおじさんだ。ホテルの入口の奥にいつもいた。
午後には、甘いお菓子をほおばり、とても美味しそうな表情をする。僕にもひとつ分けてくれたときもあった。
僕が甘すぎて食べられないよって顔をすると、ビンドー氏は、ほうばりながら嬉しそうに言った。
「ズィス・イズ・ベリベリスイーット!! バット・イッツグット!! グッチュ!!」
そんなビンドー氏は、サシーと同じケララ州から来た人であるという。そして僕のことを気に入っているという話をきいた。よく目と目が会い、ビンドー氏は、無言で微笑んでいた。
もうすぐ、次の町に移動しようかな思っていた頃、ビンドー氏が僕に、屋上に来て欲しいといい、そしてこう言ってくれた。
「私は、おまえのことが気に入っている。おまえは特別な旅行者だ。来年の二月、私は故郷のケララ州に帰る。ケララはとてもいいところだ。そのとき一緒にケララに行かないか?」
夜だったか、夕方だったかは忘れてしまったが、ビンドー氏のインド服「クルタ・パジャマ」が、風に揺れていたのを憶えている。僕自身ケララ州には行く予定だったが、さすがに2月までは待てなかった。丁寧に断ると、ビンドー氏はとてもさびしそうな表情をした。
◇◇
そしていよいよ、バラナシを出る日がやって来た。僕はその日の夜明け前に起きて、ガンガー(ガンジス河)に沐浴をしに出かけた。まだホテルの人も全員寝ている時間だ。前の日から伝えてあったので、声をかけると一番仲のいい、キッチンの人が眠そうにしがらも、ばっと飛び起きてくれて、入口の鍵を開けてくれた。
「ノー・プロブレム、ノー・プロブレム、ガンガー・グッチュ!!」
夜明け前のガンガーに入ってみる。水温は思ったよりもあたたかった。川砂は意外と柔らかい。岸の向こうで、登ってくるオレンジの朝日。僕なりの沐浴はけっこう満ちた気持ちになれた。
ホテルに戻り、荷造りをし、そして僕はバラナシを出発する準備をした。次の町は、東のカルカッタ。カルカッタは都会だし、人も違うし、いろんな週間も違うだろう。さて、僕はまた出かけることにしよう。
いつもどうりにレストランでのサシーとのジョーク混じりの会話のあと、しみじみと食事をする。ここに来た日のことが思い出される。サシーとはも本当に仲良くなれた。気が合うというのはこのことだろう。中学時代、他の学校の同じクラブの人と仲良くなったような感覚と似ている。なんだかとても愛しいのだ。
ほぼひと月滞在したホテルを出てゆくのは、なんともつらい。しかし、ここは「また来るよ」と、サラリと出たほうがいいだろう。
旅のリュックを手に持ち、僕は一階へと降りてゆく、マスターのビンドー氏は僕に言う。
「おまえのフォトを一枚、私に置いてって欲しい。何か思い出すものが欲しいのだ」
僕はパスポート用の写真を一枚、渡した。そして、靴をはいたところで、レストランの受付のサシーが、いつもどうりのブルーの布を腰に巻いた姿で、やって来た。
「グッド・ジャーニー!!」
「シー・ユー・サシー!!」
今回の旅に出て、こんなにせつない気持ちになったのは、はじめてだった。たぶん、もう会えないことは、お互いによく知っているのだ。しかし、この宿に来たという偶然に感謝する気持ちで、いっばいだった。別れよりも、嬉しい気持ちの方が強い。
ケララ州から来たという、サシー、そしてマスターのビンドー氏。僕にはなんだか、ふたりがとても身近に感じられた。それはケララという土地柄によるものなのかもしれない。
そんなことを思いながら、またバラナシの細い路地を抜けて行った。町中のスピーカーから流れる、テンプルのリズミックな説教話。始めはうるさかったけれど、だんだん気持ちいい音になっていった。
さよなら、サシー。もちろん、僕はケララには行くよ。
vol.5「コーチンまで」11/30
インドのバラナシにひと月ほど居たあと、僕は東のカルカッタへと向かった。
カルカッタは話に聞いていたとおりの大きな街であり、服装も都会風。どこに行っても活気があり、顔もバラナシの人とは違っていた。
(そうかあ、印象がまるで違うなぁ・・)
思い返せばバラナシは宗教色の強い町だったと、カルカッタに来て気付くことが出来た。
(インドは広いな。。) そう、実感した僕は、それから10日から二週間をめどに、次の町へ進むことにした。しばらく留まらないと、その町が見えてこないなと思えたからだ。
移動は夜行の寝台に乗り、次の朝には着いているというパターンになった。一晩たって、また町に降りたってみると、またちがう顔を持つインドがそこに待
っていた。
カルカッタのすぐ下の港町プリーでは、のんびりとした浜道バザールと漁師たちが迎えてくれた。宿の人たちは気さくで優しかったけれど、フッシャーマンビレッジには、僕はどこか入れないものも感じた。
インド中央の「ハイデラバード」はイスラムの町で、どこに行ってもに親切にされた。そこは今までのどの町ともちがっていた。町にはコーランが流れ、僕にとっては初めてのイスラム世界の体験となった。
西のマドラスでは、小さなな町工場が多く、ふと入り込んだ路地で、金叩きを続けるみんなの思いがけない歓迎にあった。それは本当に嬉しかった。
そしていよいよ南インドへ向かうときが来た。いつもどうりの寝台列車に乗り込む。バラナシで出会ったサシーの故郷ケララ州へ、明日の朝には着いているのだ。
ケララ州は一年を通して暖かく、大変に過ごしやすいのだという。タミル系の人たちなので、肌の色も褐色だろう。食堂では、お皿の代わりにバナナの葉が出されるとも言う。そしてクリスチャンの人たちがとても多いとも聞いた。
南インドの西側、コーチンはどんな町なのか。そこで僕は、ぜったいにゆっくりしよう。聞いた話では、コーヒーもあるという。バラナシのサシー、そしてホテルのビンドー氏に誘われた、憧れの南インド。憧れのコーチン。椰子とバナナの葉が待っている水の豊かな土地へ、真夜中の列車は向かっていた。
(ジャングルみたいなのかな・・)
しかし、そこがどんな所なのかは、着いてみるまでわからないことも知っていた。
vol.6「ハロー、コーチン」12/4
車中で知り合ったマレーシアのおじさんに何度も手を振ったあと、僕は南インド・ケララ州、コーチンの町へと歩き出した。
椰子の木に囲まれたイメージを持っていたけれど、実際は商店街が長く続いた大きめな町だった。冬だというのにおだやかなあたたかさで、それは聞いていたとうりだった。
めどをつけていた安宿はどこも満室で、結局少し高かったけれどシャワー付きのシングルに決めた。今までで一番にぜいたくな部屋だ。ベッドの上にリュックを降ろして一休み。
憧れのコーチン。まだ普通の町の印象しかないけれど、さてどんな旅が待っているんだろう。ホテルの窓の外からは暖かな陽がさしていた。思えば、シャワー付きの部屋になったなんて、これが初めて。さて、のんびりとしよう。
壁には木製の有線ラジオがつけられてあった。スイッチを入れてみると、インドミュージックが流れてくる。10チャンネルくらいあったと思う。どのチャンネルも同じようなインドミュージックなので、僕はクスッと笑ってしまった。
宿からすぐの大通りの商店街へと散歩に出かけると、なんだろう、多くの人に「ハロー」と声をかけられた。アイスクリーム屋のおじさんも、宿の前の屋台のお兄さんも、道ですれちがう人もみな、気軽に僕に「ハロー」と挨拶をしてくれるのだ。こんな町はいままでになかった。
ほとんどの町での「ハロー」は、どこか何か商売の響きがあったけれど、ここコーチンでは「ようこそ」よりももっと軽い感じがした。
なんというか、それは始まりのある響き。
夕食には、まだ少し早い時間、宿の近くのレストランに、コーチンで初めての食事をするために入った。そこは大きな掘っ建て小屋みたいなところで、下には土が見えていた。大きな木のテーブルが、広々といくつも並ぶレストラン。
そのひとつの椅子に座り、僕はベジタブルカレーを注文した。
「イエース、ベジタブルカリー」
そして、出てきたカレーは、なんとグリーンピースが山盛りのプレートだった。
(うわっ!!)
まあ、考えてみればこれもベジタブルなわけで、食べれないことはもちろんない。それにしてもこんなにグリーンピースを食べるのは初めてだ。
レストランの人は僕が気になる様子で、こっちを見ている。僕は変な顔も出来いし、半笑い答える。
ひろいレストランで、一人グリーンピースカレーを食べた夕方。
そしてまたホテルに帰り、倒れるように横になりゆっくりと休んだ。
(次はチキンカレーだ・・)
壁の有線ラジオからはインドミュージックが流れてる。ハロー、コーチン。
vol.7「ギターを買った渡り鳥」12/7
コーチン二日目の朝もまた、僕は懐かしい人の夢を見て目が覚めてしまった。
不思議なのは、懐かしい人の夢を見ると、自然と朝、心が落ち着いているのだった。
(僕は今、淋しいんだな・・)
ノートを出して、ずっと休んでいた歌の作詞を、また僕は書いてみた。
そんなふうに始まったコーチン二日目。いい天気だし今日もまた、あちこち街を歩き回ってみよう。
冬だというのに、南インドは昼は暑いくらい。相変わらず町の人は、「ハローハロー」と声をかけてくれる。ずっと続いている商店街は雑多な感じがなく、生活の豊かさを感じられた。驚いたことは、外国製のものは少なく、ほとんどのものは、MADE IN INDIA ということだった。
そんな商店街の先、僕は一軒の店の前で動けなくなってしまった。
(楽器屋だ・・)
ショーウインドーから眺めてみると、バイオリンが主に壁に掛けられてあったが、まったくそれと同じ色あいで、ギターもまた飾られてあった。それも、
普通サイズから、小さいサイズまでそろって。。まるでバイオリンギターのようだ。
ためらうことなく中に入り、その一番小さなギターを見ると、感動するくらいに完璧な旅のギターだった。ボディの厚みは5センチほどで、見るからに軽そうだ。ため息まじりで僕は、かっぷくのいいお店の人に見せてもらった。下の弦を止めるところも調整できるようになっていて、音程もばっちりだった。
たぶん、バイオリンのような感覚で作っているのだろう。値段をきけば、400Rs('86年で約4000円)。インドでの買い物としたらかなり高い。でも今の僕の財布では400Rs には足りない。しかし欲しい・・。しかし旅の荷物に・・。しかし欲しい。
「アイ・ウオント・バイ・ズィスギタール!!」
しかし財布の中には、360Rsしかなく、これしか払えないということを伝えた。
「オーケー」・・ああ、買っちゃった。。
小さなビニールのギターケースに入れてもらい、そのままコーチンの町を歩いてゆくと、なんだかみんな可笑しそうにしている。ギターを持っている姿は変に映るのかな。
(ああ、買っちゃったよ・・)その言葉を心でくり返しながら、ホテルに戻って来た。この先の旅に大きな荷物が増えてしまった。これで良かったのか。しかしこの先の旅が変わると信じよう。
ちょっと弾いてみると、心にしみるように嬉しい。指のまた喜んでいるようだ。
財布の中には、4Rsしか残っていなかった。土日なので、銀行で両替することもできない。食事はどうしよう。
(まあ、ギター弾いてればいいか、、)
理屈はおかしい。でも僕はそのとき本当にそう思った。
vol.8「パン屋の兄さん、ジュース屋の娘さん」12/11
ギターを買って嬉しかったけれど、財布の中には、土日で4Rsしかなかった。
月曜、銀行が開くまでの二日間、さて、お腹はなんとかなるだろうか。まず僕は、泊まっているホテルのすぐ近くの露店に行き4Rsで、バナナを10本買った。約40円。
「これがランチ・アンド・ディナーだよ」と、冗談半分で、露店のお兄さんに言ったら、お兄さんはブレッドをひとつかみして、「お金はあとでいいから、持っていきな」と僕に言って、首をななめにした。
「サンクス!!」
ありがとう!! この旅で、そんなふうに言われたのは初めてだ。
ホテルに戻って、僕はかたわらにバナナを置きながら、ずっとギターを弾き続けた。いろんな曲を弾きそして歌ってみると、不思議なことに昨日までの旅の淋しさがだんだんと消えてゆくのがわかった。僕はギターと話しているようだ。
(人はみんな、自分をわかってくれる話し相手が必要なんだな・・)
歌詞を思い出すというのは、偶然にも近い作業だった。たよりは記憶のみ。次々と思い出しては書き留めてゆく。
ホテルの小さな窓に置いていた食パンを、外のカラスが、一枚、鉄格子のすきまからもらっていった。
「あっ!!」。貴重な食料を、カラスは平気で奪ってゆく。
しかし、そのみごとさときたら、、まるで得した気分にもなった。
◇◇◇ そして、なんとか月曜。
結局、お腹が減りすぎて、あまりよく眠れなかった。まだ銀行が開くのには早いが町に出かけてみる。いろいろと見ようと思うのだけれど、思い出せない歌詞が気になって、町が見えてこない。
お腹は今、ペコペコだけれど、気持ちの方はギターがあったおかげで満足している。いや、満腹と言った方がいいのかな。いろんなものが腹が減るんだなと知った。
11時になり、銀行に行って両替をする。「まあ、ゆっくり」とか言われ、銀行の人はコーヒーを出してくれる。こんなことも初めてだ。
やっと財布の中にお金が入り、僕は食事の前にまず、大好きなコーラを飲むことにした。
裏通りにある、一軒の小さなお店屋さんを見つけた。そこにはテーブルがあり店内で食べたりできた。
「ハロー」
「ハロー」。お店の奥からメガネをした、感じのいい小柄なお父さんが出てきた。
「コーラ・プリーズ」「イエース」
僕はテーブルに座った。なんだか学校の前にある小さなお菓子屋さんのようだ。この路地のこの小さな店に、日本人のツーリストが来るのは本当に珍しい
と思う。
店のお父さんは、奥に何か声をかけている。すると、ひとりのまだ若い、中学生くらいの娘さんが、お店に出てきた。にこやかに微笑みながら、コーラを取り出し、栓を開けてくれて、そしてストローをさしてくれた。
「サンクス!!」
お父さんは、いろいろと英語で僕にいろいろきいてくれる。そしてその横で娘さんは、ずっと微笑んでいる。こんなふうに、インドの娘さんと近くにいたのは初めてだ。
ほんのコーラ一本だったけれど、僕はとても親切にされた。
まるで、中学校の前の菓子屋さんを、もう一度訪ねたようだった。南インドのここにも、同じ心があると思えた。
お腹は空いていたけれど、気持ちはとても満たされていた。
「スィー・ユー」
僕は町を出るときに、もう一度この店に寄ろうと決めた。
vol.9「コーチンでの雨やどり」12/14
南インドの天候は、とても暖かだったけれど、ときには突然のどしゃぶりになることがあった。
小さなギターを買った僕は、日課のように、近くのハーバーまで歌いに出かけた。港で歌うのはとても気持ちがいい。すべてのレパートリーは僕の記憶の中にあり、毎日のように増えていった。一時間ちょっと歌ったあと、またホテルへ戻ってくる。
そんな途中。突然のどしゃぶりにあった。
道の途中の一軒のシルク屋さんの店先での雨やどりをさせてもらった。
それはそれはほんと信じられないほどの雨で、とても傘なしでは、外は歩けそうになかった。ネパール、カトマンドゥでは、我慢できずに外に飛び出し
てしまっていた僕だったが、ここコーチンでは、雨があがるまでのんびりと待とうと思えるようになった。
シルク屋のおじさんはとても優しそうな人で、僕にいろいろときいてくれた。例外なくコーチンの人はみんな人がよくて驚く。僕と一緒に小学三年生くらいの男の子が一緒に雨やどりをしていた。彼の肌の色は本当にきれいなこげ茶色で、なんだか見とれてしまう。足は素足のままで、水たまりの中をカエルのように、足の指を一本一本しっかりとひらいて踏みしめていた。
僕も小学校の頃は、学校では裸足だったけれど、今のその感覚がうらやましい・・。
そんなことを思っていると、彼と同い年くらいの小学生が二人かけこんでいた。彼らはもうずぶ濡れだ。シルク屋のおじさんに何か言ったなと思ったら、ビニール袋をもらって布製のカバンを包み、また雨の中にかけだして行った。
そのあと、最初にいた男の子もまたビニール袋をもらって、カバンを包み、そして肩を叩かれ雨の中へかけていった。その布製のカバンはもうずいぶんすりきれて
いた。
まるで小さなドラマのようだった。
残った僕はひとりで雨やどりをしながら、通りゆく人たちを眺める。雨はまだどしゃぶりのままだ。
通りの向こうから、サリーを着た二人の若い女性が、悠々と一本の傘をさして歩いて来るのが見えた。
(あれぇ・・)
外の雨はまだ激しいままだ。二人は、一本の傘の中、サリーのすそをちょっとまくったくらいにして、まっすぐに傘をさして歩いて来た。のんびりとお喋りなんかしながら。きっとゆっくりと歩くことが一番濡れないのだろう。その姿にはインド女性の気品が感じられた。
(ああ、日本人はせっかちだなぁ・・)
コーチンでの雨やどり。やがて、どしゃぶりの雨はすっかりとあがり、空はうそのようにまた晴れていた。
vol.10「節約停電の午後」12/17
コーチンでの日々は実に過ごしやすく、僕はすっかり落ち着いてしまった。
インドでは生水をずっと飲まないで旅をしていたけれど、ここに来てからは、生活環境がいいせいか、やっとそのままで水がのめるようになった。インドの旅にも慣れてきたせいもあるのだろう。
テーブルにはいつも黄色いバナナがある。机に立てかけてある小さなギター。
そして歌詞ノート。壁掛けのラジオからは、インドミュージックが流れている。
昼間はなお暖かく、僕はベッドに横になってひと眠りをする。
ホテルの部屋のドアを開けると、掃除をしているおじさんがいつも廊下に見えた。
「おっ」
まあ、特に用があるわけではないが、目と目が会えば挨拶をしてしまうのは普通だろう。しかし、そのあとがここでは違う。
ちょっとたった後、コンコンとドアを叩く音がする。開けてみれば、掃除のおじさんだ。片手には水入れを持っている。水を頼んだわけではないけれど、これは挨拶だ。おじさんはなんとも嬉しそう。言葉はない。でもそれでいい。
午後の2時くらいになったとき、部屋のラジオが突然に聞こえなくなってしまった。「あれぇ?」と思って、フロントに行くと、節約のための停電とのことだ。(それはどうも自主的なものだったような気もする。。)
外に出てみると、街がなんだかとても静かだ。歩いてゆくと、道での話し声が響いてくるのがわかる。停電もまたいいものだ。いつも寄る大きなテント風レストランに入ってみると、全部が日陰になっていた。テント式ということにも意味があったのかもしれない。お客も僕しかいない。
「ハロー」
のんびりとゆっくり、カレーを待つ。僕は電気のないコーチンの午後の、ここに居ます。
vol.11「懐かしさのこちら」12/20
ここコーチンの町で、小さなギターを買ってから僕は一冊の歌詞ノートを作った。
だいたいのところの歌詞は思い出せるのだけれど、どうしても数行は虫食いのように、あいてしまうのだった。
しかし、朝起きると、頭の中では、昨日思い出せなかった歌の歌詞が自然と出てきている。そんな不思議。。
・・頭の中は、古い出来事でいっぱい。
日本を出てから、もう三ヶ月以上たっていて、その間かなり自分自身が淋しくなっていたのだろう。コーチンに来てからというものは、そんな淋しさをなんとかプラスマイナスゼロにしようと、思い出の中を行き来しているようだった。
古い友達が、 眠る前には必ず僕のまぶたの中に現れて、いろいな話をしてくれるようになった。それはもちろん僕自身が想像で話していることにはちがいないのだけれど。
そのうち、10年後の友達の姿でも現れるようになった。大好きな詩人が、勝手に現れて僕に話しかけてくるようにもなった。ホテルの部屋にある姿見の鏡をのぞいていると、友達がとなりに映るようにもなった。
僕はそんな思い出の中のみんなとここで話し続けていた。
思い出しては増えてゆく歌詞ノートの作品の数。僕はそれを眺めては、幸せな気分でギターで歌っていた。自分の歌を歌い、なんていい作品なんだろうと、我ながらほれぼれしていた。
そんな毎日。
夜、散歩に出かけていると、なんだか、ひとつの事が終わりかけているのがわかった。さよならの予感がする。
もうじゅうぷんに僕は、記憶の中に住んで、懐かしさにも甘えることができた。これもコーチンの持ってるおだやかさにおかげだろう。
また旅を続けなくてはならない。明日には、コーチンを一度はなれ、小さな旅に出ようと決めた。
vol.12「コタヤムまで」12/23
インド最南端「コモリン岬」へ向かうために、僕のその夜、宿を出た。
「コモリン岬で見るサンセットは最高だよ」と、何度もそれまでに聞いていたからだ。
数日でまたコーチンで帰って来ようと思っていたので、ほとんどの荷物は宿に置いたままで、小さなバックひとつで出かけた。
列車、ボート、バスと乗り継いで行く旅。まずボート乗り場のある「コタヤム」の町まで列車で行かなくてはならない。夜12時の最終列車に乗り、朝一番で、ボートに乗り、その夕方には、コモリン岬の夕暮れを見ようという計画だった。
最終列車まぢかの駅では、多くの人たちが列車を待っているのか、それともただ眠っているのか、どこにでも横になっていた。
こんなふうに横になれるなら、どこだってそこがベッドになるだろう。僕はちょっとうらやましい気持ちにもなった。
小さなバックひとつで、遠いどこかに出かけるなんて、なんて旅人ぽっくて、それでいて心細いんだろう。
やがて「コタヤム」行きの最終列車がやってきた。自由席の方はさすがに満員で、自分ひとりの場所を確保するので精一杯だった。
子供たちは重なりあって眠っている。いろんな表情のインドの人がいる。深夜の列車は走って行く。
二段になっている上段のシートに、中学生くらいの三人の若い女の子が並んで座り、お喋りをしていた。三人とも多くの南インドではポビュラ
ーな、半袖シャツにロングスカートというファッション。それは、茶色い肌をいっそう魅力的に見せてくれていた。
三人ともにお下げ髪。その表情はとても豊かで、とても愛らしい。
コーチンに来てからというもの、僕は南インドの女性に心ひかれるようになった。ケララ州の女性というべきだろうか。服装が清楚でとてもいい。そして話すときいつも笑顔なのがいい。そしてみんな品があり、とても美人だ。
僕がそう思うくらいだから、ケララ州に住んでいる男性諸君には、天使のようにきっと映っているだろう。どこに国に行っても、どこの場所に行っても、女性たちは、それぞれに一番似合う服装を、見つけている。
夜行列車の上のシートに座り、三人の若い女の子はいつまでも、楽しそうに話している。この満員の列車の中で、そこだけ浮かびあがっているように見える。僕はその愛らしい表情にいつまでも 、見惚れていた。
vol.13「真夜中のコタヤム」12/26
AM2:00、列車はコタヤムの駅に着いた。
まず、露店でコーヒーを一杯。。
ここ南インドでは、チャイもあるが、コーヒーもあって嬉しい。
駅の入口のところへゆくと、何十人という人たちが横になり眠っている。よく見れば家族もいて、ここをねぐらにしていることがわかる。
午前2時では、まだホントの真夜中なので、ボート乗り場までゆくにも無理がある。数時間はここで時間をつぶさなくてはいけない。なんとなく横になってもいい雰囲気なので、僕は横になってみた。
ここはインド。。
日本の友達の誰が、今こうして僕がコンクリートの上で横になっていると想像しているだろうか。
デジタル腕時計のアラームを二時間後にセットして、目をつぶってみると、急に赤ん坊が泣き出した。
母親は当たり前のように抱き寄せている。本当ここが家のようだ。そんなことも自然に感じられるのも、ここがインドというせいだろう。
ほんの少しのひと眠りをするために、僕もまたコンクリートの上に横になり、自分の腕を枕にそっと目を閉じた。
◇
そして、AM4:00、僕は腕時計のアラームが鳴る前に目を覚まし、そしてボート乗り場(ボートジェティ)まで、夜道を歩き出した。
(みんな、ではお先に・・)
夜道は当然のことながら、真っ暗のままだ。僕のシューズの音だけが響いている。見上げれば星がきれいに出ている。地面に目をやれば、道のあちこちに人が眠っている。
こんなインドの夜道を、日本人の僕が歩いてゆくなんて、とても不思議だ。僕の足は自然と早くなってしまう。こんなスピードで歩いてゆくけれど、ボートジェティの場所も、この道がどこなのか、まったくわからなかった。
vol.14「やっと見つけたボートジェティ」12/30
真っ暗なコタヤムの夜道を歩いて、僕はボートジェティに向かおうとしていた。
しかし、ここはどこだろう。まだ夜明け前ということもあり、僕は通りかかった人にたずねるしかなかった。
おじさんにボートジェティの場所をきき、その指さしてくれた道を行くと、だんだんと道が細くなり、そのまま行き止まりになってしまった。
(おかしいなぁ・・)
他のおじさん数人に道をまたきくと、ボートジェティの場所は変わったのだという。そしてさっきのおじさんは、道ではなくて、方向を教えてくれたのだとわかった。
ひとりの親切なおじさんが、途中まで一緒に来てくれた。おじさんは、その間ずっとケララの言葉を話しかけてくる。ケララの言葉は、北の言葉とはまた違い、舌を巻くような発音が続く。そしてちょっとみんな早口だ。
そんな早口なケララの言葉をおじさんは僕に話しかけ続けているけれど、さっぱり僕にはもちろんわからない。わからないのに、おじさんは僕に話し続けている。この心理はいかなるものだろう。
そのままずっとついて来るのかなと思ったけれど、おじさんは、曲がりかどのところで、「この道を行け」と教えてくれた。きっと、ここにくるのも実は大変だったのだろう。
(サンクス、おやじさん!!)
ずっと歩いてゆくと、椰子の木の隙間から水路が見えてきた。ここまでくれば、もう大丈夫だ。朝一番のボートが出るまでに僕は間に合ったのだ。それは、わかっていた気がする。だって実際、こうして着いたのだから。
やっと見つけたボートジェティ、そこにボートがある。そして僕がいる。これでいい。また出発まで1時間ほどあったので、ジェティ前のお店でチャイを飲み、ひと休みをした。
ボートに乗り込んでいいというので、一番乗りで、ボートの乗り込んだのに、なぜかもう六人くらい、そこで眠っていた。彼らは、きっとここが宿なのだ。
水路一面にホテイアオイのような浮草がみずみずしい緑色を作っていた。陽は登ってくる。今日もいい天気だ。午前6時、ボートは50人ほど乗せて、水路の浮草をわけながら出発した。
さて、勝負の一日が始まった。僕は今日の夕方には、インドの最南端に岬に立っているだろうか。
vol.15「ケララの船旅・1」1/2
50人ほど乗せたボートはそして、一面に浮草に囲まれた水面をわけながら朝に出ていった。
日本でインドのガイドブックを見ていた頃から憧れていた、ケララの船旅の始まりだ。
朝6時半。登ってまもない陽の明るさの中、ボートの回りを赤トンボが所せましと舞い飛んでいる。こんな景色をどう伝えよう。赤トンボは、トンボは止まっては進み。また止まっては進む。
左右には、椰子の木とバナナの木が生い茂り、その茂みの中を背が瑠璃色の小さな鳥が飛び抜けてゆく。その鳥はカワセミと似ている。カワセミだろうか。インドにもカワセミはいるのか。
やがてボートは広い水路に出てゆく。両岸には並び続く椰子の木の群。丸木船に乗った地元の人の姿も見える。ここ南インドの人たちはみんな肌が褐色で、自然人のようだ。
そんな椰子の水路の景色に見惚れてると、誰かが僕の肩を叩いた。チケット係のおじさんだった。これから約2時間も乗るのに、船代はたった3Rs(約50円)だという。安すぎる。
続く水路の岸のところどころに、民家が見えた。どの民家もきれいな原色で塗られていた。たぶんペンキだろう。不思議にその色合いは、とてもこの景色に似合っていた。なぜだろう。いかにも人の住みかというふうだ。
波もなく続く広い水路は、いつかみたアマゾン河のようだ。でもここはケララ。ボートは時間すべるようにを進んでゆく。
vol.16「ケララの船旅・2」1/5
波もなく、水平に続いている水路を、50人乗りのボートは進んでゆく。
船はいくつものジェティ(乗り場)に止まり、地元の人たちを次々と乗せてゆく。
(ふーん、バスなんだな・・)
このボートは地元の人にとっては生活の一部になっているようだ。僕にとってステキに見えるこの景色もまた見慣れた風景なのかもしれない。
ずっと岸に沿ってボートは進んで行き、地元の人たちの生活をいろいろと見せてくれた。ここではみんな川でものを洗い、体も洗う。歯もみがく。ときには用も足すかもしれない。家々の中からは子供たちがはしゃぎ出てくる。十代の娘さんたちもまた川へ出ては、立ったり座ったり、いろいろ仕事をしている。
それは流れてゆく景色の中で、スローモーションフィルムのように映る。そしてその娘さんたちが、なんとも愛らしいこと、、。着ている服が緑の中に映えて、とても似合っている。どの娘さんも顔立ちがいいし、目がキラキラしている。
(またホレてしまっているな・・)。でも、それほどケララの娘さんは僕の心をとらえてしまうだ。
陽は東の方からオレンジ色の光を思うぞんぶん照らしている。そのオレンジ色の光が、椰子の木の隙間からもれている。あの椰子の木の向こうでは、すばらしい太陽が姿を見せているのだ。
そしてボートはまだまだ進んで行く。今度は田んぼだ。どこまでも続く田んぼ。空は淡いブルーで、田んぼとの境目がぼやけてはっきりしない。田んぼはいったいどこまで続いているのか。
田んぼの水路を過ぎると、今度は広い広い川になった。その両岸には、椰子の木の列が川を囲んでいる。椰子の木に囲まれた水の国
道。その先がまた、ぼやけてはっきりとしない。まるで夢の中のような景色だった。
白い鳥たちが、悠々と羽根を広げてゆっくりと漂っていた。彼らの羽根はとても柔らかい。彼らの飛ぶ姿は芸術ではないかと思う。
僕は、まざまざと見せつけられた気がする。ケララの船旅は、すべてはそんな柔らかさの中にあるようだった。
vol.17「夕日に間に合うか」1/8
夢のような時間を乗せて、そしてボートは「アレッピー」に着いた。
ここでもう一度ボートを乗り換えて、次へ向かう予定だったが、そのボートは出てないと言う。出るときに、何度も確かめたのにおかしい。。でも、こういうことはよくある。
しかし、今日の夕焼けを、どうしてもインド最南端のコモリン岬で、僕は見なくてはいけない。その計画で昨夜から出て来ているのだ。悩んでいてもしかたがないので、次のボートはあきらめて、バスで最南端へ向かおう。
長距離バスの出ている場所に関しては、まったく知識もないので、地元の人にきいてゆくしかなかった。
「ハロー、ドゥ・ユー・ノウ・バススタンド? アイ・ウオントゥ・ゴー・ケープ・コモリン」
何人もの人に道を教えられ、やっとバススタンドに着いたものの、さて、どれが、南へ向かうバスなのか。そして急行(エクスプレス)はどれなのか。
コモリン岬へ向かうダイレクトバスはもちろんないので、とりあえず、どれかの一番早いバスに乗らなくてはいけない。何人もの人にたずねてみるけれど、あいまい答えてくれるばかりだ。そしてひとりの親切な人が、僕の気持ちをわかってくれて、どのバスに乗ったらいいか、教えてくれた。ホントに助かった。ありがとう。
ようやく乗れたエクスプレスバス。急行のバスはとても早く、次々と他のバスを追い越してゆく。窓からの風もいきおいよく入る。
午後のあたたかい日差しの中、僕はとても眠たくなった。よく考えたらほとんど寝ていないのだった。コックリコックリとしていると鉄の棒に頭をぶつけてしまった。回りのインド人がクスクスと笑っていた。
そして3時間半。バスはトリヴァンドラムに着いた。どんどん時間は過ぎてゆく。急がないと夕焼けに間に合わないかもしれない。コモリン岬までのダイレクトバスはないと言われ、知らない町行きの乗り換えバスに乗っていると、どうも、ダイレクトバスと思われるバスが見えていて、僕はそちらに乗り換えた。
(さて、これはホントにダイレクトバスか。ちがっていたら、もうアウトだ。。)
バスは走り出した。やっばりダイレクトバスだった。本当に良かった。ここから最南端のコモリン岬まで2時間半だ。コモリン岬では、太陽が海から昇り、また海へと沈む、インド唯一の場所。そこで見る夕焼けは最高だと何度も聞いた。
今日はいろんなラッキーがあった。いろんなラッキーがあり、こうして最後の乗り換えバスは走っている。バスの窓にはお日様が映っている。
・・・夕焼けに間に合うか。。
それは僕にも腕時計にもわからなかった。
vol.18「コモリン岬・1」1/12
午後5時。バスはコモリン岬に着いた。しかし雨。
あれだけ急いでやって来たのに、空は雨なのだ。しかし、ぜったい真っ赤な夕日は今、落ちているんだと信じて海へと向かう。
海がだんだんと見えてくる。浜道に並ぶ貝殻細工の露店。ここは海の町なんだなぁ。
そして岬。インド最南端のコモリン岬。ベンガル湾、インド洋、アラビア海に囲まれ、太陽が海から昇り海へと沈む場所・・。
しかし、海につながる空はどこもかしこも雲ばかりじゃないか。いったいどこに太陽があるのか。おまけに雨はまだ降り続いている。
(あーあ)と、思いながら、西の方をゆっくりと見てゆくと、空の下の一カ所が、なんとなくうっすらとオレンジ色になっている。あの辺に太陽は今、居るのか。あれが、コモリン岬の夕焼けなのか。
まあ、今日は最後まで太陽とつきあうつもりだ。ここに来るまで、何度バスの窓からおまえを眺めたことか。僕にとっては大事な夕焼けのはずなのに、太陽はこのまま、ぼんやりと海に沈んでしまいそうだ。
それでも待つ。待ってみよう。365日の内の今日12月12日の夕日なのだ。それは偉大な太陽、そして一日の終わりの証なのだ。良くも悪くも、今日は太陽よ、おまえとつきあおう。
そんなふうに自分自身をなぐさめながら、じっと西の方を見続ける。本当は、インド国内の観光客や新婚さんでいっばいのはずなのだろう。みんな今日の夕焼けはあきらめているようだ。
そうこうしていると、海の一番下が、横にうすくだんだんと鮮やかなオレンジ色になって来た。この浜のみんなも気づかない
くらいの、今日の終わりだ。
僕はなんとか感動的にその夕日を見ようと思ったけれど、やっぱりどこか無理があったのかもしれない。
あっとゆう間の感動の時間だった。しかし今日僕は夕焼けに間に合っただけでも素晴らしい。こんな雨の中、オレンジ色を見せてくれた太陽は僕にとっての最高のプレゼントだ。
海からオレンジ色がすっかり消えてしまうまで眺め続けたあと、僕はやっと腰をあげて、今夜の宿を決めに歩いた。海のそばのはなれの小屋のような所に決めた。小さなバックひとつの泊まり。なんて身軽なんだろう。
今日は夕焼けが見られて幸せだった。僕はぼんやりと漂うように、日が暮れたあとの浜道のおみやげ屋さんの道を歩いてみた
vol.19「コモリン岬・2」1/17
陽が暮れて、まだ明るさの残る中、僕はインド最南端の町を歩いてみた。
「コモリン岬」とも呼ばれるが、この町の名前は「カニャクマリ」。海岸の手前、露店の続く細道を歩いていみと、実に「カニャクマリ」という呼び名が似合っているように思えてくる。
露店といっても、そのほとんどがおみやげさんだ。ここはインドでも観光名所のひとつで、インドじゅうから旅の人たちがやって来るのだ。ふと気がつけば、いろんな感じのインドの人たちが多く歩いていた。
コモリン岬のポストカードを、インド人がインド人に売っている。そんな風景はとても自然だ。
海のおみやげ屋さんの並ぶ道。僕自身も海沿いの生まれなので、それはとても懐かしさに満ちている。そしてどこか、日々のせわしさから解放された楽園にちかい空気がある。
ここでは、おみやげを売ってみんな暮らしているようだ。
・・・・
露店の通りを歩いてゆくと、かっぷくのいい、やんちゃな感じのあんちゃんと、その仲間が3・4人並んで向こうからのっしのっしとやって来た。かっぷくのいい男がたぶん親分なのだろう。サンダル履きに、肌の見える黒い服を来て、貝飾りのネックレスをジャラジャラと音をさせながら歩いてくる。その姿はまるでいつか見た人形劇「ひょっこりひょうたん島」の中での登場人物のようだ。
・・カニャクマリの若親分かな。いかにもって言うその表情が、なんとも可笑しかったこと。。
また歩いてゆくと、道の隅で黒いかたまりが見えた。よく見るとそれは黒豚の親子だった。まだ小さい子豚が10匹ほど、一緒に丸まって眠っていた。そばでしばらく眺めていると、子豚たちが起きて、母豚のお乳を吸おうとしていた。子豚たちのパワーはすさまじく、母豚を押し倒して吸おうとするのだ。
それをいやがる母豚。
母豚は、10匹ほどの小さな黒豚君たちに追いかけられている。その光景は露店の道で行われていた。黒豚君たちはホント憎めない動物だ。愛しい・・。
また歩いてゆくと、いままで見たこともないようなフルーツを売っている店があった。色と形としたら、丸いどんぐりを大きくして、頭
に葉をかぶせたような感じだ。椰子の実よりは小さく、ココナツくらいの大きさだ。
露店の人はザクザクと切ってくれ、中から透明に部分をみっつほど取り出してくれた。食べてみると、今までに食べたことのない味だった。好みは分かれるところかもしれない。僕はひとつ半食べて満足してしまった。
「ハワッディズ・ネイム・ズィス・フルーツ ?」
「ズィス? パルメロ!!」「オゥ、グッネイム!!」
そのフルーツはいかにも「パルメロ」という名前だったのだ。おみやげ屋さんの並ぶ浜道は、まるで現実感がなく、すべてがふわふわと浮いているようだ。ここでは毎日が、こうなのだろう。
今日はとても疲れたけれど、僕は幸せ感に満たされていた。
vol.20「コモリン岬・3」1/20
ひととおり露店の道を歩いたあと、僕はひとりロッジに帰り、横になった。
バックひとつでやって来たので、とても身軽な一泊だ。ベッドに仰向けになり、両手を枕にして僕はさまざまな想い事をした。
上海行きの船に乗って、神戸を出てからもう四ヶ月。移動の時間が多くあったせいもあるけれど、僕は友達の事、日本での事、いろいろと想い続けて来た。
小さかった頃から学生時代、東京に来てからの事まで、思い出せるだけ思い出して、それでもまだ僕は、こうして宿で横になると、日本の事、友達の事を考えている。
・・・もう、そろそろ終わりにしないとな。。
この宿を最後に、僕はホントに旅に集中しようと思った。でも今夜は、日本の友達の事をゆっくりと想おう。
◇◇◇
翌朝、まだ陽の昇る前に、海に出かけてみると、みんな同じ気持ちなのだろう。朝日が海から昇るのを観ようと、多くの人たちが集まっていた。
そうだよ。昨日は、海に落ちていった夕日が、たま海から昇ってきているのだ。不思議すぎて、よくわからない。。
みんなで、陽が昇るのを見ているのは、なんだか嬉しい。同じ気持ちがそこにはあり、僕もまたそのひとりなのだ。インドじゅうから来た人たち、そして観光で来た世界の人たち、また自由旅行と思われる人たちもいる。海の方に目をやれば、沐浴をしている人たちもいる。
僕は、腰掛けるのにちょうどいい石を見つけ、そこからずっと海から昇る朝日を見ていた。やがて見学に見に来ていたみんなも散り散りになっていった。
僕は太陽のことを思っていたのだった。もし太陽がなかったら、ここもすべて真っ暗なのだろう。陽の光はいろんなものをぜんまいのように動かしている。こんな当たり前のことに感謝しよう。
太陽はすっかり昇り、辺りはすっかり明るくなったけれど、僕はまだ東の方を見ていた。
vol.21「予定になかった町と夜」1/24
こんな夜があってもいいだろう。
インド最南端の「コモリン岬」の朝にいた僕は、夕日と朝日も見たし満足してまたバスに乗った。
ケララ州のコーチンという街の宿に、荷物のほとんどを置いてきたからだ。宿の人も心配するだろうから、一泊くらいで帰る予定だった
のだ。
またバスを何回も乗り換えてゆく。窓の外に広がる景色は椰子の木が続き、だんだんと慣れて来てしまった僕は言葉さえも浮かばなくなってしまった。
バスはまた走ってゆく。
ボートジェテイのあるアレッピーに着いた。夕暮れ前にボートに乗り込めば、また水路の景色も見られるし、コーチンの街にも戻れる。しかし、ボートは三分前に出てしまっていた。次のボートは夜9時。。
すっかり予定がちがってしまったけれど、今夜はこの町に泊まり、明日の朝一番でボートに乗ってゆこう。
僕にしてみたら予定にない宿の夜になった。約200円くらいの宿を決めて、小雨降る中、商店街の散歩へと出かけた。予定にない夜に、僕の旅のねじはすっかりとゆるんでしまい、ぼんやりとしてしまう。
一軒のフルーツショップがあり、僕は葡萄をひとふさ買った。インドに入ってぶどうを買ったのは、初めてだった。僕が英語を使うとお店の人は「ユー・キャン・ビジネス・OK!!」と言う。この町でも、やっぱりみんないい感じのおじさんが多い。
小雨の降る町は、なんとなくどこか寂しげで、特に観光地でもなく、ここには南インドのそのままの町がある。
・・僕はずっと観光地に泊まってきたのだ。
宿に戻り、ベッドに横になりながら、僕はひとふさの葡萄を食べた。とてもとても美味しかった。葡萄といういうのは、いっばいの実が付いていて素晴らしい。なんて贅沢果物なんだろう。そんな感動が、僕の今夜の出来事だった。
vol.22「その朝の小さな話」1/27
できるだけ早くボートジェティに行くために、僕は朝7時に泊まっている宿を出た。
ロッジの外に出るとチャイ屋に声をかけられる。そのままふらふらと自然にチャイ屋に座る自分がいた。
・・朝の一杯のチャイを飲もう。
僕の座った椅子の前で、ぶかっとしたパンツひとつで、ふたりの小さな女の子が向かい合いながら、両手でグラスを持ちゆっくりとミル
クを飲んでいた。
ふたりは、まるでふたごのように見えたが、ちがうようにも見えた。本当にゆっくりゆっくりとグラスのミルクを飲んでいた。
すぐ隣にはひとりのおじさんが座っていて、たぶんおじさんの子どもなのだろうと思った。
僕の方をチラッチラッと見たり、お互いをチラッチラッと見たりして。。
そして、しばらく・・。
ふたりはカラになったグラスを急に、テーブルに音を立てて一緒に置いたかと思ったら、そのまままっすぐに道向うのテントの家にかけていった。・・その家の子どもだったのだ。
きっと毎朝、チャイ屋さんにミルクをもらっているのだろう。
ふたりが見せてくれたいろんな動作が、とても意味深いものに思えたが、今の僕にはよくわからなかった。
朝の、一杯のチャイの間の小さな話。それは今日の始まりの前の小さな話。
vol.23「こんな旅です」1/31
次の朝、またボートに乗り椰子の水路を通ったあと、コタヤムの町でボートを降りた。
列車からの乗り換えで、来るときにも寄ったコタヤムの町。ボートジェティから駅まで歩いて30分はかかる。
駅へ行く途中で、坂道を通った。そこで多くのインド人、車、そして牛たちが忙しそうに通り過ぎてゆくのを見た。坂道って不思議だ。とても生活感がある。登るのは牛も人もみんな大変だし、降りる人も、みんな自分の先をちょっとの先を忙されて大変だ。こんなにリアルにインドを感じられるのも、坂道だからだろう。
日本の坂道でもそうかもしれないな。今日はここに来れてよかった。
駅に着き、当日の切符を1時間かけて並んで取る。インドはホントのんびりとしている国だ。せわしいのかどうなのかよくわからない。
そしてまた1時間待ち、やっとコーチンへ行く列車に乗る。席の方はもういっばいなので、僕は電車の連結のドアのあるところにいることになった。
列車は走っているけれど、連結のところのドアは開いていて、外の景色が見えている。インドの人は、そこに座り、普通に外を眺めている。ちょっと間違えれば、下に落ちてしまいそうだ。
インドの人たちがみんなそうしているので、僕もまた、開いているドアのステップのところに座って、走る電車から外の景色を眺めた。みんながそうしているとはいえ、落ちたらかなりあぶないことは確かだ。しかし、ここに座っていると、とても旅を感じる。
僕は今、こんな旅をしているのだ。列車は二日ぶりのコーチンに向かっていた。
vol.24「ケララ・エピソード」2/4
午後になるかならないかという頃、列車はコーチンに着いた。
何人かの乗客は、ホームから柵を乗り越えて外に出て行った。インドでは、それも自然に思えてしまう。
さて、二日ぶりにコーチンの町に立ってみると、僕は不思議な気持ちになった。なんだかこの町のことはなんでも知っているような気がしたのだ。
どうしてだろう、町のどこもかしこも懐かしく、まるで故郷に帰って来たようだ。
道を歩いてゆけば、やっぱりみんな「ハロー、ハロー」と声をかけてくる。ホテルの前のあのユニオンの人たちも、僕のことを憶えていて、30人くらいが、久し振りの笑顔で手を振ってくれる。
たった二日間、この町にいなかっただけなのに、なにもかもが懐かしいのだ。ホテルの近くの露店パン屋の兄さんも相変わらずだ。ホテルの受付の人は、僕のことをとても心配していたと言ってくれた。
ホテルの部屋のドアを開けると、そこで待っている僕の荷物たちがいた。この町で買った小さなギターもそのまま置かれていた。
僕はおもわず「おまえたち、元気だった?」と声をかけてしまった。日本に帰ったらやっぱりこんな感じなんだろうか。
町へと出てみる。今日はみんなの「ハロー」の声も特別に嬉しい。(あのジャパニだ)と思っているだろう。アイスクリーム屋の兄さんに「コモリン岬に行って来たよ」と言えば、「 ヨカッタだろう」と笑ってくれた。
なぜこんなにこの町は懐かしいのだろう。僕はインドの北、バラナシで会ったケララ州生まれのサシーの事を思い出していた。彼もまたこんな気持ちをケララに感じているのだろう。
(サシーよ、おまえの歌っていた鼻歌の中に今僕は来ている)
いつものレストランに、二日振りに僕は入っていった。
vol.25「サシーの鼻歌」2/8
二日ぶりに帰って来たコーチンの町。
僕はいつものレストランで食事をしながら、バラナシで友達になったサシーの事を想っていた。
北インドのホテルの食堂係だった、ケララ州生まれのサシーという男。出会ったときからとても仲良くなったあいつは、僕と同い年くらいだった。
まるで小学校のときの友達のようだった、あいつ。。
そんなサシーがあるとき鼻歌を歌っていた。
♪ウンニャパッカ ウンニャパッカ・・
とても懐かしい響きのあるその歌のことをたずねると、「これはケララの唄だよ」と彼は言った。その鼻歌の中にサシーは、ケララ州を思い出していたようだった。
そしてやって来た、ここケララの町。思いかえせば、僕はあのサシーの歌っていた鼻歌に誘われてここまで来たような気がする。
ほんの二日間だけ離れただけなのに、こんなふうに町が懐かしくなるなんて初めてだ。その懐かしさは、きっとバラナシのサシーと、今度再会したときと同じだろう。
小学校時代の友達。遠く離れていても、変わらないもの。そのベクトルは、故郷に向かっている。世界中があり、世界のここがある。僕をここに連れて来た響きがある。
vol.26「コーチンとのさようなら」2/11
僕はその午後、またリュックに荷物をつめ直し、そして次の町に出かけようとしていた。
のんびりと楽しかったコーチンの町での日々。
今回からこの小さなギターが荷物として増えた。この先まだまだ旅は続くのに、ギターを買って良かったのか失敗だったのか。
しかし、ギターがあることで僕は心が落ち着き、一人旅の淋しさからかなり解放された。
ここコーチンは僕を優しく最初から迎えてくれた。町に出かけるたたびに聞こえてきた「ハロー、ハロー」の声。北インドの観光地での、あの商売っ気たっぷりの響きではなく、こうして町で去ってゆく今でさえも、さわやかな響きだけが残っている。
どの人も本当にいい人だった。
今夜には、また列車に乗っているわけだろうけれど、僕はこの町をこのまま置いてゆきたい気分だ。大きな荷物を持って、駅へと向かうのはなんだかせつない。知っている人にできるだけ会わないで、駅へと着きたい。
あのアイスクリーム屋の兄さん。ホテルの前のユニオンのみんな。大通り手前の露店のパン屋の兄さん。レストランのおじさん。
もう一度必ず、寄ろうと決めていたジュース屋さんにも、僕は寄ることが出来なそうだ。
(おじさん、ごめん、、)
このコーチンの町にサヨナラは言いたくはないのだ。
僕はこの町と「ハロー」の響きとともに、去ってゆきたい。
・・・
そして夕方、僕は電動リクシャーを拾い、なじんだ商店街を抜け、そっと駅へと向かった。
vol.27「ケララ生まれの話たち」最終回 2/14
椰子の木の鮮やかな緑色。
そんな緑色の思い出を乗せて、あの日の列車はケララ州コーチンを出ていった。
あれから僕はどこを回っていったのだろう。楽園と呼ばれるゴアの海と空の青さの中? パキスタンの国境近く、砂漠のうす茶色の景色の中? トルコ共和国、パムッカレの雪の白さの中? フランスのパリの空のパール色した雲と青さの下?
どの色の思い出の中にも僕がいて、片手にはいつもケララで買ったギターを持っている姿が映っている。
1986年の冬のインド。1987年の春、夏のヨーロッパ。
そのときのギターは押入の中で15年眠っている。
◇
そして2003年。僕の目の前にはコンピューターがあり、その横では小さなテレビがいつもある。
ある情報番組の企画で、その日たまたまインド・ケララ州コーチンの取材がテレビに映った。
「あっ、コーチンだ」
走りながら木に登り、椰子の実を落とし、「これは俺の椰子の木なんだ。のどが乾くとここに来るんだよ」と息を切らしながら言う男。
海のイワシ漁では、二人の男が網を持ち泳いで円を描いてイワシを追いつめていた。
そのイワシをイルカから守るために何度も船から思いきり落ちては音を出す男。
「バシャーン!!」
何度も船から落ちてはイルカをおどかす男は、なんだかとても嬉しそうだ。この漁はここの地方の独特のものであるという。
「この魚が食べたいか。食べたいなら俺ん家に来い!!」
番組の中で、その取材を見ていた人が顔を見合わせこう言った。
「みんな笑っていて、みんないい人だ」
15年前、僕が出会ったケララの人たちの姿がそこにあった。たった五分や10分の映像の中でさえも、人も含めてケララの明るさが満ちていた。その明るさはテレビ画面の向こうにあったけれど、僕の体や記憶の中にもちゃんと残っているものだった。
もう一度、僕の記憶の中のケララを巡ってみれば、ちょっとしたことにも、いろんな共通するエピソードがあるような気がした。
そして書きはじめたこの「ケララ・エピソード」。
たった10日ほどのケララの旅の話は僕の中で、ひとつのストーリーとなってつながっている。帰国して4年ほどしてから僕はケララの歌を作った。その歌を歌うたびに、いつもケララの明るさの中に包まれていたようだ。
何度歌っても、その歌はあきるということがない。
ケララ生まれの話には、そんな魅力があるようだ。 (2004.2.14 ケララ・エピソード終了)
「ケーララの町で」
30人の顔が、テントから僕に、手を振ってくれていた
ヤシの木茂る、南のインド、ホテルの前の町内集会
ケーララ州のここはコーチン、年中チョッピリ暑い
町を歩けば、次から次に、声かけられた「ハロー、ハロー」
ホテルのじっちゃん、目と目が合えば、水持ってやってくる
壁掛け式の有線ラジオ、全チャンネル、インドのタンタタタ
2時から4時までは、節約停電、道ばた声が響きだす
やけに広いレストランは、全部日影さ
ザザザザザ、ザザザー ヤシの木が揺れていた
どこでも、ケーララ
ホテルに荷物、置いたままで、運河下りの旅に出た
乗り換え船を、乗り継いで、最南端まで行ってみた
ひろびろ続く、ヤシの水路に、スローモーションで人が立つ
思うぞんぶんオレンジ色は、空を染めていた
トンボがえりで、最南端から、コーチンタウンに戻ってくると
パン屋のあんちゃん、屋台や小道、なにもかもが懐かしい
北のベナレスで、友達だったのは、ケーララ生まれのサシー
おまえのことを、思い出すよ、鼻唄とともに
ザザザザザ、ザザザー ヤシの木が揺れていた
いつでも、ケーララ