|
文字の歴史は、殷の時代の甲骨文字、きわめて絵画的な形の金文(きんぶん)(金文とは金属の器物などに刻まれている文字で、だいたい殷の時代から周や春秋の時代にかけてのものをいい、さらに戦国時代の武器にある字までを含みます。)金文の次に大篆といわれる書体が確かにあったのですが、確かなものは残っていません。そこで石鼓文(せっこぶん)が石鼓(太鼓の形をした石)に刻まれている文字が大篆にあたるのだろうと言われています。この石鼓文は万里の長城を作った有名な秦の始皇帝が篆書を制定する際に重要なよりどころとしました。実際には首相の李斯(りし)が遂行し、李斯が書いたと言われる泰山刻石などが有名です。漢(前漢)の時代になると中国の文化は大変栄え、ことに漢の武帝は文教が盛んになるように努めました。この時代には新しく隷書という書体が盛んに使われました。隷書には前漢の古隷(隷書の完成体である八分体(はっぷんたい)とは異なる古朴、古拙な味わいの隷書体)、比較的少なくて開通褒斜道刻石(かいつうほうやどうこくせき)や魯孝王刻石(ろこうおうこくせき)などがあり、後漢になると、はらいのついた八分体(はっぷんたい)という華やかな感じのする書体が書かれるようになりました。八分体の作品は比較的たくさん残されていて孔廟礼器碑(こうびょうらいきひ)、史晨前碑、史晨後碑、曹全碑(そうぜんひ)などが有名です。
秦の始皇帝が焚書坑儒といって医学書など以外の書物を焼き捨てた事件があり北宗の時代に地下に埋まっていた木簡や竹簡が見つかり、その後二十世紀になって沢山探検家により発見されました。これは春秋戦国時代に朱や墨を用いて書かれた文字朱墨手跡がここ5、60年の間に数多く発見されました。湖南省の楚墓(そぼ)から出土した帛書(はくしょ)、湖北省の秦墓(しんぼ)から出土した竹簡などがあります。秦の始皇帝が6国を統一する以前に一般庶民や下級官吏が書いた文字です。このなかには隷書の八分を非常に速く書いた書体がありこれを章草(しょうそう)と言い、これが後に草書になるわけで、楷書が行書になりさらに草書になったのではありません。 甲骨文や金文の文から篆書、隷書などの書への転移は文字を「刻す」ことから「引く」を経て書への転位を物語っています。 |
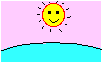 Back
to top
Back
to top