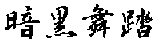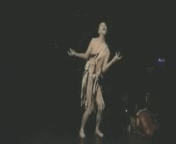偶成天 舞踏セラピー
しかし、2011年の震災を目の当たりにして、怒りの悲嘆の波をなだめ鎮めるため、 この言葉でのアプローチを開始しました。 その後、特に「舞踏セラピー」という言葉に執着することなく、 生きることにつきまとう様々な感情を、良いものもつらいものも含めて 舞踏という場の中で深めてきています。 そうしているうち、舞踏セラピーは「痛みを癒やす」… ということに近いものとなってきています。 …この文章を書いたのが2017/1/3でした。ちょうど三年前のことです。 しかし、「セラピー」という言葉を安易に使う世の中の風潮が気になり この言葉を明示的に使うことはできるだけ避けてきました。 ただし、身体心理療法の要素を丁寧に見通しながら進める「ボディラーニング」や舞踏のレッスンでは、実際的にセラピー的な展開が多くありました。 そのため、依然として注意を払いながらですが、 誤解の恐れがない範囲では、必要に応じてこの言葉を用いることにしています。 (森田一踏、1/3, 2020)
|
舞踏セラピー
|
|
舞 踏 雑 感 …
|
| ・「本当ということ…」 |
| ・「見られるということ…」 |
本当ということ…
最近、いろいろとできないことが増えてきている。一つは年齢によるものだと思うが、膝や首や腰などが一定の負担で悲鳴を上げるようになってきている。ただし、それはそれで確かなリアリティとして身心に響いてくるので、舞踏ということを踊るにはそれほどマイナスにはならないが。
若い男性のダンサー、ストリート系とかコンテンポラリー系とか、と関わる機会があるといろいろと確かめてみることがある。それは「身体のリアリティを生きているかどうか」ということだ。ただし、これは哲学的な意味合いではなく、とりあえずは「身体の重さを感じて動いているかどうか」ということから始まる。野口三千三による野口体操が初期の舞踏集団や舞踏家に伝わり舞踏の稽古に取り入れられたという時期があったことすら、最近の若い人は知らない。ステップや動きがどんどんと開拓されてきたので、そうした技術的なことをマスターして踊ることに一生懸命である。そのため、身体の重さを感じるような時間的余裕が極めて少ない。脱力してから落下するまでの短い時間すら「もったいない」ようで、時間を動きで稠密に埋め尽くそうとしていることがほとんどだ。
痙攣や振動などの自律性の動きは、私たちの舞踏では大事にしていることなのだが、そうした動きもすべて技術的に捉えられて再現される。下肢を床に落として歩いて行く動きも、ロボット系の動きとして技術化されて動いていく…。それはそういう領域としてokであり特に批判とかではないが、舞踏ということに身心のリアリティや本当であることを追求したい私としてはいろいろと愕然とすることがある。一つにはそうした動きも「表現」として位置づけられているらしいことである。
少し屈曲して持ち上げた下肢を、下肢の重さのままに股関節と膝関節と足首の関節を一挙に緩めると、下肢はズシンと床に落ちる。野口体操でいうところの「脱力」そのものである。そこにある技術らしきものといえば「下肢全体を持ち上げている筋緊張を一挙に抜き去る」ということに過ぎない。ズシンと床に落ちた下肢は、フラットな足の裏から床に着地する。足首も脱力しているから当然のことだ。しかし、ほとんどの舞踊は動きの技術体系が基本的に異なっているようで、こうした単純な下肢の落下をすぐにできる人が少ない。
足首がほとんど常時緊張している舞踊形式の場合は、足首が固まっているために足裏からフラットに床に落ちることがない。また、足首が緊張しているときは、膝や股関節もやや緊張状態にあるため、下肢をそのまま全部落下させることがなく、落ちる速度が鈍るため、落下したときに足裏全体で「ズシン」と音を立てることも少ない。音をたててみてと言うと、下肢を緊張させて固めて「ズシン」を床を踏みならす…。根本的に違うのだが,説明しても無理そうなので「まあ、いいかあ」とすぐに転身するしかない。
もちろん、こうしたことは技術的なことなのでそれなりに練習すればできるようになるものである。問題は、しかしその先にある。「なぜ下肢の緊張がすべて抜け落ちて下肢がズシンと落下することになったのか」ということは、舞踏以外のダンススタイルではほとんど問われることがないということだ。ここで哲学的な議論をしたいのではなく、私が舞踏の場でこうしたことをしたときは「下肢を持ち上げていられない身心の何か」によって「そうなった」という点である。他の人にどのように見えているかは分からないが(もちろん、どう見えているかということ自体に私は関心がない…)、私には「本当に起きたこと」であり、表現でもないし技術的な反復でもない…と書いても、分かるかなあ…。あまり分かってもらえないできたこの20数年間なのだが…。
とりあえず本人にとって本当かどうかということが分からないと、分からなくなることが多い。前にも書いたが、精神科ディケアなどでのダンスセラピーやリラクセイションの指導などで感じることは、多くの人が「本当に苦しんでいる」ことである。「本当に身体を動かせない」「本当に動けない」状態なのは、精神科に来訪している理由とも関わっているが、投与されている薬の影響、睡眠時間の少なさや疲れやすさなども関わっている思う。いずれにしても「本当に何々ができない」という点において、実に誠実に「できない状態にある人たち」を長年見てきたこともあり、頭で考えて何とかやり繰りしようという努力の現れ方もよく見えるようになったと思う。元々、私が舞踏の世界にはまり込んだのは、舞踏の集中合宿を主宰した山海塾の蝉丸は、動こうとする練習生の意思や意図を実によく見抜いていたことに衝撃を受けたことによる。
「動かそう」「動こう」とする意思の真実性はよく分かる。舞踏はそうしたことからも作り上げられているが、「脱力」の意思とは何か。技術的に「力を抜く」ということが「力を抜こうとする意思」として真実であることも分かる。しかし、何かの理由でふいにスコンと力が抜け落ちたとき、それは意思ではない。問題は、「意思」ではない何かによって人が動く・動かされるということが、舞踏(少なくとも偶成天の舞踏)ではひどく重要であり、身心の「本当のこと」につながっていることなのである。
(森田一踏 10/23,2011)
見られるということ…
舞踏以外の踊りの人と話していていろいろな違いを感じるが、その一つが「見られること」についての感覚の違いである。全体的な印象としては「観客に見られることを過剰に意識している」ということだが、たまに「見られることへのノイローゼ」とすら感じることもある。舞踏における「見られること」についてすでに何度か書いたが、かつて山海塾の蝉丸は、舞踏レッスンの際には部屋中の鏡を布あるいは新聞紙などで覆っていた。見られることに意味があるはずの踊りのレッスンなのに、鏡を見ることを拒んでいるわけである。ただし、「レッスン中に鏡を見ないようにする」のには合理的な理由がある。動きのレッスンの最中に鏡を見たら、もうすでの形や動きが崩れているから「見ない」のである。それくらいならば、ビデオなどで撮影しておいて練習の後で見る方が良いというのが蝉丸の指摘だった。
実は鏡を使わない稽古にはさらに本質的な意味がある。それは、鏡を見たりするなどのように視覚偏重にならず、自分自身の身体感覚を鋭敏にして、身体そのものへ沈潜するのが舞踏には重要だという決定的な理由がある。最近は視覚偏重の度合いがますますひどくなっているため、自分自身の身体感覚や身体的な状態への感覚がふだんの生活では養われにくい。農業や漁業や林業などの一次産業では、身体というのが重要な要素であり、自分の身体を効率的かつ適切に使っていくため、身体性と身体感覚が常に第一義的な位置づけにある。物を持ち上げたり運んだり置いたりなどの当たり前の動きの中で身体的なセンスが磨かれるからだ。かつて、小さい頃は隠れ家や林や廃墟などに誰にも見られず、自分の好きなように動き回って遊びほうけているとき、誰かに見られている…ということでは得られない自由さや主体性が嬉しかったし、身体は伸び伸びとしていたと思う。
かつて、舞踏公演のチケットに「拝観料」と印刷されたものがありへーっと思ったことがある。観客に見ていただくとか、見られるとかの意識ではなく、見ていても特にいじめたりしないので「見ていても良いですよ」というスタンスだった。だいたい、舞踏の歴史では公演を打っては赤字の額を増やしていくことになるので、見に来た観客には感謝の念を持っているけれども、特に観客のために踊る…とかの意識は薄かったと思う。極端な言い方になるが、舞踏手として人生を賭けて踊ってきた…(確かにそのように生きてきた舞踏家の言葉)その舞踏とその公演に、たかだか数千円程度の金子を支払った程度で「観客」だとのぼせ上がられても困る…。確かに困る。
正直に言って、少なくとも私は観客のために踊るという意識はないし、観客のために踊ったということもないと思う。わざわざ見に来てもらったという事実は本当に有り難いことなのだが、だから観客のために踊る…というようにはならない。それはそれとして、自分は舞踏という踊りの場に立つことに専心していて、そこに観客がいるかいないかはそれほど大きなことではないといえば良いだろうか。少し言い過ぎてしまえば、観客に向かって踊りを見せているのではなく、私の意識は観客を通り越していて、観客の上にある天井やその上の虚空や、自分が立っている舞台を下に素通しして観客が座っている座席の底の床下の暗がりにつながったり、ときには観客の心臓や内蔵に向かっているためである。
それはそうなのだが、しかし、「見てくれる人が居る」という事実には本当に大きな意味がある。一人で山の中で踊る…というのとは根本的に違う意義が含まれている。「公演」という言葉には「おおやけ」という文字が使われている。「私」のものを「おおやけ」にするという意味合いだが、私のようにやや独善的な匂いのするあり方を含めて、人前に立っているという事実そのものがとりわけ重要だと感じている。もちろん、「見る・見られる」関係についての理解や観客との関わりは、最終的にはパフォーマーの考え方や思想や信念に属するとは思うので、私の姿勢は私自身の舞踏についての考え方に過ぎない。
少し角度を変えてこの「見られる」ことについて考えてみる。ミシェル・フーコーと言うフランスの歴史哲学者・社会学者…位置づけは難しい…が、「一望監視装置 パノプチコン」という概念で、神の目のように一目で多数の人を見張る施設を位置づけた。監獄の構造などがその典型例だが、北海道大学の恵迪寮(けいてきりょう)は、「上から見ると雪の結晶の形で…」といった典雅な説明もあるが、構造は18-19世紀の一望監視施設である監獄と同じ設計思想になっている。それはともかく「神の目のようなもの」によって、自分が一方的に「見られる」「監視される」というのが「近代」という1-2世紀前の基本的要素としてある。小さい頃から我々は保護者などによって「見守られる」「見張られる」…などの「見られる立場」を長く過ごすことになる。それと同じような視線によって個人的にあるいは一望監視施設などに象徴される視線によって、自分自身が「見られる側」へと追いやられているとしたら、少し気味が悪い。非社会的・反社会的ないし脱社会的であるはずの舞踏が、「見られる」「監視される」というものへあっさり落ちてしまうなら、かつての前衛芸術・アバンギャルドの「暗黒舞踏」の面目がすたるように思う。
(森田一踏 10/24, 2011)