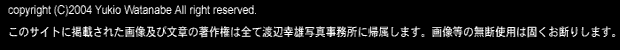久しぶりの更新
(13.6.7記) |
大変ご無沙汰しております。気がつけば、はや6月。もう少しでコトしも折り返し地点とは。月日が経つのが早く感じるのは気のせいでしょうか?今年も4月の穂高・涸沢の小屋開け(涸沢関係者はなぜか「戸開け」という言葉を好んでつかっています)から断続的に山に入っています。
例年よりちょっと早い梅雨入りかと思いきや、今のところ梅雨らしくない天候で、例年の6月上旬といった好天が続いていますが。さすがにこの先の天気は梅雨らしくなるのでしょう。と言うより梅雨らしい天気にならないと今度は夏山が心配。さらに秋の紅葉まで影響が出るでしょうから、なおのことです。
5月の山はあまり雨に恵まれなかったため、あまり雪解けは進んでいないようです。雪解けには気温も関係しますが、より重要なのは雨が降ること。コッフェルを沸かし雪から水を作る際、そのまま雪だけから始めるより水を少し入れてスプーンなどで切って暖めた方が早いのと同じ原理です。解らない方は冬山で試してみてください。燃料の消費も違います。
夏山の山雑誌では北アルプスや絶景特集等で執筆しておりますので、そちらもご覧ください。
|

コナシ咲く上高地
2013年6月3日
Canon 5D Mark3 EF24-70mm F2.8L USM |
今日の美ヶ原は明日の北アルプスか?
(13.2.6記) |
久々に更新します。先日スノーシューの足慣らしを兼ねて美ヶ原高原を歩いてきました。そこで見た光景がこの写真です。約20頭のシカの群れです。若いオスが角を突っつき合っている姿も見られました。八ヶ岳周辺を始め、長野県では近年シカが増え、対策として狩猟による捕獲ならびにジビエ料理で地産地消を推進していく方向のようですが。
この写真は望遠レンズでの撮影ですが、距離があるため点でしか写りません。200m以内に近づいていくと警戒して距離をとっていました。夏は牛の放牧地ですが、冬はシカの餌場となっているようです。麓の松本の中間山地には、下の農作物の被害を食い止めるためシカの防御柵がされてはいるのですが、完全には防げていないようです。
去年にはとうとう北アルプスでもシカの目撃情報が報告されました。後立山の稜線近くとのことです。南アルプスを始めとする各山域で、シカの食害により高山植物が減少しています。やはり北アルプスにも入ってきてしまうのでしょうか。
野生動物の生態バランスの悪さは何もシカに限ったことではなく、サルなども上高地では木の幹や枝をはぎ取って、森が無残な姿になっています。本来なら野生生物を間近に見られる事は自然の豊かさの表れではあるのですが、日本のような不完全な生態系では、ちょっとした自然界のバランスが崩れるだけで絶滅してしまう生物ができてしまうのが難しいところです。
北アルプスのお花畑が他のエリアのように柵で囲われた場所だけにならないよう願ってやみません。
|

美ヶ原高原より
2013年1月29日
Canon 5D Mark3 EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM |
秋から冬へ
(12.11.7記) |
久しぶりの更新になってしましました。夏から秋へと季節も移り変わり、北アルプスなど標高の高い山では、雪山の季節となりました。北アルプスの主だった山小屋もシーズンを終え、これからは本格的な冬山となり、自然本来の静かな山が楽しめるようになります。
今年は秋の長雨がなく、9月も人気が多く、山は賑わっていましたが、反面、こんなに人が居て良いのかという気もしました。実際、10月下旬から11月上旬に掛けて穂高では行方不明者が2名も出ており、さすがに夏山感覚で来てはいないのでしょうが、秋の穂高の厳しさを知らずに登ってしまった結果なのかと思わざるを得ません。
例年この時期に行くネパールは、今年はナシ。ちょっと寂しい気もしますが、またの機会にしてこの秋は国内の山で過ごします。
|
 槍ヶ岳/北穂高岳より 槍ヶ岳/北穂高岳より
2012年11月4日
Canon 5D Mark3 EF24-70mm F2.8L2 USM
|
雷事故のこと
(12.8.22記) |
今年の夏も雷が発生しています。季節の風物詩と言ってしまえばそれまでですが、山でも落雷により尊い命が失われました。
夏山では午後は雷の発生は当然のこと。昔から「早立ち、早着は山の常識」と言われています。稜線では特に危険性が増します。もちろん森林帯の中でも高い木の下で側雷による事故もありますが。しかし危険度は段違いでしょう。
8/18にあった槍ヶ岳での落雷事故。槍ヶ岳はご存じのようにあのような形のため、周辺では最も高く突き出ていて、雷が落ちると言うより、雷を引き寄せる避雷針となっています。
この5月にも落雷により、クサリや山頂の祠が破壊される被害がありました。何年かに一度は死亡事故が発生しております。この数年はなかったので、そろそろ危ないと思っていて、山岳雑誌のガイド記事や週刊ヤマケイ(12.8.16号)など書ける場所では注意を喚起してきましたが。それだけに残念な事故であります。しかも聞くところ今回も槍ヶ岳山荘で登頂している事に気づき、スタッフがメガフォンで呼びかけて下山を促したというのに、そのまま登ってしまわれたそうです。ちなみに槍ヶ岳山荘には雷探知機が設置されており、落雷の可能性がある場合は警報が鳴っているのですが、それすら気づかない人が多いようにも思えます。
危機管理の一番大事なことは、あらゆる事故の可能性を考えることにあると言えます。ご本人には酷なようですが、本人にとっては想定範囲外の出来事だったのでしょうか?
|
 槍ヶ岳/槍の肩より 槍ヶ岳/槍の肩より
2012年8月5日
Canon 5D Mark3 EF24-105mm F4L IS
|
14年ぶりの屋久島
(12.6.26記) |
6月の上旬、久しぶりに屋久島へ行ってきました。実に14年ぶりの訪問(今年は島づいてますなあ)。今回で3回目の訪問ですが、目的は屋久杉とヤクシマシャクナゲ。前回も同時期でしたが、シャクナゲもきれいに咲いていました。地元に人からすれば今年は当たり年とは言えないらしいけれど、充分堪能できました。今年の花は、5月までの気温が低い為、例年よりどこも遅め。一気に暖かくなったようで、登山口から山頂部まで、花を楽しむことができました。
縄文杉は左腕が掛けてしまったり、翁杉が倒れてしまってなくなっていたり、ニュースで見知っていましたが14年の歳月の流れを感じました。
縄文杉を訪れる観光客も以前に比べ倍増以上。若い方が多かったのとガイド付きのグループが多いのには驚きました。レンタルの装備も貸し出しているようです。ほとんどが往復9時間の日帰りで、大杉歩道を往復コース。こちらは新高塚小屋までなので、のんびり縄文杉と対話をしてきました。天気も3日目と最終日の下山は降られたものの、雨もまた楽し!といった山歩きを久しぶりに感じることができました。森の撮影は晴れより曇ったりした方が雰囲気が出ます。改めて屋久島の森の懐の深さに触れ、森のエネルギーを受けてきました。
ウミガメの産卵時期にも当たるのですが、今回は残念ながら計画に入れてなかったので見られませんでした。次回行く機会があれば、産卵や孵化した子亀にも会いたいものです。
|

屋久島/縄文杉
2012年6月10日
Canon 5D Mark3 EF16-35mmF2.8L 2 |
GWが終わって
(12.5.11記) |
久しぶりに涸沢、北穂と2軒の山小屋の小屋開けに行ってきました。GWも含め2週間、穂高で過ごしてきました。
GW前半までは好天が続き、ほとんど雪が降りませんでしたが一転、後半はメイ・ストームとなり、白馬岳や穂高周辺で気象遭難が多発してしまいました。GWにしては全体としては穏やかな方だったのですが、それでも10名を越える登山者が北アルプスで亡くなってしまいました。この季節の3000mは急に天候が変化します。寒気が入れば当然マイナスの世界で、風も10mは優に超えます。まだまだ稜線では真冬なみの装備が必要な時期であります。
この季節、稜線で最も恐いのは雷。油断していると知らぬうちに雷雲の中にいることに。夏と違い、いきなり雷が落ちてくるので要注意です。
GWが開けてからですが、先日(5/9)の雷で槍ヶ岳の祠も崩壊してしまったようです。槍は元々あのような形なので、穂先にはよく雷が落ちるのですが。確か昨年か一昨年奉納したばかりだったはず。GWではなく、人的被害がなくて良かったです。これも神のご加護か?最も槍ヶ岳の開山は播隆上人ですから、神ではなく、仏の山なのでしょうが。
関東では竜巻が発生して、被害も出ました。「たかが天気、されど天気」自然の中にいる以上関わらざるを得ないのですが、情報を正しく掴み、正しく行動したいものです。くれぐれも安全登山を!切に願っております。 |

涸沢岳/涸沢より
2012年5月5日
Canon 5D Mark2 EF24-700mmF4L IS
|
近くて遠い場所
(12.3.22記) |
今回のショートエッセイの写真は、ザトウクジラの親子です。先日昨年世界遺産に登録された、小笠原諸島へ行ってきました。ホエールウォッチングの際、撮影したカットです。普段は山ばかりなので、勝ってが違うのですが、広い太平洋を回遊している彼らの生命力を感じ、力を貰ってきました。
星野道夫さんの言葉に「遠くにある自然を想うことで幸せを感じる」と言うような(正確ではありません)言葉がありましたが、まさに自分の日常にはない自然環境に今回改めて触れ、感じてきました。
ザトウクジラは星野さんの写真にもでてきます。アラスカで夏の捕食期を過ごす彼らは、この小笠原周辺が繁殖地です。他にもハワイ周辺や沖縄などにも移動するようです。この小笠原諸島とアラスカは彼らによって結ばれているのです。
3・11のというか、今回のFUKUSHIMAの原発事故の影響が彼らにどんな影響があるのでしょう。地球環境は非常にデリケートであり、かつグローバルです。アラスカと小笠原が繋がっているように小笠原やアラスカ、ハワイなどもまたFUKUSHIMAと繋がっているのです。放射能汚染水を海洋に廃棄し、何年も影響が残るようなことをしたのは我々日本です。
同じ時代に生きていてくれた彼らに感謝すると共にこのかけがいのない自然を見守り続けていかなくてはと心を新たに致しました。
|

ザトウクジラの親子/小笠原諸島・父島周辺
2012年3月17日
Canon 5D Mark2 EF100-400mmF4.5-5.6L IS
|
寒中お見舞い申し上げます
(12.1.29記) |
この正月は燕岳から蝶ヶ岳・上高地へ抜ける予定でしたが、正月期間中の天候があまりよくなかったため(とはいえ本当にひどい程でもなく)、常念岳から下りてしまいました。北アルプス南部では、今年は正月過ぎまで雪の量がかなり少なめでした。
その後は霧氷の上高地を撮りに行きましたが、あとは雪のため出掛けず自宅で過ごしております。この雪は1/20から断続的に降り続き、松本市の高台、中間山地に位置する我が家では珍しく雪の日々となっています。屋根の上に積もっている量も15センチ程ですので、長野県北部や新潟、北陸と比べればさほどではないのですが・・・。この一週間ほぼ毎日の除雪作業は、毎日の日課になりつつあります。例年だと松本では雪の日が連続するようなことはないだけに、今年の冬の状況にはちょっと驚いています。日影の部分では年末の降雪以来雪が溶けず、根雪状態となっているほどですから。
とはいえ寒さも今がピーク。この寒さを逆に楽しみましょう。 |

|
久しぶりのネパール
(11.12.13記) |
久しぶりといっても一年ぶりですが、ネパールへトレッキングに行ってきました。今年はツアーがキャンセルになってしまいましたので、完全な個人トレッキングです。カトマンズのタメルを歩いていても声を掛けられるのは中国語!日本人が少ないことが分かります。
今回は普段ツアーでは行けないマカルーBCへ足を運んでみました。ツアーだとどうしてもメジャーなエベレスト街道やアンナプルナ方面が人気のため、マイナーなトレッキングコースは集客できないのです。まあ僕の営業力不足もありますが。
写真はマカルーではなく、途中の4000m超えの峠からのメラ・ピーク。ここからだと大きな山容がはっきり分かります。何年も前に登ったときには分からなかったのですが、どっしりした形のいい山で、一見西岳付近から見た穂高連峰のよいうに見えてしまいます。
今年もいよいよあと2週間余りとなりました。来年も元気に安全に山を歩いて行きたいと思います。皆様も良いお年をお迎え下さい。 |

メラ・ピークを望む/シプトン・ラより
2011年11月25日
Canon 5D Mark2 EF100-400mmF4.5-5.6L IS |
夏の終わりに
(11.09.10記) |
8月も過ぎ、とうとう9月に入ってしまいました。今年の夏山はどうも乗り切れない夏でした。海の日やお盆などの休日は、まずまずの安定した天候だったので楽しまれた方も多かったと思います。それ以外は連続して安定した天気とは言いがたく、ただただ忍耐の夏山と今年の夏は記憶に残りそう。
先日のゆっくりした台風12号も進路予報が西へ西へと移動し、一時は中部山岳を直撃との予報もありました。結果は紀伊半島を始めとする地域に甚大な被害をもたらしました。1週間で1800mmなんて聞いたことがない。甚大な豪雨だったと思います。被災された地域の皆様にお見舞い申し上げます。
この台風の前後で夏山の取材はなんとか先が見えてきましたが、夏山シーズン前の取材山行予定からすると1/3もこなせないほど。夏空が恋しい年でした。
この夏もまた悲しい事故がありました。所属している日本山岳写真集団の仲間である中司茂男氏が黒部川の上ノ廊下で遭難されました。前回この欄で遭難事故の注意喚起をしていただけに、心が痛みます。集団同人の中では比較的年が近く、穂高を撮影中に山中で会ったこともありました。地方公務員の傍らで時間を取っては山に通い続けていた写真家です。まだやり残したことがたくさんあったでしょうに。気の毒でなりません。心よりご冥福をお祈りいたします。
また8月下旬に写真学校の同期生である田中氏が病気で亡くなったと連絡がありました。もうそんな歳に足を踏み込んでいるのだと今更ながら気づかされます。「今、この一瞬一瞬を生きる。輝きをもって生きていきたい。その証が自分には写真表現だ。」と思っています。まだまだ未熟者ですが、自然や山に情熱を持ち続けていきたいと思います。
|
|
夏山本番!
(11.7.15記) |
今年は早くも梅雨が明けました。この3連休は後半台風の心配がありますが、予報ではまずまず。一気に人の入り込みとなりそうですが、夏山シーズン始めは注意も必要です。
まずは残雪によるスリップ事故。今年の梅雨は雨が例年に比べて少ないところと極端に多いところに分かれています。北アルプスで僕の良く知っている穂高では、春の雪が多かったので稜線上は雪解けも一気に進み例年なみか少なめ。涸沢などの沢筋はまだまだ多く、この連休はテントもまだ雪の上。涸沢周辺でのスリップに気をつけてください。
稜線を歩く上での注意は、シーズン始めでまだ浮き石が安定しておらず、落石の危険があります。落石注意と一言書くと皆自分に当たるのではと上ばかり神経がいきがちですが、別に自分の足下にある浮き石を落とさない注意喚起の意味もあります。
山では起きる事は、どこかの政府が言うような想定外という事はありません。身の危険に関する想像力を常に持っていれば、もし起きたとしてもその後の対応が違ってきます。もちろん事故を起こさない事が重要ですが。
リスク対効果というのが危機管理の基本です。その辺りをご理解の上、山を楽しんでください。
|
|
梅雨空の下
(11.6.16記) |
僕の住む信州では、今年は例年より早く5月下旬に梅雨入りとなりました。いつもの年だと6月上旬は梅雨入り前の移動性高気圧に覆われる日が多く、晴れの日が続くのですが、今年はあまり晴天が続きません。例年は梅雨入りしてからも最初の雨の後は前線の動きも落ち着いて、南岸の太平洋側は曇りや雨が多くても日本海側や中部山岳は天候が安定するものですが。
上高地のコナシも例年より10日ほど遅く開花し、天気さえ良ければ気持ちのいい森歩きが楽しい季節となりました。
3・11以降気になっていたFUKUSHIMAは、収束にはほど遠い状況が続いております。原発というと以前は政治的な問題として考えられてきたと思いますが、奇しくもメルトダウンという現実の前には現状の環境汚染問題として考えなくてはならない問題となってしまいました。本来このページは自然や山の素晴らしさを共感していただく思いで綴っておりますが、環境問題ということでご理解下さい。
6/15に記者発表になった「さよなら原発1000万人アクション(→HPへリンク)」という動きが現実にでてきました。脱原発のための署名活動で、この手の運動では空前の規模である1000万人の署名を集めようとしています。ネット上での電子署名もできますので一度ご覧の上、ご自身の判断でご署名下さい。
震災以降、今できることが何かを考え続けてきました。チェルノブイリ以後に本来ならFUKUSHIMAがああなる前にしなければいけない問題だったと思いますが、それでもさらなるFYKUSHIMAを起こさない為には、例え小さくても行動を起こすべきという気持ちでおります。次世代にこれ以上の負の遺産を残さないためにも。そして放射能の被爆をこれ以上増やさないためにも。
そういう意味で6/11のイタリアにおける国民投票は非常に羨ましくもあり、感動的でした。ドイツも脱原発です。日本は何故?一人一人が考えるべき問題です。
|
|
写真展のこと
(11.5.23記) |
今年の正月の東京・銀座から始まった「キヤノンカレンダー展2011・Mountain Harmony光の協奏曲」を札幌で今月いっぱい開いております。開設期間の関係で予定が合わず、仙台展は行けませんでしたが(仙台の方ごめんなさい)、この札幌展が最後になります。
写真搬入並びに初日は会場に詰めておりましたが、週末に松本に戻りました。ホントはしばらくのんびりと北海道を回りたかったのですが、予定が山積みで断念しました。それでも1日時間を取ったのですがあいにく天候が悪く、レンタカーでドライブしてきました。タイミングが合わないときはそんなものでしょう。
この後の予定は、年初頭の品川での写真展分と合わせて、7月20日~24の5日間ですが、地元松本市美術館の市民ギャラリーAで写真展を開催いたします。こちらは完全に自分でセッティングをしなければならず、ちょっと大変ですが。山の行き帰りにでもお立ち寄り下さい。松本駅から徒歩12分ほどです。山岳関係者の皆さんは夏山シーズン・インしているので難しいかも知れませんが。
このところは夏山向け山雑誌の原稿に追われております。梅雨入り前の新緑がきれいな時期ですが、今しばらく我慢の日々を過ごしています。
|
|
FUKUSHIMA原発のこと
(11.4.7記) |
この度の大地震、大津波、原発事故で甚大な災害に見舞われました被災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げますと共に、お亡くなりになった方々へ深く哀悼の意を表します。
自然のことを書き連ねる場所と思っているのですが、前回に続いて今回の災害について思っていることを書きたいと思います。と言うのも今回の災害がこれからの自分の生活にも影響が大きいと思われるからです。またこのエリア付近の自然環境についても今後大きな影響は避けられないと思うからです。
地震やそれに伴って発生する津波。阪神・淡路大震災や今回のように何千、何万という単位で亡くなられ、さらに多くの避難民がでる自然災害の恐ろしさを感じます。しかしそれもある意味、この地球上に住んでいる以上誰の身にも起こりえる出来事です。火山の噴火など自然災害では、明日は我が身という可能性は常にあります。厳しい言い方ですが、生きていく上での業であるもと思っています。
しかしながら、今回の福島第一原子力発電所の津波による非常を含む全ての電源の喪失、並びにその後に起こったメルトダウン(炉心溶融)は別物です。明らかに人災と言っていい出来事です。
今僕が心を痛めていることは、この原子力災害がもたらす環境汚染の怖さです。そしてこの危険なものの存在を判っていながら、何もできずにいた自分自身の弱さ、小ささ。現在このエリアに棲む者として、この後の世代に放射能汚染された大地しか残せないという悔しさ。原発の電力を享受してきた自分たちの世代が汚してしまった、取り返しのつかない出来事です。
我々の世代(1960年代生まれ)以前は、旧ソ連のチェルノブイリ事故(1986年4月26日)はショッキングな出来事として記憶しています。その後反原発という動きがドイツを中心に起き、国内でも「危険な話」(広瀬隆)がベストセラーになり、「Love Me Tender(RCサクセション)」が発禁(というか発売停止か)なるなど反原発の運動がありました。結局は、高速増殖炉もんじゅのナトリウム漏れ事故や東海村JOC臨界事故後でも国ならびに電気事業連合会等は、「原発は安全だ」と言い続け、国策として推進してきました。
震災発生後のニュースで地震ならびに津波に関して、国や東電幹部が「想定外の出来事」と言っていましたが、以前から指摘されてきたが耳を傾けなかっただけです。危機管理で一番重要なことは、起こりうる最悪の状況を考えることではないのか?そして2011年3月11日を迎えてしまいました。世界の人々は「FUKUSHIMA」をチェルノブイリやスリーマイル島同様、永久に忘れないでしょう。そして僕も3・11を生涯忘れないでしょう。
地球環境はグローバルな問題です。CO2の排出削減を理由に「原子力はクリーンなエネルギー」キャンペーンがありましたが、今ではむなしく感じます。僕がこの数十年間危惧していたことが、現実に起こってしまった。この国は世界最大級の放射能(放射性物質)排出国となってしまいました。
そしてこのエリアに棲む一人として今後のことが気がかりです。昔から「知りたいのは事実ではなく真実だ」と思っています。今、TVや新聞に書かれていることの裏というかホントの事を知らなければいけない。
今現在、日本政府が行っていることは、ひょっとしたらリビアのカダフィと変わらないのではないか?直接銃で撃つのではなく、じんわり何十年もかけて体にダメージを与えるもの(体内濃縮)で国民を葬ろうとしているかのようだ。放射線による危険性を軽んじているように見える(放射線は花粉か~?)。パニックを一番に恐れているのは容易に想像できるが、国民を舐めているとしか言いようがありません。放射線の体に関しての影響は、どれくらい浴びても大丈夫というモノではありません。しきり値がはっきりしない以上浴びないこと体に取り込まないこと、これしかありません。事故以来気持ちが沈み込んでいるのは、今後何十年に渡って影響が残る原子力災害の怖さからです。
WEB 上で調べていたらこのようなサイト(→)に出会いました。この予想図はあくまでも相対的なものですので参考までに。
「自分の身は自分で守る」これは山で当たり前の危機管理です。それが気を休めるべき下界生活でも強いられるとは。
とりあえず今年の目標は、家庭菜園を始めようか。これが今のところ自分でできる唯一のこととは。改めて非力さを感じてしまいます。
|
|
東日本大震災のこと
(11.03.15記) |
この度の大地震、大津波、原発事故で甚大な災害に見舞われました被災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げますと共に、お亡くなりになった方々へ深く哀悼の意を表します。
まだ今回の被害全体が分かり切っていないし、進行中の憂慮すべき事もありますが、この数日間の僕なりの思いを綴りたいと思います。命からがら大津波から逃げ切れた人、家や家族、親しい友人を失った被災者、避難勧告で自宅から離れざるを得ない原発周辺住民の方々の気持ちを考えると胸が張り裂ける思いであります。
今自分に出来ることをやる。これしかないのでしょう。中部電力エリアに住んでいるので、節電での効果は少ないとはいえ、エネルギーの消費を押さえる。僕自身はこれまでもエネルギー消費量は少ない生活だとは思うのですが、やるべきことはやらないと。あと募金に協力する(これも経済力がないフリーカメラマンなので、微々たるものでしか協力できませんが)、献血(これも先月したばかりか)くらい。改めて自分の非力さを感じてしまいます。
僕の生活拠点は信州・松本で被災地や東京から離れているので、現在の生活環境では不便さは感じないのですが、仕事の中心はやはり東京からのものがほとんど。今後の成り行き次第では生活に影響がでないとも限りません。つくづく思うことは、自分の仕事というものが平和の上に成り立っているということ。1日も早く平穏な状態になることをとみに願っております。
関東甲信地方では余震や大地震の影響かと思われる地震が続いております。松本市を震源とする地震(M3、震度1~2、一瞬の縦揺れ)がこの数日続いており、個人的には気になっています。糸魚川・静岡構造線の一部牛伏寺断層が近くにあるのでそちらが連鎖を起こさないか心配しています。ニュースでは全く取り上げていませんが、長野・岐阜県境でもあるようです。これ以上の災害に発展しないよう願います
|
|
写真展開催中
(11.2.9木) |
WELCOMのページでもお知らせしておりますように、現在カレンダー展を開催中です。基本的に(仙台を除く)開催初日は会場に終日詰めております。お越しの際はお気軽にお声掛け下さい。
今年は年明けと共に都内での展覧会となりました。初の個展となりましたが、大勢方にご来場頂きました。写真展にお越し頂きました皆様方に心より御礼申し上げます。
写真展では久しぶりにお会いした方々も多く、中には二十年ぶりくらいに会った旧友や同窓生もおり、実に楽しい日々でした。
福岡展は初日のみでしたが会場に詰めておりました。その後ちょっと九州の山へ足を運びました。霧島連山の新燃岳が噴火して大変な騒ぎとなっておりますが、今回はそこまで足は伸ばせず。九重連山の本峰久住山、最高峰の中岳を登ってきました。ここは深田久弥の日本百名山の一山。
山中に法華院温泉があり、温泉の多い九州でも最高所の温泉です。ちょっと温度が高いものの体の芯から温まる、いい温泉でした。
|
|
年末年始
(10.12.29記) |
今年も残すところあとわずかとなりました。色々あった一年でした。個人的には世間の不況にもかかわらず、順調に仕事をさせていただきました。かといっても好景気にな~んにも恩恵を授かっておりませんでしたが。
ともかくこの仕事は体が資本。健康や事故に充分気をつけ、精進して参りたいと思います。どうしたら事故を自分の回りから遠ざけることができるか。永遠の問いかもしれませんが、「出来ることはできる限り、周りに注意喚起を払うこと。」これ以外にないのかもしれません。
年内は正月明けからの展覧会の飾り付けが、最後の仕事となりました。年末年始は寒波の到来で厳しそうですが、西穂で迎えようかと思案しております。
皆様におかれましては来年が輝かしい一年になりますように、心よりお祈り申し上げます。 |
|
ネパール帰り
(10.11.22記) |
当初予定の写真撮影トレッキングのゴーキョは中止となりましたが、別件のツアーでゴーキョへ行ってきました。来年正月からの写真展開催が決まり、写真のセレクションや原稿書きなどやらなくてはならない仕事を何とかこなしたものの、直前に別件の仕事が入り、出発前はかなり慌ただしくなりました。
それでも帰国直後に出さなくてはならない原稿もあって、結局初めてネパールトレッキングにまでMACを持ち込むはめに。
最近のネットや通信事情には驚かされます。携帯は今シーズンなんとE.B.C(エベレスト・ベースキャンプ)までエリアに入ったとか。ゴーキョ方面でもドーレやマッチェルモの上部では可能でした。7年くらい前のマオイスト問題時には、回線が切られ、一般電話ですら不通の時があったのがまるで夢のよう。
ネットもWi-Fiがカトマンズのホテルでは(四つ星ですが)、宿泊者は無料で使え、ナムチェのネットカフェも有料で使えるほど普及しており、これならi-Pad持参がお勧めかも。
充電代を始めロッジの宿泊代は軒並み数年前の2倍近い値上げ、地域限定のインフレの様子。以前はチャーター便が飛んだくらい人気があったネパール・トレッキングですが、最近は何故か下火のようで、10月の最シーズンでも日本人は少なめでした。
今年はこの時期にしては珍しく、1週間ほどルクラ便のフライトキャンセルが続いており(11/20の帰国時現在)、ツアーでは旅程をこなすため(帰国の国際便に間に合うようするため)軍のヘリを有料でチャーターしたり大変でした。最も僕が同行したツアーは運良く、旅程通りのスケジュールをこなせましたが。いろんな事が勉強になったツアーでした。
|
|
キヤノンカレンダーのこと
(10.10.20記) |
昨年春に2011年キヤノンカレンダー写真作家に公募で選ばれ、この5月まで約1年間撮影してきました。ほとんどの撮影場所は、自分のよく知っている北アルプスで行ってきましたが、これまでの撮影とは違った緊張感のある1年間でした。
一番大きな点は、これが撮りたいと狙って撮影に出掛けたからといって、必ずしも狙い通りのモノが撮れない点。自然の中では開花や紅葉など、年によって数週間ズレが生じることも珍しくないからです。天候にも泣かされました。昨年の夏は梅雨明け発表こそ早かったものの、戻り梅雨となってしまい、晴天続きの季節がなかなかやってきませんでした。そんなこんなでH.P.の更新もおろそかになりがちでした。楽しみにしている方(いらっしゃるのか?)にはご迷惑をお掛けしました。と言っても今後頻繁にするという意味ではありませんが。。。。
ようやく2011年キヤノンカレンダーも完成間近となりました。キヤノンのオンラインショップ(登録が必要です)にて販売予定です。また来年1月6日からキヤノンギャラリー銀座にて「キヤノンカレンダー展2011」の写真展。1月5日から品川キヤノンオープンギャラリーにて渡辺幸雄写真展「山稜光景」の開催が決まりました。こちらの詳細は「INDEX」をご覧下さい。
|
|
追悼・磯貝先輩
(10.9.14記) |
8月29日、山岳写真家の先輩であります、磯貝猛さんが北穂高岳・南稜で不慮の事故で亡くなられました。生前のご親交に深謝いたしますと共に謹んでお悔やみを申し上げます。
あまりにも突然のことで、いまでも整理がつきません。あの事故のあった日の前日、僕は涸フェス参加型ツアーに同行し北穂で宿泊、共に一晩過ごしたのに。切なく、いたたまれない気持ちです。
ツアーで涸沢への下山行動中、別件の遭難が北穂南稜であり、救助に向かう山小屋スタッフから先輩の事故を知らされたのでした。無線のスイッチを入れ、ヘリで搬出されるまで現場と県警側とのやりとりを傍受しながら下山しました。トップを歩いていたのでツアー参加者には見られなかったとは思いますが、泣きながら涸沢へと北穂沢を下りました。磯貝先輩がヘリでピックアップされ、涸沢小屋に着いた時には、たまたま居合わせたスタッフ(モッサン)に抱きつき、彼の腕の中で泣き崩れてしまいました。
事故が起きないようにするにはどうするべきか?自分を含めて「事故を起こす可能性がない人はいない」という原則に返って考え、行動していきたいと思います。
|
|
夏山シーズン!
(10.8.11記) |
夏山シーズン真っ盛りです。今年のシーズン初めは谷筋の残雪も多かったのですが、その分まだまだ高山植物も見応え充分。特に今年は「梅雨明け10日の雨知らず」という、従来のことわざがそのままの近年まれな好天続きとなりました。
個人的には今年は下での作業や撮影が多く、登ったり下りたりで余り山に浸っていないのですが。ここらで気を取り直し、集中していきたいと思います。と言っても山に登っていない訳ではなく、梅雨明けと同時に表銀座、裏銀座の一部、乗鞍岳や穂高等を彷徨っていましたが。
山と溪谷社主催の“涸沢フェスティバル”は今年も8/27-29に開催されます。僕は今回、北穂高岳登頂コースで回っています。間もなくエントリーも締め切りとなりますが、振るってのご参加をお待ちしております。
さて、夏も後半戦。体力商売ですが無理せず、楽しみながら夏山を駆けめぐりたいと思います。またどこかの山でお会いしましょう。
|
|
春なのに
(10.6.5記) |
GWだけはなんと穂高に入りましたが、以降はなかなか山に行けずにいます。仕事的には回っていると言えるのですが、山の空気が恋しい。5月ってこんなにだるかったっけ。とPCの前にいる時間が長く感じています。
いよいよキャノンのカレンダー撮影期間も終了となります。キャノンからお借りしていた機材も返却し、ちょっと寂しい気がしています。おかげで結構楽しませていただきましたが。カレンダーの仕事も大詰めに入り、東京を(それ以外のこともあり)何度も往復した月でもありました。
夏が近いと言うことは、山の雑誌では夏のアルプス特集が組まれる季節です。ガイド記事の執筆等が入ったりして、なんとまあ切れ間無くやってくるものだわいと思わずにはいられません。
そんなこんなで慌ただしく過ごしておりました。家の花木を楽しむ余裕はないのですが、それでも気分転換に庭先を歩き、小さな自然に驚いたりしています。
アップした写真は今日撮影したモノ。そろそろかな?と思っていたのですが、カメラをセットしたのは実に今日が初めて。自宅付近からの写真です。運良く槍の奥に夕日が入りました。PCで調べれば、すぐ分かるのでしょうけれど。
|
|
今年は
(10.4.30記) |
なかなか更新出来ず、ご覧の皆様申し訳ありません。今年は3月中はネパール・カラパタールへ撮影ツアーで出掛けておりました。また帰国後はキャノン・カレンダーの撮影や原稿書きとフリーの人間としては大変有り難い事ですが、忙しい日々を送っております。
そうそうその間にもお知らせしていましたように日本山岳写真集団展があって、会場に詰めたりと相変わらずと言えばそれまでですが、バタバタしております。
おかげで、今年は涸沢・北穂といった小屋開けの山行きはキャンセル。ご関係者の皆様にはご迷惑をお掛けいたします。
さて、GWです。この冬のデポの回収もあり、穂高へと思っております。
また山でお会いしましょう。
|
|
今年は?
(10.2.25記) |
久しぶりの更新です。時折訪れてくれている皆様、ご無沙汰しております。また、懲りずにご覧頂き誠にありがとうございます。
さて、僕の近況ですが、越年登山は穂高で過ごしました。2週間ほど穂高岳山荘の冬期小屋で、寝正月を過ごしておりました。その間誰も来ず。もっともあの天候なので、無理でしょうが。国内というのに貸しきりである意味優雅に山小屋を使っておりました。
その後は数日単位で山に入ったり、家で写真整理や、家の仕事(ほとんど山小屋生活ですが)、事務仕事に追われておりました。
3月はネパール・カラパタール再訪です。今回はどんなエベレストが見られるか。楽しみです。
また4月9日から15日までは、日本山岳写真集団展が六本木・富士フイルムフォトサロンであります。そちらも是非ご高覧ください。
|
|
一年ぶりのネパール
(09.12.08記) |
ツアー会社の仕事で一年ぶりにネパールへ行ってきました。今回は10日間のショート訪問。8000m峰が2峰見られる展望地、プーンヒル。ダウラギリやアンナプルナ山群を見渡す、3100mの高台です。
下山は温泉のある(プールです)タトパニ。「タトパニ」とはネパール語でお湯(熱い・水)という意味。個々はジョムソン街道として、昔から人や物資の行き来のあるインド・チベットの交易路。チベットを訪れた最初の日本人として知られる河口慧海ゆかりの街道でもある。
このジョムソン街道が今年の春から車が通るようになった。かつてここを何日も掛け歩いたことがある身としては、隔世の感がある。もっともダートの連続であり、従来でも馬の隊列が行き来し、カリ・ガンダキ川沿いの平坦な道だったが。歩かずにムクチナート(仏教・ヒンドゥー教の聖地)へ行けるという。まさにインド人もビックリだろう。
今回はもう一つ驚いたのはタダパニやゴラパニの村で携帯が通じるようになっていたこと。ちょっと前のマオイスト問題時は一般回線も切られていたというのに、今では普通に(時間帯によってはOFFでしたが)日本へもダイレクトで繋がってしまう(音声のみ)。ネパールの山中にいて、別件の仕事の話をするのも落ち着かないが、可能になってしまった。急な仕事依頼の場合、連絡が付かない方が有り難かったりするのでちょっと複雑な思いでもある。
来年春に写真撮影ツアーでカラパタールを予定していますので、興味のある方はセカンドページをご覧下さい。
|
|
秋も終盤戦
(09.10.17記) |
稜線から始まった紅葉前線も登山口の上高地まで降りてきました。今は1500mから2000mにかけてが見ごろのようです。この夏の天候には泣かされましたが、何とか無事シーズンを終えることができそうです。といってもこれからはさらに厳しい自然環境の雪山の季節を迎えるのですが。
当初予定のバルトロ氷河、カラパタールへの撮影トレッキングツアーは残念ながらキャンセルとなりました。お申し込みお問い合わせしていただいた方には大変申し訳ございません。来年仕切り直しをして募集を致しますので、よろしくお願いいたします。
僕の近況ですが、今年もひたすら北アルプスの南部地域を徘徊しておりました。各山々でお会いした方も多かったと思います。またタイミング悪くお会いできず、「ナベの奴、最近見てないなあ。」なんて方もいらっしゃることかと思いますが、これもまた一期一会ですので、どこかでお目に掛けられると思いますのでご容赦ください。
久しぶりの更新となりました。標高の高い山はもう冬もすぐそこ。アイゼン、ピッケルの冬山装備が必要な季節となりました。雪が無くても稜線での滞在では下山時必要になりますので、皆さんもお忘れ無く。
10月の連休初日には雪が降り、大キレットを通過したものの結構シビアでした。数日後北穂から穂高岳山荘に歩荷した際も軽登山靴で歩いている人も多く、よく平気で来るなあと唖然としました。もっと多く積もれば来られないのでしょうが、この季節行けなくもないというのが実に恐いところ。キックステップもできない靴ではどうしょうもないだろうに。自殺しにきたわけではあるまいが。と、いつ事故があっても全く不思議ではない状況でしたが、意外に無くて良かった。けれど確率の問題か。何はともあれ安全登山をお願いします。
|
|
夏なのに
(09.7.30記) |
今年の夏は変。というか梅雨明けの発表後の方がまともに雨が降っており、それ以前は空梅雨の少雨傾向にあったのが、なかなか梅雨が明けきらずしとしと雨の日が続きます。ゲリラ豪雨という言葉が一般的に使われるようになったり、竜巻も発生して、安定した夏の空が恋しくなります。
個人的なことで忙しく、またとうとう僕の愛機i-book君がお亡くなりになりました。現行のOSでは動かないソフトを使ってホームページを創っていたので、にっちもさっちもいかなくなりました。ようやく現行OSの10.4.11のDreamweaverCS4を購入、H.P.の更新ができるようになりました。まあ時間がないのが大きな原因ではありますが。ブログで毎日更新やら返事を書いている人が大勢いるご時世だというのに。時代遅れで申し訳ありませんが、性格上も含めご勘弁ください。
中国・ウイグル自治区の暴動というか制圧?問題もあり、バルトロ撮影ツアーは残念ながら中止となりました。政情の安定を望みますが、チベット同様奥が深い問題です。ここでもチベット同様にウイグル人ではなく、ほとんどの報道でウイグル族でしたね。今後もこのエリアの政情から目が離せません。
マア何はともあれ、早く来い来い夏の空。 |
|
気の早い奴
(09.6.9記) |
上高地では小梨が見ごろとなり、久しぶりに(と言っても10日ぶりですが)歩いてきました。こんな書き方だといかにも行ってきた感じでしょうが、この一週間ほど穂高の稜線にいて、下山ついでといったところですが。
上高地の新緑も落ち着いた感となり、ニリンソウもすっかり咲き始めのころの新鮮な色が薄れてきたようです。一方小梨平の地名があるように、上高地の森の所々に、白い花を沢山付けた満開の小梨が咲き誇っています。
普段だと小梨が終わり、6月下旬になってレンゲツツジの季節となり、上高地の初夏の風物詩も終焉を迎えるのですが、今年はちょっと違います。アップした写真のようにレンゲツツジがもう咲き出していました。場所は岳沢湿原の外れ。他の木はまだ蕾でふっくらしたオレンジ色で開花までまだ先でしょうが、一本だけ気の早い奴が咲き出していました。今年は全体的に雪の量が少ないせいか場所によって早く咲くのがいるようです。マスコミだとすぐに温暖化の影響と判断しがちですが、まだ自然の多様性にある幅の中にいるとは思います。
いろんな可能性を自然で考えてか、次世代へ受け継ぐべき種を落とす花を早く咲かしたり(昆虫では早く成虫になる奴)逆に他のより遅く咲いたりして絶滅から逃れるために備えているようです。これも自然のもつ多様化の表れなのでしょう。
温暖化は確実に訪れているとは思いますが、自然自体が環境の変化に順応できるかどうかが問題です。種の絶滅を逃れるために彼らなりに自然淘汰されないように必至で今を生きている。そんな姿に僕も力を貰っています。
|
|
|
プレゼンの報告
|
このショートエッセイに以前書いた(09.3.13記)プレゼンテーションの結果報告です。精密機械メーカー・キャノンのカレンダー作家の公募が08年のカレンダーから行われており、今年の公募に応募いたしました。今回が4回目の公募なのですが、実は第一回目より応募しており、今回ようやく選考に通りました。詳細はキャノンのホームページでリリースされておりますので、そちらをご覧ください。(→キャノンH.P.へ)
というわけで、これから先一年間、キャノン・カレンダーの撮影に集中し、恥ずかしくないカレンダーにしたいと思っております。乞うご期待ください。
今回のカレンダーはある意味、これまで撮影してきた山岳写真とは違った切り口での写真撮影となります。これまでの僕の写真とは、全く違う写真で組むこととなるでしょう。自分の写真により深みが増すように一年間頑張って参りますので、温かく見守ってください。
|
|
|
シーズン・イン
|
早いもので5月になってしまいました。なかなかHPに変化がなくてスイマセン。久しぶりにアップします。
GWに向けて4月中旬から涸沢、北穂と小屋開けに行っておりました。それぞれ数日間ではありましたが、久しぶりの穂高を満喫してきました。
現在はJOY夏号等の執筆活動中です。GW後半は再び涸沢で取材となります。
この時期は夏に向けて夏山の出版が相次ぎ、また何ページか写真掲載の記事他があり、これでも何かと忙しい日々となっています。松本の桜も葉桜となってしまいましたが、山に行けばまだまだピンク色の桜が点在して花見を楽しみながらの山行が出来そうです。5/11、6/15とアルパインツアーでアルペンガイドを使った槍穂高連峰の机上講座があります。時間がある方はお越しください。
また掲載誌が発売になりましたら、「お知らせ」にてアップします。
左の写真は北穂高小屋入山時のヘリ内の映像です。パイロットは知る人ぞ知る「ナベさん」といってももちろん僕ではありません、あしからず。その左コーパイ席に座っているのは我が先輩カメラマンの磯貝猛氏であります。前穂右に写っており、吊り尾根を越えましたが、風が強く、北穂到着前に機体が沈み込みましたが、無事着陸、除雪作業に入りました。
|
|
|
春の気配
|
毎年のことだけれど、今年も春の訪れを日に日に感じるようになりました。春になると鼻がむずむずしだし、くしゃみが出始めます。体で感じる春の風物詩です。まだこちら松本や山の方ではそれほどでもないのですが、先日都内や実家の埼玉に行った時は、一日に何度となくくしゃみがでて、鼻もぐすぐすする有様。梅の花が咲き出す季節から桜の咲く時期までが僕のいやな意味での春となります。
でも自分では花粉症ではないと信じているので、医者にも行かず自然治癒というか季節の去りゆくのを待ち、耐え続けています。医者に行って花粉症の断定をされるのが嫌なだけとも言えますが。
先日八甲田山に行ってきました。この時期は樹氷で知られているのですが、やはりというかひどいものでした。2月があんなに暖かかったのだから無理もありません。気を取り直し来年もまた行ければと思っています。
先月都内で、今までで最も大きなプレゼンテーションをしてきました。僕を直接ご存じの方はお判りのように、プレゼンやコンペに弱い僕です。結局は写真次第なのでしょうから相手の望む写真が提出できなかったから落ち続けるのか。とほほ。さて今回の結果はいかに。細かいことは別の機会があれば書きます。
|
|
|
また暖冬
|
ついに暖冬もここまできたか、この数日間そんな感じでおります。2/14には松本で19.7度。平年より14度高い気温で、4月上旬から5月上旬並だそう。各地で春一番の強風も吹き荒れ、このまま春になってしまうかと思うと夏のことが心配になります。自然のことだから一気には春に向かわず、それが却って異常とも言える天候になるのでしょうが。
この何日間かの温かい時期は、雪の層にしっかり刻まれたことでしょう。春に山小屋の除雪面を見るとしっかりわかるはずです。直近では、これまで降った雪と今後の降雪で弱層面ができるので、この一週間で山には入る方は十二分にご注意を。雪崩の危険が高くなる季節になります。晴れていても雪崩れるときには雪崩れます。
自然を撮るカメラマンにとって、天候は一番気がかりなこと。冬らしい冬があってこそ夏らしい夏がやってくるし、鮮やかな紅葉の彩りもあると思う。こんな状況だと、天候不順(空梅雨だったり、盛夏がなかったり)になってしまうのではと今からはらはらしている。
この冬は西穂や上高地に入ったりしていますが、長期の山行はなく、松本ベースで写真整理や原稿書きをしています。ディスクワークは元来好きではないので、なかなかはかどりませんが。そろそろ確定申告の計算もしなければと思いながらも、天候を見ながら山へ脱出する頃合いを見計らっています。
|
|
|
明けまして
|
2009年の年明け、皆様如何お過ごしでしょうか?
僕の方は年末までネパール、キリマンジャロと海外を駆け回っていたので、正月は下界で過ごしておりました。諸事情があり、20年ぶり?に関東(埼玉の実家)での越年でした。丑年ですので、お仲間の「ヌー」をアップしました。キリマンジャロ登山の後廻ったンゴロ・ンゴロN.P.での一コマです。
今年一年元気で、事故のない年にしたいと思いを新たにしております。もちろん優れた山岳写真を撮るというのが目標であるのは、今までと変わりはありません。カメラマンは撮れてなんぼの商売ですからね。
昨年は夏以降、モンゴル、パキスタン、ネパール、タンザニアと海外を飛び回っておりました。そのため、あわただしく時が流れてしまいましたが、ようやく撮影した写真が見られる時期となりました。ここしばらくは、撮影してきた写真(山積みになったまま)の整理で追われそうです。例年冬の期間しかできないモノクロのプリント(暗室です)などもあり、冬の間も何かと忙しい日々を過ごしております。なかなか実益には結びつかない作業ですが、一枚一枚の写真とじっくり向き合える大切な時間でもあります。
|
|
|
久しぶりにネパールへ
(08.10.27記)
|
残念ながら集客が芳しくないため「ネパール三大ピーク・撮影トレッキング」は中止となってしまいました。来年また募集をしたいと思いますので、今年お申し込みいただいた皆様、並びにご興味をお持ちの方は来年の企画にご期待ください。
撮影ツアーでは行けませんでしたが、個人的にこの2年ほどネパールを訪れていなかったので、今年は時間を作って出掛けて参ります。
この夏以来“移動の民”となっております。7月の海の日以降この10月20日までの3ヶ月間、自宅を含め4連泊(?)以上しませんでした。ようやく一箇所で5晩過ごしたのが北穂高小屋。松本はほとんど洗濯所・着替え場所と化しています。年によっては取材中に悪天のため、同じ山小屋に1週間停滞を余儀なくされることもあるというのに。こんな年もあるのですね。
ゆっくりというか、じっくり腰を落ち着けた方が良い作品ができるのは判るのですが。まあこれもタイミングなので、なるようにしかならないか。
で、ネパールです。今年は海外付いているようで、再び長期取材となります。海外の山は海外の山でライフワークとして取り組んでいかないといけないので、踏ん張りどころでもあります。国内の仕事をおろそかにするという意味ではありませんので、編集者の皆さん(このHPを見ているのでしょうか?)、お仕事ください。
まあ何はともあれ、自然の中に入り浸っていることには変わりありませんネ。
|
|
|
海外トレッキング
|
集客人数が少なかったものの何とか今年はツアーが催行でき、バルトロ氷河撮影トレッキングへ行ってきました。32日間の長いツアーでしたが、比較的天候に恵まれた為日程も順調に進み、予備日を使わず下りてきました。余った日は宮崎駿の「風の谷」のモデルと言われる、風光明媚なフンザ(カリマバード)で過ごしてきました。
個人的には行きたかったウルタル峰BCですが(長谷川恒男氏の墓参り)、又の機会となります。生前のあの人を思い出しながらのトレッキングでもありました。
日本の山は秋真っ盛りの季節となりました。季節も足早に移っていきます。10月は日本の秋を楽しみ、下旬からはネパールへ参ります。ただし、募集しておりました「ネパール三大ピーク撮影」は残念ながら催行されませんでした。また次回企画を考えたいと思います。
今年は長期の海外取材・ツアーが続きます。そこで問題なのが、最近デジタル化しているためバッテリーが一番の悩みの種。GPSやフォトストレージ、カメラなどバッテリーが無くては動かないものばかり。さすがにPCまでは持って行かないものの、ツアーであれば非常時の連絡手段として衛星携帯も持参せざるを得ません。
基本はリチウムイオンの予備バッテリー。それぞれの機種の専用電池を持って行きますが、さらに非常用に外部端子から充電するリチウムイオンのバッテリーも持って行きます。7.2Vで4,400mAhと大容量なので重宝しています。JTTというメーカーの“My Pro n”という製品です。興味のある人はお試しあれ。
|
|
|
悲しいこと
|
この夏の終わりにまたしても知り合いのガイドが遭難事故に遭い、命を落としてしまいました。例えどんな状況であれ、事故は絶対に避けなければならず、遭難が発生してしまった以上は判断が甘かったと批判があるのもプロである以上は背負わなくてならない宿命です。プロとはそういった厳しい状況下であっても顧客を守らなければならず、新聞報道等でみる限りその状況下では職務を全うしたと思うのですが。プロガイドではない僕には彼を批判することはできません。
あの日、とあるガイドと赤木沢の沢登りに行く予定があり、登山口の折立に向かっていたのですが途中で中止となり引き返しました。上高地に入り、南岳に取材に向かうかどうか迷ったあげく、今日は寝不足で適切な判断ができないと思い、明日に延期をして松本で昼寝をしていました。夕方のニュースで事故があったのを知りましたが、名前を知ったのは南岳小屋で。何度か山であったことのあるガイドでした。
山で事故はつきものです。本当は山でだけではなく、日常の延長に山があり、僕のような人間にとっては日常が山なのですが。それにしても悲しいことです。特に知り合いや山関係者の遭難事故は。
事故を起こさないよう自らにも常に言い聞かせ、すれ違う知り合いにも「事故るなよ!」と葉っぱを掛けております。まあ口の悪い親父だと思われているだけかもしれませんが。それで事故が無くなるならと願わずにいられません。
同じ時間を一緒に過ごす、この一瞬一瞬が貴重な時間なのだという思いが募ります。心よりご冥福をお祈りいたします。
|
|
|
梅雨の山
|
梅雨時ではありますが、今年は陽性というか空梅雨に近いようで、あまり雨が降らないのが却って心配でもあります。九州や四国では平年より10日ほど早く梅雨が明け、僕のフィールドである中部山岳も夏本番まで秒読みといったところでしょうか。早くも今年の夏の天候が気になってしまいます。気にしてもこればかりはしょうがないのですがね。
久しぶりに白馬岳から朝日岳へ縦走してきました。もちろん楽しみは梅雨時期に咲くツクモグサやウルップソウ。登山者も少なく、盛夏の花とはまた違った趣があり、見応えある稜線のお花畑を満喫できました。珍しいところでは他にムシトリスミレ。咲いているところには咲くのだと、判っているけれど自然の妙味を感じます。やはり白馬岳は花の時期に限ると改めて思い知りました。
曇り空が多かったですが、梅雨の中休みでほとんど雨に降られず、この時期としては大変ラッキーな山行となりました。
今年は今のところ梅雨の雨が少ないので残雪は例年より多め。夏山シーズン初めは残雪のスリップ事故に要注意です。ストックや場合によってはアイゼン、ピッケルもお忘れなく。
|
|
|
|
春の訪れが遅い北アルプス山中にもようやく芽吹きや山桜、林床を彩る花々が咲き出しました。
3000mの穂高稜線へはまだ沢筋の雪の上を歩かなければたどり着けず、この季節が一番雪面が固くなり、ピッケル、アイゼン歩行がしっかり出来ていないと危険な状況になります。夏に近づいているため油断があるのかもしれませんが、G.W.以上に厳しい山となります。日中の気温はTシャツ一枚で行動できても朝方にはマイナスとなり、一日の気温差が高いので、装備や服装も夏から冬の物まで幅広く必要です。穂高稜線を目指す方は、夏道が完全に出る7月まではくれぐれも装備に怠りなく。
この5月末に山と溪谷社からガイドブック「ヤマケイ・アルペンガイド7 槍・穂高連峰」を上梓いたしました。昨年夏から取材、執筆とほとんどこの本に費やしてきました。ようやくこの度出版の運びとなりましたのでご案内致します。
|
|
|
自然災害
|
ビルマ(ミャンマー)のサイクロンの被害、そして今回(08.5.12)の中国・四川省の大地震。いずれも自然災害ではあるが、想像を絶する規模での自然災害という点ともう一つ共通する問題もある。
軍事政権下のビルマ(ミャンマー)ではサイクロンに対する情報が皆無の状態で上陸、被害を広めた点が否めないが、それでも衛星写真を見ると水害の範囲の広大さは恐ろしい。ほとんど一つの地域が水没してしまったのではと思えるほどだ。チベット同様情報がなかなか外部に出てこないが、かなり甚大な被害が想像できる。G.W.前に大型のサイクロンが発生して上陸の可能性を示唆していた記事を見ていたが、これほどの規模の災害になろうとは。死者・行方不明併せ6万人以上という結果はあまりに惨い。
また一方の中国も震源となる場所が四川省のアバ族自治区で、3月に中国当局による僧侶のデモ弾圧があった地域でもあり、チベット仏教徒の多いエリア。彼らの遭遇している度重なる困難を考えると心が痛む。アメリカならこんな状況下であれば、暴動が発生し、非常事態宣言下になるだろう。
監視のため駐留していた解放軍が救助に当たるという皮肉な事もある(一部の報道)ようだが、実際どうなっていることか。
また気になるのが、この2ヶ月ほど前(08.3.21)に起きた同じ中国の新彊ウイグル自治区での地震も規模が大きかった点(M7.1)。直接の関連はあるのか無いのか専門家ではないので判りませんが、気になることです。ウイグルの地震は、被害状況がニュースで全く伝わって来なかったけれど、今回は都市部に近く、あの国にしてはかなり伝わっている方か。震源地から離れている大都市・重慶市ですら被害が出ているのだから、想像を絶します。同時に自分の無力さを感じます。
最も苦しんでいるのは、今現在も瓦礫の下敷きになっている人。日本の阪神淡路大震災の時もそうだが、当局側が他国に援助要請するのが遅すぎる。この手の災害時における国際協力のあり方を考えるべき時期ではないか?何も武力を持って救助隊が入ってくる訳ではないのだから。悲しいことだが、いつも泣きを見るのは力のない小市民だ。亡くなられた方に心より哀悼の念を表します。
|
|
|
桜咲く春
|
松本も桜が咲く季節になりました。例年より1週間くらいは早いようです。遅い年だとG.W.で満開でしたから。山でも雪解けが進んでいることでしょうが、富士山や槍・穂高など標高の高い山では、この後の5月が最も積雪が多くなります。
今、里で降っている雨が上では雪となり、今でもまだ降っているからです。同時に底雪崩の季節を迎え、降雪後や稜線で雨の時など沢筋では要注意となります。
チベットの状況は予想していたことですが、なかなか真実が表にでてきていないようです。中国側の発表は、大日本帝国軍大本営発表のような感じ(あんな感じだったんでしょう)のメディア統制がされ、改めて自由のない一党独裁政治の怖さを世界に知らしめています。出してきた映像はすべて武器の持たないチベット仏教僧の暴動シーンのみで、重火器等で軍当局が制圧するシーンは一切無し。犠牲者の数も軍や漢民族だけなのでしょう。
サイバーテロの一種と言っていいでしょうが、ダラムサラのチベット亡命政府のH.P.が何者(これが怖い)かによって見られなくなっているとの報道もありました。
政治とオリンピックを一緒にするなという人がいますが、オリンピックは政治です。世界中の注目を集めているこの時期だからからこそ、おおきなうねりになっています。今までのかれらの行動を知っていた人がどれだけいたでしょう。世界中で「Free Tibet!」の声を上げていますが、4/26長野で聖火リレーが行われます。日本では欧米各国のような聖火リレーにはならないのでしょうかね。欧米より歴史的にも地域的にも関係が深いのに。
世界の屋根を擁するチベットは、僕にとっては非常に興味のある地域です。この地域の一日も早い安定を、そしてそこに住んでいるチベタンたちの幸福を願ってやみません。
ネパールのニュースは大きく取り上げていませんが、憲法制定議会選挙が10日に行われ、共産党毛沢東派(マオイスト)が第一党になるようです。独裁だけは勘弁してほしいと思いますが、政情安定を強く望んでいます。
|
|
|
チベットのこと
|
この数日、新聞等のメディアでチベット、ラサの暴動が大きく報じられています。中国当局側(新華社通信)ではチベット族の暴動により市民10人の死亡とあり、公安による発砲、武力弾圧の様子は一切報道せず、「ダライ・ラマ一派の策動」と言い放っています。インドのチベット亡命政府側からは軍による発砲で80人死亡を報じており、この事態を憂慮しています。
報道によると「公安当局などが出した通告は、17日中に自首すれば処罰を軽くするとしたほか、他の参加者の摘発に協力すれば処罰を免除するとして切り崩しを図っている。また、参加者をかくまったら処罰するとしたうえ、参加者の摘発した住民には褒賞を出す」とあり、この事一つを見てもチベット人の迫害の様子が伝わってきます。今さらながら中国の絶対統治の印象を受けました。50年前から何も変わってないのでしょう。
外務省の海外渡航情報で「渡航の延期をお勧めします」とレベル3の危険情報が出ており、旅行ができない状況となってしまいました。海外メディアを一切閉め出しており、何がチベットで起こっているのか、わかりにくい状況ですが、注視し続けたいと思います。
日本のマスコミの内、最も早く報道していたのはTV朝日系で、14日の報道ステーションでこの件を知りました。この国の公共TVであるNHKは、翌朝にトップニュースで報道していましたが、日本のマスコミの報道のあり方も知る機会となりました。チベット人かチベット族かという表現の違いからもでもどう見ているかが判ります。今回の報道では市民という言い方が多く見られ、状況が理解しにくくなっているといえます。中国側に遠慮しての報道と強く感じました。知りたいのは事実ではなく真実です。
二年前の青蔵鉄道開通以来多くの観光客がラサを訪れています。奇しくも今回の事態で鉄道本来の目的である(と開設時から言われておりましたが)軍事利用がされているかもしれません。多くの人民解放軍兵士を運ぶために。
中国の民族問題は以前からいくつかあり、分離独立を求めている新橿ウイグル自治区にも波及することが懸念されています。個人的なことでは、この8月のバルトロ撮影ツアーで中国(ウイグル)から陸路パキスタンに入るので、非常に心配しています。あ~あ。
|
|
|
もうすぐ春
|
3月に入り、松本も春の気配を感じるようになりました。朝起きるとまず手を伸ばすのがティッシュペーパー。花粉症は自認していないのですが、それでもこの季節は、鼻水やくしゃみがよく出ます。本人は気のせいだと思っていますが。
この冬は最近の例年以上に寒さが厳しかったようです。という言い方なのも例年のように野外での活動がほとんどない、フォトグラファー人生初めての冬となってしまったからです。あまり出歩いていないものだから、寒かったのかどうなのかもよく分からなかったということです。この冬は、数回雪かきをしたので、昨年の冬よりは多かったのは確かですが。
冬の間はずっと籠もりっぱなしで、パソコンのお守りをしていたようなものです(決してPCが壊れたわけではありませんが。。。)。画面に向かって原稿の打ち込み作業をずっとしていました。まだ現在も続いていますが、ようやく先(春)が見えたところです。
未だ予定としか言えませんが、この5月に槍穂高のガイドブックを上梓する予定です。昨シーズンの夏から秋は、この取材で山に籠もっておりました。3月に入り、ようやく一段落付いたところで、あともう少し。ラストスパートをかけようかといったところです。お楽しみに。
また今年の年明けから発刊しています、朝日新聞社発刊の「週刊日本百名山」にも号によって、写真・文を掲載しておりますのでこちらもご覧ください。
|
|
|
|
新年明けましておめでとうございます。
今年が皆様にとってよい年でありますように、お祈り申し上げます。
デジタル化をすることで写真家が得たものがあり、また逆に失ったものもある。今回は前回に続いてデジカメの短所と長所を語ります。
まずはプラス面として得たものは、多少の失敗でもフィルム以上に救済が可能なこと。現場で写っているかどうかの確認ができる安心感(またこれは同時に落とし穴でもあるのだが)。ワークフローがPC中心で完結し、プリント出しする際にもボタン一つで可能なこと。このプリントに至るまでフィルム時代だとラボに持ち込み、あがりまで数日かかっていた。自分の色に合わなければリプリントしなければならず、いい調子に焼いてもらうのが大変だった。カラープリント(ネガプリント)を自分でやっていた時代もあったが、薬品の温度管理などかなりの手間だったので、隔世の感があります。顔料プリントだと耐久性がいいのも魅力で、オリジナル・デジタルプリントの可能性も見えてきたかな?
雑誌その他で出版する編集サイドやデザイナーにとっては、データでやりとりできるのでリサイズすれば、極端な話では、はめ込めばOKとなる点。家にいればすぐにデータを送れるは、締め切りタイトな時には助かります(その分仕事が慌ただしい気も。実際問題あまり家にいないので、それがさらに困ることに)。
逆に失ったものは、撮影する楽しみ。楽に撮れることで緊張感がなくなってしまう点。ラボからあがってきて、ライトボックスで初めて撮影したポジをチェックする瞬間の感動。またモノクロプリントの現像液に入れた印画紙から画像が浮き上がる瞬間の感激。みんな無くなってしまいます。その分合理性がアップってことですか。
結局未だにフィルムを捨てきれない部分があるのは、フィルムの表現の幅がデジタルでは叶わないという点。写真のおもしろさを忘れたくないから。緊張感を含め楽しんで写真が撮りたい。ということでしばらくは両刀遣いとなりそうです。これもまた「写真が選択の芸術」と言われているように、文化としての写真が背負った宿命と言えるのかな。
|
|
|
|
今発売の「山と溪谷・12月号」でデジタル一眼のアンケートがあり、掲載されているように、デジタル一眼を導入して一年経ちます。この間にも新しい機種の発売が相次いでおり、以前と比べればある程度落ち着いてきたとはいえ、まだまだ新しい機材=よりよいスペックといったところがあります。
紙面でも書いているように出版界の情勢からもカメラマンとしてデジタル化は避けられない状況です。一方では銀塩ならではの世界があり、当分は併用することとなりますが。実際35ミリサイズでは、9割がデジタルとなっています。
この一年使用して感じたことは、デジタルであれ銀塩であれ、写真は写真ということ。何をどう撮るかは写真家自身の問題ですので、機材はあくまで表現の道具に過ぎないということを改めて思いました。
デジタル機材の長所は機動性、迅速性、一台で何にでも対応できる利便性。今までなら、モノクロを撮るにはフィルムを入れ替えなければならなかったのが、ボタンとダイヤル操作でできてしまうのですから(もちろんPC上で撮影後でもモノクロになりますが)。
一方、欠点は特に文明から離れた山岳ロケーションや遠隔地では、バッテリー、メモリカードのデータ管理が、一番頭を悩ます問題。充電ができる環境であればいいのですが、ストレージにしてもカメラ本体にしてもバッテリーは命。予備を持っているとはいえ、長期にわたる取材では不安がつきまといます。またレンズ交換時にどうしても付いてしまう埃。PC上のソフトで消せるとはいえ、モノクロのスポッチングのような作業は、カラーフィルム時代にはない作業工程であります。
|
|
|
映画「ミッドナイトイーグル」のお知らせ
|
この11月23日から全国松竹系で「ミッドナイトイーグル」という映画が上映されます。厳冬の北アルプスを舞台に繰り広げられる、山岳サスペンス・アクションの大作です。
なぜこの映画をお知らせするかというと、大沢たかお演ずる主人公の西崎勇次が、戦場カメラマン崩れで、現在は山の写真を撮っているという設定でして、彼が撮った山の写真として僕の写真が使われております。墜落した爆撃機はさすがに合成となっていますが、西崎の事務所に飾られているパネルや子供が手にしている写真など、映画をご覧になる際、本編とは別にお楽しみください。
まだ完成した映画を見ていないので、どのような映画になっているのか僕も楽しみにしております。是非ご覧ください。
この11/5に北穂高小屋の小屋閉めを終え、下りてきました。雪は2800mから上の稜線上にありましたが、この時期にしては少なめ、沢筋の雪山ルートではなく、南稜を下ってきました。
その前日にはパキスタンの非常事態宣言の発令があり、今後の情勢の変化に予断が許されない状況にあります。興味のある地域のことなので一日も早い事態の沈静化を祈ってやみません。
|
|
|
今年の夏山
|
もう彼岸入りだというのに信州・松本でも30度を記録するほどです。この時期ってこんなに暑かったかなあと、今年は夏がまだ終わっていない ように感じております。皆さんの夏山はいかがでしたでしょうか?
僕の夏山はカムチャッカのアバッチャ山から始まりましたが、8/24からのバルトロ撮影トレッキングは、諸事情から残念ながらキャンセルとなってしまい、一夏中北アルプスを回っていました。その他もちょっとした取材の予定がキャンセルになり、予定が予定として回らなかった年でありました。
夏山に居てさえ暑いと思う日があった今年の夏。森林限界を超える稜線歩きのときですら、「ジー」という、なんとセミの鳴き声が至るところで聞こえてきて、ちょっと変な年であります。これだけで温暖化とか言いたくはないのですが、セミの鳴く稜線が当然になってしまうのもどうかと。
この何日かでようやく稜線付近の草紅葉も始まり、少しずつ秋の気配を感じるようになりました。でも3000mの稜線ですら初氷となっていないようで、今年の紅葉は例年より遅れそうな気配です。
|
|
|
もうすぐ夏山
|
もうすぐ北アルプスの梅雨も明け、いよいよ夏山シーズンの到来となります。8月下旬からはバルトロ氷河・フォトトレッキングがあり、短いシーズンとなってしまいますが、その分例年以上に動き回らなくてはならず、休み無く槍穂高及び周辺を彷徨っております。皆さんとも何処かでお会いするかもしれません。
春先PCのシステムを変えたのだけれど、全てが新しいソフトの導入となっていない関係でこのHPの 更新も古いシステムから。山からの更新もできにくくなってしまい(こちらは設定変更していないから)。ショートエッセイも間があいてしまっています。楽しみにしている一部の方には申し訳ありませんが、これも私のアバウトな人間性だと思って気長にお待ち下さい。
先日北穂高岳から下山した際、南峰の分岐付近で雌の雷鳥が地面に身体をすりつけ、妙なディスプレイをしている。ふと見てみると岩陰には生まれてまだ間もない雛の姿が。二羽しか見なかったけれどひょっとしたら卵をまだ暖めていたのかも。脅かしてゴメンね。その時の写真がアップした写真です。でもね、ここ、登山道だから、もうすぐいっぱい人が歩くから。踏まれないようにね。
|
|
|
追悼
|
去る4月24日、私が大変お世話になっている山小屋、北穂高小屋の初代ご主人、小山義治さんがご逝去されました。享年87歳。謹んでお悔やみ申し上げます。
先日5月13日、告別式がご自宅近くの松本市神宮寺で行われ、山小屋関係をはじめ多くの弔問者が訪れ、私も参列して参りました。
初めて北穂高小屋のスタッフとして山には入る際お会いして以来、20年以上おつきあいさせていただきました。戦後すぐの時代に梁を担いで北穂沢を登り、全く一から始めて北穂山頂一角のあの場所に山小屋を建てる偉業を成し得た方です。年齢を感じさせない気迫が溢れ、昔のことを事細かく覚えていらして、数々の武勇伝を直接お伺いできたのも今となっては楽しい思い出となってしまいました。山小屋を自らの意志と力で築きあげた最後の人だと思います。
改めまして今までお世話いただいたことへ感謝申し上げるとともに、穂高を愛し続け、見守り続けてきた意志を我々の世代も受け続けていきたいと思います。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
|
|
|
桜咲く
|
春遅い信州・松本ですが今年はもう桜が咲き出しました。それに伴って年中行事のひとつ、花粉によるのか?くしゃみが連発、目がショボショボしてかゆい、といったつらい季節でもあります。花粉症とは自認していないのですが、くしゃみと眠さで感じる春です。
北アルプスの山小屋も小屋開け間近。いよいよ今年もシーズンが明けます。雪が少ないという情報がありますが、奥深い山中ではこれから降る里の雨が山では雪になり、降雪量は一番多くなるのがこれからの時期です。
今年の冬の異常とも言える(そのうちこれが普通の冬になるのかも)降雪量、平均気温が今年のこの後の天候にどう影響があるのか。自然の中で活動していると非常に気にかかります。冬らしい冬があってこそ、夏らしい夏になり、秋の紅葉もまた鮮やかに色づくのですから。
ここのところ執筆作業や写真選び等のディスクワークばかりで体がなまり気味。そろそろ冬眠から目覚めて動き出そうと思います。
|
|
|
最近は・・・
|
ここところ妙にせわしいというか忙しくなってきました。まだ春だというのに頭の中はすでに夏山。もう少しで終わってしまう名残の雪山にも出かけたいのにパソコンに向かっての夏山の原稿書きと写真の切り出しに追われております。その合間にも風邪を引いてしまい、某旅行会社(アルパインツアーサービス株式会社)のヤマケイ登山教室で八ヶ岳に2週続けて出かけ、また来週は八方尾根の撮影ツアー(内田良平さんと同行)に出ている予定です。じっくり腰を据えて自分の写真に取り組みたいところですが、今しばらくは我慢といったところです。
またしてもモノクロのバライタ紙が値上げとなってしまいました。僕が愛用しているイルフォードのMGFBという製品です。製造を続けてくれているだけまだまし、という気もするのですが、一年半前の価格と比べると5割アップ。かなり厳しい状況になってきました。今思えばいい時代にモノクロを勉強できて良かったなあとちょっとノスタルジックに感じてしまいます。今からモノクロプリントを勉強しようと思うと大変なことです。特に若い人には厳しいことです。写真の調子を覚えるにはそれこそ湯水のようにプリントしないと見えてこないですから。モノクロも今後はデジタルでの出力となっていくのでしょう。これもまた時代の流れでしょうが、ちょっと寂しい気がします。なんと言ってもあのグラデーションと質感はバライタペーパーのファインプリントじゃあないと再現できないものです。そして世界に一枚しかないというビンテージ性もあります。
そんな中オリエンタルという印画紙メーカーがWEB販売で安く販売していることは唯一の光と言えるでしょうか。アンセルアダムスが愛用していたニューシーガルといえばお判りになる方もいるかも。こちらの製品も久しぶりに今度使ってみたいと思っています。
|
|
|
|
実はこのホームページの写真は全てフィルムからスキャナで取り組み、データを非常に軽くして(画像を劣化させて)アップしています。というのも撮影は全てポジでしているからなのですが・・・。
そうは言ってもこの写真業界ならびに印刷業界のデジタル化は急速に進んでいます。もはや避けられない状況であります。昨年からの業界の流れを見るにつけ、これはいよいよやばいぞとひしひし感じていたわけですが。そこで今更ではありますが、昨年暮れからデジタルでの撮影を始めました。
これまでの撮影スタイルは超がつくほどアナログ至上主義。銀塩での撮影は全てがマニュアル(ピントや露出です)。そしてレンズも単玉(ズームではない単焦点レンズ)。それがデジタル一眼システムの導入ではズーム、AF、AE,おまけに手ぶれ防止までついている。3世代ほどの新技術が導入されることになるのです。これで一気に文化開花、デジタルの夜明けとなってしまいました。
いままで情報を仕入れなかったわけではないので、右も左も判らない状況ではないのですが、まだ撮影を開始したばかりで、RAW現像をはじめ印刷媒体とのカラーマッチングやプリント出力など課題は山積みです。でもなんとなく新鮮で、これまでとは別の意味で撮影を楽しんでいます。
とは言ってもこれで全てデジタル化するとは思っていませんが。印刷原稿のポジ、なかなか発表の機会に恵まれないモノクロ、それにデジタルが加わったというように考えています。撮影に関しては、結局は銀塩でもデジタルでも基本は一緒。写るものがイメージセンサかフィルムかの違いだと思います。撮るのは僕ですから。
|
|
| やはり温暖化?
|
立春が過ぎ暦の上では春となりました。例年だと春を待ち遠しい様な去り行く冬が寂しい様な気持ちになるのですが、
この冬はちょっと違います。
皆さんもお感じでしょうが、今年の冬は変。なんでしょう、この暖かさは?冬が冬らしくない。やはり・・・。
自然環境の世界のことだから今年の冬だけでは一概に言えないのですが、いつだったかTVで、日本列島が300km南に
下がった様なものと表現していたが、なまじ大げさとも言えない気もしてくる。そのうち動物園のように冬眠しない熊も
出てきてしまうかも。
前回書いた映画「不都合な真実」、東京で時間があったので見ました。感想といっても特別新しい事実が出てきたわけ
でもないので、まあそんなものかといったところ。でも見てみないとなんとも言えないのも事実で、興味のある方は是非
見て下さい。
唯一なるほどと思ったのが、北半球が夏の時期は二酸化炭素量が減り、冬は増えるという点。地球の陸地は北半球に集
中していて、二酸化炭素を減らすことになる植物の活動が夏期の方が活発という理由による。直接の温暖化問題に関係す
ることではないが、季節ごとに二酸化炭素量が増減するとは思っていなかったのでこの点は目から鱗でした。
結局この映画で言っていることは、17年前出された「地球を救う簡単な50の方法」からなんら進化していないようで
悲しくなってしまう。17年という時間が経っているだけにその間にも悪化の一途をたどっている。事態はより深刻になっ
ているのだが。それでも解決方法はあると断じて、ポジティブなところはさすがアメリカ映画。まあ敵を作るより少しで
も理解者を増やすべきだろうし。
この映画はことアメリカでは、'05年に超大型ハリケーン・カトリーナの被害を受けた当事国だったこともあり、かな
り深刻な状況にあることを一般市民に訴え、地球温暖化に警鐘を鳴らすことにはなったようだ。今後少しは希望が持てる
ようになるのだろうか?
|
|
| 今年の冬は・・・
|
年明けから早くも3週経ってしまいました。この正月は久しぶりに北アルプス・燕岳で迎えました。
年末の寒波明けに登ったので、登り始めから雪があったのですが、その一週間前に行った西穂ではこれが12月下
旬の穂高か?というほどの積雪量。暖冬と喜んでいる人も中にはいるのでしょうが、自然相手の仕事をしている身
としては空恐ろしい気がしてなりません。
昨年の冬は結構冬らしい冬で、松本ではほとんど雪が積もりませんでした。冬型が続くと大町以北(白馬方面)
は雪が多いのですが、松本平では乾燥した晴天となります。この冬はというと年末と年明けの2度家の前の除雪を
しました。その分冷え込みは厳しくなく、-10度近くまで下がったのはわずか1日です。
最近TVでも地球温暖化による影響が危機的レベルにあると報道されております。もう既に遅いのかもしれませ
ん。グローバルな環境問題は日本がバブルで浮かれていた時代には既に存在し、20年以上あえて目を瞑ってきて
いたのですから。
アメリカ元副大統領アル・ゴア制作「不都合な真実」が1月20日から上映されます。この映画の日本公開に向
けてのPR的な要素があるのでしょうが、地球環境問題が取りざたされることは大事なことです。一人でも多くの
人がこの星の環境に対してよりインパクトの少ない生活を心掛けることができるなら、まだ手遅れにならない可
能性も残っていると思いたい。100年後、1000年後もこの星がこの環境のまま存在していく為に。
|
|
Merry Christmas
|
メリークリスマス!師走の慌ただしい時期になりました。結局今年はポスト・モンスーンのネパールには行けず、
国内で過ごしております。年末年始にかけては北アルプスへ入る予定です。山のように溜まった写真に埋もれ、諸
々の写真整理や写真選びをしているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。松本の事務所兼自宅で写真の山と
格闘している日々です。
昨シーズンから11月25日まで営業するようになった燕山荘に行ってきました。他の北アルプスの山小屋が11月
上旬で小屋閉めとなる中、さらに3週間も北アルプスの稜線で小屋があるとういのは登山者にとって、この季節とて
もありがたい存在です。真冬とは違って登山口まで車で入れるのでアプローチもよく、また稜線では快適な山小屋
空間があり大変助かります。燕山荘スタッフの打ち上げにも飛び入りさせていただき、楽しくすごしました。
12月5日に新穂高から西穂高に上がろうと思っていたらなんとロープウェイが5-6日と送電線点検のため運休中。
ウィークデーに調べず行ったのが失敗でしたが、なにか運と言うか巡り合わせの悪さに嘆いてしまいました。
いい写真を撮るのに何が必要か。いろんな要素があるのですが、山岳写真や僕の撮影しているような自然現象の
場合、そのシーンに巡り会わなければ撮れないものがあります。偶然と言うだけではないのですが、必然でもない
光景との出会い。それに出会うためにこちら側からのアプローチ。その時々変化していく相手をどう見極め、巡り
会えるか。
その一つに何かうまく言えないのですが、運命というか巡り合わせの妙と言うものを感じざるを得ないことがあ
ります。うまくそれが回った時いいシーンに会えるような気もします。そんな時は自然との一体感のようなものも
感じます。運と一言に言ってしまえばそれまでなのかもしれません。
|
|
|
狐火?
|
11月6日北穂高小屋の小屋閉めをして、稜線を後にしました。今度穂高の稜線に上がるにはテント装備を背
負って、重装備での行動となるので、気軽に登れなくなります。
左の写真はその下山前日の夜8時頃、北穂高小屋のテラスから横尾本谷を写したものです。折しも丁度満月で
月明かりがとても奇麗でした。屏風岩の下にある横尾本谷から光が揺らいで見えます。40代後半の小屋スタッ
フK氏が「何っすかねぇ、あの光。狐火すかねぇ。」キツネ火なんて言葉、会話で初めて聞いた気がする。辞
書で調べた「燐火、鬼火」Wikipediaでは項目ではなく、関連として「人魂―青白い炎の玉―」とあった。
ヘッドライトを点けて涸沢のスタッフが一足早く下山しているのでは?という憶測まで飛び交う。下から登っ
てきているのでは?そんなはずはない。ヘッドライトにしては明る過ぎるのだ。松明を燃やしている?誰が何の
ために?
既にお判りと思うがこの明かり、月光が横尾本谷の水面に反射して見えたもの。紅葉が終わり冬枯れした裸木
の為、水面がよく見えるようになったので月明かりが正反射してこれほど明るく見えたのだ。他の季節だと谷が
雪で覆われているか、木の茂みで隠れてしまい見えない。月が出てくる方向も関係するだろうし。
一目見て月明かりの反射だとは判ったが「狐火」であってもいいなあ。なんてロマンチックに揺らいでいる明
かりを見ながら思った。
満月の夜、ちょっと神秘的なことが起きるかも。
|
|
|
秋の夜長に
|
9月下旬から稜線で始まった紅葉前線も徐々にその高度を下げ、上高地周辺の1500mまで降りてきました。
今年の紅葉はある意味予想どおりとなり、沢筋は夏に残雪が多かった影響で遅く、長く楽しめる紅葉の年とな
っています。
日照時間も11時間ちょっととなり、夜が長くなってきました。そんな秋の夜長を過ごすのに最近ちよっと気
になる本(といってもコミックですが)を紹介します。この頃は昔のようにはコミックを読まなくなったので
すが、それでも山漫画(山を舞台にしたコミック)だけは買って読んでいます。
その中で現在お勧めなのが「ビックコミック」で連載中の石塚真一さん作の「岳」という山岳レスキュー漫
画。小学館から現在2巻が出ております。
詳しい内容をここで書くのは野暮なのでしませんが、レスキューの技術的な面や穂高界隈の状況描写、微妙
に現実とは異なる地名など非常に楽しめるコミックです。これはかなり山の事や内部事情に詳しい人なのか、よ
く取材されているなあといった印象です。作者はクライミング・バグの生活をアメリカでしていたよう
で、漫画の作品以上に作者の石塚さんに興味を覚えました。
興味をお持ちの方は是非一読を。
|
|
|
今年の紅葉は?
|
さていよいよ待ちに待った紅葉のシーズンに入りました。今年の夏は好天続きだった
ので期待したいところですがどうなることでしょう。これまでのところ森林限界付近の
最上部が色づいていますが、谷筋は残雪が多かった影響で遅れ気味。どうやら長く紅葉
が楽しめる年のようです。
雪があまり着かない尾根筋や露岩帯は例年並みそれ以外の沢筋部分は例年より1週間
は遅れ気味といったところでしょうか。沢部分では未だトリカブトやイワギキョウ、ア
キノキリンソウなどが咲いていたりして、今の季節が何時なのかよくわからない今年の
秋山です。今年の残雪の多さから紅葉と新緑が共に見られることは予想していましたが
(涸沢ではまだ雪も沢筋にあります)、なんとも妙な感じもしています。
稜線の初氷、初雪とも2週間遅れ。遅い遅いと言っても自然のサイクルは着実に冬に
向かって歩んでいます。年によってこれくらい季節が例年よりずれることはこれまでも
何度となくありました。何年かに一度は今年のような年があるものです。といってもこ
の後、足早に季節が移行することもよくあることです。これからの秋山、3000mの稜
線では雪が降ってもまったく不思議ではありません。装備、天候の情報には気をつけて
山行をお楽しみ下さい。
|
|
|
今年の夏山
|
この夏は7月30日にようやく関東甲信地方の梅雨が明けたと思ったら、それから3週間好天続き。
2度ほど台風の上陸予報があり、北ア山中では登山者が減りましたが、実際は進路予想がはずれ西
へ。天候への影響はほとんどありませんでした。
夏山でこれほど好天が続くこと(午後はにわか雨や雷雨はありました)は僕が知る限りなく、少
なくともこの20年来なかったことです(1985年は良かった気がしますが。学生の頃ですので自分
の歩いていた時の記憶しかありません)。皆さんも夏山を思いっきり楽しまれたことでしょう。こ
の冬の豪雪の影響で谷筋には例年以上に残雪があり、高山植物の咲き具合も例年より遅め。おかげ
で盛夏の花がお盆過ぎまで楽しめました。先日行って来た裏銀座(槍~双六~烏帽子)もウスユキ
ソウがまだ見ごろで、一緒に歩いていた方も大変喜んでおられました。
また残念ながら、8/25から予定していたカラコルム山群の撮影トレッキングは催行人数に達せず
キャンセルとなりました。来年以降に仕切り直しとなります。また興味をお持ちの方はご参加くださ
い。
というわけでネパールのベストシーズン(10~11月)まで日本におります。
|
|
|
遅い梅雨明け
|
いよいよ梅雨明けと思っていたのに、カムチャッカから戻ってみると相変わらずの梅雨空。
東京から松本へ戻る日は岡谷で土石流が発生した日で、JRや中央道は通行止め、長野新幹線
で長野廻りを余儀なくされました。個人的にはその位の影響しか受けず助かりましたが。被
災地の方々にお見舞い申し上げます。?
そのカムチャッカですが、2741mのアバチャ山という山に登ってきました。台風3号から
変わった低気圧の影響で到着日、2日目のベースキャンプは小雨。登頂日は、登り始めは雲が
多かったものの上部は雲海の上にでて、最高の登山が楽しめました。前日の雨が2000mから
上部は雪だったようで、所々新雪を踏みしめながらの登山でした。富士山のような山で、ザラ
ザラして滑りやすいので、雪で小石が安定して却って歩きやすかったです。
アバチャ山は最近では91年に噴火したバリバリの活火山で、山頂付近には熔岩ドームがあり、
足元に硫黄が噴出しています。日本だったら登山規制がかかっているでしょう。地熱が高いの
で水蒸気も立ち上げっていて、迫力のある山です。カムチャッカ半島の火山群として世界遺産
に登録されていますが、日本の山とはスケールが違い過ぎます。
遅れている梅雨明けの為、夏山取材はちょっと天候待ちの状態ですが、さすがにそろそろ明
けそうです。夏山らしい夏山となってくれることを切に願っています。皆さんも安全で楽しい
夏山を楽しんでください。山でお会いしましょう。
|
|
|
夏山
|
間もなく梅雨明け、いよいよ夏山シーズンが始まります。僕の今年の夏山はカムチャッカのアバ
チャ山から始まります。今回のツアーは撮影目的ではなく、一般の登頂ツアーでツアーリーダーと
しての同行です。1900mの標高差を1日で登下山する、ツアーとしてはハードな山登りです。全
日程5日間ですのでゆっくり回るわけではいのですが、久しぶりに北の大地へ行ってきます。
10年前このカムチャッカの地で動物写真家星野道夫さんが亡くなりました。
「山と渓谷/8月号」で特集を組んでいるようですので、興味のある方は御一読を。10年前のあの
日、8月8日は西穂高岳で取材中でした。西穂山荘のTVのテロップで流れた「カムチャッカで動物
写真家の星野道夫さんが熊に襲われ死亡した」とのニュース速報に呆然とした事を思い出します。
星野さんに限りませんが、撮影取材で命を落とすカメラマンと聞き人事に思えませんでした。あれ
ほどアラスカに入り込み、素晴らしい写真を発表してきた生き様は、羨ましく思えるほどです。
一般の方には亡くなった後の方で星野さんの世界に触れる機会が多かったようで、ある種伝説化
してしまった感があります。それほど彼の写真そして残された自然に対する想いが書かれた多くの
文章がすばらしい証でありましょう。
|
|
|
原稿書き
|
この数週間いくつかの原稿書きがあり、慌ただしく過しています。そのうちの一つは「ヤマケイJOY・夏号」
(山と溪谷社)。5月31日発売です。槍穂高付近のガイドページ他で写真と文を掲載しておりますので御覧下さ
い。
もう一つは6月15日発売の「山と溪谷・7月号」(山と溪谷社)。こちらはグラフページと穂高の稜線ガイド
記事等で掲載しております。今年の「山と溪谷」はグラフとリンクする形で表紙の写真を使っており、表紙も担当
しております。
また先年夏取材で行った蝶ヶ岳から燕岳への常念山脈の写真は、5月31日発売の「岳人別冊/夏山」(東京新
聞出版局)で掲載します。?
と言う訳で、ちょっと気が早いのですが頭の中はすでに夏山の状態。今年の夏山はどうでしょうか。天候その他、
今から気掛かりです。
今年の5月は何か変。雨上がりの後はくっきりするはずが、なぜかフェイズが入って遠方が霞んでいます。昨年は
雨が降らなかったので、霞むのもやむなしと思っていたのですが。何と言うか、ピナツボ火山の時に近い状況にあり
ます。
この春先は黄砂がひどかったようですが、その影響がまだ残っているのでしょうか?中国の大気汚染や巨大ダム建
設による大河の水量の変化などがもたらす影響もあるかもしれません。いずれにせよ地球レベルでの大気の流れによ
るものだと思います。自然環境に国境がないということを、今更ながら思い知らされます。
|
|
| ネパールから帰国
|
4月19日予定通りネパールから帰国しました。カトマンズに戻った16日にTVのニュースで市内の
デモの様子が流れ、日本でも連日報道されていることを知りました。今回のツアーでは運良く騒動に
は大して巻き込まれることなく済んだものの(オプショナルでの市内観光ができなかったくらい)、
日程が数日ずれていたらヘリでカトマンズに戻って来られなかったかも。考えるだけでぞっとしm
今回の騒ぎは主要7政党の呼びかけによる王政に反対するゼネストで、本来4月6日から4日間の予
定で行われるはずだったものが継続されたものです。騒動がこれほどまで大きくなるとは、さすがに
カンチェンジュンガ山中にいて予想だにできませんでした。20日間近くの道路封鎖で街中ではガソリ
ン、灯油などを買い求めての長い列ができ、デモの通過でタメル地区も店のシャッターが下りゴミ収
集もされないためゴミの山ができ、外出禁止令(カーフュー)も一時出ていた(トレッキング中)よ
うです。
20日のデモに際し渡航延期勧告(レベル3)の危険情報が外務省からだされ、ツアーは催行されな
い状況となってしまいました。24日にギャネンドラ国王が演説で下院議会の復活を宣言、どうやら沈
静化へ向かいそうでほっとしています。とはいえマオイスト(毛沢東主義者)の問題はあいかわらず
残っているですが。
90年の民主化以来の騒動にあやうく巻き込まれるところだった今回のツアーですが、パンペマや?</p>
ミルギン・ラで天候に恵まれ満足のいく撮影トレッキング・ツアーでした。
|
|
|
春です
|
長い冬も終わり、各地から桜の便りが届く季節となりました。インデックスのページで
お知らせしておりましたネパール・カンチェンジュンガのツアーに3/30から出掛けます。
それに伴って現在夏山の原稿書きやら出発の準備に追われております。
ネパールから戻ると北アルプス南部も小屋開けの季節。そしてゴールデンウィークとまた
冬眠から目覚め活動期に入ります。
この冬は今までため込んでいた写真の整理や暗室ワークで結構家に籠もりがちの生活。気を
引き締めて山に向かいたいと思います。さて今年はどんな山との出会いが待っているでしょ
う。楽しみであります。
近況でとして「カメラマン4月号」(3/20発売 モーターマガジン社)で銀塩写真のカメラ
マン紹介のページで取り上げていただいておりますのでご覧下さい。また4/24発売予定の
Mook「撮影ガイドー日本の山風景ー」(日本山岳写真集団著・モーターマガジン社刊)にも執
筆しております。山岳写真の撮影ポイントをガイドする本です。興味のある方はご購入ください。
|
|
|
暗室の季節
|
今年もまた暗室の季節の到来です。水が冷たく快適とは言えませんが(薬品もろもろの
処理温度は20℃ですから)、スケジュール的に毎年この時期となってしまいます。今年の
JPS展も昨年同様「私のこの一枚・モノクローム」となっており、その為のプリント出し
もあります。
2月に入って冨士フイルムもモノクロ印画紙の値上げとなりました。それで安定供給され
るのであれば致し方ないところでしょうが。
プロの立場でいうとモノクロームは営業に直結する作業ではないので、多くの写真家は
敬遠しているのが実状です。僕の場合も発表作品のほとんどはカラーですし、雑誌等では
モノクロームをまだ発表したことがありません。(ページ構成上でのモノクロページは別
です)
いかんせん趣味的な要素が強いのですが、それでもいいものはいい。カラーや昨今のデ
ジタルでは決して感じられない世界があります。それはひとつに現像、プリントと自家処
理ができるので、画像を作っているんだという作品に対する想いが入るからかもしれませ
ん。現場での撮影だけで映像が出来てしまうカラーとは違い、ひとつひとつの画像を見続
ける時間の違いともいえるのでしょうが。
プリントという現物を見なければわからない、印刷やインターネットでは見えない部分
があるのがモノクロームです。20年以上前にアンセル・アダムスのビンテージ・プリント
が6000万円以上(正確な額は忘れましたが)で落札されたことがありました。当時は写
真が美術品として扱われていることを表す一つのトピックでした。
複製出来るものと思われている写真において、この世にあるものはここにあるこの一枚
だということ。オリジナル・プリントの持つ深み、ディティール描写、ディープシャドー
からハイエストライトまでの滑らかなグラデーション。無くしてはいけない写真表現のひ
とつだと思います。なかなか発表の機会が恵まれませんが、このモノクロームの世界を追
求していきたいと思っています。
|
|
|
ついにきた
|
1月11日ついに恐れていたこの日がやってきた。カメラメーカーのニコンがF6、FM-10以外のフィルムカメラの生産の打ち切りを発表した。しかも大判レンズや引伸ばしレンズも含めて。銀塩時代の終焉への序曲と言える出来事。おそらく今年中に主要カメラメーカー各社も同様の動きとなるであろう。
昨年よりコダックのB&W印画紙の生産打ち切り、イルフォードB&W印画紙の価格変更(2割アップ。それでも生産を続けるだけましか。)ドイツのフィルムメーカー、アグファの倒産など銀塩派にとってはまさに冬の時代、というより氷河期へ突入したといえる。
システムがデジタルへ移行するのは時代の趨勢としてやむをえない。企業としても最新の最先端の技術で製品を開発し続けなければならないのは宿命。しかし写真文化として今までのモノクロ並びに銀塩の世界を簡単に切り捨てていいのか?銀塩の持つオリジナリティはデジタルでは絶対表現出来ない物なのに。
今の出版事情は製版の段階までに全てデータ化され印刷されている。撮影の段階からデータであってもある意味問題はない。というよりその方が良くなりつつある。しかし僕が撮っている対象は山を始めとする自然の世界。マイナス30°以下になる環境下で果たして機材が動くのか。厳しい環境の中、自分自身の身を守るのが手一杯の状況。しかも当然バッテリーの充電もままならない。そんな極限の状況ではデジタルではまだ無理なのだ。
大判レンズ、引伸ばしレンズの生産打ち切り。銀塩写真のおもしろさがデジタルというシステムによって失われようとしている。
|
|