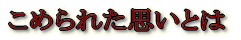 |
| 武藤先生、越谷先生に共通して言える事は、お二人とも大正デモクラシーという、うたかたの花火のように現れて消えた、自由な心と感性が溢れでた時代に人生の多感な時代を過ごされ、その後芸術の道に入られていると言う事です。ご承知のようにその後の日本は、そうした人々の心とは裏はらに、「自由」というものは踏みにじられ、戦争の渦の中に巻き込まれてしまい、余りにも大きな犠牲をはらった敗戦を体験することになりました。 |
統制下の日本、そして戦争という時代に抑圧された人間性や人々の思いを目の当たりにしてこられた後で、戦後に教育者の道を選ばれたお二人にとって、新生日本を担っていく若者たちにどうしても伝えたかったものがあったのではないでしょうか。
|
山村先生は敗戦後の何もない時代に青春を迎えられ、初めて日本にもたらされた自由と言うものに触れられ、それまでの日本で完全に否定されていた「文化的なもの=戦争遂行にはもっとも無用な物」に一気に触れる事になりました。
怒涛の如く入ってきた、スイング・ジャズやコンビーフの缶詰、総天然色の映画などなど、その中で先生の心の琴線に触れたのが「演劇」でした。
|
私は、3人の先生方が支えてこられたこの「先生方によるお芝居」には、ただ先生方がやりたがったとか、余興のようなものではない「何か」があったように思えてなりません。戦争という非人間的な不幸な時を通して、「人間としてどんな時でも忘れず大切に自分の内にもっていなければならないものがある。」と言う事を、そして「自由に物事を考えられる幸せという事」と「自由な感性、自由な発想というものが、生きて行くうえで、非常に大切なものなんだ。」という事を、自分の身を持って、自分の姿を生徒の前で見せることで伝えたかったのではないかと思うのです。
そして、それが生きて行く上で、どんな時でも、どんな状態になったとしても「心のバウンド」となり、「自分を助けてくれることになるんだ。」というメッセージがそこにこめられていたのだと思います。
|
 次:先生からのメッセージ 次:先生からのメッセージ
|
|
|