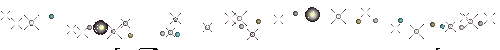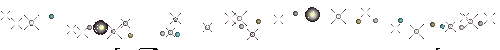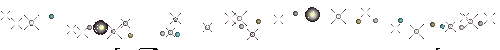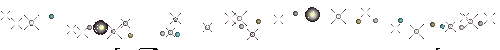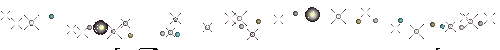コバルトちっくな天の川を題材にした話しが作りたくて発行した本です。
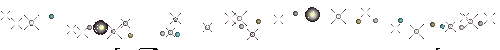

ミルクの河が氾濫する頃に
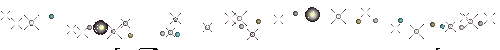
1
デネブが北極星になる。
その奇妙この上ない話を知ったのは中学生の頃だった。
近所にできた博物館の『秋期特別企画』と書かれたチラシは、ごく当たり前のような顔をして渡り廊下の掲示板に貼ってあった。
いつもならそんなチラシ、ろくに見もせず通り過ぎるのだが、何故かその瞬間、チラシの右隅に小さく載っていた白鳥座のイラストが視界に入ってきてそのまま居座ってしまったのだ。
その頃の私は特別天文が好きな女の子じゃなく、どちらかというと雑誌の最後のページに載っている星占いを読むほうが好きな普通の女の子だった。
それでも自分の星座と有名な星座ぐらいは知っている。
興味半分……というよりは、興味本位で掲示板の前に立つと、白鳥座のイラストの横に書いてあるコラムを読んでいる。
それは特別企画の付録のように行われる展示会の説明だった。
でも、その記事は少なからず私にカルチャーショックを与えてくれたのだった。
2
夏の夜空は賑やかこの上ない。
勿論、一番賑やかな星座が冬であることぐらいは知っている。一等星ばかりの冬の星座はまさに圧巻だ。色とりどりの星たちが夜空を占拠している。それに比べると、夏の星座は些か物足りないものがあるかもしれないが、星々以外の乱入があったりして、冬の星空と競えるぐらい賑やかになってしまう。
街中ではイルミネーションの影に隠されて見られない星たちも少し街から外れてみると、次から次へとその姿を空に現していく。「こんなに多くの星があるなんて」と、声をあげずにはいられないほどだ。
ずっと見続けていたらしまいに自分も宇宙に吸い込まれて星の一つになるんじゃないかと変な錯覚さえ感じてしまう。
そんな満天の空から一斉に降り注ぐ光りは、遥か昔の科学者たちからのメッセージなのかもしれない。こんなことを言うと笑われてしまうかもしれないけど、私は少なからずそう信じていたりする。
今地上に降り立つ光りは何億年前に放たれた光りで、昔の科学者が眺めた時の星の輝きはまだ地球に届いていないものが殆どだ。
宇宙はなんて広くて大きいんだろう。それを昔の科学者のように私は見ることができる。そう思うと胸が一杯になって苦しいくらいだ。
「おい、行くぞ」
「う……うん」
夜空に魅せられ、感無量になっている私の耳にしびれを切らした声が後ろからかかってきた。
(良い気分でいたのに……)
すこしムッとしてしまったが、言った相手の気持ちを考えてみると、それも仕方ない話だ。
手元の時計をみてみると、かれこれ星を眺めてから小一時間が過ぎようとしている。
声のした方を振り返ってみると、いま流行の四輪駆動に背をあずけている拓哉がこっちを見ている。
原っぱの真ん中で満足な明かりもなく暗くてよく表情が見えないが、憮然としているのが雰囲気で伝わってくる。
「おいていっていいんだな?」
言うだけで決してそんなことをしたことのない拓哉がわざと運転席のドアを開けて車に乗り込むふりをする。
「待ってよ!」
おいてけぼりをくらうはずはないと分かっていても、趣味として星を見ることに興味のない拓哉をこれ以上待たすのも無理な話しだ。
私は小走りにエンジン音のする車に駆けていった。
案の定、乗り込んだ途端に拓哉がエンジンを吹かしてレンジをドライブに入れる。
拓哉の態度からして、どうやらだいぶ我慢していたようだ。些か運転が荒くなっている。
「ごめんね。せっかくのドライブが星空の鑑賞会になって」
それとなしに声をかけると、
「いつものことだろ。お前とのドライブに関しては諦めているから」
と、少しぶっきらぼうな返事がかえってきた。
「でも、星って飽きないよ。見ていると吸い込まれそうになるもん! 拓哉なら尚更そう思うんじゃないの? 天文学を専攻しているんだからサ」
「全然思わない。天文学っていっても星を眺めるだけのもんじゃないんだゾ。気の遠くなるような数字との戦いなんだ。瞳は天文学を専攻してないからそんな悠長なことが言えるんだよ。講義なんか聞いていたら頭がいたくなって、なんで天文学なんぞ専攻したのかと毎回後悔しているんだから。極力、星とは勉強以外に付き合いたくないね」
運転をしながら吐き捨てるように言った拓哉の顔は本当にうんざりしているようだった。けれど、天文学を専攻できなかった私には拓哉の言い草は贅沢なわがままでしか聞こえない。
こんな風に喋る拓哉の台詞は全部気に食わなかった。ことごとく私のカンに触る。
数字との戦い。
(それでいいじゃない! 昔の科学者は今より随分不便な設備で星を観測していたんだから)
講義を聞くと頭が痛くなる。
(甘えなさんな! 聞きたくても聞けない人間があんたの横にいるんだぞ)
星とは勉強以外に付き合いたくない?
(それじゃぁ、何で天文学をしようなんて思ったのよ? 私と一緒で星に魅せられたから天文学の勉強をしようと思ったんじゃないの? そうじゃなかったら、さっさと天文学なんて辞めればいいのよ。そうすれば、素直に星を見ることができるわ!)
声に出さず、心の中で私はハンドルを軽快に動かす拓哉の横顔にグチる。言葉にしないのは、こんなことを思う自分が拓哉に対してひがみを持っていないと言えないからだ。
天文学を専攻するには自分には成績がなかった。
天文学がある大学に通学しているのに、自分が専攻しているのは天文学と違う。それは悔しさ以外のなにものでもない。そして、付き合っている拓哉は天文学を専攻しているのに星を見に行こうと誘う度にしかめっ面をする。
私は拓哉をひがんでいるのかもしれない。
こうやって横に座って拓哉の運転する姿を見る度、私は拓哉に、そして自分に問いかけるのだった。
3
順調に車を運転していた拓哉が急にブレーキを踏んだ。
「どうしたのよ?」
危うくフロントガラスに頭をぶつけそうになった私は額に手を当てながら非難めいた声をあげた。
「北極星が見える」
何かに憑かれたように拓哉が呟く。
「エッ?」
前方を見てみると真っ直ぐ続いている道路の真上に北斗七星と北極星が輝いていた。
「北極星がどうかしたの?」
自分から星のことを話さない拓哉がこんなことを口にするなんて珍しいことだ。
何があったんだろう? と、まじまじと拓哉の顔をのぞき込んでしまう。けれど、拓哉にはそれが目に入らないのか、サッと車を路肩に寄せて止めると、ハンドルの上に置いた手に顎をあずけ、じっと北極星を眺めだしたのだ。
「なぁ、知っているか? ……ああ、星好きのお前なら知っているよな。星々はすこしづつ動いていて、いつかあの北極星も北極星じゃなくなる日が来るんだぜ!」
独り言のように拓哉が話す。
勿論そんなことぐらい知っている。それを知ったから今の私がいるのだ。そのことを知らなければ、きっと私は別の大学に通って拓哉とも出会わなかったんだろう。
口の中でぼやいている私のことなど放っておいて拓哉が話しを続ける。
「俺たちがジジィになって死んでいってから何万年、いや何億年後かな? その頃、北の空を見上げたら北極星が白鳥座のデネブに変わっているんだぜ。不思議な話だよな。今は夏の大三角形だの言われて夏の中天を飾っているのに、末は北極星だ。見てみてぇよなぁ……」
最後に呟いた拓哉の台詞に私は驚いてしまった。星に関しては、いつもはぐらかして天文学を専攻した理由さえも教えてくれない拓哉が、初めて星への好意を口にしたのだ。
それは間違いなく拓哉の本音。正直、拓哉がこんなことを考えていたなんて思いもしなかった、時々、クールに天文学の知識をひけらかす拓哉からは想像もできないくらい素直な台詞だ。
ピクリとも動かず、じっと北極星を見つめてる拓哉の横顔は少年のように輝いていた。
ああ、私はこんな拓哉にホレたんだ。
ぼんやりと拓哉を眺めながらそんなことを改めて自覚した。
「その頃は天の川もこんな風に綺麗に流れていないんだろうな。それこそ、思いっきり氾濫しているかもしれないね」
今の拓哉の耳には届いていないんだろうなと思いながら私は独り言のように呟き、そして自分の発想に笑ってしまった。
きっとその頃は、天の川が氾濫しているとか、していないとかのレベルじゃなくなっているだろう。天の川と呼べるミルキィ・ウェイ自体が存在しているかどうかも妖しい話しなのだから……。
昔の科学者たちが名付けた星座もその原型を保つこともできずに、新しい星座の名前を未来の科学者たちからつけてもらって輝いているはずだ。
それでも……。
「それでも、……ミルクの河が氾濫していても、生まれ変わった私がその星空を眺めることができていたら、側に拓哉がいてほしいな」
「いいよ。俺もデネブが北極星になっているところを拝んでみたいからさ」
北極星からやっと視線を外した拓哉が、照れ笑いを浮かべながらこっちをみている。
「約束だよ」
拓哉に向かって右手の小指を差し出す。
「ああ」
その小指に拓哉の小指が絡む。
「お前のほうこそ約束を破るんじゃねぇぞ」
ゆびきりを終えた拓哉が照れくさそうに早口で喋り、再びエンジンをかける。
「そんな拓哉が好きだよ」
もう二度と星に対して何も言わなくなった拓哉の横顔に小さく呟いてみる。
「ミルクの河が氾濫していても、その時はまだデネブが北極星になっていないかもしれないけど、また拓哉と星を追いかけていけるのならそれもいいかもね」
叶うかわかりもしない約束だけど、私は前方に輝く北極星を眺めながら、叶った日の想像をして幸せな気分になったのだった。
Fin.
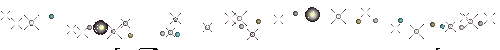


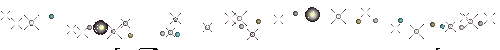
メールで感想なんかを頂ければ、うっれしいな♪