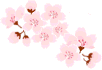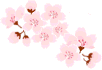
松の妖「松皇子(まつのみこ)」が初登場した作品です。季節は新緑の季節5月です。


緑 な す 桜 の 元

序
斎場(さいじょう)にある木と言えば昔から桜と相場が決まっている。
薄紅色に染めた花弁が風に揺れる様はどことなしに趣きがあり、人の命の終わりを告げる場所にしっくりとはまっていた。
春になるとパァーッと一斉に花を咲かせ、時間(とき)が来れば潔く花弁を散らしていくその姿は、誰もが心の中で願う理想の死に似ている。
人がこの世に生まれた瞬間から、避けて通れないものとして用意されているものが死だ。何事にも始まりがあるから終わりがある。それを漠然と人は知っているから、出来ることならその終わりを毅然(きぜん)とした態度で迎えたいと懇願する。けれど、それが出来るほど人は強くない、弱い生き物だ。だからこそ、せめて死に対して恐れを抱かないように、安らかな死を迎えられるようにと斎場にはたくさんの桜の木が植えられているのかもしれない。
それとも……。
それとも、昔の故人が話した通り、桜は人の血を得るために斎場に存在しているのだろうか?
「桜の木の元には死体が埋まっている。そうでないと、あんなに綺麗な花を咲かすことなど出来ようはずがない」
どのような理由から故人がその言葉を紡いだかは分からない。しかし、故人の言葉を鵜の呑みにすれば、なんと桜の木は狡猾に出来た生き物だろうと疑わずにはいられない。
桜の木は誰に教わったわけでもなく、人の血が得られる最高の場所を知っていて、そこに根を這って生きているのだ。斎場なる場所は、誰に知られることなく、また非難されることなく、大量の死体から多量の血を得ることが出来る。
誰が信じよう? 桜が斎場に運ばれた死体の血を得て春に見事な花を付けようなどと……。けれど、斎場の桜が一番綺麗な薄紅色をつけるのもこれまた事実なのだ。
とにかく。
斎場には桜の木が植えられている。
それは、死に行く者への生ある者からの最後の手向(たむ)けなのか、死に行く者を生あるモノへの最後の糧とするためのものなのか、誰も明確な答えを出す者はいない。
1
五月のある穏やかな昼下がり。雲ひとつない青空にモクモクと灰色の煙が上がっていく。煙突から出ていった煙は青空の途中まで昇っていくと、上空の風と交じり、空の一部となっていった。その様子を煙突のある建屋の前で黒い服に身を包んだ人々が目頭にハンカチを当てながら眺めている。
言葉もなく、亡くなった人への哀悼の意を向けて佇んでいる大人たちの姿は、この場所では当たり前の風景だが、人がそれに『慣れる』ことはない。
そんな沈んでいる人々の中でいつもと変わりない行動をとっているのは年端もいかない子供達だけだ。退屈な時間から解放された子供達は、霊柩車が出入りする道路の脇に植えている桜の木をポールに見立ててジグザグ走行したり、墓場のほうまで行って鬼ごっごを始めたりと忙しい。
そんな中の一人が、急にある桜の木の下で駆けていた足を止めると、幹を仰ぎ見ながら
「お姉ちゃん、そこで何しているの?」
と、独り言のように呟いたのだった。
今年、小学校に上がったばかりの少年の視線の先には、白い着物を羽織った二十歳前の女が少し高い位置にある枝に腰を下ろし、空を眺めている姿があった。
「おい、まぁちゃん。どうしたんだよ。早くしないと鬼に追いつかれるぞ!」
じっと女から視線を外さないでその場に立ち止まっている少年に向かって、後からやってきた少年の従兄弟が声をかける。
「う……うん。でも……」
二つ年上の従兄弟の顔色を伺いながらも少年には枝に座ったまま視線を空に向けている女のことが気になって、なかなか走りだすことが出来ずにいた。
「先に行くぞ!」
歯切れの悪い返事しか返してこない少年にとうとうしびれを切らした従兄弟は、苛立たしげに早口でまくしたてると、来た道を一度振り返り、鬼がまだ自分たちに追いついてないのを確認した後に墓場のほうにダッシュしていった。
「そうよ。早く行きなさい。鬼に捕まりたくないでしょう?」
墓場のほうに消えていく従兄弟の後ろ姿を目を細くして見送る少年の耳元にガラスの破片(かけら)のようなか細く、そして冷たい響きのある声が入ってきた。
「!!」
声を聞いて慌てて桜の幹を見上げた少年を、氷のように冷たい目をした女が見下ろしていた。
(雪女)
均整の取れた顔と羽織っている白い着物が、昔話に出てくる雪女を少年に連想させた。
透き通るほど白い肌に紅い唇は、本当に吹雪で人を殺めそうな危うい雰囲気があり、少年を瞬間怯(ひる)ませる。
でも、季節は春。第一、こんな街の中に雪女がいるはずない、それに雪女なら自分のような子供より大人を殺めるはずだ。
小さな脳が瞬時にそう回答し、それを少年は素直に信じた。だから、
「お姉ちゃんはそこで何を見ているの? お母さんたちみたいに天国を探しているの?」
と、首を傾げながら聞き返すという選択肢を選んだのだ。
素朴な少年の質問に、一瞬女が顔をしかめた。しかし、少年に向かって曖昧な笑みを作ると、一言、
「そうよ」
と、頷いたのだった。
「木の上に登ったら見えるの?」
意外とあっさり答えてくれた女の態度に気を良くした少年は、顔をほころばせると、手の届く場所にある枝に手をやり、女の側に行こうと木登りを試みた。
その瞬間、
「触るでない!」
厳しい声が辺りに響き渡ったのだった。
ビクリと体を震わせ、びっくり眼で声のしたほうを見てみると、少年を般若のような怖い形相で睨みつける女の顔があった。
「ここはお前のような下種(げす)な者どもが立ち入れる場所ではない。身分をわきまえろ! 子供と思って情けをかけたわたしが馬鹿だったわ。とっととこの場から失せろ!」
人を威圧せずにはいられない迫力と子供には意味の分からない言葉の集まりが、少年の脳を直撃した。
(やっぱり雪女なんだ!)
少年の目にはもう目の前の女が雪女としか映らなくなってしまった。殺されるという恐怖に脅えながら、少年はじりじりと後ずさる。そして、安全圏と思える場所まで来ると、踵(きび)すを返して大声で母親の名を呼びながら、会場のほうに向かって走りだしたのだった。
「これだから、人間の子供は困る」
ため息をつきながら走り去っていく少年の後ろ姿に女が冷たく吐き捨てる。
少年が見た女は、勿論雪女ではなかったが、人間でもなかった。女は古くから桜の木に棲んでいる妖だった。昔の人はその妖を『桜姫』と呼び、あるときは恐れおののき、あるときは神のように崇めていた。時代時代によって『桜姫』に対しての人の接し方は違ったが、身近な存在であった。しかし、文明の発達した現代では御伽噺(おとぎばなし)か、迷信程度にしか伝えられていない。だからなのか、『桜姫』を見れる人間も少なくなってしまった。女を見ることが出来た少年は稀(まれ)な存在であるといっても過言ではないだろう。
その少年が大声で泣きながら会場の中に消えていく姿が枝に腰掛けている女の視界に入ってくる。何回も転びながら逃げこむその姿は、女に昔を思い出させた。
「昔は、話しかける男がたくさんいたというのにね」
昔を懐かしみ、独り言を呟いた女の背中に
「子供相手に手厳しいことで……」
と、笑いを含む声が飛んできた。
「!!」
女が渋い顔を作り舌打ちする。
「子供を脅してどうするんだよ!?」
女に尋ねる声は、必死に笑いを押さえようとしているのだが上手くいかないようで笑いが小さくもれている。それがまた女のカンに触る。
相手が誰なのか分かっていつつも女がゆっくりと振り返る。その先には、白い羽織りに鴬色(うぐいすいろ)の袴を着た二十歳をすこし越えたくらいであろう男が、空中に体を浮かばせ、女に向かって微笑みかけていたのだった。
2
女の後ろに現れた男は、斎場近くの松林に棲んでいる松皇子(まつのみこ)だった。松皇子は桜姫のように自分の木を守る妖だったが、桜姫と違い、ちょくちょく自分の木を抜け出しては、斎場に棲んでいる桜姫の元に遊びに来るのだった。自分の棲んでいる木から片時も離れず、長い間守りを続けている桜姫から見れば、松皇子のそんな姿はちゃらんぽらんな守りにしか映らない。
今日も松皇子はそのちゃらんぽらんな守り姿を桜姫に見せにきたらしい。
女は男に分からないように軽く息をつくと、
「『待つ君(まつきみ)』。これはまた奇な場所でお会いするものね」
と、空中に浮かんでいる男に向かって厭味のたっぷり含まれた挨拶をしたのだった。
けれど、男のほうは一向にそんなことなど気にならないのか、嫌な顔一つせず、反対ににこやかに微笑むと、
「『さくら』の顔が見たくなってね。今日もご機嫌はよろしいみたいだね」
と、空中を女のほうに歩いてきながら挨拶を返したのだった。そして女の隣まで来ると膝を立てドカッと座り込む。
「お前ぐらいだよ。こんな態度のわたしを見て機嫌がいいなどとふざけたことをいうのは……」
表情を崩さず抑揚のない声で女が男に向かってきつい一言を放つ。しかし、男はそれに答えようとはせず、会場前のロータリーに佇んでいる人々に視線を落とすと、
「今日の獲物は学校の先生か……。結構人に慕われていたようだね。見送る人の人数が日ごろとケタはずれだ」
と、聞いてもいない感想をもらし、女の横顔に視線を移したのだった。
「やけに詳しいわね」
思いもかけない男の台詞に女は些か驚いていた。今日の獲物の素性を男がどうして知っているのか不思議だった。隣に座っている男は今斎場に来たばかりというのに……。
そんな女の心を読み取ったのか、男はニヤリと口の端に笑みを浮かべると、
「こんなに人が多ければ、斎場に住んでいなくても何人かの強い思考が飛んで来るってもんだ。とりわけ学生時代のイメージが多かったから学校の先生だって安易に予想がついたよ」
と、種明かしを始めたのだった。
「……で、死亡理由は病死か何かかい?」
どうやら死亡原因までは予想がつかなかったらしい。興味津津(きょうみしんしん)の顔で女に尋ね返してくる。それに女がうっとうしそうに
「事故よ」
と告げ、
「学校の上空写真を撮るためにチャーターしたヘリコプターが墜落したらしいわ。それにカメラマンと一緒に乗っていて事故にあったと、この下を通った女たちが話していた」
と、答えた。
「じゃぁ、『さくら』の好きな綺麗な血をここに持ってきてくれたというわけか」
嬉々とした口調で喋りながら男が女の顔色を伺う。
「確かにね。病死の血は濁っている。それに比べ事故死はね……」
綺麗な血が無条件で手に入るのだからうれしいはずなのに、頬杖をつきながら淡々と言葉を連ねる女の態度は、どこか面白く無さそうに男には見えた。
「どうしたんだよ? 浮かない顔して……。あっ、そうか。ヘリコプターの墜落だったら焼死か? じゃぁ、あの煙は……」
女の顔と煙を交互に見比べながら男が呟く。
「そう。あれは形だけのもの。死体は墜落時にあっというまに骨と化してしまったわ。柩の中に死体はない。あるのは骨のみ」
空を仰いだまま女が話す。
「そうか。それじゃぁ、仕方ないな。でも、その割りには珍しく執着しているじゃないか。『さくら』が獲物じゃない人間の昇天を見送るなんてさ」
「そう?」
女が首を傾げ、けだるそうに答えた瞬間、二人の足元の方から中年を迎えようとする女の金切り声が聞こえてきたのだった。
「お願い! 何でもするから、何でも渡すから先生を返して! もう一度先生を生きかえらせて!」
涙を拭いもせず泣き続ける女が、二人のいる幹に向かってすがるように何度も同じ台詞を繰り返し始めた。
3
少年と違い、その女には二人の姿が見えないらしい。必死に幹に同じ台詞を繰り返して泣くだけで、二人に話しかけようとしない。
「止めなよ、百合子。そんなことしたって、先生は帰って来ない」
カツカツとヒールの冷たい音がアスファルトに響く。音のしたほうを見てみると、キリリッとした顔付きの、いかにもキャリアウーマンぽい女が泣き崩れている女に向かって歩いて来る姿が見てとれた。女は泣き続けている女の横に立つと、些かきつい口調で声をかけたのだった。
「大の大人がみっともないよ。さぁ、もうそろそろ戻ろう。みんなが待っている」
そう言って腕を取ろうとした女の右手を百合子と呼ばれた女は思いっきり振り払い、
「嫌!」
と、叫んだのだった。
「百合子……」
驚いている女に百合子は、涙でくしゃくしゃになった顔を上げると、必死の形相で訴えだしたのだった。
「こんな別れかたって優雅(ゆうが)だって納得いかないでしょう? わたし、昔おばあちゃんから聞いたことがあるの。この斎場には死人を甦らせてくれる桜があるって。その桜にお願いしたら叶えてくれるって! その桜がこの桜なのよ。間違いないわ。だってこんなにしっかりした幹をしているんだもの。斎場の人に聞いてもこの桜が一番古いって言っていた。だからお願いするの。ねぇ、優雅も一緒にお願いしよう。二人でお願いしたらきっと……」
パァーン!
百合子の頬が鳴った。
「しっかりしなさい、百合子。いい!? 先生は死んだの。もう生きていないの。仮に、百合子のおばあちゃんが言うように死人を甦らせることが出来る桜があったとしても、それに願っちゃいけないわ。安らかに死なせてあげなくっちゃ! それが後に残るわたしたちの仕事なのよ。それに先生を甦らせてその後どうするって言うの?」
百合子の両肩を掴んで優雅が必死に言い聞かす。けれど、百合子は不気味なほど優しい笑みを浮かべると、
「わたしたち二人だけのものにすれば良いじゃない。わたしも優雅もあんなに先生のことが好きだったじゃない。あのときは既に奥さんも子供さんもいてあきらめるしかなかったけれど、今度は大丈夫。先生を縛るものは何もないわ!」
「バカ!!」
もう一度、優雅の右手が百合子の頬をはたく。
「しっかりしなさい。もう一度言うわよ。先生は死んだの。もうこの世にいないの。お焼香のときに百合子も見たでしょう? 柩のあるべき場所に小さな白い箱が置いてあったのを。先生は骨になってしまったの。もう息をしていないの。ばかな迷信に縛られないで。……さぁ、行こう」
項垂(うなだ)れた百合子の腕を掴むと優雅は無理やり会場のほうに引っ張っていく。さすがに百合子も自分が取り乱していたのに気づいたのか、おとなしく優雅の肩をかりて一歩を踏み出した。
「……ごめんね。優雅。そうだね、一番苦しいのは優雅だよね。自殺を考えたぐらい優雅は先生のことを……」
呟くように話す百合子に優雅は軽く首を振ると、
「いいの。もう済んだことなんだから。百合子が分かってくれたらそれでいいの。それよりも先生に伝えなくっちゃいけないことが天国に行った先生にも分かるようにこれからがんばっていかなくっちゃね」
と言ったのだった。
「強くなったね、優雅は……」
「当たり前でしょう? 一度三途の川を渡りかけたんだから。人間死ぬ気になったら強くなれるよ。まぁ、あまりオススメできる方法じゃないけどね。……さぁ、本当に急ごう。みんなが待っている」
百合子を促すと優雅は小走りに走りだした。一度、百合子に分からないように桜を睨みつけながら……。
「もう人を惑わさせないで!」
そう、優雅の瞳が見えないはずの二人に訴えていた。
4
「怖い姉ちゃんだったな。桜姫のお前と松皇子の俺にガンを飛ばしていきやがった」
恐い恐いと小声で呟きながら、男は以外とうれしそうに目を細くして女たちの後ろ姿を追っていた。
「『待つ君』は、気の強い女が好きだものね。一人になったところを狙って松の世界に連れ込んで自分のものにしてみたら? 少々歳はくっているみたいだけど暇つぶしにはなるんじゃない?」
冷ややかな視線で男を見ながら女が皮肉めいた台詞を口にする。それに男はニヤリと笑うとそっと女の肩を抱き、
「やきもちはみっともないぞ。確かに好みの女だけど、アレは俺が待っている女じゃねぇ。……それより『さくら』に、死人を呼び戻すなんて芸当が出来るとは思わなかった。噂ではそうなっているみたいだけれど、実際のところはどうなんだい?」
と、聞いてきたのだった。
女は自分の肩に置かれた男の右手を迷惑そうに見た後、
「優雅という女が言った通り、ただの戯れ言よ。一度もそんな得にもならない馬鹿げたことに力を貸した覚えもないし、もともとそんな能力なんて持ち合わしてないわ。……そうね、前にこの桜に棲んでいた桜姫が何回か人間を騙して、あの世で会わしたことがあったそうよ!? それを百合子の祖母は言っているのかしら? わたしもしたことがあるけれど、どっちにしろ騙される人間の方が悪いのよ……」
罪の意識を全然感じていない口調で女が言葉を紡ぐ。
「ふうん。大概『さくら』も悪党だね。桜の花を綺麗に咲かせるために人を騙して殺して平気でいられるんだからサ。まぁ、それが『さくら』らしくて俺は好きだけど……」
「当たり前でしょう? わたしは昔から桜姫と人に呼ばれている妖なのよ。桜を咲かすためならどんなことをしてでも人の血を手に入れるわ。たとえ人を騙して殺してでもね。わたしが斎場に棲んでいるのだって、誰にも怪しまれず人の血を得ることが出来るからなのよ。『待つ君』のようにただ自分の木に居座っているだけじゃないの」
手厳しい女の台詞が、男に飛ぶ。それに男は大袈裟に驚いたふりをし、
「ご挨拶だね。俺だって自分の棲んでいる松に何かあれば、存在が消えてしまうんだよ。ちゃんと最低のことはしているサ。まぁ、『さくら』のように自分の木のために何かしなくちゃいけないということはないけれどね」
と、自分をかばう台詞を口にした。そして、急に真面目な顔をすると、
「それにしても、あの優雅という女、まるで俺たちが見えているような感じでいたけど、『さくら』心当たりあるか?」
と、女に尋ねてきたのだった。
「……」
男の問いに女が珍しく黙り込んだ。それは喋らずとも関与したことがあると認める瞬間だった。
「百合子、優雅、未来(みく)……だったかしら?」
突然、独り言のように女が口ずさむ。
「何だよ、それ?」
訝(いぶか)しげに女の顔をのぞき込む男に女が一言呟いた。
「仲良し三人組の名前よ」
と。
5
「百合子、優雅、未来」
もう一度、女が呟く。そして、すくっと立ち上がると何もない空に一歩を踏み出したのだった。勿論、桜姫である女には、簡単なことだ。そこに地面があるかのように平気な顔で宙に浮いている。
空中から女は男を見据えると、
「この桜の木には未来がいる」
と告げた。
「……と言うことは、『さくら』の獲物になったということかい?」
目を細めながら慎重に男が事実を問う。それに女がコクリと頷いた。
「あそこにいるのは、あの三人の中学のときの担任だった男サ」
女が空に溶け込んでいく煙を指さす。
「男前で思いやりもあり、『待つ君』の言った通り、結構生徒に慕われていた。当時、その先生にあの三人は、熱を上げていた。わたしにはあの年頃特有の『好き』という感情の勘違いだとしか見えなかったけれどね。仲良し三人組の中でも特に優雅と未来の思い込みは激しいものだったわ。……激しい分、行動も突拍子がなかったけどね」
突然、女の口調がきつくなり、顔に憎悪が走った。
「あいつら、『さくら』の木に何をしたんだ?」
女の表情を読んだ男が真面目な声で聞いてくる。
「……たいしたことじゃないわ。ウサギの血をこの木にかけてくれただけのこと」
女のドスの効いた声が斎場の木々の中にこだました。
「!!」
さすがに悠長に構えていた男にも動揺が走った。
古来から桜が必要にしているのはあくまでも人間の血であって他の動物のものではない。桜は人間以外の血は何があっても求めたりはしないのだ。それが桜の誇りであり、桜である所以(ゆえん)だった。桜は木の中でも一番プライドの高い木だ。その桜に小動物の血を振りかけるという行為は侮辱以外のなにものでもない。男の目の前にいる女が憎悪に顔を支配されても仕方ないことだろう。十数年経ってもこんな調子なのだからその瞬間の女の感情がいかほどのものだったか想像もつかない。
言葉を失っている男に女が挑戦的な目をして続きを話しだした。
「そんなに切羽詰まるほど人間の血を欲していたわけじゃなかったけど、あまりにもしてくれたことが面白かったから、からかってやることにしたの」
急に女が思い出したように空中でくるりと一回転を行う。
着物の裾が風にまくれ上がり、遠心力の法則に従って、フワリと膨らむ。なんら変わりない一回転のように見えたが、よく見ると白い着物の裾に赤い染みが所々についていた。
「噂とは面白いものね。口伝えに伝わっていったらしいの、この斎場にある桜の木に血を与えると自分の望みを叶えてくれると。だから、二人は小学校の飼育小屋からウサギを盗んできて、それでわたしの着物に汚らわしい斑点をつけてくれたらしいわ。優雅と未来は『先生とデート出来ますように』とわたしの前で願ったわ。なんと浅はかな夢。……その浅はかな望みのためにわたしの着物は汚れてしまった。あの二人には、それなりの代償を払う必要があると思わない? だからその場で思いついたことを耳元で囁いてやったのよ。『そんなことをしなくても簡単に先生を手に入れることが出来る』と。『お前たち二人の命をこの桜に捧げてくれたら先生とお前たち二人だけの世界を作ってやる』と。……そんなことあるはずないと考えれば分かるはずなのに、優雅と未来はその場で決心すると、カバンからカッターナイフを取り出して、迷いもせず手首を切ってこの幹の下に崩れ落ちていったわ、見事な様でね。そして、未来は出血多量で死亡。優雅は九死に一生を得、今こうしてわたしたちにガンを飛ばしていった。まぁ、優雅にすれば、もう騙されてたまるものですかという心境かしら?」
会場前のロータリー前で佇んでいる優雅に女が視線を向ける。穏やかすぎる女の表情は嵐の前の静けさのようで、返って男を震え上がらせた。
「優雅の血も欲しいのか?」
なにげなしに聞いてきた男の問いに女が首を横に振って返事する。
「この凌辱(しみ)がとれることはないわ」
それが女の答えだった。確かに優雅の血を得たとしても着物に染みついた斑点が消えるわけでもない。
「でも、こうやって再びあの女の顔を見たら複雑な気分になるわね。何故、わたしに斑点をつけた女が平気な顔をして生きているのかしらって……」
優雅を見つめる女の顔が一瞬般若のそれになるのを男は黙って見つめていたのだった。
6
季節はもうすぐ夏を迎えようとしていた。あと二週間もしないうちに梅雨も明け、眩しい季節がやってこようとしている。もしかしたら、梅雨はその季節を迎えるための準備期間なのかもしれない。一カ月前の五月晴れが嘘のように月が変わってからは雨の日々が続いていた。
しかし、斎場にとっては太陽が照りつけようが、豪雨が降ろうが、たいして意味のあることではない。人が死ねば、天気が悪くても火葬しなくてはいけないのだ。
今日も例外ではない。しとしとと糸のような雨が降る中、人の命が煙となって天に昇っていく。それを桜の枝に腰掛け、女が無表情のまま見つめていた。
「血なんか要らないと言っておきながら、やっぱり殺したのか……」
女の背に皮肉った台詞が浴びせられた。それに女は別段答えようとしなかった。
女には今日男が自分の元にやってくるのが分かっていたらしい。別に慌てる様子もなく、振り返って男を見ようともしない。
「人聞きの悪いことを言わないでくれる? 優雅は勝手にこの桜の木の下で死んだのよ。『先生の側に行けますように……』と願いながら。百合子には偉そうなことを言っておきながら、実は一番自分がそれを望んでいたなんて、滑稽すぎるわ。でも、そんなところが優雅らしいわね。あのときもそうだった、先生の生きている世界に執着して未来を残して死に損なった。結局、優雅はわがままなのよ。百合子だけを残して自分だけ楽な道を選んだ。はたして、百合子は我慢出来るかしら?」
意地悪そうに女が呟く。
今、天に昇って行く煙は優雅の命だった。
一昨日の晩、優雅は女の棲んでいる桜の元にやってくると、枝にロープをかけて首吊り自殺をしたのだった。今度は九死に一生を得ることはなく、あの世へと旅立って行ったのだ。女の言うように『先生の側に行けますように……』と遺書を残して……。
「何故、そんなに死に急ぐのかね? 命の数を全うしていくのが生まれた者の使命だと思うが……」
女の隣に座り込むと、男が独りごちる。
「女はそんなに強くないからね。楽な道を選びたがるのよ。綺麗に死にたがるのよ。だから女は『桜姫』になるのかもしれないわね。わたしだってそうよ。わたしもあの男に恋をして思いを告げられなくて、『桜姫』になってしまった。だから、優雅の気持ちも分からないでもない。命の数を全うした後に松皇子になった『待つ君』には分からないでしょうけど」
「分かりたくもないね。これから何があるか分からない未来を放棄するなんて。考えられないよ」
うんざりといったような男の台詞を女が即座に否定した。
「放棄するんじゃない。賭けるのよ! 残りの命の数を引き換えにして……。今よりも自分の望みが叶えそうな世界を手に入れようとするの!」
語気を強くして女が『女の事情』を語る。
そんな女に男は冷ややかに
「『さくら』は手に入れたのかよ?」
と聞き返した。
その途端、二人の廻りの時間が凍りついたかのように静かになった。雨の音も、斎場の横を走る自動車の音も何も聞こえない、無音の世界。その中で二人がお互いを凝視する。短くて長い時間が二人を囲む世界の外で流れる。
「……手に入れたと思わなければ、悲しすぎるわ」
それが女の答えだった。それに男は苦笑いを浮かべながら頷く。
「そうだよな。命の数と引き換えにしたものが、間違ってましたなんて洒落にもならない。未来も優雅も自分の選択が間違ってないと思っていることを祈るよ」
男の台詞に対して、女は何も唱えようとせず、会場前のロータリー前に佇んでいる人込みに目をやる。
「百合子が優雅の後を追うのは時間の問題ね。彼女たちは仲良し三人組だったから。裏切りはしない。今晩あたり、丁重にお迎え致しましょうか」
女の焦点は既に目を涙で一杯にしている百合子に絞られていた。
「なぁ、『さくら』。俺がどうしてお前に『待つ君』と呼ばれているか、知っているか?」
獲物を狙っている肉食獣のように百合子を見つめている女に男が尋ねてきた。
既に桜姫の顔に戻っていた女は、顔を上げると、昔――初めて男と会ったときに男が話してくれたことを口にしたのだった。
「待っているのでしょう!? 『待つ君』がまだ人間の頃、契りを交わした女が自分の後を追ってきてくれるのを……。まぁ、松皇子をもじって『待つ君』と言ってるのも知っているけど。それが何かあるの?」
首を傾げる女に男は曖昧な笑みを返すと、
「覚えていてくれたならいいんだ」
と安堵の息を吐いた。そして、
「なぁ、俺が『さくら』に『待つ君』と呼ばしているのと同じように、俺だから『さくら』は、お前のことを『さくら』と呼ばしてくれているんだよな!?」
と、不安そうに聞いてきたのだった。それに女は、
「さぁ!? どうかしら」
と、高飛車な態度で答える。
「わたしは桜姫だから松皇子の考えていることは分からないわ。今は獲物をどうやって手に入れるかで頭が一杯なの。血はもらえるときにもらわないとね? さぁさぁ、用事が済んだのなら帰ってくれるかしら? 優雅の血を迎える準備をしなくちゃ」
高らかに笑う女に向かって男が一言漏らす。
「そんなに恋敵の女の血を得るのがうれしいことか?」
その台詞に女の笑い声が止まった。そして、般若のような形相を一瞬男に向ると、
「当たり前でしょう? 先生は誰のものでもないのだから。ましてわたしを凌辱した優雅たちのものにさせてたまるものですか! 優雅も未来も百合子もみんなわたしの桜の肥料になっていくの。……来年の春はきっと見事な花がつくでしょうね、わたしが恋した男を三人とも追いかけたのだから。気持ちは一つってね」
おかしそうにコロコロと女が笑う。それを男は何とも言えない顔で眺めていた。
「『さくら』は桜姫だからね。でも……」
「でも……」
笑いを止めて女が聞き返す。それを男は頭を振って断り、
「今日はもう帰るとするよ。ここにいても仕方がない。俺は『さくら』が人を殺めるところを見るのは好きじゃないからね」
と言い、空中を歩いていった。
「早く気づいて帰っておいで」
しばらくして、夏を迎える前の湿気を強く含んだ風が男の女を前にして言えなかった言葉を運んでくる。それを女は煙を眺めながら聞いたのだった。
珍しく女の頬を涙が流れた。
「わたしは桜姫。自分が望んだ世界を手に入れたと信じなければ悲しいじゃない」
女の悲しげな台詞が雨の降る緑の空気の中に溶け込んでいった。
終
通夜の席から抜け出した女子高生が二人、青々とした葉が生い茂る桜の木を仰ぎながら、あまりよく知らない故人について噂の花を咲かせていた。今晩通夜に出席したのは担任にクラス代表として連れて来られただけで、実際なら通夜があることさえ知らない二人だった。
「でも、よくここで通夜をする気になったものね。ここにある桜の木のどれかにもたれるように死んでいたんでしょう?」
桜の幹にもたれながら話す少女に、向かい合っているショートカットの少女が相槌を打つ。
「本当。わたしだったら気味悪くて絶対したくないわ。でも、ここらへんじゃ、斎場はここしかないから仕方ないか……。それにしてもあの噂、本当だと思う?」
首を傾げてショートカットの少女が独り言のように呟く。
「少し前に事故で亡くなった恩師の後を追っての自殺っていう噂でしょう!? どうなのかしらね。でも、今さっきチラッと斎場の人が言ってたのを聞いたんだけど、二、三日前にもあったらしいわよ、後追い自殺が……。それも桜の木の下で。世も末よね。いい歳した大人が後追い自殺するなんて。それともそんなにその先生にはカリスマ性があったのかしら?」
「さぁ? 結構、恩師じゃなく桜が呼んだのかもよ!? ホラッ、言うじゃない。『桜の木の下には死体が埋まってる』って。わたしのおばあちゃんがよく言っていたわ。桜は死体から血を吸って綺麗な桜色の花をつけるって。案外、本当のことかもね」
少女が言い終わるか終わらないうちに、二人は互いの顔を見合わせると、小さくクスクスと笑い出してしまった。
「それじゃぁ、桜に狙われないうちに戻ろうか? まだまだ生きたいものね」
「そうだね」
またおかしそうに笑い出すと、二人は手を取り合って会場のほうに走っていった。
言葉では軽く流していたが、二人のその走り方は桜に捕まらないようにと言わんばかりの逃げるような走り方だった。
そして、それをあざ笑うかのように、風になびかれた桜の木が葉擦れの大きな音を斎場の広場に響き渡せたのだった。
〈了〉




メールで感想なんかを頂ければ、うっれしいな♪