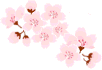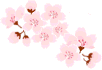
無料情報ペーパーに掲載したショートストーリー。松の妖「松皇子(まつのみこ)」が主人公です。


薫風の中で −松皇子 抄−

序
「待つ」ことは苦にならない。
少なからず、わたしにとってはそうだ。
もう随分長い間待っているが、それを苦に感じたことは一度もない。わたしにとっての「待つ」は苦ではなく、楽しみだ。
いつかわたしの元に戻ってくると約束してくれた「かの君」
彼女を待つことのどこが苦になるのだろう? 愛しい彼女を捜すことが苦になるはずがない。彼女がわたしの元に戻ってくる日を想像するだけで幸せになる。もう一度、彼女の側で生を感じられたら、どんなに素晴らしいだろう。
大切な大切なわたしの永遠の伴侶。
だからわたしは待てるのだ。
こうやって松の妖として生きていても……。
1
前世は人間だった。だから来世も人間に生まれ変わって彼女と出会えると信じていた。たとえ、人間に生まれ変わらなくても、なんらかの生き物として生を授かり、そしてまた生まれ変わった彼女との幸せな生涯を疑いもしなかった。それほど、彼女とわたしはお互いを求めて止まなかったから。
なのに、何の悪戯だろう? わたしは輪廻転生の輪から外れてしまった。もう二度と人間界への生を授かることはない。
わたしの死は幸せだったと思う。さすがに後に残す彼女が心配だったが、彼女と幸せな一生を送れ、最後も多くの人に看取られ極楽浄土へ旅立つことが出来た。否、人間界での命の炎が途絶える瞬間までそれを信じていた。
なのに、どういうわけだろう?
再び、重い瞼を開けた瞬間に飛び込んできた風景は、一面の砂浜と青く輝く大海原だった。決して、僧侶から聞いた極楽浄土の版図ではない。
しばらく、呆然とその風景を眺めていたが、ふいにわたしはそのことに気づいた。
「ああ、わたしは輪廻転生の輪から外れてしまった」
誰に聞くこともなく、言われることもなく、自然に理解できた。
わたしはこれから松の妖として生き、この砂浜に植えられている松の木を守るために生を送るのだと。
奇妙な脱力感を覚えたが、それもそんなに長い時間ではなかった。
新しい生を授かったのだ。それを素直に受け入れるしかない。それこそ新しい生が嫌だからと自ら死を選べば、愛しい彼女と再び相見えないかもしれない。その方がわたしには怖かった。もしかしたら、彼女も「彼女としての生」を終えた後にわたしのように松の妖に生まれ変わるかもしれない。
待とうと思った。再び彼女と相見える日を夢見ながら……。まだ新しい生を授かったばかりだ。時間はたくさんある。遠くにではあるが、彼女の生を感じることもできる。
たとえ、側にいることはできなくても、彼女の息吹を感じながら彼女の幸せを祈り生きてみよう。
2
その日は突然やってきた。もしかしたら「その日」ではなく、「その瞬間」だったかもしれない。
彼女の息吹が止まったのだ。それも元気だったものが突然消えたのだ。
不吉な予感が胸を横切った。
病などではない。まして、夜盗などに襲われたのでもない。
側にいなくてもわたしには分かった。病や不慮のものならば、少なからずこの世に情が残ってしまう。それが見あたらない。空気と一緒になって風に運ばれてこない。
彼女は……。彼女は、自害したのだ。
認めたくないけれど、それしか考えられなかった。
わたしは彼女を買い被っていたのかもしれない。
彼女は強い女性だと思っていた。わたしがいなくても残りの生をしっかりと生きていくのだと信じていた。彼女はまだ若い。もしかしたら、新しい伴侶を見つけ、その男と残りの生を幸せに送るかもしれない。それはそれでいいと思った。彼女が幸せな一生を送るのなら、先に逝ってしまったわたしに負い目など感じず、新しい生活を始めて欲しいと思った。
なのに、彼女が選んだのは死。この世との決別。
なんと愚かなことをしたのだろう?
ぽたりと砂浜に雫が落ちた。そしてまた一つ。
わたしは泣いていた。止めどなく涙を流していた。
「約束したじゃないか」
もうその言葉で責める人はいない。
生前、決して何があっても自らの命を絶ったりしないと約束したのに……。
それを彼女は忘れてしまったのだろうか?
彼女に会って問いつめたかった。けれど、それはもう出来ない。彼女を捜すこともできない。「彼女」は忽然とこの世から消えてしまった。妖としての不可思議な力をもってしても彼女の形跡を探し当てることは出来ない。
待とう。
再びわたしは強く決意した。
彼女がわたしの元に戻ってくるのを待とう。
こんなに強く願うのだ。叶わないはずがない。
3
長い時間が経った。
自ら命を絶ったというのに、彼女はわたしと違って幾度も人間界に生を授かり、ある時は幸せな一生を、ある時は薄幸の一生を過ごした。
それをわたしは彼女がこの世に生まれると敏感に感じ、見守ってきた。自分がいる場所とほど遠い場所に生を受けても伝わってくる空気で彼女を感じ取れた。
輪廻転生の輪から外れない彼女。それをわたしは不思議と妬ましいとも寂しいとも思わなかった。妖と人間。相見えることは出来なくても、彼女が幸せな時間を過ごすのを感じるだけで、わたしは幸せな気持ちになれた。
「わたしの元に戻ってきた時に一緒に笑おうね」
一度、彼女がわたしの棲んでいる松の並木を通り過ぎたときに囁いたことがあった。
その声が聞こえたのか、彼女は不思議そうに松の木を見上げた。そして、優しく笑いかけてくれたのだ。
彼女とわたしは繋がっている。
そう信じられた。
いつか巡り会える。
そう疑いもしなかった。
彼女が再び不幸な死を選び、形跡が消え、再び彼女を感じ取るまで……。
4
「ところで。『待つ君』が探している愛しの『かの君』は見つかったの?」
白い羽織を羽織り、長くつややかな黒髪を風の思うがままになびかしている桜の妖は、思い出したようにわたしに問いかけたのだった。
桜の時期も随分前に終わり、桜の木には眩しい限りの青々とした葉が生い茂っている。薫風が気持ちいい初夏。
わたしの返事を興味津々に待っている桜の妖−桜姫−にわたしは苦笑せざるをえなかった。
「見つかったのなら『さくら』の元に遊びに来たりはしないさ」
わたしの返事に今度は『さくら』が苦笑した。
「そうよね。『待つ君』にとって一番大切な人なんだもんね。早く見つかればいいね」
珍しく『さくら』がわたしに優しく微笑みかける。
「でも、『待つ君』って呼び名は松の妖−松皇子−からもじっているのも確かなんでしょう?」
これまた興味深げに『さくら』が尋ねてきた。
「そうだよ。……でも、『待つ君』と呼ばしているのは『さくら』だけだよ。『さくら』が俺にしか『さくら』と呼ばしてないようにね」
「ふうん」
『さくら』は生返事を返すと、斎場の煙突から空に昇る煙に視線を移した。
「今日も誰かが死んだんだ」
あまりにも無機質な声で『さくら』が独りごちる。そして、次の瞬間にはすでに喉をゴロゴロと鳴らしている。
それをわたしは複雑な気持ちで眺めていた。
「『さくら』だから毎日でもこの場所に来るんだよ」
『さくら』の横顔に口の中でそっと呟く。
なんという悪戯なんだろう?
ようやく彼女が輪廻転生の輪から外れる日が訪れたというのに……。
終
ある朝、彼女が同じ妖になったのを風が教えてくれた。
だからわたしは必死に彼女を捜し、そして、見つけたのだ。桜姫となった彼女を……。松の妖となったわたしとはどこまでいっても相容れない妖となった彼女の姿を……。
それが分かった瞬間、わたしは全てを呪った。
待ったのに……。長い時間、それこそを気が遠くなるような時間、彼女を待ったのになんということだろう?
でも、それは短慮だった。
『さくら』にわたしとの前世の記憶はない。しかし、笑いかけてくれるのだ。口では煙たいことを言いながらも、邪険にしながらも、わたしと一緒の時間を過ごしてくれる。そして、無邪気にわたしの「かの君」のことを尋ねてくる。その「かの君」が自分であると気づかずに……。
この頃、わたしはふと思ったりしてみる。
ここまで待ったのだ。もしかしたら、『さくら』にわたしの記憶が甦る日がやってくるかもしれない。
だから、もう少し待ってみよう。
そう思う。
こんなにも彼女のことが愛しいのだから……。
〈了〉




メールで感想なんかを頂ければ、うっれしいな♪