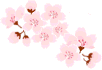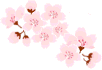
桜姫幻想譚は、合同本でした。ここでは僕の話のみ掲載しています。


落 日

1
高層ビルが立ち並ぶ都会の雑踏の中、ちょっとした息抜きのために用意
されたような広場で一組の男女が佇んでいた。
二人を取り囲む気まずい雰囲気が、ただ行き交うだけの人たちにも伝わっ
ていくのか、チラチラと横目で二人の姿を確認するのみで誰もそこに近づ
こうとしない。
どこにでもある別れ話。
遠くから眺めても男のほうが項垂れているので、振られたのが男で振っ
たのが女であることが一目でわかる。
一向に黙ったままの男に、紅くぬめった女の唇からトレンディー・ドラ
マの台詞のような別れの言葉がスラスラとでてきた。
「もう終わりにしましょう。このままじゃ二人ともダメになってしまうわ。
今なら、お互い取り返しがきくはずよ」
涙の一つも流さず、それでいて人生最大の別れのように切り出す彼女は
なかなかの役者だった。そして、それに付き合う男は間違いなく恰好の道
化師役だ。
男が女と出会って二年。付き合いだして一年と半年を迎える春。桜が爛
漫と咲きほこるこの時期に別れはやってきた。それも女が用意していたか
のように、なにもかもが女の思うとおりに進んでいく。
それを男は心の中で苦笑しながら他人事のように受け入れていたのだっ
た。
(どうしようもない……)
男の口から人知れずため息がもれる。
ここで男の知っているすべてを暴露したらこの女はどうするだろう?
一笑の元に事実を否定するだろうか。それともあっさりと認めるだろう
か……。
自分の目の前で艶やかに装う女が影でしていることを男はすべて知って
いた。
人を引きつけずにはいられないこの女は、自分と会わない時間には別の
男の胸に抱かれ、その男に自分にいつも言っている愛の言葉を同じように、
否、それ以上の妖艶さを乗せて囁き、そして自分のことをなじり、別れた
いだの、あれはだたのペットだのと呟いて、より一層新しい情人の気を引
くのだった。
男にとって女はたった一人の情人だったが、女にとって男はたくさんい
る愛人の中の一人でしかなかった。一度、男が仕事帰りに駅前で見かけた
女は、年下の男の腕に自分のそれを絡ませ、年上の女性を悩ましげに演じ
ていた。思わず何も知らずに歩いている男に同情するくらい相手の姿は可
哀想なものだった。まるで、女を引き立てるペットそのものに見えた。
この一年半の間。幾度、男は別れを切り出そうと悩んだことだろう。
付き合って間もなく気づいた女の正体を始めは受け入れることが出来ず、
頭の中で何度も否定し続けた。が、さすがにそれにも限界がある。悩んだ
末、男は別れを決意したのだった。
しかし、それを言葉にすることは男にとって容易なことではなかった。
女と会う度、肌を触れ合わす度、男の意志はぐらついた。『今度こそ、今
度こそは』と、自分に言い聞かせるのだが、結局別れはだんだんと延びて
いき、今日という日まで来てしまったのだ。その理由はたった一つ。簡単
な答えだ。男が一重に女を本気で愛していたからだ。女を失うことがこわ
かった。
男の目の前で、広場に植えられている桜の花弁の舞い落ちるさまを感慨
深くもなく眺めている女は、確かにどんな男も魅了する何かを持っていた。
一度見れば忘れることなんて出来ない。それほどの強い印象を人に与える
のだった。そして、自分もそれに魅了されたうちの一人だ。けれど、それ
を悔いたことはない、こうして別れを告げられた今でも……。その証拠に
女の一挙一動から目が離せずにいる。
男のそんな心情を知ってか知らずか、女はおもむろに赤い……血のよう
な鮮明さを持ったジャケットから煙草とライターを取り出すと口にくわえ
火をつけた。
春とはいっても、まだまだ夕方になると肌寒い。なかなか返事をよこさ
ない男への催促なんだろう。煙草をふかしながら時々チラッと男に視線を
送る。足元のほうでは、高いヒールが幾度も地面をカツカツと打つ。
それを見て男は曖昧に笑うしかなかった。
まさか、今日、自分から別れを切り出すつもりで彼女を呼び出したとい
うのに、女から先に別れを告げられるなんて皮肉なものだ。何と言ってい
いのか、適当な言葉が見つからない。
そんな男の曖昧な笑みをどう理解したのか、女は口の端に不敵な笑みを
浮かべると、ふかしていた煙草をヒールでもみ消し、
「それじゃ、もう会うこともないわね。さようなら」
と、淡白な台詞と共にポケットから出した合鍵を男に渡して猫のような
しなやかさをもって雑踏の中へ消えていったのだった。一度も男のほうを
振り向きもせずに……。
その後ろ姿を眩しげに見送りながら男はポツリと言葉を落としたのだっ
た。
「君のこれからが輝きに満ちあふれていれば良いけどね」
2
陽が西のビルの彼方に見えなくなると、途端に辺りは暗幕をかけられた
ように暗さを増したのだった。
本来ならば家路を急ぐ人で一杯になる歩道もこの二、三日は状況が違っ
ていた。
頃は桜の季節。年若いサラリーマンは昼から上司黙認の外勤を強いられ、
中間管理職らしき背広の集団が定時のチャイムと同時に花見で有名な公園
へと足を向ける。
そんな春ならではの情景を男は広場のベンチからぼんやりと眺めながら、
その集団に入り込むチャンスを伺っていた。きっと、男がスルリッと一集
団に紛れ込んでも、こう人が多ければ誰も気に止める人間なんていないは
ず。
「すこし肌寒いが、酒が入れば大丈夫」
なんて反対に陽気に話しかけてくる人間がいるかもしれない。
みな行き先は同じ。咲き乱れる桜の元。たぶん、今日が一番の見頃だろ
う。
だから男は公園に向かって歩きだしたのだった。勿論、男のスケジュー
ルに花見などという悠長な行事はない。公園に行けば酒と花に浮かれた奴
らが、からんでくるかもしれないがそれも仕方ない。だって、この時期に
しか、彼女とは会えないのだから……。
男は女とお揃いで買った腕時計で時間を確かめる。これで時間を確かめ
るのも今日が最後になるだろう。女と別れたのだ。もうつける必要もない。
高かったが気に入っている品物でもない。見栄のみでつけていたにすぎな
い時計。
豪奢な文字盤の上で針が七時を指す。
(もうあの女と別れて一時間が立とうとしているのか……)
男は、そのことに気づいて思わず吹き出してしまった。
愛していたはずの女と別れたというのに、なんて心は軽いんだろう。こ
れは、もしかしたら、もうすぐ彼女と会うからかもしれない。
(彼女は……会ってくれるだろうか?)
初めから答えはわかっているはずなのに、それでもあえて男は自問自答
してみる。
とにかく。
男の視界に桜の咲き誇る公園が見えてきた。
3
今年の陣取りが、来年の出世に大きくかかわる。
桜の下では年若いサラリーマンが寒さに身を震わせながら上司が来るの
を今か今かと待っている。そんな光景を横目で見ながら、男は公園の奥の
方へと歩を進めていった。
奥の方へ歩いて行くほど、ブルーシートをひいて待機している集団が少
なくなっていく。自前で明かりを用意しなければいけなくなるのもあるが、
やはり花見は知らない他人と肩を並べ自分の頭上の桜を見ながら酒を酌み
交わすのが楽しいのだ。
男も会社に入りたてのときはそうだった。
毎年、戦争のように見栄えのよい桜の下にシートをはり、寒さに身を震
わせながら早く上司が来ることを願ったものだ。そして、酒がふるまわれ
酔ったころに上司が知りもしない隣の集団に、偶然取れた桜の木の下を自
慢するのだった。
「うちの部下は優秀だからね」
誉められて嫌な思いはしない。それが初めの二、三年はうれしかった。
上司に認められているとさえ錯覚した。しかし、現実はそうではなかった。
年下に順番が変われば、上司はそいつにも同じ台詞を繰り返す。
思うように先に進めない自分が見えたとき、男は彼女と会ったのだった。
今日のように花見で人がごったがえすこの公園で……。
今、男が立つ桜の大木の下で……。
4
満開の桜の木が、風もないのに突然揺れた。
ざわざわと音を立てて、桜の花弁が男の元に舞落ちる。
「こんにちは。お久しぶりね」
凜とした涼しげな声が薄暗くなった空間に響き渡った。
男が舞落ちる花弁に気をとられている間に、着崩した着物をまとった女
が男の目の前に忽然と姿を現したのだった。
一瞬、江戸時代の遊郭の女を連想させる装いに強く目を引かれるのだが、
次の瞬間、男の視線は女の潰れた右目に釘付けになるのだった。何によっ
て潰されたのかは定かでないが、女の潰れた右目は妙に痛々しく、それで
いて印象的だった。まるで、その女が女であるという証拠のように女の顔
に存在している。
そんな右目にかかる前髪をうっとうしげに女がかきあげる。
はたして、男を意識しているのかいないのか……。そんななまめかしく
て色っぽい仕草に男はゴクリと音を立てて息を飲む。
はっとするほど艶やかな女の仕草は、男の欲情をそそるのに十分だった。
手を伸ばせば届くところに女の体がある。ほっそりとした体は男が押し
倒せば簡単に地面に倒れ込むだろう。そして、そんな男の行動に女は決し
て嫌がらないはず。自分の目の前にいる女はそんな女なのだ。男は感覚的
にそのことを悟った。男に悩ましげな笑みを送り、それに対する男の行動
を密かに伺っている。まるで男を試しているかのようだ。その証拠に、依
然として潰れていない左目は、しっかりと男の顔を見据えている。
そして、見据えたまま薄く笑みを口元に浮かべると女は、
「でも頼んでいたものは持って来てくれなかったのね」
と、冷たく言い放ったのだった。
「!!」
こうも単刀直入に用件を言われるとはさすがに男も予想していなかった。
思わず返す言葉に苦慮してしまう。けれど、そんなことなどおかまいなし
に再び女の手厳しい台詞が男に襲いかかる。
「言ったはずでしょう!? あの女の首を持ってきてくれって……」
子供を諭すような優しい口調で言葉を並べるのだが、それは男にとって
この上ない残虐な仕打ち以外の何物でもなかった。女が静かに言えば言う
ほど、男にはつらいものだった。
「ミイラ取りがミイラになるなんてネ……。予想してなかったなんて言わ
ないけど残念だわ」
「俺だって!」
ため息まじりに話す女に男は反撃を試みる。
確かにここにきた時点では、女に何を言われても我慢しようと思ってい
た。女が望んだものを自分は持って来れなかったのだから……。でも、女
の言い方が男のかんに触わった。
自分だって言い分はあるのだ!
グッと女を睨みつけると、男はジリッと女のほうに一歩踏み出した。け
れど、女はそれに動じる様子もなく無表情で男を見つめ返すのみ。
「俺だって何? 言いたいことがあるなら言いなさいな。聞いてあげるわ」
腕を組み、高飛車に女が声を発する。
「ただし、分かっているわよね? あなたは今度わたしと会うときは、間
違いなくあの女の首を持ってくると約束したのよ!? だから、わたしはあ
なたが望むものを渡したの。忘れてはないでしょうね!?」
はらはらと桜の花弁が舞落ちる中、残念とばかりに喋る女の姿が一瞬鬼
女へと姿を変えていった。もしかしたら、それは桜が見せた幻だったのか
もしれない。しかし、それは間違いなく女の意志だった。女の心の中は般
若のごとく荒れ狂っていた。それほどに女は男がその女の首を持ってくる
ことを心待ちしていたのだ。それが男にも分かるので、慌てて必死な声で
弁解を始める。
「お……、俺だって始めは貴女と交わした約束を守るつもりでいたさ!
あいつを今年こそはこの桜の木の元に連れて来ようとした」
「じゃぁ、何でここにあの女はいないの?」
怒気を孕んだ声で女が聞き返してくる。
「アレを使えば、簡単に連れて来られたはずよ!!」
「ああ。確かにそうさ。でも、ダメだった。あいつの顔をみていたら出来
なかった。だって俺が貴女との約束を守らなければ、あいつは死ななくて
すむんだ。そして俺は再び貴女と……」
「でも、新たな犠牲者がこの地上に増えていく原因を作ったわ。あなたが
あの女に要らぬ同情をかけたばかりにね……」
辛辣な台詞が女の口から飛び出した。それに反抗するように男が怒鳴り
返す。
「同情なんかじゃない!!」
一瞬、辺りの空気がピンッと張った。その中に男の絞り出すような声が
もれていく。
「仕方ないだろう? あいつは……。あいつは、血はつながっていなくて
も一時は『妹』と呼んだ女なのだから!!」
冷たい春の空気が男の体を静かに包み込む。
そして。
男は改めて自分の言った台詞の重大さに気づいたのだった。
5
口に右手を当て、動揺を隠しきれずにいる男に女は軽く息をつくと、再
び口を開いてきたのだった。
「あの時、あなたはなんて言ったの? 『あいつはもう俺の知っている妹
じゃない、妹の体を奪った妖だ。だから妹の仇を討つためにも絶対首をもっ
てくる』……確か、そう言ったわよね。だからわたしはあなたに媚薬を渡
したのよ!? 桜姫が好んで止まない香をね。あれの匂いに耐えれる桜姫なん
て一人もいないわ。あの女だって然り。猫がマタタビに酔うように媚薬を
つけたあなたに酔ったでしょう? その効果のあるうちにここに連れて来
てくれれば良かったものを……。そんなにあの女が良かったの?」
ほとほとうんざりしたというふうに女が男を見つめ返す。その視線が男
には痛すぎて逃げるように項垂れると、吐き捨てるように呟いたのだった。
「あれがもう俺が知っている妹じゃないのは分かっていたさ。貴女が言う
『桜姫を放棄した堕ち姫』に体を乗っ取られたことも理解できた。けれど、
あいつは喋るんだよ、あいつの顔で、あいつの声で。普通の人間には耐え
られないことだよ。妹と呼んでいた女と恋に落ちることさえ罪なことなの
に……。これ以上、どうすれば良かったというんだ!? 愛している女と妹
を自分の手で殺すなんてできやしない」
男の疲れた台詞に、けれど女は同情する様子もなく、
「あなたはわたしがあんなに『堕ち姫』のことを話したのに全然理解出来
なかったのね」
と、冷ややかに言い放つのだった。そして男に背を向けると、自分の後
ろにどっしりと根を張った桜の大木を仰ぎ見る。
「わたしたち『桜姫』は、自分の欲望のためだけに人間を惑わしてはいけ
ない。『桜姫』である以上、人間の血を求めていいのは自分の棲まう桜の
ためのみ。それは『桜姫』であるがための当たり前の理。それをあの女は
平気で犯したの。人間の男と交わる快楽さに溺れた女は自分の桜を顧みず
出て行ったわ……」
再び男のほうに振り返った女の目には哀愁が漂っていた。
「あれがあの女の桜……」
女の指さした先には、蕾さえもつけていない桜の大木が一つ、闇の中に
浮かんでいた。周りの桜は艶やかな花をつけているというのに、その大木
のみ枯れ木のようにぽつりと満開の中に佇んでいる。
「あれが桜姫を失った桜の木の末路よ。去年までは辛うじて花もつけてい
たけれど、今年は無理だったわ。花をつける力もなくなった。桜姫を知ら
ない人間には不思議に思うかもしれないけれど、これが事実なの」
哀しみを含んだ声が闇の中にこだまする。
「何がきっかけであの女が『堕ち姫』になったのかは分からない。ある日
突然桜の木から飛び出すと、偶然公園を通りがかった女の体に乗り移って
しまった。それからはあなたも知っての通り。自分の欲望のために次から
次へと男を虜にしていったわ。一度、『堕ち姫』になった桜姫は二度と『桜
姫』に戻れない。けれど、そのまま放っておくわけにもいけない。だから、
あなたに『堕ち姫』狩りを頼んだというのに……」
「分かっているさ」
男がポツリと呟く。
「妹のためにも自分がどうすればいいのか痛いほど分かっている。それは
初めてここで貴女の話を聞いたときと変わりはしない」
男は女の向こうに立っている桜に視線を移すと囁くようにここで初めて
女と出会ったときのことを回顧しだしたのだった。
「貴女と出会ったのは、ちょうど付き合いだしてすぐに豹変した妹と上司
と意見が合わず仕事に行き詰まってすべてが疲れきったときだったね。気
づけば会社の花見を抜け出して桜に誘われるままにここに足を運んでいた。
そして貴女は俺に『桜姫』と『堕ち姫』の話をしてくれた。愛しい女の行
動がおかしくなったのは『堕ち姫』に捕まったから。愛しい女を『堕ち姫』
から救い出す術は、ただ一つ。『堕ち姫』を狩ること。ここに『堕ち姫』
を連れてきて桜に封印すること。でも……」
「桜姫に憑かれた体はもうどうしようもない」
桜姫の口から厳しい台詞がでていった。抑揚のない声はあくまでも淡々
としていて、認めざるをえない事実を語っていた。
「一度『堕ち姫』に憑かれた人間は、もう二度と人間として生を受けられ
ないわ。だからわたしは、あの女を桜に封印した後、あなたの妹を新たに
桜姫として生きるように取り計らうと言ったの。それしかあなたの妹が無
事に生きる術はないのだから。……それにあなたも頷いたはずでしょう?
なのに、あなたがあの女を逃がしたおかげで、あの女はこれからも男を
溺れさせて滅ぼしていくことになったわ。わたしたち『桜姫』は桜のため
にしか人を殺めてはいけないのに……」
情けなさそうに女がため息を一つつく。
「まぁ、いいわ。あの女をここに連れてくるのは別にあなたじゃなくても
いいものね。もうあなたには期待しないわ。『堕ち姫』もあなたの元から
去ってしまったことだし……。あなたには愛想がついたからさっさとわた
しの前から消えてくれるかしら? あの女の首を持ってくる男は他に探す
わ。あなたのような男は他にもたくさんいるし、あの女は誰でも体を許す
からね。わたしはこうして自分の桜から離れることが出来なくても千里を
見通せる目を授かっているから、いつでもあの女の近くにいる男を捜して
『堕ち姫』狩りを頼むことが出来るわ」
言いながらだんだんと女の姿が桜の木に同化していった。笑いもせず、
怒った顔もせず、冷たい顔のまま大木の中に消えていく。
「ちょっと待ってくれ。俺は……俺はどうしたらいい!?」
慌てて消えゆく女に男が問う。
「さぁ? あなたの血を貰っても桜が綺麗な色をつけるとも思わないし……。
好きにすれば?」
桜と同化する瞬間、女の最後の声が聞こえてきた。
「桜姫!」
再び男が呼んでも女は桜からでて来ようとしなかった。
「俺はどうすれば良かったというんだよ……」
小さく呟き、男は女が消えていった桜の大木に額をもたせながら、ポケッ
トから小袋をとりだした。それは、女から『堕ち姫』狩りのために使うよ
うにと渡された媚薬の入った袋だった。この薬を使ったらどうなるか……。
男はそれを想像して結局怖くなって使うことが出来なかった。最後まで男
は『堕ち姫』に憑かれた妹でも愛していたのだ。『桜姫』への畏怖を淡い
思いだと自分の中でねじ曲げようとしたが所詮無理な話しだった。
結果は一つだけ。
「願わくば、君のこれからが輝きに満ちあふれていることを……。『桜姫』
に捕まるんじゃないぞ!」
夜空高く自分の目の前から消えていった愛しい女に届けとばかりに男は
吠えた。そして男は握っていた小袋を開けると、その中身を桜姫の消えて
いった桜の根元に振りまいたのだった。
小袋からさらさらとこぼれていった粉末は地上に降りた途端に桜のほの
かな香りへと姿を変えていった。
確かにこの香りにかなう桜姫なんていないだろう。これは桜姫の勲章で
もあるのだから……。
「さようなら。桜姫。もう会うこともないだろうけれど……」
ピンッと背筋をただすと男は桜の大木を後にしたのだった。一度も振り
向きもせずに、ただ前を向いて……。
〈了〉




メールで感想なんかを頂ければ、うっれしいな♪