LPのCD化 - LP (EP) レコードの 超高音質 CD デジタル化の方法
LPレコード の超高音質 CDデジタル化 を考えているあなたのために
by ADC System http://www.adcsystem.net/
LP (EP)レコードの超高音質 CDデジタル化 を考えておられる方のために機材の揃え方からソフトについての手順や方法等を説明させていただきます。超高音質と銘打っていますのでそれなりの予算は必要となります。なぜなら 音質と使用機材の価格は 一定のところまでは概ね正比例するからです。
LP(EP) レコードのアナログ音源をデジタル化し、CD-Rではなく 192kHz 24bit or 96kHz 24bit ファイルで HDD に保存すれば、CD-R よりもはるかに高音質で( レコードと違って気軽に)好きなときに好きなだけ聴くことが可能です。PC オーディオの世界にも思う存分に浸ってください。
「うーん、これだけの機材は揃えられないし、手間も ・・・・ 」という方は こちらへ (192kHz 24bit or 96kHz 24bit ファイルも入手可能です。)
| 1.アナログレコードプレーヤー・トーンアームを用意します。 |
||
 |
LP (EP) レコードの超高音質 CDデジタル化には、何より レコードの再生を行なうためにアナログレコードプレーヤーが必要です。しかも、超高音質での変換を行なう訳ですから、それなりの機材が必要になります。 現在市販されているアナログレコードプレーヤーの中で、高音質を謳うアナログレコードプレーヤーは数多くありますが、機能性の点で VPI SuperScoutmaster with Signature Tonearm か その上位機種の VPI HR-X を一押しでお薦めします。VPI SuperScoutmaster with Signature Tonearm の税込価格は 1,155,000円 です。価格相応の音質と機能を備えています。 上位機種の VPI HR-X は税込価格 2,310,000円 です。私は どちらかというと VPI HR-X は機能面よりデザイン面を重視しているように思いますので、VPI SuperScoutmaster with Signature Tonearm の方がコストパフォーマンスが高いと思います。 もちろんトーンアーム等は上位に位置するものが使用されていますから予算が合って、デザインが気に入ればこちらの方が良いでしょう。( VPI HR-X 用の トーンアームを別途購入し、VPI SuperScoutmaster のトーンアームと交換しても VPI HR-X よりも安くできます。 ) オークション等で往年のオールドアナログレコードプレーヤーが安価で出品されていることがありますが、アナログレコードプレーヤーのメンテナンスには相応の知識が必要ですので、初めての方は安くても10万円以上の新品のアナログレコードプレーヤーを使用される方が良い結果を得られると思います。 回転系のパーツは磨耗疲労するものですが、オールドアナログレコードプレーヤーでは交換部品の入手も困難です。 |
|
 |
トーンアームにも十分気を配ってください。VPI SuperScoutmaster は VPI JMW-9 Signature Tonearm 【 税込価格294,000円 】 を使用しています。 トーンアームのベアリング部のフリクション(摩擦)はアームの感度やトレーシング能力に大きな影響を与えるため、アーム設計において最大の要といえます。 ハイマス/ハイコンプライアンス化された VPI JMW-9 Signature Tonearm にはオイルダンプ機能が追加され、より安定したトレーシングが可能です。ここには、VPI社が独自に開発した理想のベアリング構造の、ピンポイント・スパイクによるユニ・ピボット・ベアリングを採用されています。 非常に鋭利なスパイクによる1点支持とすることで、ベアリング・フリクションを事実上ゼロ とし、アームの感度、コンプライアンスを極限まで高めています。 |
|
 |
通常、ストレートアームは S字カーブアームに比べて音質面で音の濁りが少なく高音質とされていますが、カートリッジの交換が大変だという問題を抱えています。
この VPI JMW 9 Signature Tonearm は交換用 Tonearm Armwand 【税込価格 168,000円 / 1本】
が用意されており、30秒強でアームごとカートリッジの交換が可能です。私は 合計 3本 の Signature Tonearm Armwand
を所有していますのでカートリッジごとトーンアームを交換して音色を楽しんでいます。 内部ケーブルには 米国 Nordost社 Valhalla製ケーブルが使用されており スイス レモ社のコネクタ と相まって トーンアーム交換後も安定した高音質が得られます。この点も VPI SuperScoutmaster with Signature Tonearm をお薦めする理由の一つです。 もちろん、より上位の 12インチ VPI JMW - 12.7 【 税込価格 458,000円 】 というアームも販売されていますし、 SME Series V tonearm 【 税込価格 735,000円 】 といったアームも販売されていますので予算に合わせて購入してください。 |
|
 |
安価なロングアームとしては SME Series M2-12 【税込定価 283,500円】 という 12インチアームもお薦めです。SME Series
M2-12 はストレートアームですが、一般的なヘッドシェル交換型の SME Series M2-12R という製品も発売されています。 弊店では SME Series M2-12 も使用していますが、なかなか音質の良いトーンアームです。ストレートアームにもかかわらず 専用ヘッドシェルを使用することにより、カートリッジの交換も簡単に行なえます。 |
|
 |
VPI SuperScoutmaster with Signature Tonearm 以上の VPI の機種には 6.8kg のアウターリングウエイトが標準で用意されており
0.75kg のセンターウエイトとの相乗効果により、通常のレコードプレーヤーでは再生できない反りのあるレコードもターンテーブルに密着させ、再生させることができます。 反りのない新品のレコードでもこのアウターリングウエイトの効果には絶大なものがあります。非常にお薦めのアイテムです。 |
|
 |
回転系に目を移すと VPI SuperScoutmaster with Signature Tonearm は モーター部に 24極300RPMのACシンクロナス・モーターを2台使用し、高いイナーシャを誇る 5.3kg ものフライホイールを介してプラッターを回転させています。 300RPM 弱で回転するフライホイールはターンテーブル質量の約60倍以上にも及ぶイナーシャを持ち、モーターの振動による影響を大幅に低減します。 もちろんこれを受け止めるレコードプレーヤー本体は、不要共振を排除し、高い内部損失を誇る重量級MDF素材をベースに、高剛性を誇る肉厚スチールプレートをプラスした異種素材積層三重構造のキャビネットを有し、リジッド構造ながら制振性に優れ、高いハウリングマージンを確保するとともに素材固有の共振モードを効果的に分散することにより、クリアでナチュラルな音質を獲得します。 また、プラッターには内部損失と剛性、表面精度を極めて高いバランスで融合させたアクリル素材を採用。 45mm厚の重量級プラッターによって、ランブル・ノイズを大幅に排除し、高いイナーシャによる安定した回転精度を実現しています。 このプラッターには、先に記載した 6.8kg ものアウターリングウエイトと 0.75kg のセンターウエイトが配置されますので、プラッターの総重量は、12kg を超えます。 |
|
 |
ACシンクロナス・モーターはAC電源の周波数に連動した回転速度で回転しています。そのため、電源周波数を安定化することにより、回転精度がさらに安定し、モーター振動も抑制することが可能です。 このため モーター電源部には VPI SDS ( Synchronous Drive System ) 【 税込価格 231,000円 】 を使用しています。 VPI SDS は高価ですが最新のデジタルテクノロジーと水晶発振精度を誇る画期的なモーター・スピードコントローラー/電源安定化システム(電源ライン・アイソレーター)です。 内蔵された水晶発振器により、正確なスピードコントロールおよび回転の微調整を可能としています。アナログ・ターンテーブルの心臓部ともいえるモーターの性能を最大限に引き出す画期的なシステムです。 |
|
 |
アナログターンテーブルの下に設置する オーディオボード にも気を配ってください。 私は ターンテーブル設置台に、特注 40mm 厚 本大理石 オーディオボード を使用。モーター部の振動を遮断するため、大理石オーディオボード を 2分割 しています。特注ですが 合計で 50,000円程度と安価です。 |
|
2.MCカートリッジ、MCトランス、フォノイコライザを用意します。 |
||
 |
次に トーンアームの VPI Signature Tonearm に MCカートリッジを取り付けます。 取付にあたっては 専用の VPI Signature Tonearm 調整用治具を利用して細心の注意を払います。(別のトーンアームの場合は お使いのトーンアームの説明書を熟読してください。) 針圧やアライメント、VTAアジャストメント、アジマス、アンチ・スケーティング等々精緻に調整するところが沢山あります。 調整を誤ると、いくら高価な機材を使用していても満足する音質を得ることができません。 |
|
 |
カートリッジは高いもので 100万円以上、安いものでは 数千円からあります。この多種多様なカートリッジの中から自分に合ったものを選択するのは大変ですが、アナログレコードを奏でる楽しみの一つです。 カートリッジはその機構上大きく分けて MCカートリッジと MMカートリッジの 2つがありますが、振動系のコンプライアンスが少ない MC系カートリッジの方が高音質を目指す場合 近道だと思います。 私は、価格と機能の点から MC ortofon MC cadenza black 税込価格 236,250円 を選択しました。消耗品ですので、まめに交換することを考えると、これ以上の価格のカートリッジはランニングコストも考慮する必要があります。 MC ortofon MC cadenza black には音質的には有利であると分かりながら加工が困難だった ボロンをカンチレバーに使用し、ダイヤモンド 無垢シバタ針と 6N 高純度銅線金メッキ仕様を組み合わせた最強発電エンジンは、これ以上は望めないと言う絶妙なコンビネーションで、まさに豊潤としか言えないサウンドを堪能させてくれます。 |
|
 |
アナログレコードプレーヤ VPI SuperScoutmaster with Signature Tonearm の RCA コネクタ部に フォノケーブル
ortofon 6NX-TSW1010R 税込価格 22,050円を接続します。 このフォノケーブルも安いですが、2重シールドが施されており 外部ノイズに非常に強いだけでなく、音質も良いケーブルです。お薦めのケーブルです。 アナログレコードプレーヤ から ADC コンバータ までの配線は 全てこの ortofon 6NX-TSW1010R で統一しています。ここに記載した以外の機材もありますので 全部で 10本ほど用意しています。 |
|
 |
MC カートリッジの微小な信号を増幅する方法には ヘッドアンプを使用する場合と MC トランスを使用する 二つの方法があります。 ヘッドアンプを使用したフォノイコライザを使用する場合には、静粛感とパワフル感でダントツの性能を誇る Whest Audio Whest PS.30 R 【税込推定価格 688,000円】 をお薦めします。 MC トランスを使用するか、ヘッドアンプを使用するかは それぞれ使用する MCカートリッジにとの相性もありますので、色々と聴き比べすることも楽しいひとときです。 |
|
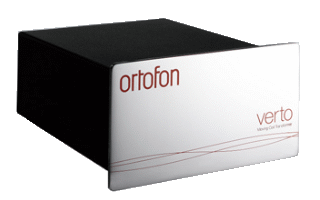 |
MCトランスを使用する場合は 税込価格 126,500円 の ortofon Verto をお薦めします。 ortofon Verto MC トランスは革新的な技術から生まれた新しいMCトランスフォーマーで、音質は何処までも高く澄み切っており、低音域は暖かく乾いた音質です。音像はダイナミックでオープン、音の広がりがはっきりとわかります。 従来のMC-Transformerとは全く異なるアイデアで開発されたオルトフォン独自のトランスですが、心臓部のトランスは 高音質ゆえにプロが絶賛して選ぶことで有名な Lundahl 社で製造されています 。 |
|
 |
MCトランスで昇圧した信号を増幅し、RIAA規格に沿って変更されたレコードの信号を復調するのがフォノイコライザです。 MCトランスとの組み合わせでは clearaudio BASIC PLUS (MC / MM イコライザ) を使用しています。微信号を取り扱うため、電源の質が問われますが、電源は本体と別筐体になっているだけでなく バッテリー(電池)駆動が可能ことと 非常にさっぱりとした透明感のある色付けの少ない音で低域及び中音域の厚みが感じられる音が得られることが選択理由です。 Battery Power Adapter とセットで約 360,000円 です。 これでようやく 通常のアンプに接続できる信号になります。 |
|
3.ADCコンバーター(アナログ => デジタル変換コンバーター)とパソコンを用意します。 |
||
 最下段 = Prism sound Orpheus、中段 = RME Fireface 800 |
最新の注意を重ねて、ようやく LP (EP)レコードのアナログ音源を通常のライン信号にまで復調できました。 次はこの信号をデジタル化する作業です。これには ADCコンバーター(アナログ => デジタル変換コンバーター)を使用します。 ここの機材も価格に応じて大きく音質に影響を及ぼしますので、予算の許す限り高音質高品質なものを選択してください。 私は、妥協のないサウンドクオリティー基準をもつ数少ないトップブランドメーカーで、世界最高水準の高音質アナログ <=> デジタルオーディオインターフェースメーカ として有名な Prism Sound 社の Orpheus ADC/DAC FireWire Audio Interface【 税込価格 850,500円 】を選択しています。 |
|
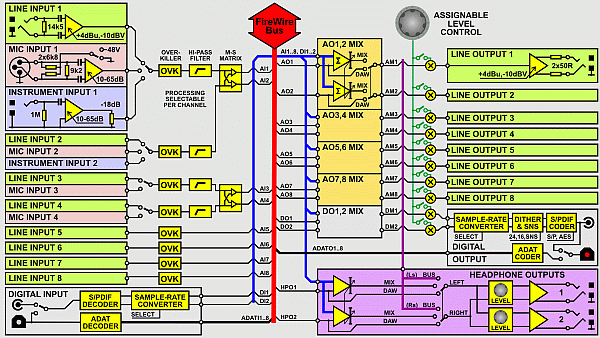 |
ブロック ダイヤグラムです。(左図をダブルクリックすると拡大します。) この ADC( Prism Sound Orpheus FireWire Audio Interface ) を パソコンと IEEE1394 FireFace ケーブルで接続します。 使用するパソコンは、録音再生時にはそれほど CPU 能力を使用しませんが、プチパリノイズの削除等の編集を行なうには極力能力の高いパソコンを選択したほうがストレスなく作業ができます。 2010年5月現在 使用している パソコンは intel i7 920 + 12GB Memory under Windows 7 64bit です。 192kHz 24bit でファイル処理をする場合 LPレコード 片面で 約 2GB の容量を使用しますので、HDD の容量は有り余るほど用意したほうが良いでしょう。私の場合は 192kHz 24bit ファイの保存用に 10.5TB RAID 5 ファイルサーバを立ち上げています。 |
|
 |
パソコン には使用する OS に合わせて Prism Sound Orpheus FireWire Audio Interface 用の Windows7
64bit driver をインストールします。 ASIO 2.0 driver だけでなく、WDM driver もインストールしておくと itunes や Windows Media Player からも Prism Sound Orpheus にアクセスできます。( 逆に言えば WDM driver をインストールしませんと Windows7 64bit の起動時に流れる音楽等が聞こえません。) Prism Sound 社の Orpheus ADC/DAC FireWire Audio Interface には 高品位なヘッドフォン出力端子がありますので、モニターには AKG701 【 税込価格 85,000円 】 クラスの高音質ヘッドフォンを使用してください。 AKG701 もお気に入りのヘッドホンの一つですが、ナチュラルな聴き疲れのしない忠実な再生をしてくれますのでお薦めです。 |
|
4.LP (EP)レコードの再生とデジタル保存をします。 |
||
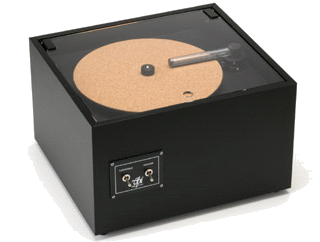 |
LP (EP)レコード をアナログレコードプレーヤに載せる前に忘れてはいけないことがあります。 それはレコードのクリーニングです。新品のレコードではそれほど心配することはありませんが、オークション等で中古レコードを購入した場合は、必ずクリーニングをして下さい。 クリーニングをする方法も色々ありますが、私は VPI HW-16.5(バキュームレコードクリーナー) 【 税込価格 134,400円 】 を使用しています。 VPI HW-16.5(バキュームレコードクリーナー) のターンテーブル上にレコードを装着。専用のクリーナー液をブラシでレコード盤に塗布しながらクリーニングをした後、 バキューム方式によりディスクの溝に入り込んだ微細な埃や汚れを強力に吸い取ります。 ディスク溝の埃やゴミによるスクラッチノイズの低減やレコード針のスムースなトレーシングに効果を発揮します。 美しく洗浄されたアナログディスクのサウンドを聴けば、埋もれていた名盤の数々を、もう一度聴きたくなるほどの魅力を感じさせるレコードクリーナーです。 |
|
 |
編集ソフトは Prism Sound 社の Orpheus ADC/DAC FireWire Audio Interface の多入力システムに対応し、ASIO 2.0で ADC/DAC をコントロールできるものが必要です。 更に、録音(サンプリング)後に レコード特有のプチパリノイズを低減する編集作業が必要ですので こちらにも対応するものが必須となります。 私は Sound Forge Pro 10 を使用しています。Sound Forge は 英語版の 4.5 から継続して使用しており慣れていることもありますが、高音質での編集作業が可能で かつ 税込価格が 57,750円 と安価な点からお薦めできるソフトです。もちろん 再生時の音質にも合格点が付けられます。 WAVE などのソフトも優秀ですのでご一考されたらいかがでしょうか。ただ、 WAVE はレコードの編集に使用するには多機能すぎる感じがします。 |
|
 |
LP(EP)レコードを VPI SuperScoutmaster のターンテーブルに載せ、アウターリング、センターウエイトを使用してレコードをターンテーブルに密着させます。 EP レコードの場合は、センターの穴が大きいので、スピンドルアダプターが必要です。 アームリフターを使用して、アームを上げたまま トーンアームの指掛け(赤矢印)を利用して、そっとアームをレコード最外周に位置を動かします。 アームを下ろす前に カートリッジの針が定位置にあるか確認をして下さい。 確認ができたら ターンテーブルを回転させます。 回転が安定したことを確認したら、編集ソフトの録音ボタンを押し、アームリフターを下ろします。 |
|
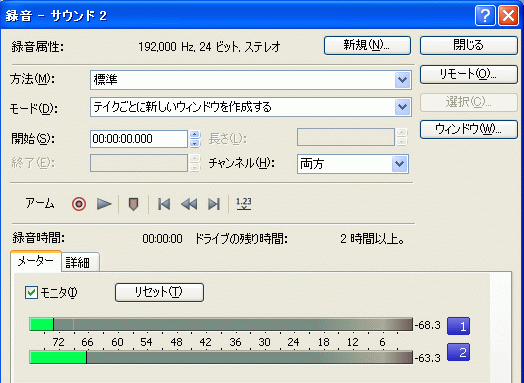 (ダブルクリックで拡大) |
Sound Forge Pro 10 の使用方法は簡単です。詳細はこちらをご覧下さい。 Sound Forge Pro 10 をインストールしたら 最初に オプション => ユーザー設定 => オーディオ の画面 でオーディオデバイスを選択してください。Prism Sound Orpheus の場合は ASIO Fireface と表示されます。 左図は 録音開始画面です。赤色の二重丸をクリックすると録音が開始されます。 録音がうまくいかない場合は、レベルメータの横にある青い 「1」「2」 のボタンをクリックして、入力先が正しく設定されているか確認してください。 録音が終了すると 赤色の二重丸ボタンが 黒い四角に替わっていますので、この四角ボタンで停止させます。 |
|
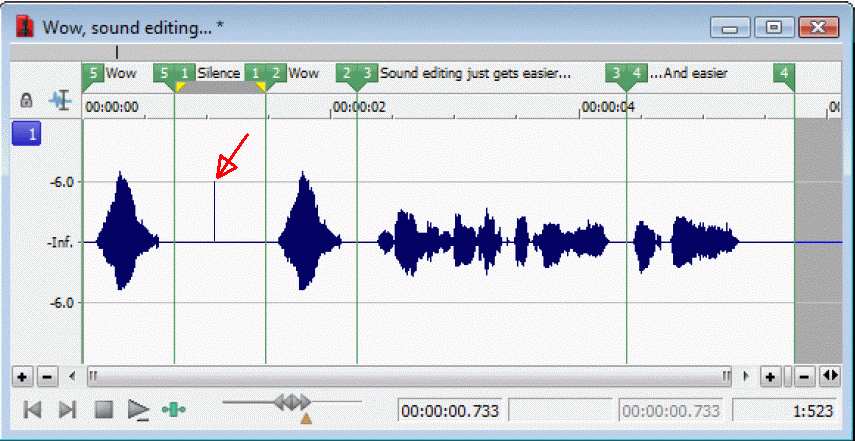 |
録音(サンプリング)は 192kHz 24bit または 96kHz 24bit で行ないます。 録音(サンプリング)後、ファイルを開き、大きなピークノイズ(赤矢印)は手作業で取り除き、レコード全体に含まれるノイズは Crik & Clacle 除去をソフト上で実行します。 |
|
 |
ところで なぜ、192kHz 24bit or 96kHz 24bit で録音(サンプリング)するのでしょうか? 最終的には、CD にするのだから、最初から 44.1kHz 16bit でサンプリング化(デジタル化)しても同じではないかと思われるかもしれません。 写真撮影もアナログの被写体をデジタル化する点では同じですので、音楽のサンプリング図形を比較するより、画像処理の方が分かりやすいのでご覧下さい。 左図 は 3456x2304 の大きさで撮影 => 時計方向に画像を 18度回転 => 320x135 にトリミング したものです。 |
|
 |
左図 は 320x213 の大きさで撮影 =>時計方向に画像を 18度回転 => 320x135 にトリミングしたものです。 画像処理を行なう前のデータ量が小さいと、画像を18度回転させた後の翼のライン等が綺麗に処理できないことがよく分かります。デジタル加工する場合は大きなデータ量で作業してから リサイズしたほうが加工跡が目立たないということです。 音楽の波形デジタル処理でも同じ事が言えますが、大きな量のデータ加工には大量の CPU パワーと メモリー量、HDD容量 が必要ですので注意してください。 |
|
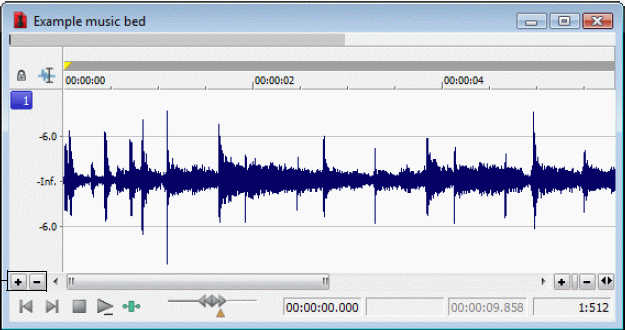 |
こうして丁寧に LP (EP) レコードから サンプリングした 192kHz 24bit or 96kHz 24bit ファイルはノイズ対策の編集を施してから
CD用の 44.1kHz 16bit WAVファイルに変換し、CD-R に焼きこみます。 この場合も CD-R には国産の高級 CD-R を使用し、焼きこみ速度は最大速度ではなく余裕を持った速度で焼きこむように注意を払ってください。 これで 超高音質で LP (EP) レコードから CD-R への変換ができました。 |
|
LPのCD化 - LP (EP) レコードの 超高音質 CD デジタル化の方法 -
LPレコード の超高音質 CDデジタル化 を考えているあなたのために
by ADC System http://www.adcsystem.net/