Art of the treble〜sounds’Library (JAPAN)
Leo Meyer Leo Meyer
| EP | 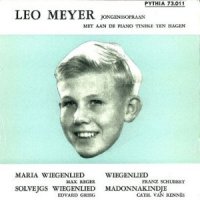 |
LEO MEYER JONGENSSOPRAAN (PYTHIA
73.011) met PIANOBEGELEIDING van TINEKE TEN HAGEN KANT 1 1. Maria Wiegenlied, Op.76, No.52 (MAX REGER) 2. Solvejgs Wiegenlied, Op.23 (EDVARD GRIEG) KANT 2 1. Wiegenlied, Op.98, No.3 (FRANZ SCHUBERT) 2. Madonnakindje, Op.54 (CATH. VAN RENNES) ジャケットの表情・歌声から、知る限りの録音物では最も若い時期のものと思われる。成熟した声を聞かせるレオの、初々しさを含んだ揺るぎない歌唱もまた良い。時折、前の音を引きずって歌う古風な歌い方もいやみがなく、柔らかな声で子守唄を披露している。堂々たる風格と清涼な少年声の魅力を兼ね備えている、ソロ活動向きのソリスト。 グリークの曲は「ソルヴェイグの歌」かと思って入手したら「ソルヴェイグの子守唄」で、同じ組曲の中のものだった。 (by Nao) 2006/03/09(Thursday)up |
| EP | 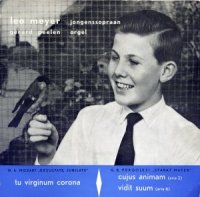 |
Leo Meyer(106 812.1E) 1面 Mazart - fu virginum corona 2面 Pergolesi -Stabat Materより Cujus Animan(Aria 2) Vidit Suum ( Aria 6) |
| EP | 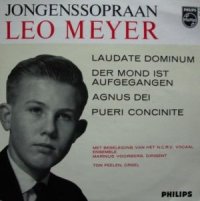 |
JONGENSSOPRAAN LEO MEYER(Philips/411 678
NE)1962年?/Marius Voorberg/NCRV Vocal Ensemble,Ton
Peelen(organ) Side 1 1.Laudate Dominum(Mozart) 2.Der Mond ist aufgegangen(Schulz) Side 2 1.Agnus Dei(Bizet) 2.Pueri Concinite(Von Herbeck) ボーイソプラノのがどうのというより、完成された一人の(プロの)歌い手なんだろう。歌声のゆるぎなさ、声量と豊かさにはただただ圧倒される。そして高音。かすかにビブラートをきかせつつも、根幹では声量と張りをもって、豊かに朗々と聞かせてくれる。たった7インチのEPだが、まるでリサイタルを聞いている気分である。実際に舞台やオペラの中のアリアなどで是非聴いてみたいタイプ。大舞台でさぞ映えるだろう声は、しかしビブラートがききすぎず、声は膨らみつつもいわゆる少年の声の持つ硬質の響きを持っていて、おばちゃん声にならずボーイソプラノとしての魅力を存分に味わえる。選曲も朗々と歌えるものを選んでおり、Leoの豊かな歌声を最大限に生かしている。62年の録音なのに音がクリアなのも、驚くと同時に嬉しい。Leoの声の、ねっとりとしていない、現代的な雰囲気に合う。 (by Emu) 2006/01/26(Thursday)up |
| 10inch | 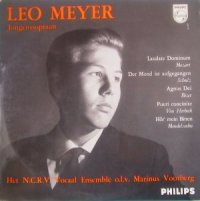 |
LEO MEYER, jongenssopraan (PHILIPS 600
713) Kant 1: 1.Laudate Dominum(Mozart) 2.Der Mond ist aufgegangen(Schulz) 3.Agnus Dei(Bizet) 4.Pueri Concinite(Von Herbeck) Kant 2: 1.Hor' mein Bitten(Mendelssohn) カバー写真は代表作をまとめることが出来るまでにネームバリューが上がった頃(?)なのか後年のものだと思うが、収録曲は初期の初々しくも朗々とクリアで高い声が溢れていた当時に歌われたものを集めた盤になっている。モーツァルトのオルガンは、っぽくなくって(編曲が違うのかひたすら暗い。)新人ソリスト故か伴奏は必ずしも上手だとは思えないが、伴奏がどうであろうと、LEOの声がこの盤では何処までも何処までも果てしなく出ていることに驚いてしまう。私は「4.Pueri Concinite」をただ呆然として聴いてしまった。今まで何度もたくさんのトレブルで聴いた曲ではあるけれど、ここまで声も心も豊潤なのは初めて。しかも、決して歌曲ではなく宗教曲として聞こえてくる作品の精神性&精神性を感じさせる気高い声。彼ってどういう存在だったのだろう? 「Kant 2:1.Hor' mein Bitten(Mendelssohn)」はHear my prayer。こちらも最初の一声でグッと引きつけられる。彼のバックコーラスは成年男女だが、大人ではないと彼の声に迫力で負けてしまうからだろう。(実際、負けていると感じる箇所はある)合唱からスッと浮かび上がる彼の声は美しく、渋さが加わる前の、ソプラノの艶がありながらも可憐なテイストも味わえる貴重盤と言える。(by Hetsuji) 2006/04/27(Thursday)up |
| 10inch | 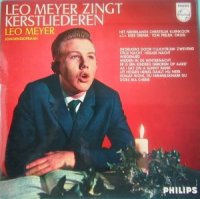 |
LEO MEYER ZINGT KERSTLIEDEREN, LEO MEYER jongenssopraan
(PHILIPS 600 382 PR) Kant 1: 1.Engelkens door't luchtruim zwevend 2.Stille nacht, heilige nacht 3.Wiegelied 4.Midden in de winternacht Kant 2: 1.Er is een kindeke geboren op aard 2.As I sat on a sunny bank 3.Uit hogen hemel daalt Hij neer 4.Schlaf wohl, du Himmelsknabe du 5.Dors ma cherie 正直なところ、実はこのカバーの彼はなんというか好きではない。写真、もっと・・・。 「レオ・マイヤー、クリスマスの歌を歌う」とでも訳すのか?見れば右下にクリスマスキャンドルがある。荒野の果てに、聖しこの夜・・・とメジャーな曲が続き古い時代の曲へ。Kant 2ではバックコーラスが活躍し始める。古き良き時代と家庭のクリスマスの雰囲気。非常に端正。いつの時代の声だろう?録音の仕方のせいかもしれないが、ろうろうと聴かせたモーツァルトやヘルベックの頃よりは高い声がイガイガして聞こえる。不思議とビブラートはかかっていない。ストレートに押してくる。巻き舌も麗しい。あ、「5.Dors ma cherie」での高音部がさりげなく美しかった。ただ声だけで歌っていた頃と違って、この盤では歌い手の考え深さも伝わってくる。敬虔なクリスマスに相応しい演奏と言える。 (by Hetsuji) 2006/05/05(Friday)up |
| 10inch | 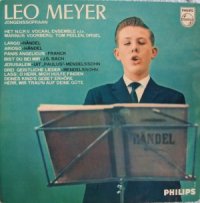 |
JONGENSSOPRAAN LEO MEYER (PHILIPS 600 381
PR) Kant 1 1.Largo 2.Arioso 3.Panis angelicus 4.Bist du bei mir Kant 2 1.Jerrusalem 2.Drei geistliche Lieder 1)Lass', o Herr, mich Hulfe finden 2)Heines Kind's Gebet erhore 3)Herr, wir trau'n auf deine Gute ボーイ・ソプラノの帝王の1枚。声が進化した後の定番というか安定した盤。夜の女王のアリアも行けそうだが、かといって、女声では決してない、ボーイソプラノにしか出せない声。彼の演奏だけではなく、バックコーラスその他、万全の体制盤。ここまでくると何も言うことはないが、私は円熟期に入る直前の、声に更に伸びを残した演奏が残っていたら、聴きたいし、是非にコレクションに加えたい。これもHetsuji欲。(by Hetsuji) |
| EP | 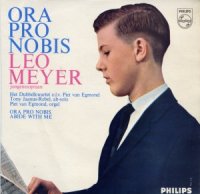 |
ORA PRO NOBIS LEO MEYER, jongenssopraan (PHILIPS 411 704 NE) Tony Jaanus-Rebel, alt-solo Kant 1: Ora pro nobis Kant 2: Abide with me オルガンの音はいかめしくも厳か。バックコーラスが大人なのも彼の声に似合っている。というよりも、少年声のコーラスでは彼の声は大人びすぎ、浮いてしまうことだろう。 このときのMEYERは、ボーイソプラノと呼ぶよりメールソプラノに雰囲気が近く女性ソプラノ的な香もあり、かつ、メールソプラノや女声にはあまり感じられないクリアさ透明感が声に残っている。聖歌隊のソリストとしてではなく、歌からは一人前の歌手の姿勢が見える。1曲1曲の密度と完成度が高く、これがステージだったら、1曲聴き終えるごとに、余韻を楽しむ時間が曲と同じくらいは欲しいところだろう。 ここでバックを務める、成年男女(たぶん)の合唱も又、良い。それにしても「 Ora pro nobis」は、ソロよりは合唱がメインですべてが聴きどころではあるのだけれど・・・暗い曲だ。なあ。 MEYERの声は、Kant 2の「Abide with me」で、より楽しめる。・・・どう聴いても、大人として対等以上に扱われているソリストの演奏に聞える。オルガンもバックコーラスもMEYERを大人のソリストとして共演している。声の響きが女声に聞えたり少年に聞えたり響きの不思議も楽しめる。が、少年ということにこだわらなくても、十二分にMEYER&彼のチームとしての演奏を心ゆくまで堪能できる作品になっている。又、おそらくTony JaanusなのだろうがMEYERと負けず劣らずなもう一人の声が聞こえるのも驚きだ。 leo meyer (106.812.E) のときは「いかにもボーイソプラノらしい少年の声&演奏&作品そのもの」の魅力に溢れていたが、時を経て、声にも歌心にもMEYERを支える伴奏にもグッと渋みを増し、作品として完成した姿がここにある。 (by Hetsuji) 2006/03/09(Thursday)up |
| EP | 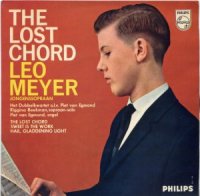 |
THE LOST CHORD LEO MEYER, JONGENSSOPRAAN (PHILIPS 411 705 NE) Kant 1: The lost chord Kant 2: Sweet is the work Hail, gladdening Light 変声前の少年の声、とだけでは形容できないこの時期に、MEYERのソプラノで、本格的な大人の合唱団をバックに録音したのは、”少年”の域を超え、声として成熟したLEOのソプラノ故に表現できる世界があると踏んだから、ではなかろうか・・・などと思ってしまう。決して女声ではない、ふわっと丸みのをおびたやわらかな広がりのあるソプラノの、温かいけれど生臭さのないギリギリの響き。これじゃ、メンドリ的な女声はいらないなあ。曲を締める「アーメン」もこの響き故に似合う。悲しみも苦しみも耐えることも祈ることも、この声故に、出来るような気がする。昔みたいに明るいソプラノではないが、バックコーラスもオルガンも含めて、この時期の演奏も捨てがたい。 (by Hetsuji) 2006/03/16(Thursday)up |