Art of the treble〜sounds’Library (JAPAN)
リトアニア少年合唱団"AZUOLIUKAS"BOYS' CHOIR
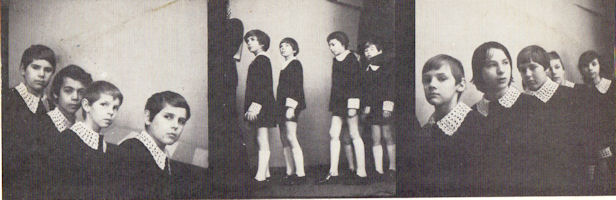
LP (LUIGI CHERUBINI REQUIEM (CTEPEO 33 C10-10661-62)カバー裏に掲載されている写真より
| CD | 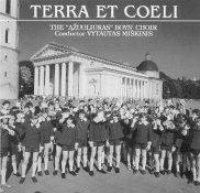 |
TERRA ET COELI
CD番号と録音年月日の記載なし 1.Visions of Zemaitija(A.Martinaitis/M.Martinaitis) 2.Nocturne(S.Taneyev/A.Fet) 3.A Romance (N.Rimsky-Korsakov/A.Tolstoy) 4.Le Temps Chemine-Hiver-Printemps-Ete-Automne (B.Andres/M.Laheurte) 5.The blue bird (CH.V.Stanford/M.Coleridge) 6.Here's that rainy day(J.van Heusen/J.Burke) 7.Exultate Deo (A.Scarlatti) 8.Notre Pere (M.Durufle) 9.Ave Maria(J.Busto) 10.Salve Regina(J.Kalcas) 11.Salve Regina(P.Eben) 12.Ave maris stella(T.Kverno) 13.Cantique(G.Faure/J.Racine) タイトルから見ると、雰囲気のあるロマンチックな感じの曲が並んだ。テノールもバスもとても音がきれいにそろっている。しかし、私には信じられない。本当に、このCDはboys and menだけで歌っているのだろうか? 合唱は綺麗だが、ソプラノが、大人の女声に聞こえてしまう。少年の気配が合唱に感じられないのだ。いきなりこの音を聴かされて、boys and menの編成を聞き当てる人が何人いるだろう? boys air choirの十八番のThe blue birdが収録されている。女性的なソプラノが原因か、ここでのB-Sは不透明なこもった声で、B-Sファン的耳には、boys air choir以上の演奏(少年だからこその演奏)にはならなかった。ここの合唱団は、少年的な透明感よりも、むしろもっと大人の、混声的な声をboys and menだけで作っていることが魅力なのかもしれない。(by Hetsuji)1999/11/ 21 up |
| LP 1959 |
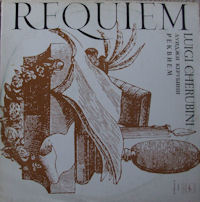 |
LUIGI CHERUBINI REQUIEM (CTEPEO 33 C10-10661-62) I CTOPOHA-19.22 1.Introitus 2.Graduale 3.Dies irae 4.Offertorium II CTOPOHA-20.55 4.Offertorium 5.Sanctus 6.Pie Jesu 7.Agnus Dei おそらく録音は1959年頃かも、です。音の輪郭が曖昧です。レコードでも古い時代の録音から出てくる音です。 ケルビーニにはレクイエムが2作(c-mollルイ16世用とd-moll自分のお葬式用)あります。このレコードカバーに記載された文字ですがHetsujiは曲名と数字しか判別できないので、この盤を譲って下さったお方のc-mollというメモによりルイ16世用の曲だと想定して鑑賞しました。(蛇足ですが、カバーEXで盤はNMという自己評価でして…2面でプツプツしていたのですが…信じてc-mollで良いですよね?) ケルビーニ氏、ルイ16世が断頭台の露と消えた姿を実際に見たらしいです。とすると、私が単に人生や命のはかなさを曲に感じているところですが、作曲家氏は、それ以上に相当に心が動いていたことでしょう。 合唱団の編制は少年声と男声です。この合唱団のボーイ・ソプラノについては他でも書いているところですが、この少年声が、微妙に危うい温度で決して女声ではない豊かさで高音を奏でるのです。再生される音の輪郭がシャープで無いのが残念なのかそれゆえに幽玄なのか・・・。音は、まさに、カバー裏の写真のイメージ。儀式が欲する高音なのだと思いました。男の子の声では無いです。そして絶対に女声で少女声でもありません。 ケルビーニ氏のレクイエムはソリストが活躍する曲ではありませんでした。作曲者がルイ16世を悼む思いと、録音した1959年当時の空気感までもが伝わって来るような演奏のレコードでした。 (by Hetsuji) 2018/03/23 Fri UP |
| CT | 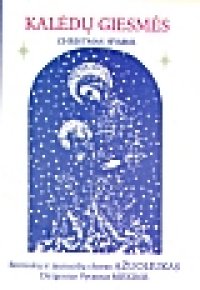 |
KALEDU GIESMES CHRISTMAS HYMNS (VSMK 011)
A 1982年録音。 1.TYLIAJA NAKTI / A Voice in the Night 2.ATSISKUBINO BETLIEJUN / Hurriedly to Bethlehem 3.GUL SIANDIENA / Today in the manger 4.PIEMENELIAMS / Herald spoke to the shepherds 5.SVEIKAS JEZAU / Hail, Jesus (Treble Soloが入る) 6.DIDIS DZIAUGMAS / Bountyful joy 7.PRELIUDAS VARGONAMS / Organ prelude このカセットを聴いている時点では、この合唱団の名前も読めないし、何処の国の合唱団かもわからない状態である。さすがは外国語文盲のHetsujiである。 雰囲気的には、旧ソビエトとかバルト3国系の響きに聞こえる。ひとりひとりの声が聞こえ、個々の声を編んで太い糸にしたかのような合唱だ。声は、きらきらと輝いているが、歌っている言葉の(語感の)関係で、煌びやかでありながらも、陰があり、音の印象は立体的。少しだけのTreble Soloの、ソリスト名は無いが、東欧系の少女の声に、きらきらの砂金をまぶしたような声で、魅力がある。もしかしたら、初めて聴く曲ばかりだが、どの曲にも、広々と広がっていくような空間を感じた。 B 1989年録音。 1.NAKTIES TYLOJE / In the Silence of the Night 2.LINKSMA STAI NAUJIENA / Joyful News 3.KALEDU GIESME / Christmas Hymn(Treble Duetが入る) 4.SIA NAKTI, SIA RAMIA / This peaceful Night 5.MES ATEJOM / We have come to adore(Treble Solo)(TenorSolo) 6.KALEDU GIESME / Christmas Hymn(Treble Soloが入る) 7.PLELIUDAI VARGONAMS gis-moll ir Es-dur / Organ preludes in G sharp minor and E flat major 合唱の残響が比較的長く、その残響に次の音が重なって、それが綺麗に聞こえる。少年合唱だけで歌われる3.KALEDU GIESME / Christmas Hymnは、声が切ないほど細く高い。一瞬のTreble Duetも安定して高い。この録音当時、どうも超ソプラノがいたようだ。その少年の声が、合唱の音の印象をシャープにしている。そして一人が、合唱の上空で歌うシーンが演出される。B-Sソリスト名の記載がないのは残念だ。いつものセリフではあるが、様々な点を考えて、カセットよりはCDでの購入を勧める。(by Hetsuji) 1999/11/ 21 up |