|
★ 《雑誌「風景」が創刊されたのは昭和35年の10月であった。舟橋聖一が主宰する「キアラの会」によって編集されたが、全64頁のうち24頁が広告で、残り40頁が本文という、これまでに例を見ぬ小型の文芸誌だった。》(大村彦次郎『文壇挽歌物語』より) |
坪内祐三の「雑読系」第48回(雑誌「論座」2003年6月号掲載)のタイトルは「このところ、『風景』のバックナンバーを拾い読みしている」で、以下の一節がその冒頭である。
《『風景』という雑誌があった。昭和35(1960)年10月に創刊され、昭和51(1976)年4月、通巻187号で廃刊となった。文芸誌である。といっても、いわゆる文芸誌とはちょっと違う。より正確に言えば文壇誌。》わたしが「風景」という雑誌のことを初めてきちんと認識したのは、去年8月に訪れた新宿歴史博物館でのこと、常設展示を練り歩いていた折に遭遇した田辺茂一コーナーがきっかけだった。田辺茂一が関わった雑誌のうち唯一長続きした「風景」は、舟橋聖一と田辺茂一のコンビで作られた最後の雑誌。その「風景」関係の展示を見て「あっ」と、戸板康二の三月書房発行のエッセイ集でも幾度か初出誌としてその名前が掲載されていたことがうっすらと記憶にあったから、ああ、この雑誌かと、エッセイ集の片隅にポツンとその名があった雑誌がクッキリと立体化した感じがして、とても嬉しかった。思えば、わたしが田辺茂一の名前を初めてきちんと知ったのも、戸板康二の『あの人この人』がきっかけだったから、「何を見ても戸板康二を思い出す」状態の身としては、「風景」という雑誌を知ったことで、モクモクと戸板康二に関する類推の輪がさらに広がっていくような心地になったのだった。
 後日、新宿歴史博物館で平成7年に、《田辺茂一と新宿文化の担い手たち―考現学、雑誌「行動」から「風景」まで》という展覧会が催されていたことを知った。おっ、8月に見た常設展示の田辺茂一コーナーは、この特別展のエッセンス的内容なのもしれぬと、さっそく図録を入手してみると、これが思っていた以上に面白くて、あらためて田辺茂一とその時代、あるいは田辺茂一とその東京などなど、田辺茂一にまつわるいろいろなことに胸を躍らせることとなった。さらに大収穫が、この図録のおかげで、雑誌「風景」に一気に興味津々になったこと。去年8月に常設展示でチラリと目にしたときは、単に「『風景』という雑誌があった」ということを心に刻んだに過ぎなかったのが、図録の数々の資料や記事などを見るにつけ、坪内祐三の言うところの「文壇誌」としての「風景」、その面白さを目の当たりにしてウキウキだった。
後日、新宿歴史博物館で平成7年に、《田辺茂一と新宿文化の担い手たち―考現学、雑誌「行動」から「風景」まで》という展覧会が催されていたことを知った。おっ、8月に見た常設展示の田辺茂一コーナーは、この特別展のエッセンス的内容なのもしれぬと、さっそく図録を入手してみると、これが思っていた以上に面白くて、あらためて田辺茂一とその時代、あるいは田辺茂一とその東京などなど、田辺茂一にまつわるいろいろなことに胸を躍らせることとなった。さらに大収穫が、この図録のおかげで、雑誌「風景」に一気に興味津々になったこと。去年8月に常設展示でチラリと目にしたときは、単に「『風景』という雑誌があった」ということを心に刻んだに過ぎなかったのが、図録の数々の資料や記事などを見るにつけ、坪内祐三の言うところの「文壇誌」としての「風景」、その面白さを目の当たりにしてウキウキだった。嬉しいことに図録には、「風景」全号の目次のダイジェストが載っている。こういうものを見るとすぐさま「戸板をさがせ!」状態になる身としては、ついまっさきに戸板康二の名前を探してしまうのだったが、いくつか見つけることが出来た戸板康二の名前、そのなかになんと! 戸板康二と大岡昇平の対談記事があるではないか! 見つけてびっくり。戸板康二と大岡昇平の対談を企画してしまう雑誌だなんて、それだけでもうただものではない気配だ。……などと、きわめて個人的な理由で、一気にわたしの中で大ブレイクした「風景」であった。
では、雑誌「風景」はいかにして誕生したのか、以下その軌跡を大雑把にたどってみることにしよう。
□
田辺茂一は紀伊國屋書店の創始者、新宿の地に本屋を開業したのは昭和2年、茂一22歳のときだった。薪炭問屋の息子として生れた田辺茂一は元来文学少年で、大正天皇崩御の折に父に連れられ訪れた日本橋丸善、その2階に並んだ洋書棚に心を奪われ、このとき「本屋になろう」と決心したのだそう。昭和2年には家業を継がせたいという父の反対を押し切って、炭問屋の敷地に自らの設計で書店を開業したのだから、茂一の行動は早かった。
新宿歴史博物館の《田辺茂一と新宿文化の担い手たち》展は、書店という空間そのものの魅惑を伝えるのみならず、開業と同時に創設された紀伊國屋ギャラリーのこと、田辺茂一が関わったいくつかの雑誌のこと、戦後には紀伊國屋ホールが開場することで演劇との関わりも生じていたりと、様々な文化の舞台装置としての紀伊國屋のことを鮮やかに伝えてくれている。
特筆すべきは、紀伊國屋の開店とほぼ同時に設立されたギャラリーにて、さっそく《しらべもの展覧会》なる催しが開かれているということ。今和次郎と吉田謙吉による「考現学」誕生の瞬間である。昭和2年の東京、震災復興のまっただなかで激しく変貌していく東京、モダン都市の胎動を象徴するかのような展覧会だ。
書店開業の3年後、昭和5年には新店舗が増築され、早くも書店の規模が拡大している。《田辺茂一と新宿文化の担い手たち》展の図録の巻頭インタヴュウで、八木義徳はこの時代の紀伊國屋書店のことをこう振り返っている。
紀伊國屋ってところにはモード、それも文壇的なモードが立ち込めていたものねえ。つまり、紀伊國屋の中に一歩入るというと、一種の精神的な充足感が店全体にこもっていてね、なんて言うのか、凡俗の世界から違った所に入っているという感じになったものですね。店を出ると、友達と行ったときは喫茶店行きますね、そうすると言葉がたくさん出てくるんですよ。いくらおしゃべりしてもしゃべり足りないような、精神的高揚を感じたのね。同じく昭和5年には銀座6丁目に支店を出店しており、やはり2階にはギャラリーを併設していた。戸板康二は、『あの人この人』の「田辺茂一の大鞄」の冒頭でこう書いている。
木造でね、トントントンて階段を上がっていくと、踊り場の所に古賀春江の油絵が掛かっているんだ、それを見てから2階に上がっていくんだけどもね、二科で一番新しいと言われた古賀春江のかなり大きい油絵が掛かっていました。
私の学生時代、銀座6丁目の松坂屋の側の新橋寄りのところに、紀伊國屋書店があった。2階には画廊があり、近藤や教文館とはまたちがった雰囲気を持っていたが、この店で買う特製の便箋は、上を余白にして、中川一政画伯のハサミだの、魚のカレイだのの絵がはいっているのがうれしくて、愛用したものである。田辺茂一は書店の経営のみならず、紀伊國屋に集う作家たちと文芸誌の創刊に相次いで参加し、単行本の刊行も手がけた。田辺と同窓だった舟橋聖一との共同作業は、雑誌「文芸都市」に始まり、特に昭和8年に創刊された「行動」は2年で廃刊になるものの、一時は文壇を席巻する勢いだったという。編集長は豊田三郎で、編集部には野口冨士男がおり、後に『徳田秋声伝』を執筆している野口が秋声の知遇を得るきっかけが「行動」の編集者としてだったというから、遺産は決して少なくない。のちの「風景」へつながるいろいろなこともこのあたりにすでに潜んでいる。
昭和20年5月の空襲で紀伊國屋は焼失したが、戦後、いち早く営業を再開し、昭和21年には株式会社に改組し、田辺茂一の個人商店から一気に巨大書店として業績を伸ばした。現在の新宿本店の建物は昭和39年に完成した新店舗で、この新築に際して4階にホール、5階に画廊が開設されて現在に至っている。昭和41年に紀伊國屋演劇賞が制定、制定当初から戸板康二が審査員のひとりに選ばれ、平成元年まで勤めた。前述『あの人この人』の「田辺茂一の大鞄」で描かれる交遊は、このときから始まったようだ。
戦前に挫折した恰好となった田辺茂一の文壇活動であるが、懲りることなく、昭和23年には同人誌「文芸時代」を刊行している。が、折からの商業雑誌隆盛と35人の同人に一貫性がなかったこともあって、これまた1年半で頓挫、しかし「文芸時代」がきっかけで親しく交際を持つことになった作家たちが「キアラの会」を結成することになった。この「キアラの会」が編集母体となって昭和35年に創刊されたのが「風景」である。
□
「キアラの会」は田辺茂一と同窓だった舟橋聖一を中心にしたグループで、当初のメンバーは舟橋・豊田三郎・野口冨士男・船山馨・北條誠・三島由紀夫・八木義徳の7名だった。当初は作家仲間の親睦会的な要素が強かったのだそうで、野口冨士男は結成当時のことを以下のように振り返っている。
「君から舟橋君にたのんでみてよ」「ある人」とは誰のことだろう? さてさて、「キアラの会」はその後メンバーを増やし、上記7名に加えて、有馬頼義・有吉佐和子・井上靖・遠藤周作・北杜夫・源氏鶏太・澤野久雄・芝木好子・林芙美子・日下令光・三浦朱門・水上勉・吉行淳之介の計20名にまで増えて、昭和34年になった。ふたたび、野口冨士男の文章を参照してみよう。
私は「文芸時代」の廃刊直後に、ある人から、せっかくあの雑誌で結ばれた交友がこのまま絶えてしまうのは残念だから、親睦会のようなものを作ってくれと言われて、豊田さんと目白の舟橋家を訪問した。それば、ずっと後に雑誌「風景」の編集母体となった「キアラの会」結成の端緒で、24年8月に舟橋邸へ参集したのは豊田、船山、八木、北條のほかに「文芸時代」とは無関係だった三島由紀夫の諸氏と舟橋さんと私という7名で、舟橋さんは、かんじんの発案者を人選からはずしてしまった。舟橋さんは、そういう好き嫌いの非常に激しい人だった。
34年の年末におこなわれた野間賞のパーティー会場で、私は田辺茂一さんから相談を持ちかけられた。それは、田辺さんが東京都内にある50店ほどの有力な書籍商だけで結成している「悠々会」の会長をしているが、小売店は定価販売を規制されていて、値引きなどのサービスができない。ついては「悠々会」の加盟店が買い取るというかたちで金を出し合いながら月刊誌を発行して、無料で得意客に進呈することにしたいが、編集のすべてを「キアラの会」にまかせて自分等はなにも口出しをしないから、それを会員にかってもらえないだろうかということであった。なんだか、人々にいろいろ頼まれがちな野口冨士男、その人となりが如実に伺えるような気がする。このあと、舟橋聖一を訪れた野口冨士男だったが、なんやかやともったいをつける舟橋、しまいには、野口は舟橋に啖呵をきる。「……どうして、そんな見栄をはるんです。あなたは、雑誌を持ちたくて仕方がないんじゃありませんか。この機会をのがしたら、今後絶対にキアラの会の雑誌は出ませんよ。これが最後のチャンスですから、もっと正直になってください。……」。
やがて、野口が「キアラの会」の諸氏にはたらきかけると、おおむね雑誌発行に賛成の方向になったが、最後のネックは大手書店主の広告料で発行をまかなうという田辺茂一案に PR 誌的なイメージがつきまとうことへの懸念だった。が、最終的には、「野口さんが編集をしてくださるのなら私は賛成です」という源氏鶏太の一言が決め手となって「風景」発行が決まったという。こうして、雑誌「風景」は生まれた。
大久保の高千穂尋常小学校以来の幼馴染みで、協力しあったり反目しあったりと屈折の多い間柄だった、田辺茂一と舟橋聖一。本業は異なるものの、破天荒な文壇人として強烈な個性を発揮していた二人の男、「風景」は彼らを支柱に誕生した雑誌だった。しかし、野口冨士男のたゆまぬ尽力がなければ誕生しなかった雑誌でもあった。このことを見逃してはならない。
さて、田辺茂一の条件は、総64ページで、うち広告が24ページ、2ページは目次なので実質38ページの文芸雑誌をつくってくれ、というものだった。迷いに迷ったあげく、野口はこの38ページに、評論・小説・随筆・時評・対談・書評と、文芸雑誌のあらゆる要素を詰め込むというスタイルに決めた。ここに至るまで、あまりに考えすぎて、野口は神経衰弱状態にまでなってしまったという。《田辺茂一と新宿文化の担い手たち》の図録には、このときの野口の熟慮が伺える、野口本人によるレイアウト試案の草稿が紹介されている。その著作でも野口冨士男の決して手加減せずに対象にうちこんでゆくサマが本全体の魅力になっているけれども、「風景」編集においても野口の緻密な仕事ぶりは素晴らしい。このときに野口が考案した雑誌のスタイルは、終刊まで変わることなく継承されていった。
と、野口冨士男が初代編集長となって、雑誌「風景」は創刊された。当時の編集委員は北條誠・日下令下・吉行淳之介の3人、舟橋聖一と田辺茂一が上の方で眺めているという感じのオブザーバーとなった。編集長および編集委員はその後「キアラの会」のメンバーのなかで交替したり戻ったりしつつ続いていった。創刊当初から「風景」の役割分担は経営側=田辺茂一、編集側=「キアラの会」の作家たち、というふうに、経営と編集とが明確に分離されており、このことが雑誌成功の理由となった。
□
《田辺茂一と新宿文化の担い手たち》の図録冒頭に、八木義徳のインタヴュウがあって、ここで「風景」刊行当時のことが懐かしそうに語られている。2回にわたって編集長を勤めた八木義徳は、「編集長というものは文壇を俯瞰していなければいけない」と野口冨士男から編集の技術をずいぶん教えられたという。八木が言うには、「風景」という雑誌の大きな特色は、「一般の読者にも、その時々の文壇の俯瞰図みたいなものが、執筆者の目次を見ると分かった」ということ、「文壇内部で、作家に愛された雑誌」だったということ。初代編集長の野口と二代目の有馬頼義が名編集長だったおかげでいい形が出来あがって、三代目以降の編集がスムーズにいったという。
野口冨士男と文化学院で一緒だった飯沢匡が、朝日新聞の文芸時評に「風景」を取り上げたことで、その後「風景」掲載の小説が文芸時評の対象になり、文壇への影響力が大きくなっていた。さらに、吉行淳之介がそれまで一本立てだった小説を二本立てにして、若い才能の発掘に成功して、中上健次や色川武大などが文壇に知られるようになった。八木義徳は「風景」を「文壇内部の作家とか評論家が、非常に気を付けて見る雑誌だった」というふうに振り返っている。「文壇誌」としての「風景」の様子が鮮やかにうかがえる。
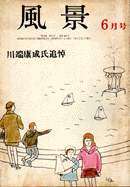 「風景」はかくも特殊な雑誌だった。田辺茂一が発案して、舟橋聖一を中心とする作家グループ「キアラの会」が編集を担当した。創刊の裏には野口冨士男の並々ならぬ努力があった。たった38ページの誌面には、評論・小説・随筆・時評・対談・書評と、文芸雑誌のあらゆる要素がコンパクトに詰まっていた。書店で無料で配布される雑誌だったから、経営面のことを考慮に入れることなく自由に編集できた。また、評判が上々でも間口を広げず、同じ規模で続けたことも成功の要因だった。「キアラの会」の作家たちが編集をすることで仲間意識が生れ、原稿依頼がスムーズにいったという面もあり、大家から若手まで、あらゆる層の文壇人の名前が目次に並んだ。特に、川端康成の原稿が載ったときは大反響で、川端の登場は「風景」の全盛時代を象徴していたという。舟橋聖一の時事・文壇エッセイ『文芸的グリンプス』が巻頭に毎号掲載された。『文芸的グリンプス』とともに「風景」の名物だったのが意外な人選の対談記事と、創刊号から終刊まですべて風間完が描いた表紙絵。パリの街かどの水彩画、その瀟洒な風景画が表紙だった。
「風景」はかくも特殊な雑誌だった。田辺茂一が発案して、舟橋聖一を中心とする作家グループ「キアラの会」が編集を担当した。創刊の裏には野口冨士男の並々ならぬ努力があった。たった38ページの誌面には、評論・小説・随筆・時評・対談・書評と、文芸雑誌のあらゆる要素がコンパクトに詰まっていた。書店で無料で配布される雑誌だったから、経営面のことを考慮に入れることなく自由に編集できた。また、評判が上々でも間口を広げず、同じ規模で続けたことも成功の要因だった。「キアラの会」の作家たちが編集をすることで仲間意識が生れ、原稿依頼がスムーズにいったという面もあり、大家から若手まで、あらゆる層の文壇人の名前が目次に並んだ。特に、川端康成の原稿が載ったときは大反響で、川端の登場は「風景」の全盛時代を象徴していたという。舟橋聖一の時事・文壇エッセイ『文芸的グリンプス』が巻頭に毎号掲載された。『文芸的グリンプス』とともに「風景」の名物だったのが意外な人選の対談記事と、創刊号から終刊まですべて風間完が描いた表紙絵。パリの街かどの水彩画、その瀟洒な風景画が表紙だった。舟橋聖一を中心とする作家グループ「キアラの会」が編集し、経営面では田辺茂一が面倒をみた雑誌「風景」は昭和35年に創刊され、昭和51年の舟橋聖一の死で幕を閉じた。やはり長く続くことでマンネリは免れず、あるとき、吉行淳之介は舟橋に「もう『風景』は役目を終えたので止めてはどうか」と提案したこともあったという。そのとき舟橋はひどくがっかりした様子だったとのことだが、結果的には「風景」は舟橋の死をもって終刊となり、見事な幕ぎれとなった。毎号「風景」の巻頭を飾った『文芸的グリンプス』は舟橋聖一の仕事の代表として残るだろうと、野口冨士男は言う。
参考文献:
★ 坪内祐三「このところ、『風景』のバックナンバーを拾い読みしている」(朝日新聞社『論座』2003年6月号「雑読系」)
★ 新宿歴史博物館特別展図録『田辺茂一と新宿文化の担い手たち―考現学、雑誌「行動」から「風景」まで―』新宿歴史博物館企画展示室、平成7年10月28日〜12月10日(新宿区立新宿歴史博物館編集、新宿区教育委員会発行)
★ 野口冨士男『作家の椅子』(1981年、作品社)「自伝抄『秋風三十年』」
□
ここから先は、「風景」誌上の戸板康二の仕事について。全187号のうち、戸板康二の登場は計14回。
|
演劇時評 |
と、まずジャンル別に並べてみたのは、初代編集長・野口冨士男の編集術を思い出してのこと。熟慮に熟慮を重ねて、野口が考えた誌面構成は、38ページの誌面に当時の文芸雑誌を構成する要素をコンパクトに取り入れるというものだった。文芸評論・文芸時評・小説・随筆・日記・座談会・劇評・詩・対談といった要素が詰まっている「風景」の誌面構成はその規模とともに、創刊号から最終の号まで一貫していた。最初から最後までほぼ同じスタイルを保っていた「風景」誌上の仕事を眺めることで、おのずと戸板康二の仕事全体を概観できるのだからおもしろい。演劇評論が本職で、その一方で小説も書く、たくさんの滋味あふれる随筆をサラリと優雅に書いて、座談の名手の洗練された社交が持ち味の都会人。そんな戸板康二のエッセンスを「風景」の仕事を見ることでコンパクトにたどれる仕掛け。全187号のうちの計14回だから登場回数は決して多くないけれども、戸板康二の往年の仕事ぶりを体感することができるという点において格好の資料なのだ。
□
「風景」に登場した戸板康二、その計14回の仕事を追いかけてみよう。
|
「ひいき」:昭和36年10月号《一周年記念号》(第2巻第10号) |
「風景」初登場は一周年記念号。野口冨士男編集長の仕事が2年目に突入したとき。新宿歴史博物館『田辺茂一と新宿文化の担い手たち』図録には、野口作成の「風景」原稿依頼用紙(越谷市立図書館野口冨士男文庫所蔵)が掲載されている。このお手紙が戸板康二の手元に届いたのはこのとき初めてだったのか何度目かだったのか、とにかくも戸板康二の「風景」初掲載は、随筆「ひいき」であった。
この文章は『ハンカチの鼠』に収録された。市川門之介のことなのだが、あるとき芝木好子にひいき役者を見破られたというくだりがある。このエピソードに垣間見えるのは、戸板康二の劇評を熱心に読んでいる芝木好子さんの姿。ごくごく最近芝木好子の熱心な読者となってしまった身としてはなおのこと嬉しくて、つい頬が緩む。
ところで、「風景」創刊からしばらく文芸時評を書いていたのが十返肇。戸板康二は昭和31年から東宝の砧撮影所顧問として同席することで、十返肇と急速に親しくなり、当時、十返から舟橋聖一に関するゴシップなどもいろいろ耳にしていたという。彼らの間で「風景」の話題も出たに違いない。
|
演劇時評 |
5月に久保田万太郎が急逝し、8月に十返肇が亡くなった昭和38年、4月号から6月号まで3回連続で演劇時評を担当している。編集長は有馬頼義に交替している。「風景」の演劇時評は刊行当初からほぼ毎月掲載されていて、戸板さんが登場するまでもっとも頻繁に書いているのが武智鉄二。何号かあとで、演劇時評のページはなくなっている。
4月号の「新かぶきの持ち役」では、2月の大劇場3軒で幸四郎・團十郎・松緑の三兄弟が新作を上演したことを書いている。前年に十一代目團十郎が誕生し、その前年に幸四郎が東宝に移籍という事件があった歌舞伎界、渡辺保著『歌右衛門伝説』のことをちょっと思い出してしまった。5月号の「書きにくい劇評」は《いつもの持ち役を俳優が演じて、この前には見られなかった何かが発見できるという喜びを求めている劇評家の悲願》についてと武智鉄二の活動について。6月号の「新劇の世界」はその年1月に分裂した文学座と福田恆存の「雲」のこと。《ぼくが「どっち側」でもなく、また絶対に「どっち側」でもありたくないという点を、ハッキリさせたかったからである。》と、ここでは矢野誠一著『戸板康二の歳月』のことをちょっと思い出してしまった。
この3回連続の演劇時評で、新作・旧作という歌舞伎の二つの側面、新劇というふうに、当時の劇壇を思いのほかヴィヴィッドにたどることができるのはおもしろい。
戸板康二の演劇時評が掲載された直後の、昭和38年9月号に十返肇の病床日記が掲載された。絶筆となったこの文章は、七回忌に刊行された野口冨士男編『十返肇著作集』上下(講談社、昭和44年)の最後を飾っているのだが、壮絶なまでに見事な文章である。戸板康二は『あの人この人』の「十返肇のアンテナ」に《十返さんは、最後の「日記」に、「酒をくらっては、ひとの悪口ばかり蛮声張り上げてしゃべっている私にどうしてこんなによくしてくれるのだろう」と親切な友人たちに対する深い謝意を述べ、「 "文壇" に棲む幸福を痛感せずにはいられない」と書いている。そういう澄んだ心境があったのを知って、私の心はなごんだ。しかし、同時に、もっと生きていて貰いたかったとしみじみ思う。》というふうに書いていた。「キアラの会」の同人というわけではないけれども、創刊からわずか3年で死んでしまった十返肇は「風景」の誌面にいかにも似つかわしい書き手だった。とにもかくにも生粋の「文壇人」だった。
| 「あの頃」:昭和39年8月号(第5巻第8号) |
「風景」を見ていると、小さな囲み記事でもその豪華な執筆陣が面白かったりする。同じタイトルで何人もの書き手によるコラムが数号にわたって掲載されるというシリーズがいくつかあって、これを眺めるのも「風景」のたのしみ。「あの頃」というコラムもそのひとつ。戸板さんの「あの頃」は昭和11年1月のこと。『ハンカチの鼠』所収の「あの雪の日」にもこの当時のことが印象的に綴られている。以下、全文抜き書き。
ぼくがはじめて原稿を活字にしてもらったのは、和木清三郎氏が編集していた時代の「三田文学」である。まだ水上瀧太郎氏が健在で、その番町の邸で若い作家たちを集めて会合が開かれていた頃である。丸の内のマーブルというのは、水上瀧太郎が重役をしていた明治生命館の地下にあったレストラン。昭和11年ごろの丸の内というと、戸板康二より一歳上の芝木好子さんも通勤していて、当時のことを『丸の内八号館』という小説に書いている。ふたりがすれ違ったこともあったかもしれない、煉瓦の丸の内。と、桑原甲子雄の写真集『東京昭和十一年』を開いて、いろいろ夢想してはうっとり。ところで、戸板康二が十返肇の姿を初めて見たのも「三田文学」の紅茶会、マーブルでのことだったという。和木清三郎の代になってから、広い範囲の寄稿家が集うようになったという「三田文学」、戸板康二に劇評を書かせたのも和木清三郎だったというわけで、ぜひともこの人物に注目したい。
もっとも、ぼくはその会には出なかった。しかし、別に隔月ぐらいに麻布の竜土軒や丸の内のマーブルで開催される紅茶会には、大先輩水木京太氏につれてゆかれた。メイン・テーブルには、岡本かの子、高田保というような来賓もいて賑やかな会だったが、昭和11年1月のマーブルの会は、いまだに忘れられない。
その頃学生狩りと称して喫茶店にいる学生を検挙する話が話題になり、今に大へんなことが起る、こんな会も開けなくなると誰かが発言して、みんな暗い顔をした。
その翌日2・26事件がおこり、日本は戦争に突入した。そして「三田文学」に小説を書いていたぼくと同期の塩川政一氏、田中孝雄も、末松太郎も、戦死してしまったのである。
昭和39年の「風景」には新庄嘉章と白川浩司による「三田文学早稲田文学の復刊」という対談がある。昭和39年、『久保田万太郎回想』(中央公論社)という本が万太郎一周忌にあわせて刊行されているが、もともとは「三田文学」復刊第一号の企画だったのだそう。
| 対談「劇評のあり方」秋山安三郎&戸板康二:昭和40年8月号(第6巻第8号) |
「風景」に毎号掲載された対談は、名物になるのが当然なくらい、ほかでは見られないような豪華な組み合わせ及びテーマというのが少なくない。山口瞳×木山捷平とか、木山捷平×深沢七郎などなど。坪内祐三も、《中でも一番読みごたえがあって資料価値が高いのは「対談」である(資料的価値というのは、『風景』に掲載されたそれらの「対談」はそれぞれの作家や文筆家の著書に収録されることなくそのままで放置されているものが多いからだ)。》と書く「風景」誌上の対談は名物であっただけに、編集長は毎回テーマや人選を考えるのに大変苦労したのだそう。戸板康二が「風景」の対談に初登場したのは創刊から5年後、このときの編集長は吉行淳之介だった。その1年後には、なんと大岡昇平との対談も実現しているのだから、吉行淳之介にはいくら感謝してもしたりないほどである。
劇評を書く日常のこと、劇評家にまつわるいろいろなことが語られていて、新聞劇評はどうあるべきか、現場取材と批評とはどう折り合うべきか、役者は劇評をよむか、劇評に反響はあるか、その年上半期の収穫、などなど、ここで語られる劇評にまつわることは相も変らぬ問題として、現在に残されているのではないだろうか。今日の劇評はいったいどうなっていて、今後どうなっていくのだろうと思いつつも、実は劇評というものをほとんど読んでいないので、ちょっと反省。
ちなみに、この対談と同じ号に、色川武大の小説『蒼』が掲載されている。吉行淳之介編集長がこの年の5月号から小説の掲載を2篇に増やし、1つは若手の作品にあてている。のちに、野口冨士男が挙げた「風景」の美点が「新人発掘」で、「吉行編集長の時代になってから小説が二本になって一つ別の角度が出てきたと思う」と語っている。いろいろな意味で、吉行淳之介は名編集長だった。
| 対談「毀誉褒貶」大岡昇平&戸板康二:昭和41年8月号(第7巻第8号) |
と、大岡昇平と戸板康二という夢の顔合わせが実現したのも吉行編集長のとき。これこそ「資料的価値」満点である。「風景」誌上の戸板康二を眺めることになったそもそものきっかけは、この対談を目当てに図書館へ行ったからだったし、「風景」に興味津々になったのもこの対談がきっかけだった。と、くどいようだが、いくら感謝してもしたりないのだ。
昭和38年5月に当時染五郎・万之助の兄弟共演で『赤と黒』が芸術座で上演され、大岡昇平が脚本を担当した。大岡初めてのシナリオ執筆だったのだが、いざ公演が始まってみると、劇評はほとんど惨憺たるもので、このことにプリプリと腹をたてる大岡昇平の姿は、たとえば『わが美的洗脳』(番町書房)所収の「『赤と黒』を脚色して」で読むことができて、「東京新聞」が初出のこの文章には次のような一節がある。
一週間ばかりすると、新聞の劇評が出はじめた。配役は豊富だから、大体演技中心になるだろうと思っていたら、劇評家が一斉に私の脚本を攻撃してきたのには驚いた。本紙の戸板康二氏が「大人の脚色」と頭をなぜてくれただけで、「ダイジェストにすぎない」「退屈」「気の抜けたような脚色」などなど、ろくなことは書いていない。友だちから「よくこなした」とおほめにあずかり、割引きしても七十点ぐらいあるだろうと思っていた矢先だけに痛かった――と書くと実はうそになる。……というわけで、唯一「頭をなぜてくれた」戸板康二を相手に、文壇の世界から足を踏み出して大岡昇平が、はじめて劇壇の世界を垣間見たことによって感じた劇評家の態度や劇界に対する違和感などをチャキチャキと語っている。冒頭で戸板さんが「きょうは劇評家を代表して、ゴールキーパーのつもりで来ました」と言っているとおり、戸板康二の方がわりかし聞き役にまわっている恰好だけれども、大岡昇平のチャキチャキとしたしゃべりも面白いし、戸板さんも大岡昇平ののしゃべりをうまく引き出すような、なかなか絶妙なもの。一方的に大岡昇平がまくし立てるのではなく、かといって戸板さんも追随するばかりでもなく、なかなかいい感じの対話を繰り広げている。戸板さんの座談の名手ぶりを味わった。
開口一番、大岡昇平は「戸板さん、ぼくはあなたが芝居だけではなく、先輩だと思っているんだけど、どうですか。ぼくは明治42年生れです」と言っているのだったが、戸板康二は大正4年生れだから、大岡昇平とは6歳違い。なんとなく戸板康二の方が年上だと思っていた大岡昇平、往年の戸板さんの貫禄(のようなもの)が伺えるような気がする。
昭和25年に岸田国士が「文学の立体化」を目指して結成したのが「雲の会」で、大岡昇平も戸板康二もその一員だった。「雲の会」のことは『回想の戦中戦後』の「わが交友記」に詳しい。
戦後の演劇人たちの集まりとして、「雲の会」というのがある。岸田国士氏が、文壇と劇壇の二つの分野を交流させようとして、提唱したものだ。定款があったり、役員がいたりする会ではなく、もっぱら親睦の集まりだが、文壇の人たちが、劇場を総見したりすることがあったらしい。……雲の会があったために、文壇の人たちが、戯曲を書く機縁が生まれたのはたしかである。福田、三島はすでに書いていたが、その後椎名麟三、石川淳、中村光夫、大岡昇平、石原慎太郎、武田泰淳といった作家の作品が、舞台にのる。これは岸田さんの播いた種子に咲いた花というべきであろう。岸田さんがなくなってから、いろいろな分野の人間が、たまに寄り合って芝居の話をしようとする気持ちがあり、椎野英之が幹事で、赤坂の阿比留とか、有楽町のレバンテとかで時折り会を持った。「横の会」と称した。この対談では、文士が戯曲をよく書いた、いわば文学と演劇とが密接に交わっていた大正時代のことがチラリと語られていたりもする。と、まあ、文学と演劇、という問題になるとどうもわたしには荷がかちすぎてしまうのだったが、ひとつだけ確かにいえることは、両者とも「言葉を扱っている」ということ。もちろん劇評だってそうだ。この対談も最後は「ことば」のことで結ばれていて、大岡昇平は、
戸板さんの小説でも、セリフがきれいなので、失礼ですが推理小説の段取りよりは、ぼくはそういうところを読んでたのしむのです。と言っていて、実はこの対談でもっとも嬉しかったのがこの発言。大岡昇平のこの発言を知ることができただけでも大収穫だった。これからも折に触れ戸板康二を読むとき、小説にかぎらず、そこにあらわれる言葉に敏感でありたいと思う。
| 「拍手」:昭和44年12月号(第10巻第12号) |
この年の1月、「風景」は創刊100号を迎えている。「拍手」は戸板さんお得意の劇場エッセイで、『夜ふけのカルタ』に収められている。最後の一文が《思い出したが、パーティーで、話が終る時、いつもいい呼吸で刃拍手を誘導したのが、今は亡き安藤鶴夫だった。あの手の音が、耳に残っている。》、戸板康二はこういうサラリとした人物描写が実にうまい。これだけでも、安藤鶴夫の姿がス―ッと見えてくるかのようだ。安藤鶴夫は同年9月に急逝している。戸板さん、書いていて突然思い出したのかもしれない。
| 対談「リトル・マガジンについて」戸板康二&巌谷大四:昭和46年2月号(第12巻第2号) |
あまカラ、学鐙、銀座百点、花椿などなど、日本の雑誌史をたどってみると、単なる PR 誌・同人誌の範疇を越えたある種の香気を醸し出す、リトルマガジンの系譜を見つけることができる。当の「風景」だって、そうだ。そういうリトルマガジンあれこれに心ときめかすことになったのは、戸板康二のエッセイ集の初出誌として知ったのがきっかけで、「あまカラ」「銀座百点」などもそうして興味津々になった雑誌だった。と、そんなわけで、大正四年生れ同士の「リトル・マガジン」についての対談は目が覚めるくらいに面白かった。「風景」誌上の戸板康二、一番の収穫といっても過言ではないくらい。わたしが戸板康二を通して一連のリトル・マガジンの系譜に興味津々になったのは決して偶然ではなくて、戸板康二が自身の文章が載る舞台装置として好んでいたのがリトル・マガジンだったのだということがよくわかった。数々のすばらしきリトル・マガジンそのものへはもちろんのこと、そういう小粒だけどキラリと眩しい雑誌にいかにも似つかわしい書き手及び文章の系譜、ということへも思いが及んだ。日頃の古本屋さん行きの際に出会いたいのはまさにそういう書き手であり、そういう文章集なのだ。……と、自分自身の好みのルーツを解き明かしてくれた対談だった。
開口一番、「やっぱり楽しみなのはまず『学鐙』です」と語る戸板さん。
「罪と罰」を訳した魯庵から、イプセン学者の水木京太、フランス演劇研究家の本庄さんという、これがエディターになっているという伝統ね。水木さんはぼくの慶応の先輩だから、よく日本橋なんかへ行くと、この椅子は魯庵がすわっていた椅子なんだよって、得意そうに、一ぺんすわってごらんよっていうもんだから、ぼくはすわったことがありますよ。って、このくだりにさっそく頬が緩む。福原麟太郎の『チャールズ・ラム伝』や谷崎精二の『明治の日本橋 潤一郎の手紙』を例に、戸板康二は「学鐙」について、「後に本になって、その本が非常にいい文献であり、資料であるような原稿が連載で載るということが、『学鐙』なんかにあるわけですね」と言う。そうそう、ある書物に魅了されて、初出の雑誌を見ると「ああ、この雑誌か」と、あらためて一目置くということよくあるけれども、わたしにとっても、これぞまさしく戸板康二を読むようになって覚えた愉しみ。
このあとも、リトル・マガジンの名前がいくつか登場、戸板康二のエッセイ集で見覚えのある雑誌名を見つけて、「あの雑誌はこれであったか」と納得したりも。「あまカラ」は原稿料のかわりに、鶴屋八幡のようかんと菊正宗の蔵出しのどちらかを選ぶ仕組みだったのだそうで、文字通り「あまカラ」、戸板さんはちゃっかり両方もらったらしい。
同時代の雑誌だけではなくて、過去の雑誌についてもいろいろ語られている。戦後、岸田国士が甲鳥書林から出したのが「玄想」、パンセを訳して「玄想」としたのだそう。紅葉の「十千万堂」、硯友社の「我楽多文庫」、鴎外の「めざまし草」、「ホトトギス」などなど、明治の同人雑誌へのことへも話題は及び、戸川秋骨の「文鳥」など、個人を中心とした雑誌もリトルマガジンのひとつの系列だと語られる。最後のほうで、話は「学鐙」および丸善へと戻り、戸板さんは《自由劇場の初日のことを谷崎さんだの島崎さんだの、いろんな人が書いていけど、丸善のことを書いている文献も、一ぺんちゃんと整理したら、たいへんなものがあるんじゃないかと思います。丸善の書だなを見てどう思ったといかいうことをいろんな人が断片的に書いていますよ。》と言っていて、 わたしも今までなんとなく「書物のなかの丸善」を見つけて喜んでいたりもしたから(たとえば、野上弥生子の『真知子』など)、わが意を得たりで嬉しかった。このことに限らず、本読みの歓び・書物の快楽がモクモクと胸に煮えたぎる対談だった。
戸板康二の発言から、いくつか抜き書き。まずは久保田万太郎の「春泥」について。
ぼくも後年多少関係したことがあるのですが、よく知っているのは「春泥」という雑誌ですよ。これは久保田万太郎とその周囲のいとう句会を作るメンバーが主体となってやったのです。明治製菓の宣伝部長だった内田水中亭がパトロンでね、表紙が鳥の子に小村雪岱さんの画を毎号新しく出して、口絵に木村荘八だの、山本鼎なんかの絵を入れて、毎号いい座談会を百尺とかああいうところでやってね、金に糸目をつけない雑誌だった。……昭和14年から、ぼくは内田水中亭のところで、それこそリトル・マガジンの「スヰート」という雑誌を編集していたことがありましてね、「スヰート」は明治製菓の宣伝誌だったから、ぼくが月給をもらうためのオフィシャルなものだけど、それと並行して、「春泥」の編集も堂々と手伝ったことがある。その「春泥」雪岱追悼号をいつかぜひともこの目で見てみたいッ。次は、池田弥三郎の実家、銀座の天ぷら屋「天金」のこと。
これはいま古本屋でたいへん高くなっているのは、小村雪岱さんがなくなったときに、「春泥」で小村雪岱追悼号というのを出した。昭和15年になくなって、16年に出しているのですが、もう世の中非常に悪くなっているときに、光村原色版印刷にある、とっておきのアートを無理に引っぱり出して、全アートの追悼号を出したのです。それに小村さんのいろんな絵を原色版で入れて、当時よく怒られなかったものだと思いますね。
余談になりますけど、その時分に森永で「スヰートランド」という雑誌があって、明治も両方ともスヰートという名前を使っていた。森永にそのころ十返肇がいたのです。だから十返とぼくはあの時分お互いに競争会社にいて、またお互い知らなかったわけだ。
いま思い出したんですけど、銀座の天金が「ひと」という雑誌を、昭和12、13年ごろに創刊して、5、6年出していましたかね。これは天金のお客にただで配っていたんだけど、天金の広告は裏表紙に出ているだけで、あとは当時の店主の弟の池田大伍さんが「元曲論」を書いたり、それから天金に所蔵されている、仮名垣魯文が翻案した「ハムレット」が載ったり、池田弥三郎がこれを編集して、ぼくなんかが末席を汚してね。これなんかリトル・マガジンのある種のタイプだと思う。これはぼくのところに全冊そろっていたけど、池田君のところで焼けて一冊もなくなったというので、向うにあげました。また、戸板康二は《エッセイということばが、日本ではかなり乱用、あるいは誤用されていう傾向があるけれども、エッセイの本質はリトル・マガジンに載るものだという気がするな。》とも言っている。エッセイの名手・戸板康二の舞台装置としていかにもふさわしいリトル・マガジン、その所以を解き明かしてくれる発言だった。
| 「チーズ」:昭和47年1月号(第13巻第1号) |
昭和47年は川端康成が自殺した年、「風景」6月号は一冊まるごと川端追悼号となっている。「風景」が特定の作家の追悼特集を組んだは川端と最終号の舟橋聖一追悼号の2回のみ。川端康成の原稿が「風景」に何回か連載されるようになったのは、師事していた北條誠が依頼したことがきっかけで、最初に載ったのは創刊まなしの第4号、昭和36年1月だった。川端は当時ほとんど原稿を書いていなかったこともあって、川端の原稿があるというだけで一気にその雑誌のステイタスが高まったという。このことが創刊まなしの「風景」を大いに元気づけた。「風景」が内容的に充実していたのは、すなわち雑誌の全盛期は川端康成の連載が続いていた頃だというふうに、当時の編集者は回想している。第4号から何度かの連載をした川端康成、その最後の原稿は昭和45年7月号である。
そういえば、昭和23年の「暮しの手帖」創刊号にも川端康成の短篇小説が載っており、「川端先生にも書いていただいています」の一言でその後の原稿依頼がスムーズにいったという。と、川端康成は、初期の「美しい暮しの手帖」の豪華な執筆陣実現に貢献していたわけだ。こぶりだけどキラリと光る素敵な雑誌を二度にわたって元気づけている川端康成、その隠れた功績に注目しよう。ほかにもそんな雑誌があるかもしれない。
この文章は『午後六時十五分』所収。フランスでの旅行のことをさらっと綴っている。戸板さんは前年4月、ナンシーの第八回世界演劇祭のため渡仏。ここで寺山修司とも顔を合わせ、のちパリで金子信雄と合流し、エルバ島へ足を運んでいる。自身の戯曲『風車宮―エルバ島のナポレオン』の取材旅行だった。ナンシーのことも同じく『午後六時十五分』で詳しく読むことができる。
| 対談「舞台と観客との間」戸板康二&日下令光:昭和47年3月号(第13巻第3号) |
昭和41年の大岡昇平との対談以来、6年ぶりの演劇に関する座談。この間の戸板康二の最大の変化は、批評の世界にいた戸板さんが劇作、演出などを手がけることで演劇制作の現場に立ち会うことになったということ。その場となった「新演劇人マールイ」の発足は昭和41年の9月だから、くだんの大岡昇平との対談のわりとすぐあとということになる。大岡昇平との座談ではもちろんそのことは話題になっていないが、戸板さんのなかで何か思うものはあったのだろうか。昭和41年は「悲劇喜劇」の復刊もあり、戸板康二は編集同人として参加している。「悲劇喜劇」には、戸板康二の芝居エッセイ、劇評だけでなく、自身が執筆した脚本も掲載されていくことになる。……とかなんとか、戸板康二の演劇制作の仕事に関しては、まだあまり深く追求していないのだけれども、この対談「舞台と観客との間」での戸板康二の数々の発言には、演劇制作の経験をしていることが色濃く反映しているように思った。そこが興味深かった。
| 「井筒」:昭和48年1月号(第14巻第1号) |
関東大震災と当時住んでいた芝の風土といった、自身の幼少時代がここまで色濃く反映されているのは、戸板康二の作品ではちょっとめずらしい。こういう「ちょっとめずらしい」作品、初出が「風景」だったというのもいかにもという感じがする。本読みの快楽の関東大震災の文学誌に選出されている一篇、小説の筋云々よりもまずはこの小説に登場する震災体験と大正末期の東京風景が非常に興味深い。
馬場房枝の家は、芝の増上寺の山門の前の、築地塀をめぐらした末寺の境内にあった。瀬戸物の表札に馬場と書いてあった。高島は、同じ山内だが、いま東京タワーのある丘の一角の金地院の境内にいた。そのころ祖母が三田四国町にいたので、祖母のところにゆくたびに、馬場の家の前を通った。わざと通ったといってもいい。短篇小説『井筒』が収録されている『孤独な女優』の巻末に山口瞳との対談がある。ここで戸板さんは《あの中の話は全部フィクションなんだけども、あの中に出てくる男が震災のときにどうだったってこと、あれは全部僕のことなんです。》と言っている。水道橋の能楽堂帰りに寄ったバーで、フランス文学者・高島が小学校二年生のときに同じクラスだった「好きな子」馬場房枝のことを回想するところが発端となり、震災で通っていた愛宕小学校が焼けてしまってそれっきりになったことが語られる。そのあと、では対面してみましょう、とちょっとした小話、コントが展開されるというわけだ。愛宕小学校が焼けて暁星に転校した戸板さんの体験がそのまま描かれて、好きな女の子というくだりもそのまま用いたそう。フランス文学者の「高島」という名前も、若かりし日に教師をしていた頃に劇評を書いた際に使った筆名「高島悠太郎」が由来なのかも。多分に自身を投影しているに違いない。
金地院の本堂の前を道に出ると、その道は飯倉のほうから上って来て、久松という華族の屋敷と料亭の紅葉館の前を通って、公園の中を縦貫する広い路に合流する。それを右に行き、弁天池の脇をぬけて、円山の下の梅林や、運動場の前を通るほうが、距離としては近いのに、わざわざ増上寺の塀のすぐ横についているせまい道を、電車通りまで出てから右折したのは、馬場房枝がそのへんに住んでいたからだ。
大正12年9月1日は、朝から蒸し暑い日だった。……まもなく、東京の下町に大火が発声した。芝公園の中には、火災はなかったが、夕方までに、焼け出された人たちが荷物をかかえて、家の近くの水道部と呼んでいた浄水場や、寺内の広場に避難して来た。暗くなると、火が急に大きく見え、時々ものの爆発する轟音が聞こえる。「あれは汐留の貨車が燃えてるんです」と向いの家のゲートルを巻いた小父さんが説明した。……
戸板康二の震災体験は『回想の戦中戦後』に詳しいが、ここに《この日の経験を、ぼくは「井筒」という短編に書いた》と書き添えている。また『回想の戦中戦後』には、《震災は、大きなショックで、それ以前の回想をプツンと断ち切ってあいまいなものにする、厚い壁のように、ぼくには感じられる。》という一文がある。突然思い出すのが、戸板さんと同年生れの山本夏彦が『「社交界」たいがい』所収の「かわいそうな戸板康二」なる文章で、《大正12年の震災を境にして歌舞伎は滅びたのである》と書いていたこと。なにはともあれ、震災後の東京に生きたという時代感覚は戸板康二を読み解く上で非常に重要であることは間違いない。
とかなんとか、戸板康二の小説を読むといつも、小説の内容そのものというよりも戸板康二の筆のあとさきの方に思いが行ってしまうのだった。このところ、丸の内から等々力行きの都バスにたまに乗ることがあるのだけれども、バスが愛宕山あたりを通過して芝公園に近づくとき、その緑が車窓に見えてくる瞬間が大好きで、ここを通るたんびに戸板康二の文章で読んだ東京風景を思い出している。
| 「父子相伝」:昭和49年10月号(第15巻第10号) |
これも『孤独な女優』所収。《大正のおわりに、芝園館の主任弁士として鳴らした石沢天声》とその子のスポーツアナウンサーのストーリー。冒頭に登場するのは、
新橋駅西口近くの食傷新道という路次にある花の家には、いろいろな常連がいる。古い映画人がよく集まる店で、松竹蒲田時代からメガフォンを持って名画を何本も作った監督だの、その監督によってスターの座についた、かつてのスポーツ俳優だの、同じ時代のシナリオライターだのが、しじゅう顔を見せている。という新橋の小さな酒場、このモデルは、戸板康二も常連だった「トントン」かしらどこかしら、と想像がふくらんでたのしい。新橋と戸板康二というと、奥野信太郎編『東京味覚地図』(河出書房新社、昭和33年)で戸板さんが担当しているのが新橋なので、ついページを繰ってあれこれ想像してしまう。と、戸板康二の小説に垣間見える、戸板康二の見たかつての東京を、小説の文章とともに追体験することが、わたしにとっての戸板小説における一番の愉しみなのだ。
ところで、このころの「風景」は持ちまわりで再び野口冨士男が編集長を勤めている。「父子相伝」掲載号の野口冨士男による編集後記は、
この2年ばかりのうちに、東京のいろんな場所を歩いた。一つは永井荷風の作品の背景をさぐる目的だが、必要があるから行くだけでは味気ないので、それ以外の所も出たとこ勝負のように歩く。六義園、深大寺、小石川植物園、後楽園庭園、新宿御苑、多摩湖といった、きわめてありふれた場所ばかりだ。入谷の朝顔市、冨岡八幡の祭礼もみた。というもの。ここでいう「この2年ばかりのうち」というのは、野口冨士男が名著『わが荷風』を連載していたころにあたることにハタと気がついて胸がジンとなった。
医者から散歩をすすめられてもアテのない散歩などバカらしくてできないから、地図で目的地をきめて出かける。早起きは苦が手なので、午後から家を出ても行ける所ばかりになるが、多摩湖など、着いたらたちまち暗くなって心細かった。
こんな行動も足がダメになる前に歩いておこうという心理の現われかもしれないと新宿の喫茶店で八木義徳に話したら、彼もこのごろはせっせと郷里の北海道へ行ってあちこち見ているが、深層心理はあんたと同じかもしれないといった。
| 「その一瞬」:昭和50年5月号(第16巻第5号) |
「風景」は昭和51年4月号をもって終刊となったが、戸板康二歳後の登場はその1年前の昭和50年。初登場は創刊のちょうど1年後だったから、「風景」の歴史をほぼ網羅しているといえる。戸板康二最後の「風景」執筆は短いコラム、前述の「あの頃」とおんなじように、何号かにわたって何人もの書き手が同じタイトルでコラムを書いているシリーズで、戸板康二2度目の登場となるコラムのタイトルは「その一瞬」、伊馬春部の随筆「今年の三月十日」と同じページに掲載されている。さきほどの『井筒』と同じように、戸板康二少年時代の東京風景が垣間見られる。全文抜書き。
小学のころ、祖父が伊皿子に住んでいて、その家のそばに、いま考えると嘘のように広い原っぱがあった。この年編集長は八木義徳に交替していて、「風景」が終刊となった翌年は吉行淳之介が編集長だった。新年早々の1月13日に舟橋聖一が急逝、吉行淳之介と井上靖と野口冨士男の3人で「風景」の廃刊を決めたのはその通夜の席でのことだったという。その数日後、野口冨士男は『わが荷風』が読売文学賞を受賞したという知らせを聞くこととなった。
ぼくが木に登っていると、六つ下の弟が崖っぷちに立っている。「危いからやめろ」と叫ぶと、わざとすべり落ちる真似をする。
止めようと思って、木から降りることにした。降りきるまでには自分の足もとに気を取られているので、そっちを見なかったが、地面に立って崖のほうに目をやると、弟の姿が見えない。こんなに肝をつぶした経験は、あとにも先にもない。ほんとうに、落ちてしまったのである。
幸運にも、崖の下が石置き場の屋根だったので、軽傷ですんだが、石置き場に屋根がなかったと思うと、今でもゾッとする。
伊皿子坂を下り、泉岳寺のそばに出て、迎えに行った。落ちるのは簡単だが、上にあがるのは大変だった。先日、弟とその崖の下を車で通ってその一瞬の追想をした。
← Top