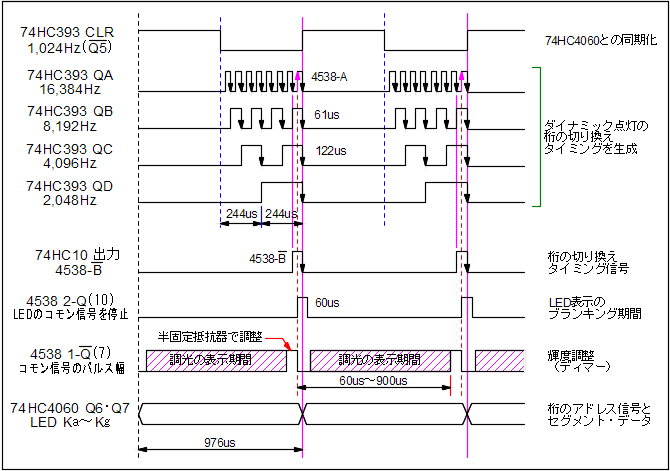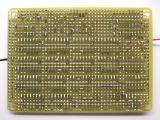1.電源回路
・5VのACアダプターを使用します。
(電流容量は300mA〜2A程度の物で、安定化された物に限ります)
・LSタイプのTTL-ICを使用しているので、動作電圧は4.75V〜5.25Vです。
2.基準信号 発振回路
・時刻カウントの基準となる正確な1Hz信号を作ります。
・74HC4060は、水晶の発振回路と14段の分周回路(最大1/16384)を一つにまとめたICです。
・水晶(Xtal)は、時計用の32.768KHzを使用して、分周器の最終段からは2Hzの信号が出ます。
・この2Hzの信号を、さらに74HC393(余りのIC)で1/2分周して1Hzを得ています。
・この水晶発振回路は、電源ノイズや基板のパターンにより大きく影響を受けますから、
各パーツはICの近くにまとめて配置します。
・周波数カウンターがあれば、TP端子の周波数が32.768KHzに近づくようにトリマー・コンデンサー
を調整して下さい。
・水晶の個体差や電源電圧により、発振が不安定になる場合がありますので、TP端子が
32.768KHzから大きくずれる場合は、100PFのコンデンサーを取り付けてみて下さい。
・周波数カウンターが無い場合は、1日〜1週間の誤差を見ながら、トリマー・コンデンサーを回して
微調整して下さい。
3.秒カウンター回路
・74HC390は、10進(2進+5進)の非同期BCDカウンターが2回路入っています。
・74HC393は、16進の非同期カウンターが2回路入っています。
(いずれもクロックの立ち下がりでカウントアップします)
・1つめの74HC390で0〜9秒を計数し、2つめの74HC393は0〜5をカウントした後、出力が6に
なった瞬間にこのカウンターをクリア(リセット)するので、2つ合わせて00秒〜59秒を計数します。
・最上位の出力S12(QC)は、次の「分カウンター」の計数信号(1分)になります。
・時刻の設定時には、[Sec Reset & Hold]スイッチをONにすると、秒カウンターが強制的に[00]に
固定されますので、標準時刻が00秒になった時点でスイッチを解除します。
4.分カウンター回路
・秒カウンター回路と同じ74HC390と74HC393の構成で、00分〜59分をカウントします。
・最上位の出力M12(QC)は、次の「時カウンター」の計数信号(1時間)になります。
5.時カウンター回路
・前作のSP-521パネルと同じく、12時間制の構成としました。
(24時間制の方が回路は簡単になりますが、市販の時計は12時間制が多いと思います)
・74HC160は同期式の10進カウンター、74HC107はJKタイプのフリップフロップです。
・12時間制の場合、AM12:59の次にAM1:00になるため、カウンターをクリア(リセット)する際に
[1]にセットする必要があります。
・この動作のために「時カウンター」が[12]になった次の時間で、74HC160に[1]をロードさせます。
・時の上位桁は[0]と[1]しか必要が無いので、74HC160が9になった時に出力されるキャリー
[CRY]信号で74HC107を[1]にセットし、一連の動作で1時〜12時を計数します。
・AMとPMの表示は、AM11:59の次がPM12:00になるため、「時カウンター」が11になった次の
時間で、AM/PM用の74HC107を反転させます。
・通電が開始されたときには、抵抗器・ダイオード・コンデンサーによる「パワーオン・リセット回路」
により、「分カウンター」と「時カウンター」が0にリセットされます。
(通電の最初のみ、時刻はAM0:00から始まります)
6.時刻設定スイッチ
・2つの押しボタンスイッチは、抵抗器とコンデンサーの積分回路と74HC14によるシュミット
トリガーで、スイッチのチャタリングを除去します。
・74HC153は、4入力1出力(×2回路)のセレクターです。
・[Time Set (L)]ボタンを押すと、「分カウンター」に接続されている1分単位のクロックが2Hzの
信号に切り替わり、「分カウンター」が0.5秒単位で進みます。
・[Time Set (H)]ボタンを押すと、「分カウンター」のクロックが8Hzの信号に切り替わり、
「分カウンター」が0.125秒の高速で進みます。
・「時カウンター」は「分カウンター」を高速で進めることにより、桁上げされて設定できます。
・設定時刻が表示と大きく離れている場合は、[Time Set (L)]ボタンと[Time Set (H)]ボタンを
同時に押すことにより、クロックが32Hzの信号に切り替わり、「分カウンター」をさらに高速で
進めることができます。
7.ダイナミック点灯と秒表示回路
・LEDの桁数が4桁なので、秒の表示はスイッチにより切り換えます。
・74HC151は、8入力1出力のセレクターです。
・下位4つの入力(D0〜D3)で、[時:分]表示中の4桁ダイナミック点灯に使用するBCDデータを、
桁ごとに選択します。
・上位4つの入力(D4〜D7)で、[分:秒]表示中の4桁ダイナミック点灯に使用するBCDデータを、
桁ごとに選択します。
・ダイナミック点灯は、1,024Hz(約976μS)間隔で桁ごとの表示を切り換えています。
・桁の選択に用いるアドレス信号は、基準信号 発振回路のQ6とQ7を流用します。
・ダイナミック点灯では、桁アドレス毎にセグメント・データを切り換えますが、この切り換え時に
信号の微少な遅れから、隣接する桁に漏れ表示(ゴースト)が出てしまいます。
・これを無くすために、桁アドレスとセグメント・データを切り換える際には、表示を消すブランキング
信号が必要となります。
・このブランキング信号を作製するためにはアドレス信号Q6・Q7より高い周波数のQ1〜Q3が
必要ですが、74HC4060にはこの端子がないので、別途74HC393を74HC4060と同期化させて
表示の切り換えタイミング信号を作製しています。 (下のタイミング図を参照)
・この信号から4538単安定マルチバイブレータで、桁切り換え時の前後30μS(合計60μS)の
表示を禁止するブランキング信号を作製します。
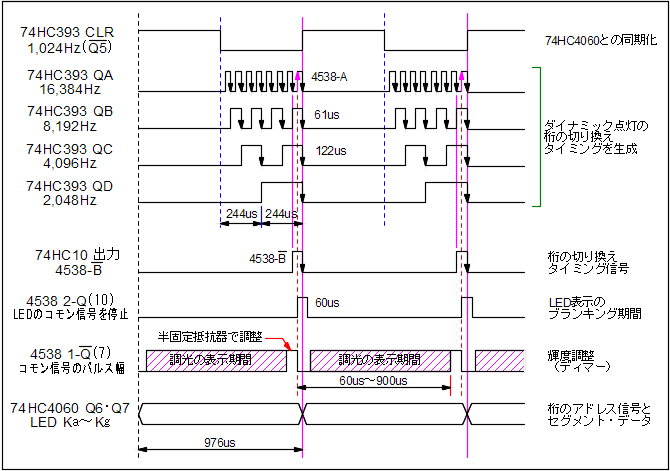
8.輝度調整(ディマー)回路
・室内の明るさに応じてLEDの輝度を変えるため、明るさの検知にCDSを使用します。
・ブランキング信号と同じく表示の切り換えタイミング信号から、4538単安定マルチバイブレータの
遅延時間をCDSの抵抗値で可変して、表示期間のパルス幅を変化させてLEDの輝度を変えて
います。
・CDSに並列接続してある半固定抵抗器で、暗さに対する感度調整が行えます。
・自動輝度調整(ディマー)が不要な場合は、CDSのみを取り外すことで、半固定抵抗器が
輝度設定に使用できるようになります。
9.LEDのコモン・ドライバー回路
・桁アドレス信号からLEDの桁ごとにC1〜C4の4つのコモンを選択するために、3 to 8デコーダ
74HC238を使用します。
・ LEDのコモン端子には100mA近い電流が流れ、C-MOSやTTL-ICではこの電流が駆動できない
ので、ソース電流ドラーバーTD62783APを使用しています。
・トランジスタを4個並べても良いのですが、実装面積や配線の手間が簡便となる専用ICを使用
しました。
10.LEDのセグメント・ドライバー回路
・この回路のみ74LSタイプTTLを使用していますが、理由は74HCシリーズに相当するICが無い
ことと、4000シリーズC-MOSにあるデコーダー4511の[6]と[9]の文字が気に入らない事です。
・AM/PM表示を[時]の上位桁の左側に加えるため、出力がオープンコレクタになっている
74LS247を選択しました。
・同じくオープンコレクタの74LS38で、AM/PM信号を加えています。
・1時〜9時の間に、[時]の上位桁(左側)の[0]表示を消したいので、10時桁のみゼロサプレスが
働くようになっています。
・LEDの電流制限抵抗器は、使用するLEDのVf電圧とLEDに流す電流量によって調整して下さい。
|