本書は、ideaは、政治的帰結の説明に欠かせない要因である、と主張するものである。
筆者らは、学説史のなかで、どのように本書を位置づけているのだろうか。 本書は、合理主義的アプローチと、reflectivistに対する挑戦なのだという。合理主義的アプローチは、ideaを軽視し、アクターの所与とされた外生的な利益・選好から政治的帰結を説明していこうとする。このアプローチを出発点とした研究に、リアリズム・リベラルインスティチューショナリズムといった今日の国際政治学において主流をなすシステミック・アプローチも含まれる。筆者らは、利益とパワーは分析の出発点としては重要だが、これだけでは不十分であると主張する。これにideaを含めて分析を行うと、説明できない例外とされてきた現象も説明可能となり、説明能力が増すからである。 一方のreflectivistは、逆に、ideaをきわめて重視する。ここでは、利益・アイデンティティの形成過程を間主観性等に着目することで説明しようとする。しかし、研究方法に実証性が乏しいことを、本書の筆者らは批判する。
本書は、政治的帰結をideaがどのように左右するのかを実証的に示すことで、合理主義的アプローチにideaという要因を加えて、より豊かなものにし、同時に、reflectivistに代わるideaに関する適切な分析方法を提示しようという試みなのである。
分析を明確化するために、ideaが三つの類型、1.世界観(world view)、2.規範的・原理的信念(principled beliefs)、3.因果的信念(causal beliefs)に分けて考えられている。
まず、1.世界観は、「行為の可能性の宇宙を規定するidea」とされる。これは、文化のシンボリズムに埋め込まれており、市場の合理性・主権・プライヴァシー等の、基本的概念を了解可能にするものである。従って、ideaの類型のなかで、最も広範に、人間の行為に影響を及ぼす。
2.規範的原理的信念とは、「よい」と「わるい」、「公正」と「不公正」といったように行為を分節する、規範・倫理上の基準を提供するideaである。また、世界観を、特定の政策に関する結論および人間の行為へ、媒介・転換する機能も果たしている。
3.因果的信念は、エリートとして認められた人々の共有されたコンセンサスから権威を与えられた因果関係についての信念である。また、アクターが抱いている何らかの目標を達成するための戦略も示唆する。また、この種の技術的な知識の性格上、他の信念の類型に比べ、頻繁かつ急速に変化するという特徴が見られる。
筆者らは、分析上、信念をこのように分類したわけだが、実際には、これらの類型は混在していることを認めている。
では、どのように、そして、いかなる条件下で、ideaは政策へ影響を及ぼしうるのか。筆者らは、その三つの経路を提示する。
第一は、アクターの「ロードマップ」としての機能をideaが果たす場合である。行為の帰結がわからない不確実な状況を想定しよう。ここでは、行為の帰結についての「期待」に基づいて、行為の選択を行わざるをえない。この行為の帰結の期待を決定するのが、他ならぬideaであるということになる。
因果的信念であれ、規範的原理的信念であれ、何らかのideaが一度信じられたなら、それに沿った選好・目標達成の戦略に選択が限定化され、他にあり得た現実解釈のあり方は、排除されることになる。
なお、この分析では、どのideaが利用可能であり、説得力をもつに至るのかについては、問わない。
第二は、「focal point、連結的接着剤」としての機能をideaが果たす場合である。戦略的相互作用をゲーム論でとらえた場合に、均衡解が一つでない状況があり得る。この場合、どの均衡解に落ちつくのかは、ideaから決まってくると言える。このように、協力的な解決方法を定めるfocal pointとして、あるいは、集団の凝集性を促す連合のための接着剤としての機能を、ideaは果たすのである。
第三は、「制度化」である。ideaが一度制度化されると、将来にわたって、そのideaが政策を制約する。あるideaが選択され、制度化されたのは、利益、パワーといった、その時点での様々な条件によって説明されよう。しかし、その後、決定づけた条件が将来変化したとしても、過去のideaは制度化されることによって、影響を及ぼし続けるのである。この分析では、そもそもにして、あるideaが、なぜ採用されたかについての説明は行われない。
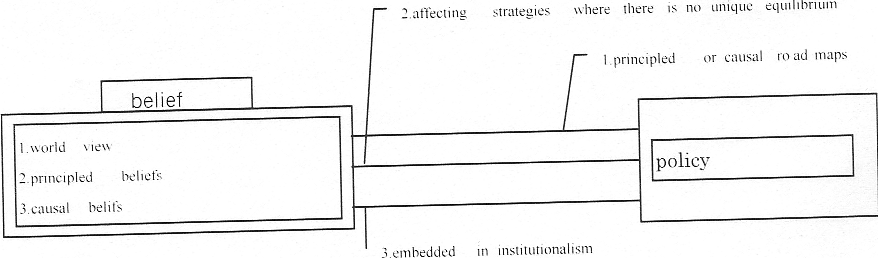
なお、ideaの変化は、即座に政策変更をもたらすのではなく、コンセンサスが壊れ、パワーの関係が流動化し、利益と戦略が不明確になった不安定期になって初めて、あらたなideaが求められ、安定期には相手にされなかったideaが政策にインパクトをもつようになる、と、されている。
不確実な状況のなかで、因果的信念というideaがロードマップとしての役割を果たすことを、Ikenberyは、第二次大戦後の国際経済体制に関する英米間の合意形成の事例を取り上げて、示している。
英米間の合意は、国益とパワーからだけでは十分に説明できない。英米両国の経済専門家からなる、一種のepistemic communityが、ケインズ主義というideaを示し、このideaによって、利害の構造が代わり、交渉のあり方まで変わって、合意に至ったからである。
当初、金融面のイシューと貿易面のイシューは不可分であり、国家の政策の国際経済に対する自律性の高さのみが交渉のイシューとなっていた。アメリカは、国家の自律性の低い自由な貿易体制、新古典派的な経済政策を志向し、イギリスは、地域ブロック的な閉鎖的な貿易体制とケインズ主義的な経済政策を志向していた。従って、この段階では、両国間で妥協は不可能だった。
しかし、英米の経済専門家グループが抱いていたideaによって、金融イシューと貿易イシューが相互に独立したイシューとして認識されるようになる。このことから、英米間の妥協によってお互いの利益を高めうる可能性が発生した。
この可能性の成立によって、英米の専門家集団の新しいトランズガヴァメンタルな連合が形成され、両国で主流を勝ち得た。ここから、両国の合意が形成されたのである。また、アメリカは、トランズガヴァメンタルな専門家集団の提示したこのideaによって、新秩序に正統性を与えることに、自らのパワーによって、新秩序を他国に強制させるというコストの高い選択を回避することも可能になったのである。
このように、ideaは英米間の合意に強力な役割を演じたのだったが、それが可能になったのは、そのときの状況によるところが多い。この点で、ideaの役割はもろかったともいえる。このとき経済専門家集団のideaがインパクトをもちえたことは、30年代の経済危機によって既存の経済理論への信頼が崩れていた点、戦争があった点、政府の社会的経済的役割が積極的なものへと変化していっていた点等の、特殊な状況なしには、考えられないのである。
Halpernは、中国とユーゴがソ連スターリン型経済体制を採用した事例から、信念がロードマップとしての役割を果たした点を考慮にいれない、パワーと利益のみによる政策アウトカムの説明が不十分であることを論証する。東欧諸国についてはソ連の軍事侵攻のおそれというパワーの圧力からスターリン型経済体制を採用した点を説明可能であろう。しかし、中国とユーゴの場合、ソ連軍の介入もなく、さらに、二国はソ連と対立していた状況から考えると、パワー・利益のみによる説明には無理がある。この二国がソ連型経済体制を選択したのは、スターリンのideaが、直面していた状況への対応策ーいかに工業化をおこなうか、イデオロギー的に正しい方法は何かーを提示したからである。なお、一度、ideaが制度化されると、将来このideaが不適切であると指導者が認識しても、政策が制約され、この体制が維持されてしまう点も示唆される。
一般的には、ウェストファリア条約によって、ヨーロッパの政治秩序は中世的な世界から、主権国家体系へ転換したといわれる。しかし、これは神話にすぎない。なぜなら、ウェストファリア条約以前も以降も主権国家の組織原理は存在し、他方、それに競合する他の政治的組織原理も存在したからである。
では、何故、主権国家というideaは、「ウェストファリア」の神話化に象徴されるように、影響力を持つに至ったのか。
まず、ヨーロッパにおいては様々な組織原理をもった政治体が存在し、多様な政治思想もまた存在していた。そして、それぞれの政治体は自らの行為・政策を正当化するために、適合的な政治思想を利用した。国家という政治体は、他の政治体に対抗するために、主権というideaを活用した。ここで注意すべき点は、国家が主権というideaに先だって存在し、そのideaを利用したにすぎない点である。そして、ideaのためではなく、物質的条件によって、国家は他の政治体に優位な地位に昇っていった。この国家の優位が合って初めて、それを正当化する主権というideaが影響力を持つに至ったのである。
筆者は、主権というideaが制度に埋め込まれたために、主権国家システムというideaのインパクトが感じられるようになり、それがさらに、他の制度に比して、国家という制度を強化したと論ずる。
しかし、私には、逆に、このケーススタディは、ideaは重要ではなく、物質的諸力こそが重要であることを示しているように思えてならない。
他の地域よりも、ヨーロッパでは多様な政治思想が存在し、これが政治体の広範な振る舞いを正当化して馴致できたために、状況の変化によるショックを小さくできたと論じている点は、興味深い。
本書は、政策決定の要因としてideaが欠かせないことを示そうとする試みである。しかし、執筆チームも認めていることだが、なぜ特定のideaが選択され、制度化されるのか、そして、なぜ、特定のideaを組み込んだ制度が存続・消滅するのか、という点は、中心的な問題とはされていない。この問題は、パワー・利益といった物質的条件からのみ答えられるのか、それとも、やはり、ideaの要因をいれなければ答えられないのだろうか。
パワー・利益からでなければ、特定のideaの選択や、制度の生成崩壊を説明できないのなら、ideaは、パワー・利益と政策をつなぐ消去可能な媒介変数にすぎない。たとえば、パワーのある国の政策にideaが正統性を付与し他国が自主的に従うようになるといった説明が本書に登場するが、これでは、ideaはパワーの一要素と考えてもかまわないことになり、ideaは本質的な、決定的な要因とは言えない。
Ideaの選択・制度化、特定のideaを組み込んだ制度の存続・消滅を、パワー・利益のみからでは説明できないが、ideaを含めると初めて説明可能になることを示して初めて、ideaは本質的に重要な要因であると判断できよう。
このようなわけで、説明要因としてのideaの重要性を確定するためには、Ideaの選択・制度化、特定のideaを組み込んだ制度の存続・消滅の要因の検討―とくに、これらのどれだけがパワー・利益の帰結なのかの検討―が不可欠であると考える。
不確実な状況においては、行為の帰結がわからないために、アクターの選好は期待にすぎないのであり、ideaとして相対化してとらえなければならないことが示唆されたが、この点は意義ある指摘だといえよう。