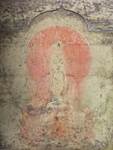|
伊豆横道33観音霊場巡り 第1回 慈眼寺・滝見観音・長光寺・円成寺・正法院 2014/06/16 |
|||||
|
写真のスライドショー&動画 https://www.youtube.com/watch?v=ZuPUugqvSGQ&feature=player_detailpage |
|||||
|
|
アプローチ(バス・徒歩) 松崎バスターミナルから宮が原行きのバスに乗り堀坂で下車 宮が原行のバスは午前中1本のみ 慈眼寺〜滝見観音〜長光寺〜浜橋(まで徒歩合計4km) 浜橋からバスに乗り、バス停円成寺で降車 円成寺〜正法院(徒歩2.2km) 帰りは月の浦上からバスで松崎・下田へ 途中、沢田公園に寄る ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ガイドブックなどを見ると、1番から33番まで何を基準にして順番をつけたのか疑問に思うほど、巡礼の順番が入り組んでおり、必ずしも番号が付けられた通りの巡礼ではありません。
これはひとつには、当初、順番通り巡礼出来たのが、例えば災害などで消失したり、別の理由で廃寺となって後に場所を移して再興したという事情もあったのだろうと想像されます。 いずれにしても、とにかく、地域的に各ブロック別に分け、その中で巡礼の順番を付けた結果、今回は頭書に挙げた通りの順番になりました。
それから、札所巡りの倣いにしたがって、各寺から御朱印を頂くのを基本といたしましたが、無住のお寺が結構あって、別のお寺や、個人のお宅を探す必要もありました。
第6番と第1番が無住職のため長福寺(この寺は88か所札所)にて御朱印拝受。第5番は管理している個人宅が留守のため御朱印無し。第8番と第9番ではそれぞれ住職から拝受。以上のようにすべてがすんなりとはいきませんでした。
さて、札所巡りは単に御朱印を集めて回ることが、巷間によくある景品交換の動機であってはなりません。今回の伊豆横道33か所をすべて踏破したお駄賃として、今生のご利益を願うということでは余りにも惨めです。
明日から、今日一日のすべてを記録してゆくことによって、あらためて今回の総括をしてみようと思います。今はただ、ある予感めいてものがあるだけで、本日の行動を逐一書くことによって、おぼろげに得たものをはっきりとしたものにしようということです 第6番 慈眼寺 臨済宗 如意輪観世音菩薩 MAP 松崎を過ぎて程ない浜橋から、仁科川上流に向ってバスに乗ること数分。バス停堀坂にて下車。畑の草取りをしていたオバサンに慈眼寺の場所を訊ねると、この集落に落ち込む小沢に沿って上がって行けば直ぐに見つかるという。それから、慈眼寺は「じげんじ」と呼ぶそうだ。
慈眼寺の標識は一つもないが、多分これが第6番札所だろうと、オバサンに教えられた通り、庭の右手にある小屋の扉を開けて本堂のカギを探した。柱に取り付けた小箱を覗くと、やはりこの中にカギがあった。
はからずも本堂に入ることが出来たのはオバサンのお蔭である。しかし、立派な堂内には大師さまと思しき坐像と左右の掛け軸以外に仏像、特にご本尊の如意輪観音の姿はなかった。
このお寺を探していた時、小沢に掛かった橋の向こうに小さなお堂が建っていたのを忘れることなく、ちょっと寄ってみた。石橋を渡り、古木の脇にある小さく狭い石段を上がる。傍から見ると、全体に風情のある佇まいだ。このお堂も表面の文字は消えて名前がわからない。 お堂の中を覗いていたら、老婆が通りかかったので何の神さまかと訊いたら、“てんばくさん”だという。ただし、住民の信仰が篤いのはわかったが、どういう神さまなのかは彼女も知らなかった。 県道に出たら、最初に会ったオバサンにまた会えたので、首尾よくカギを見つけて堂内に入れた報告をし、感謝した。33観音霊場の最初のお寺の訪問はこうして無事終えることが出来た。
県道59号線に戻って、1.5キロほど南下すると東福寺がある。ここで慈眼寺の御朱印を頂く。このお寺は伊豆88か所の札所の一つ。ご住職は元は堀坂の人と聞いていたので、“てんばくさん”について訊ねてみたが、名前は知っているけれども由来については分らないとの返事。 達磨さんのような温厚で親しみのあるご住職は、来年が観音さまの祭事がある年だから是非またご来遊ください、と丁寧に応接してくれた。これから訪問する予定の1番札所滝見観音の御朱印もここで頂いた。ただ、残念だったのは慈眼寺の本尊の行方を訊き忘れたことだ。さて、東福寺を辞して次は滝見観音へ向かう。 第1番 滝見観音堂 臨済宗 聖観世音菩薩 仁科川にかかる海名野橋を目標に県道を歩く。寺川のバス停の待合所で年配の男性が休んでいた。傍らのカートに野菜がたくさん積んである。無人の野菜売り場で買ってきたのかな。「札所巡りかね。この暑い中、たいへんだなあ」でも、風が冷たいのでそれ程きつくは感じない。 ここから見える橋が海名野橋(かいなのばし)だそうで、第1番札所滝見観音堂は「そこを渡って左の道をゆけばすぐ見つかるヨ」と教えてくれた。礼を言って別れてから、もう少し話を聞くんだったと悔やんだが、戻ることもあるまい。
だが、ここはたたき台から中を見ただけだった。正面に5,60センチほどの聖観世音菩薩が細身の流麗な姿で立っていた。お顔の表情は暗くて見えない。ここでお経の一つでも唱えることが出来たら、菩薩と会話が出来たかも知れないと本気で考える。
立派な正門をくぐると、左に六地蔵が立ち、その脇に看板があった。六地蔵の説明を読む。「六道とは地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天の六つの世界をいう」六道が輪廻する中で、それぞれの世界の地蔵がそれぞれの苦悩を救うとされる。
正門をくぐって直進した先にある小さなお堂が本堂か。中を覗くと、左手に宝珠、右手に錫杖を持った坐像で、丸々とした童顔の地蔵菩薩(だと思われる)が薄目で微笑んでいた。 . 門を出てから、更に沢沿いの細い道を上がって神明神社に詣でる。看板によれば、神社正面の雌雄2本の古木はナギの木で天然記念物に指定されているという。また、拝殿の扉に貼ってあるコピーを読むと、ここで18世紀から毎年秋に三番叟が奉納されているそうである。
なお、この海名野には立ち寄りの温泉施設と、それとは別に温泉スタンドもある。いずれも町営の施設。一浴したいところだが、訪問予定が未だ3寺残っている。次は、橋を渡り返して長光寺を目指す。 第5番 長光寺 聖観世音菩薩 堀坂のバス停からいよいよ巡礼を始めたのが9時過ぎ。第6番と第1番を終了した時刻は11時を回っていた。予定よりだいぶ時間がかかった。しかも次の長光寺では御朱印をもらえないというアクシデント。しかし、最初に述べたように、この旅は御朱印集めのための巡礼ではない。またあらためて出直せばよいことだ。
さもありなん、2年ごとの持ち回りで管理しているようだから、部落外の人にはわかるわけがない。とにかく、この道の突当りまで歩いてゆき、そこの家で訊いてみた。「みんなの家」という看板が出ていた。どうやら介護ホームのような雰囲気である。 忙しそうな中で玄関に顔を出した娘さんに長光寺の御朱印のことを訊くと、この家が担当していることが分った。しかし、肝腎のこの家のご主人が外出中でハンコがどこにあるかわからないとのこと。でも、昼食には帰ってくるから、遅くはならないだろうという。そこで、取りあえず参拝を済ませることにした。
ただ、正面の横木の彫刻が立派で、さすがに寺の雰囲気があった。滝見観音堂のほうは簡素で、その装飾の色合いが如何にも観音堂の雰囲気を感じさせた。長光寺は明治の時代に廃寺になり、観音堂として現在に至るという。
このお堂の隣に神社があったので立ち寄る。地図には天満宮と記されている。小さな神社の割には拝殿の奥に立派な本殿が梯子段の廊下で続いていた。 グラウンドでは体育の授業で子どもたちが高跳びのコーナーへ移動していた。参拝を終えてその前を通ったら、その中から“こんにちは“の声がかかった。棒高跳びかと訊いたら、ハイジャンプだという。今は普通の跳び方になっている背面跳びの練習のようだ。本格的だ。
受け応えがハキハキして、礼儀正しく明るい子どもたちである。カメラを向けたら、喜んでピースサインまでしてくれた。結局、御朱印はもらえなかったが、この生徒さんたちの笑顔に救われた気持ちになった。また来ればよい。 第8番 円成寺 臨済宗 聖観世音菩薩 MAP 浜橋に戻った時には12時を過ぎていた。食事できる店を探しながら国道136号線を北上してゆくと、バス停「大浜」の少し先に「喜久屋食堂」が見つかった。この辺には役場や郵便局、保健センター、信用金庫などがあり、仁科の中心地のようだ。
ここでかき揚げ蕎麦を注文したら、ワカメがたくさんの付け出しとポテトサラダが付いてきた。かき揚げ蕎麦だけではちょっと物足りない気がしていたので嬉しいサービスだった。
時間を見計らってゆっくりと食事を済ませ、大浜からバスに乗る。仁科漁港から海岸線の変化に富んだ景色を楽しみ、堂ヶ島温泉に到着。ここは昔子どもたちと共に家族で一度来たことがある。更にその先の田子入口からバスは国道と別れて左に海岸へと下ってゆく。
田子の集落に入って大田子を過ぎ、坂を上って国道に再び合流すると田子上でバスは終点。ここまで車窓風景は初めてのことでもあり、充分に楽しめた。バスを降りてまた国道から分かれ、少し上がると墓地が広がって、直ぐにそれと分かる円成寺の上手に出た。
その“山門”をくぐって六地蔵の前に立つ。左手から参道の石段が上がって来ており、その正面に厳殿山円成寺の本堂があった。庫裏に案内を請うと、若いお上人が現れて本堂への参拝を許された。
本堂には立派な仏像が左右に置かれ、また、正面裏にも安置されていたが、どれがご本尊の聖観音であるかは分らなかった。一般に仏像の撮影は拒否されることが多く、お上人が御朱印のために奥へ引き込まれた間に秘かに撮影したという負い目があって、ついに聞きそびれてしまった。
今こうして撮った写真を見て、ご本尊らしき仏像とは思っても、これが祭壇の中央にあったものではないので確信できない。こんなことなら、撮影はやめて直接お聞きすれば良かったと悔やんでも後の祭りである。
ただ、寺のコメント付きの古仏があったので、ここに記しておこうと思う。像高60センチ余りの一木でできた不動明王立像で、破損が激しく両腕もないが、腰の線が流麗で平安時代後期の作とされていた。貴重な文化財である。
この円成寺で御朱印帳なるものを初めて購入した。先の長福寺で予定していたのだが、この33観音霊場巡りでは円成寺が最北にあるため、ここにだけ用意してあるということだった。
さて、海岸線に出ると、平行して建てられた堤防の切れ目から島々が浮かぶ駿河湾が開けた。砂浜で若いカップルが長い竿を海に向けている。平和な光景である。田子漁港の海岸道路が西へずっと続いており、ここも一度歩いてみたいところだが、いつかまたその機会があることだろう。 第9番 正法院 臨済宗 聖観世音菩薩 船揚げされた田子漁港を覗いてから、さて、本日の最後の観音霊場、正法院を目指す。海岸線から分かれ、田子隧道と書かれた小さなトンネルを過ぎ、バス停田子まで来たところで、外に出ていたオバサンに寺の場所を訊く。
山側の路地に入ると足元はタイル張りである。「七夕通り」と名前が付いた小路がずっと入り組んで続いていた。中にはナマコ壁の大きな土蔵が二つも並べている家がある。元はこの辺一帯がこの家の土地だったのかも知れない。とにかく、魅力ある路地である。
礼を言って寺を辞し、門前のお題目を再度復唱する。曰く、
意(おもい)は寂静(しずか)なり 語(ことば)もまた寂静なり 身になす業も寂静なり かかる人こそ 正しき知恵もて解脱(げだつ)を得 安息を得たるなり 惟うに、齢を重ねた者の望ましき姿がここにある。而してなぜに解脱の道の遥かなるか。
バス通りに戻って坂上のバス停月の浦でバスを待つことにした。本日の目標をすべてクリアしたことで達成感を味わう。時刻は2時を過ぎたばかり。予定通り、沢田公園の露天風呂に向う。
堂ヶ島温泉を過ぎて間もなく乗浜で下車。浜沿いの道を沢田公園に向って歩く。堂ヶ島を包み込むように沖に点在する小島が岩肌を荒々しく見せている。遊覧船はこの小島を縫って外に飛び出すようだ。
事務所のオジサンの話では、冬は西風が強く、時に大波が痩せた岩尾根を乗り越えてくるという。駐車場が水浸しになり、側溝に流れ込んだ水は暴れてコンクリートの蓋をこわしてしまうほど。現に、修理したばかりの真新しいコンクリートがそれを物語っていた。
この沢田公園にあった仁科灯台は何年か前の台風で崩れて今は無いとの事。岩尾根伝いの道が途中でストップになっていたのも、その時以来だそうだ。公園の中の散歩は諦めて入浴しただけで引き上げることにした。
船溜まり沿いにバス通り手前まで歩いて行くと、立派な伊豆漁協仁科支所の建物があった。その前には直売所もある。人が出入りしていた。後で調べたら、この中の食堂のイカめしが人気らしい。素通りしてしまったのが残念。 第1回終り |
|
|||