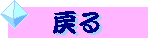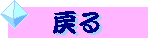採集できる石
| 鉱物名 | 量 | コメント |
|---|
| 黄鉄鉱 | 多い | あとが大変 |
| 輝安鉱 | 少ない | 1Cm以下です |
| しん砂 | 微量 | 紅安鉱か? |
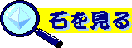
1985年11月30日
独身であった土曜日、秋の日は短いが、退屈で退屈で仕方がなかった。K氏を石採りに誘ったが、いい返事はもらえなかった。仕方がないので一人で何か探しに行くことにした。とはいっても、産地などあまり知らなかった。鉱物を集めだした最初の頃である。
あてもなく、うろうろしていたが、一週間ほど前にK氏から大峠のことを伺っていた。きれいな黄鉄鉱の結晶であることや、研究はかなりされて高校生が理科の夏休みの課題の研究にして国で選ばれ外国に研究発表に行った話があることなどを聞かせていただき自分も見てみたいものだと思っていたことを思い出した。そこで、桜井方面に車を向けた。
地元の奈良県出身なので地図も持たず、ただK氏から聞かせていただいていた、
「橋を渡ったらすぐ滝が見える。」
「その橋を渡って2Kmほど上に行くと行き止まりになる。」
「そこは広場になっていて、その上にある。」
という、すごくわかりやすい、誰でも産地に到着できそうな情報を元に出かけることにした。
確かに地元だが、「この道は私が小学生の時に1回通ったことがある」と、大きくなってから父母に教えられたことのある道であって、物心ついてから通るのは初めてであった。ただ、近くの道は何回も通ったことがあるので、この道を曲がればあの辺りに出てくるだろうと言う「カン」はあって不安はみじんも感じなかった。
だいたい目的地に近づいたと思われたが、滝がいったいどれほどの大きさのどんな滝で右にあるのか左にあるのかさえもわからない、滝のようなものが見えたので、たぶんここだろうと左折してみたが、そのあとの2Km進むことができずに道がなくなった。ここではなかったようである。
元の道に戻って少し行くと先ほどよりはもっと大きな滝と言える大きさのものが左に見えてきた。これは間違いなさそうである。どうせ時間もあるし、これだけの手がかりで探し出せるわけはないし、またK氏に連れてきていただけばよいだけの話である。気楽な気持ちで道を進んだ。1Kmほど進むと、対向するのがやっとのアスファルトの道が二手に分かれている。左の道は地道でその先の道ははなさそうである。右の道は小さな川沿いに、コンクリートの道になっている。右の道を行くしかなさそうである。
このコンクリートの道はまた細く、軽四輪でないと通れない。2000ccの車は入ってこられない道である。その上コンクリートが壊れて、わだちになっていたり、岩が転げ落ちていて車高の低い車ではとてにも最後まで行くことはできない。大変曲がりくねった道であった。ようやく1Kmほど登り終えて、広場に出た。聞いていた事とほとんど同じだった。ただし、広場と行っても車を3台も置けば一杯になってしまうほどの広さで、しかも坂になっている。下はコンクリートだし、想像とはかなり違っていた。
そこで車を降りて、探しに出かけることにした。しかし本当にここだろうか。山には、特別な神様がいて、似た場所を作ってみんなをよく迷わせる。だから山で「迷う」ことを「さまよう」と言うのだが、山岳信仰ではよく話題に上る「さ」の神様である。
酒=「さ」気(人格が変わって何かがのりうつったように、神様の気持ちになる)
桜=「さ」倉(「さ」の神様が倉のごとく、たくさん入っていて、枯れたような冬の木から、葉っぱより花を先に咲かせる。だから日本の国の木である。)
仏の顔も「さ」ん度まで。(3=さんは神様につながる神聖な数字)
など、よく山里で聞く話である。
こんな所など、どこにでもあるように思えてならない。そうは思っても別に当てもないので、登ってみることにした。道を探したがどこにも見えず、獣道のような細いところを見つけてそこを上がっていった。足元はぐちゃぐちゃの泥で、スニーカーでやってきた私は大変な目にあってしまった。
50mほど登ると、やっと道に出た。林業の人や登山者が通る道らしく、わりと歩いた跡がついた道であった。右の斜面や左の崖をゆっくり見て歩くが、黄鉄鉱のようなものは見つからなかった。20分は歩いただろうか、山の稜線に出てしまった。これから先は熊笹が生い茂っていてとても鉱物採集どころではなかった。やはり間違っていたようである。
落胆の思いで、今来た道を戻ることにした。せっかくここまで登ったのに間違いである。まだ20歳代だが、さすがに疲れがこみ上げてきた。帰りの下りはしょんぼりと下を見て帰ることになった。今までは意気揚々としていたのに、大違いである。
20分ほどかけてやっと戻ったとき、ふと気づいた。私の車が杉の間に見えているのであるが、先ほどはスニーカーを泥だらけにして登ってきたのに、帰りはこのまま広場に戻れそうなのである。どうも広場に続く道があるらしい。
先ほど道に出たあたりを過ぎて少し下ってびっくりした。足元に黄鉄鉱の粒が見えるのである。慌てて出所を探すと、西側の斜面の下に白い粘土の露出したところがあり、人が踏み荒らしたような場所が見えている。下りてみると、白い粘土の中にきれいな周囲が完全な黄鉄鉱の粒が無数に顔をのぞかせている。どうも、しょんぼりと下を見て帰ることになった事が幸いしたらしい。ここまで来ればもうこちらのものである。腰を据えて採集に取りかかった。
白い粘土の部分は、幅8m長さ10mくらいで斜面に広がっている。白い粘土は雲母の風化したものだと聞いていた。その中に最大2Cm、普通で3mmくらいの黄鉄鉱の粒がほとんど完全な結晶で含まれていた。
まわりは杉の林で川はすでになくなっており、水の得られる所はない。水さえあればその場で黄鉄鉱だけを分離できるのだが、粘土をそのまま持って帰るしかなさそうである。
考えれば、ここで選鉱をするよりここでできるだけの良さそうなものを採集して、家でゆっくり選鉱した方が楽しめるし、また、違う発見もあるやもしれない。
できるだけ良さそうなところを探し、選鉱の時にどこが一番良いものが出るかが判るように、分類しながら、5カ所ほどの場所から採集をしておいた。
しかし、一番下から採ったとき、スコップの先に新聞の塊があたった。最初は新聞とはわからなかったが、掘り出してみてわかった。新聞の日付を見ると1975年のものであった。そのころからもう採集に来ている人があったのであろう。しかし、10年の間に10Cmほど埋まってしまったのには驚いてしまった。
重くなったリュックを背負って自分の車に戻ったが、やはり、その道は自分の車の横に出られる道であった。どうやらいい加減な探し方で道を探したので見つからなかっただけらしい。もし、この道に最初に気づいていたら、40分は早くこの産地を見つけ出していただろう。今思えば情けない。しょんぼりと下を見て帰ることになった事が幸いしたらしい、などと考えていた自分がおかしくなってきた。
帰った次の日から選鉱作業に入った。
大きめのバケツに水を入れ粘土ごと一晩つけておくと柔らかくなり取り出しやすくなる。水をホースから勢いよく出し、バケツの中の粘土に吹き付けるとしばらくして粘土部分は全て外に流れ出し、大きな粒だけ残る。相手は鉄なので少々荒っぽくてもびくともしないのが助かる。
しかし、何度かやっているうちに「液状化現象」のことがよくわかった。地震の時に出てくるヤツである。水流がないときは下にたまった砂は硬いのに、水を吹きかけたとたんに今まで砂があったのかと思われるくらいの、水だけのような感触になるのである。不思議な感触だった。そんなこんなで選鉱作業も5日間ほどで終えたが、すばらしい完全な結晶には驚かされた。まるで作り物のような感じがあって、鉱物を知らない人が見たらいつも人工物と間違われてしまう。
採れた場所の違いを見ようと5種類を比べてみたが全く差はなく、しばらくして混ぜてしまったらどこかわからなくなってしまった。どの場所でもほとんど変わらないものと思う。
しばらくしてK氏に産地に行ったことを話すと、たったあれだけの情報で、よくたどり着けたものだと感心しておられた。しかし、この執念深さを、誇ってよいものやら恥ずかしがるべきものやら、どんな顔をすればよいのか四苦八苦したことを覚えている。(ここで「エヘン!」となるともうマニアの域に入るのだろう。しかし、あのときの私はまだ若かった。)
その後、K氏につれてきていただいたが、やはり同じ所であった。
ちなみにここの黄鉄鋼はポケット図鑑「日本の鉱物」のP265に載っている。