
八王子七福神めぐり
 八王子七福神めぐりの色紙です。
八王子七福神めぐりの色紙です。
真ん中の宝船の色が毎年変わり7色あるそうです。
7色の色紙を集めると(7年かかります)金の色紙がいただけるそうです。
ちなみに我が家は今年3色目です。金色の色紙にはまだまだです。頑張ろう!
では、しゅっぱ〜つ!
今年の七福神めぐりは2002年1月4日(金)快晴の気持ちのいいお天気、実にお散歩日和の1日だった。
こんなに穏やかな日だったら、みゃあくんもお留守番は大丈夫、安心して、七福神めぐりが出来る。
(腎臓が悪いため、寒さには弱く、常に部屋の中を暖かくしてあげなくてはならない。長時間の外出はなるべくひかえている。)
去年までは八王子駅から歩き始めたが、今年は時間短縮のため、西八王子駅から歩き始める事になる。
吉祥院 〜 了法寺

 まずは吉祥院を目指す。駅より歩いて20分くらい、チョット高台にある。
西八王子の駅からは歩行者専用道路を通り、淺川を目指す。五月橋、とっても小さな橋、睦橋を渡り少し先の階段を上って
畑の道を通ると近い(気がする)。詳しくは地図などで調べて欲しい。
まずは吉祥院を目指す。駅より歩いて20分くらい、チョット高台にある。
西八王子の駅からは歩行者専用道路を通り、淺川を目指す。五月橋、とっても小さな橋、睦橋を渡り少し先の階段を上って
畑の道を通ると近い(気がする)。詳しくは地図などで調べて欲しい。
吉祥院は坂の上にある。階段を上ると御朱印を押していただける事務所があり、その上に目的の吉祥天(写真左)がある。
七福神には吉祥天様は入っていないが、八王子の場合は7寺八福神ををまわる事となる。(八王子にかけたのだろうか…)
見晴台もあり、八王子の町が見渡せる。鐘つき堂で鐘をつくこともできる。また近所に竜泉寺(別名ぽっくり寺と呼ばれる)もある。
時間があれば一度よってみようと思っている。
吉祥院を後にして、了法寺をめざす。淺川に戻り少し土手沿いに歩いてみる。お正月だというのに暖かく、これぞお散歩日和で、
土手に座ってお弁当でも食べたくなるくらいだ。(残念、持ってくればよかった。)橋を渡り甲州街道を目指す。お散歩のいい所は
どんなコースを通っても文句を言われない所、好き勝手に歩ける。街道沿いのお店を眺めたり、案内にはのっていない道を曲がってみたり、
色々迷って見るのも楽しい。のんびり、テクテクこれがお散歩だ!
甲州街道へ出たら、追分交差点方向を目指す。
陣場街道を通り、追分交差点を目指すコースもあるが、今回は甲州街道沿いを歩いてみた。追分交差点手前に了法寺はある。
新護弁財天(写真右)がある。御朱印は本堂に上がり中で押していただける。七福神まわりの期間だけだろうが、弁財天様を
間近に見せていただけるもありがたい。又ここには、七福神飴も売っている。金太郎飴の七福神判だ。なんとなくありがたい気が(?)する。
弁財天様は/音楽・学芸の神様として信仰を集めているようだが、ここの新護弁財天様は、厄除け・縁結びの功徳もあるようだ。
しっかり拝んで次へと向かう。
次は 善龍寺 〜 信松院
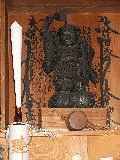
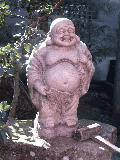 了法寺より北側、秋川街道沿いにある善龍寺は大黒様がある。走大黒天(写真左)と、チョットユニークな名前になっている。
これは大黒天様が右足を一歩踏み出されている所から、銘々されたようだ。本堂に上がり思わずじっくりと足元を見てみると、確かに一歩踏み出していた。
1月と9月には走大黒天様のお祭りがあるようだが、走り回って福を授けていただけるそうで、拝んだだけも、元気をもらったような気がした。
本堂手前にたわし地蔵があり、お水をかけ、悪いところをたわしでこすると良いそうだ。思わずゴシゴシ!良くなりますように…
了法寺より北側、秋川街道沿いにある善龍寺は大黒様がある。走大黒天(写真左)と、チョットユニークな名前になっている。
これは大黒天様が右足を一歩踏み出されている所から、銘々されたようだ。本堂に上がり思わずじっくりと足元を見てみると、確かに一歩踏み出していた。
1月と9月には走大黒天様のお祭りがあるようだが、走り回って福を授けていただけるそうで、拝んだだけも、元気をもらったような気がした。
本堂手前にたわし地蔵があり、お水をかけ、悪いところをたわしでこすると良いそうだ。思わずゴシゴシ!良くなりますように…
秋川街道に戻り、南にひたすらまっすぐ向かう。線路を渡りまもなくすると、信松院が見えてくる。ここには布袋尊がある。何でもこのお寺は、
武田信玄の四女松姫を開基としているそうで、1590年創建のお寺だそうだ。(武田信玄の名前が出てくるなんて、ほんのチョット、
歴史の教科書に触れた気がする。)本堂下・地階には観音堂があり、ここに安置されている布袋蔵のお腹をさすると福徳を授かるとされているが、
七福神の布袋尊(写真右)とは別だ。地下の布袋蔵は見るからに福々しく、お腹もピカピカで思わずなでなで。誰も見てなかったら、舐めちゃいたいと思わせる程だ。
肝心の七福神の布袋尊だが、建物の中ではなく外にある。石で出来た、実にかわいい布袋様だ。地下の布袋様も立派だが、
私はこの小さめの布袋様が好きだ。雨風にはさらされてはいるが、それにも負けずニコニコと福を授けてくださる、これぞ神様と思ってしまう。
寺内に雲水持鉢料理「喜心」、喫茶「セラード」があり、この時期七福神カレーなるものもやっていた。
チョット一息 金剛院 〜 中村屋
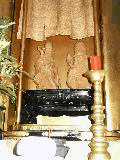
 信松院から郷土資料館前を通り、10分ほどで金剛院につく。ここには、寿老尊と福禄寿(写真左)二人が待っている。(そこで、7寺八福神となる訳でだ。)
ここは今回まわる7寺の中で一番大きいのではないだろうか。八王子から西八王子へ向かう電車の中からも見える線路に近い所だ。本尊を拝む左側に
二人並んでいる。幕がかかってチョット見えずらいが、腰を低くして下から見上げるとしっかり拝める。本堂の左脇には光明真言が刻まれた石輪があり、これを一回まわすと
真言を1回唱えたと同じになるという。尚この石輪は知らないと素通りしてしまうくらい、何気なく置いてある。(それもまたいいもんだ。)二人を拝んでから、御朱印をいただきに
建物の中に入る。ここにはありがたくも休憩所を設けてくれている。椅子とテーブル、その上ポットに入った暖かなお茶まで用意してくれている。ほっと一息、チョット休憩する。
ここのうれしいのは、おトイレも広くて綺麗で靴をはいたままいけるのもありがたい。しばしの休憩の後、次へと向かう事とする。
信松院から郷土資料館前を通り、10分ほどで金剛院につく。ここには、寿老尊と福禄寿(写真左)二人が待っている。(そこで、7寺八福神となる訳でだ。)
ここは今回まわる7寺の中で一番大きいのではないだろうか。八王子から西八王子へ向かう電車の中からも見える線路に近い所だ。本尊を拝む左側に
二人並んでいる。幕がかかってチョット見えずらいが、腰を低くして下から見上げるとしっかり拝める。本堂の左脇には光明真言が刻まれた石輪があり、これを一回まわすと
真言を1回唱えたと同じになるという。尚この石輪は知らないと素通りしてしまうくらい、何気なく置いてある。(それもまたいいもんだ。)二人を拝んでから、御朱印をいただきに
建物の中に入る。ここにはありがたくも休憩所を設けてくれている。椅子とテーブル、その上ポットに入った暖かなお茶まで用意してくれている。ほっと一息、チョット休憩する。
ここのうれしいのは、おトイレも広くて綺麗で靴をはいたままいけるのもありがたい。しばしの休憩の後、次へと向かう事とする。
ここで、チョット本道からはずれ寄り道をした。去年七福神をまわった時に、余りのいい香りに思わず立ち寄った所だ。中村屋さん(写真右)といって、
ピーナッツ専門店である。店先でピーナッツを炒っていて、その香りがナントもいえず思わず店の中に入ってしまったのである。小さな袋で1ツ500円と値段も確かにいいが、
それに見合うおいしさだと思う。今年は最初から、是非買って帰ろうと実はこの前を通るを楽しみしていたのである。地図を確かめて、道を間違えないように気をつけたのは、
この付近を通るだけだというのは、実に食い意地が張っているのだろうか…
ラストスパート 伝法院 〜 毘沙門堂

 中村屋さんからまもなく、伝法院につく。私達には一番なじみがある?恵比寿天(写真左)がある。福を招き商売繁盛、庶民の神様という所だろうか。
絵にも描きやすく、釣竿持って、鯛を担いで…子供でもわかる神様、やはり一番の おなじみである。10月20日から3日間恵比寿講大祭は相当賑わうらしい。
何でも七福神(ここでは八福神か)のなかではだた一人日本出身だそうで、なじみが深いのは、それもあるのだろうか!
中村屋さんからまもなく、伝法院につく。私達には一番なじみがある?恵比寿天(写真左)がある。福を招き商売繁盛、庶民の神様という所だろうか。
絵にも描きやすく、釣竿持って、鯛を担いで…子供でもわかる神様、やはり一番の おなじみである。10月20日から3日間恵比寿講大祭は相当賑わうらしい。
何でも七福神(ここでは八福神か)のなかではだた一人日本出身だそうで、なじみが深いのは、それもあるのだろうか!
恵比寿天から商店街を抜けて、最後の毘沙門堂へ向かう。NTTを目指して歩くといいと思う。NTTを過ぎるとちらほら案内が見えてくる。最後の力を振り絞って頑張ろう!
北大通りの案内(ここを曲がるの看板)を左折すると、毘沙門堂が見えてくる。こじんまりとした住宅街の一角だ。決して広くない敷地に結構な人がいた。早速毘沙門天様(写真右)を
拝み最後の御朱印をいただく。そして出来上がったのが、
最初の色紙となる。
ここでは、干支の手書きの色紙が売っている。ご住職の筆だそうだ。見ている間に結構売れていた。
ちなみに、七福神色紙は期間内であれば、各お寺に置いてあり(無地)色紙1枚300円、御朱印(一神様)200円で押していただける。何箇所か七福神めぐりをしたが、これは大変安価で、これも人気の要因ではないかと思われる。
ここでナント金色の色紙と交換している人を目撃した。最初にも書いたが、7色集めなければならないので7年かかることになる。2年や3年は簡単だが、7年毎年これを続けるのは、
大変なことである。ましてや、お年を召した方だと尚更だ。金色の色紙がとてもまぶしく見えた。我が家は3枚め、まだまだである。あと4年健康でお正月に七福神めぐりを出来るように
祈るばかりである。
無事にまわり終えて
今年も無事に七寺八福神をまわり、新しい1年が始まった。今年が素敵な1年であります様、八神様に見守っていただこうと思う。
駅へ戻る途中、ついでといっては失礼だが、八幡八雲神社もお参りする。1日でも長くみゃあくんが健康でいられますよう、お参りをした。さてあとは、夕飯のお買い物をして、
みゃあくんの待つ家に帰るだけである。
とにかくいい天気でよかった(次の日は一転して寒空、雪もちらつこうかという天気となった。)
それが何よりのご褒美(御利益)だった気がする。(終)










