 ハーシェル・アーカイブ
ハーシェル・アーカイブ
 ジョン・ハーシェル=ショーランドさんのご自宅とアーカイブは、ノーフォーク州のハーレストンという小さな町にあります。ロンドンから電車とタクシーを乗り継いで2時間半ほどかかりました。今まで写真で見たりした肖像画などのオリジナルや、初めて目にした一族の愛用品(カメラルシダなど)、手紙その他の文献類など、貴重なものが数多くありました。何か具体的に調べたいテーマがあれば、きっと大きな収穫があると思います。
ジョン・ハーシェル=ショーランドさんのご自宅とアーカイブは、ノーフォーク州のハーレストンという小さな町にあります。ロンドンから電車とタクシーを乗り継いで2時間半ほどかかりました。今まで写真で見たりした肖像画などのオリジナルや、初めて目にした一族の愛用品(カメラルシダなど)、手紙その他の文献類など、貴重なものが数多くありました。何か具体的に調べたいテーマがあれば、きっと大きな収穫があると思います。
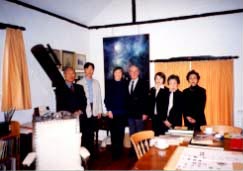 奥様が描かれたという絵がアーカイブの壁に何枚か掛けてありましたが、ジョン・ハーシェルの幻想的な肖像画など、どれも見事なものでした。
奥様が描かれたという絵がアーカイブの壁に何枚か掛けてありましたが、ジョン・ハーシェルの幻想的な肖像画など、どれも見事なものでした。
 大英図書館
大英図書館
ケルト文化の影響を受けた彩色写本の傑作と言われる「リンデスファーンの福音書」を見るのが目的でした。その後ギフトショップで「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」の複製画を見つけました。大英図書館ではなくパリ近郊のコンデ美術館の所蔵品なのですが、私にとってヨーロッパ中世写本と天文の両方の興味の接点となるものでしたので、つい購入してしまいました。
ベリー公はフランス国王シャルル6世の弟で、1410年頃に画家ランブール兄弟に命じて豪華な挿絵入りの教会暦のカレンダーを作らせました。これが「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」で、20年程前にNHKがカール・セーガンの「コスモス」をもとに特集番組を制作・放送したとき、ヨーロッパ中世の教会暦にもとづく時間概念の例として取り上げられていました。
バースはローマ時代からの温泉以外にアンティークでも有名な町で、家具や装飾品のアンティークショップのほか、古い印刷物を売る店もありました。18世紀末にフランスの博物学者ビュフォンが編集した百科事典「自然誌」のなかのカーネーションのカラー図版(恐らく銅版画)の1ページと、1900年頃の天文書に付いていたらしい太陽系の図版を買いました。太陽系図には1930年発見の冥王星は描かれていませんでした。
 ハーシェル講演会
ハーシェル講演会
今年のウィリアム・ハーシェル協会主催の講演会は "The History of Astronomy & Music from Pythagoras to Voyger II" と題し、ピタゴラスの数学的音楽理論から惑星探査機ボイジャーに載せられた音楽レコードまで音楽と天文の関わりを追ったものでした。科学史的には、「天球の音楽」はルネサンス期の自然思想に特徴的な概念で、世界の構造(特に惑星運動)に神が天地を創造するにあたって設定したであろう数学的調和を読み取ろうとするものです。ケプラーの惑星運動の三法則もこの発想から導かれたものです。18世紀には自然科学の関心が、世界中のあらゆる事物を収集し分類しようとする博物学に移行していき、近現代においては一般に「天球の音楽」は宗教的なバックグラウンドを持つ古い思想とみなされるようになります。
しかしウィリアム・ハーシェルが天文学に関心を持つきっかけとなったスミスの著作はこの「天球の音楽」の観念を受け継いで、数学的調和を音楽に求めるものでした。ウィリアムはまた宇宙を庭園にたとえて「あらゆる成長段階のサンプルを収集することができる」と述べていますから、博物学的な関心も持ち合わせていたことがわかります。
このようにウィリアム・ハーシェルはルネサンス自然哲学と近代博物学との接点に立っており、科学史の面から見て非常に興味深い人物なのです。こうしたハーシェルの科学史的な位置付けや「天球の音楽」について私の知っている限りのことを、また別の機会に改めてまとめてみたいと考えています。