mori's Page 騒音の対策
3.3.吸音型消音器
吸音型消音器は消音器内部に吸音材を配置し、音波による振動で吸音材を振動させ、吸音材の粘性や摩擦によ
り、音のエネルギを熱エネルギに変換して減音効果を得る。
り、音のエネルギを熱エネルギに変換して減音効果を得る。
音のエネルギは非常に小さく、通常では観測出来ない。このため単位時間内のエネルギが大きい、高い周波数帯域
での効果が大きい。
での効果が大きい。
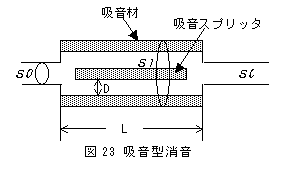
図23は拡張室内に吸音材を配置したもので、減音せずに通過する高い周波数帯域を減ずるため、中央に吸音スプ
リッタを配置している。(吸音スプリッタ:吸音材を充填した板状のもの)
リッタを配置している。(吸音スプリッタ:吸音材を充填した板状のもの)
次式は拡張室内に吸音材を配置したときの透過損失を得る計算式である(巻末計算式17下段の式)。
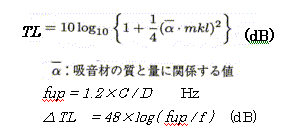
式によると減音量(透過損失)は断面積比・吸音材配置長さの2乗に比例している。 は一般的に使用されている吸音
率とは違い、消音器内の吸音力を表したもので吸音材の充填率に依存している(図24参照)。
率とは違い、消音器内の吸音力を表したもので吸音材の充填率に依存している(図24参照)。
周波数が高くなるにつれ減音効果は上昇し、吸音材の配置間隔で決まる周波数(fup)まで倍周波数で約6dB上昇す
る。fupを過ぎたところから急激に効果は減ずる(△TL)。(図25参照)
る。fupを過ぎたところから急激に効果は減ずる(△TL)。(図25参照)
図26は拡張室長さ850mm、拡張比7、吸音材充填量50%で吸音材配置間隔100mmの透過損失を計算したものであ
る。
る。
吸音材の減音効果は、吸音材の厚さにより各周波数における消音効果に違いが生じる。
図27、28は吸音スプリッタの厚さと効果のある周波数帯域の関係を示したもので、吸音材が厚いと低い周波数帯域
で効果があり、薄く間隔の狭いものは高い周波数帯域に効果がある。
で効果があり、薄く間隔の狭いものは高い周波数帯域に効果がある。
表1は吸音材の種類と特徴を示したもので、温度や経済性で用途を決める。
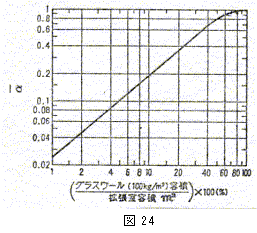
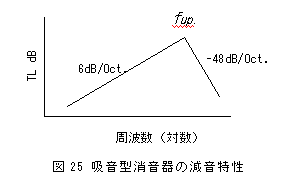
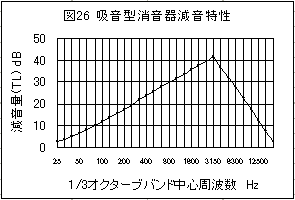
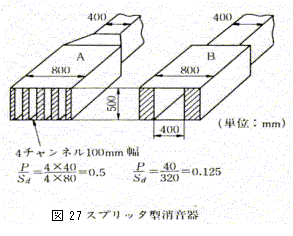
図29はダクトの曲がり部に吸音材を内張したときの減音効果の測定例を示したもので、ダクト幅が大きく吸音材厚み
が厚いものほど低域の周波数帯域まで効果がある。
が厚いものほど低域の周波数帯域まで効果がある。
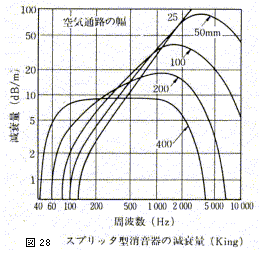
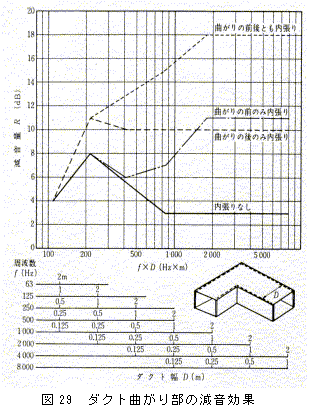
前へ ページの先頭へ 次へ
|

