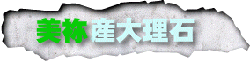
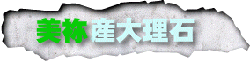
|
美祢産大理石の歴史
|
 大理石鉱山 山口県美祢市台山
大理石鉱山 山口県美祢市台山
| 古墳時代 | 石棺の妻石の一部として使用されている。 |
| 江戸時代 | 美祢地域の神社やお寺で数多くの白大理石製の造形物を見つけることができる。(鳥居、狛大、灯籠、仏像、お墓、石碑、橋、石段、石垣など)この時代の物は、石質が非常に似ているので、どこかに共通の石切場がすでにこの頃からあったと考えられる。なかには3メートル近い石もあり、採掘の専門家がいたと思われる。現在、美祢市の伊佐小学校の近くに、この時代の看によく似た石質のものがある。 |
| 明治初期 | 画家高島北海が大田村で大理石を発見したと、美祢市史に記載されている。 |
| 24年 | 明治の元勲で長州人だった井上侯爵が、麻布鳥居坂の自宅新築の際に応接問のマントルピースに美祢産大理石を使った。この石は非常に良質なもので透き通るような美しさだったという。 |
| 35年〜 | 陸軍省の委託を受け本間俊平氏が山口県で初めて秋芳町で組織的に採掘加工を始めた。彼はキリスト教精神で不遇の青年や出獄人などを献身的に会社に受入れ、社会活動家としても非凡な存在であった。当時、工業の動力がスチームエンジンから電気に変わり始めたのをきっかけに電気の配電盤を大理石で作るのを本問氏が事業化した。これが時代に乗り、国内で使用される配電盤はほとんどが美祢地域産で独占されるまでになった。 |
| 38年〜 | 美祢市、台山に大嶺大埋石採掘所が創業。班紋、純白、普通の三種類の大理石を採掘した。当時の省庁等から注文があった。 |
| 大正12年 | 関東大震災をきっかけに建設材の需要が増大し、美祢の業者も本格的な建設用石材の採掘に取り組み始めた。この頃すでに秋吉、別府、伊佐、大嶺にわたり6ケ所の採掘所があった。 |
| 昭和4〜5年 | 国会議事堂建設にあたり、使用される石材は全て国産のものを用いることになり、明治45年から全国の石材調査が始まった。採石の大きさ、見込み量、石質、風化強度、産地の状態、運搬、価格、とともに科学的、物理的試験も行われた。結果、美祢地域からつぎつぎと新しい大理石が発見された。年代順に並べてみると、小桜、黄更、霞、黄華、白鷹、青華、長州オニックス、白鳳、白千鳥、等が脚光を浴ぴ、山口県の大理石の名を一躍広めた。 |
| 8〜9年 | 国会議事堂の内装用に選ばれた全国の大理石37種の中で、10種(霞、薄雲、黒霞、鶉、紫雲、白鷹、小桜、吉野桜、山吹、長州オニックス)が美祢地域から選ばれた。一地域でこれ程多くの石が選択されたのは特筆に値する。 |
| 10年〜 | 洋風近代建築ブームで大理石採掘作業がにぎわい始める。 |
| 26年 | 山からの大理石の切り出しに、採掘権が必要になり、小規模な業者の負担となる。 |
| 30年〜 | 秋芳洞の観光化が進み、おみやげとして色大理石で作った工芸品が人気を得る、そのため美祢郡市に大理石加工所が、100社以上誕生しこの地域独特の産業として定着した。当時、大理石採掘も盛んになり、この頃までには30種類の色大理石が発見されている。 |
| 36年 | 秋吉台が国の特別天然記念物に指定され、台上にあった数種類の色大理石が採掘不可能となる。 |