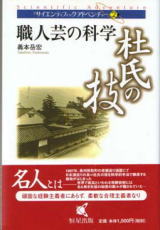|
(本文より) 私は従業員4人にプラス自分の家族で酒造りをやっているだけの、時には自分でトラックを運転して配達に行かねばならない小さな地酒蔵のオヤジであります。紆余曲折を経て家業を継ぐため蔵に戻ったのが昭和62年のこと。万延元年より140年間、この熊取町小垣内で酒造りを営んで参りました。折しも杜氏の高齢化にともない後継者の問題が深刻になっており、若手社員による酒造りを試みるにあたって、これまで杜氏の経験と勘が頼りとされた作業の見直しを迫られることになりました。科学的な手法を用いて、数値によって麹の出来不出来を分析する方法を取り入れ、あるいは今日的な労働条件に合わせるために麹の製法や酒母づくりそのものを試行錯誤で修正してきました。その中で、戦中の米不足によって途絶えていた純米酒の復活、あるいは夏仕込みの酒などへも挑戦することとなり、新聞やテレビでこれらの成果が紹介されたことで、今回のお話もいただいたものと思います。 内心、今までやってきたことをまとめる意味からも、ありがたくお受けしたいという気持ち半分、書けるかどうか不安な気持ち半分です。
問題は、私には経営者の一面があるということです。会社の規模、業界を取り巻く環境、それらの制約以上のことは、仮に知っていても書けないということです。たとえば酒類には酒税が絡むため、各種規制が存在し、私たちは研究のためといっても規制にふれるような酒を造ることは禁じられています。他社に知られたくない製法もありますし、他社を批判するような記載も避けたいと思います。今の段階で、偉そうなことをいうのはおこがましいかとも思います。
今でも、「杜氏が夜遅くまで『もろみ』を観て、丹誠込めて造った大吟醸」というような批評をする人がいますが、夜を徹しての作業は明らかに労働基準法違反です。しかし、ベテラン杜氏の経験と勘で造ったという方が売りやすいのも事実でしょう。
ただ、酒造業界はいままで出稼ぎの杜氏にあまりにも依存してきた上、(酒造りをまったく知らない経営者も多くいるようです)、世代交代がなかったために、意外なほど技術革新が遅れています。若手がほとんど育っていないため、杜氏制度を樹木にたとえれば、きれいな花や葉が茂っているように見えますが、根本は腐っています。数年後の倒壊を見越して杜氏の技を残すためにも、経験年数の浅い社員だけで並以上のことはできるのだということは示したい、一部の人の酒造りではなく、國酒として民族に根付いた清酒造りを目指したいとも思っています。そして、これまで受け継がれてきた酒造りの文化を、絶やすことなく次の世代へ伝えていきたいと思うのです。
本のご注文はお近くの書店またはScientific Workshop K's (e-mail kswork@office.email.ne.jp)までお願いいたします。 |