「グルメの話 おいしさの科学」
(京都大学農学研究科教授 伏木亨著)
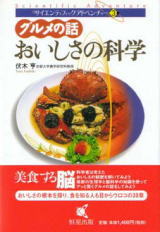
「グルメの話 おいしさの科学」(京都大学農学研究科教授 伏木亨著) |
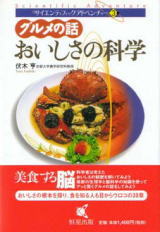 |
|
本書に貫かれるキーワードは「美食する脳」。おいしさは感じるのは舌ではなく、実は脳だというのです。もちろん、味を感知する感覚細胞は舌にあります。でも感知した味を「おいしい」「もっと食べたい」あるいは「おいしくない」「この味は飽きた」と評価するのは脳に他なりません。脳によるおいしさの評価基準がどこにあるのか、というテーマが解き明かされていきます。 脳は「もっとおいしいものを!」と要求する暴君ではありません。生きるために体が必要とする栄養素を判断し、いま何を食べるべきかを舌に伝える名君です。 たとえば塩。私が改めて述べるまでもなく、吸い物の味を左右するのは出汁そのものの味とともに塩加減にかかっています。ぴたりと決まるおいしい塩加減というものがありますが、それは人間の血液の塩分濃度に非常に近いのです。辛すぎる塩は体にストレスとなり、薄すぎると今度は生きるための塩分が足りなくなります。汗をかいた後などには、おいしく感じる塩加減が変化することをみなさまもご存知でしょう。 ただ脳がこのような名君であるためには、幼い頃の教育が大切であることも忘れてはなりません。出汁の話がでましたが、昆布やカツオの出汁のおいしさで脳が満足できるためには、離乳期から幼児期のうちにその味を覚える必要があるといいます。ステーキやトロなどとろけるようなアブラの味には脳を虜にする秘密があり、「おふくろの味」として出汁の味を知らない脳はアブラなくして満腹できません。話題は生活習慣病へと導かれていきます。 おいしさを判断するのが脳であるが故の問題も語られます。またいま話題の「情報」もおいしさには深く関与します。 最終章のタイトルは「黒船到来」。日本の食卓に到来した黒船とは? それはぜひ本書をお読み下さい。
<本書で扱われた食材、食品> くさや・ワイン・おにぎり・ポテトチップス・焼きそばソース・カニ・ファーストフード・ステーキ・カレー・醤油・キムチ・ビール・ふきのとう・日本酒・発酵食品・刺身・ウナギの蒲焼き・ラーメン・香辛料・ゲテモノ・出汁と塩・パンとご飯 など本のご注文はお近くの書店またはScientific Workshop K's (e-mail kswork@office.email.ne.jp)までお願いいたします。 |