「21世紀に何を食べるか」
葛西奈津子編・著
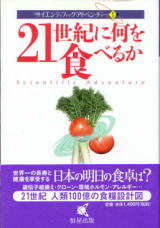
「21世紀に何を食べるか」葛西奈津子編・著 |
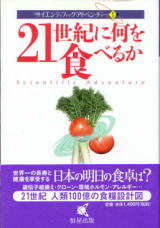 |
|
21世紀を迎え、遺伝子組換え食品が食卓に登場し、ダイオキシンによる汚染や食中毒事件が次々に起こり、さらには狂牛病など・・・食品に関する人の関心が急激に高まりました。一般向けに多くの本も出版され始めましたが、科学的根拠に基づいて正しい知識を提供しているものは少なく、しかも多くの問題を網羅するものがないと感じていました。この本は、11人の専門家がそれぞれ独立のテーマで執筆し、1冊で食をめぐるさまざまな問題点に関して知識を得られるように構成しました。 各章で科学者によって語られる内容には、ちょっとした発見、驚きがあります。たとえば「第4章食物アレルギーへの挑戦」。日本人に多い食物アレルギーの原因食品は何だと思いますか? 以前は卵や大豆でした。でも最近の食生活では、そもそも大豆食品を食べる機会が減っているので、大豆アレルギーも減っているそうです。では、代わって台頭してきたアレルギー食品とは? それは本書を読んでください。この章ではアレルギーに関する疑問が氷解するでしょう。 また、私たちがいかにマスコミ報道に翻弄されているかを解説するのが第8章です。クローン牛が食用肉として販売され、「クローン牛はついこないだ研究開発されたばかりのものじゃないか、そんな実験段階のものを食べて大丈夫なのか」という心配を消費者に抱かせました。この本はそんな疑問にも生物学的な見地からこたえています。 さて他にも「おいしいってどういうことか」「どうして体にいい食べ物が自然界に存在するのか(自然が人間のために役に立つ食べ物をご親切につくってくれているはずがないのに)」などという楽しいテーマが並んでいます。さらにじっくり読んでいただきたいのは、本書の後半部。食資源の有効利用や持続的農業といった観点から、食料科学と地球環境が調和して維持・発展していくための考察が行われています。21世紀の食糧不足に備え、これまで利用されてこなかった素材を新しい食材として活用するとともに伝統的な食品加工の良さを見直す、あるいは食文化や地域に根ざした農業のやり方も含めて食料生産のあり方を考える、といったふうに、時空的な広がりを持った視野で方策を見つけようと提案しています。つまり、「遺伝子組み換え作物」の問題に対して、組み換え大豆を使っていない豆腐を選んでスーパーで買うという行動だけでは解決できないということを訴えています。 この本を通して、読者の皆さんには自分の食べるものについて学び、考えていただきたいのです。また、研究者や食品製造業者の方々にも是非読んでいただきたい本です。 最後に、この本のエピローグを書いているときに著者の一人からいわれました。「この本は日本に在住する人だけを対象としているね」と。たしかに、食糧不足に苦しむ地域の人をきちんと視野に入れた本ではありません。それはぜひ「続・21世紀に何を食べるか」として企画したいと思います。 本のご注文はお近くの書店またはScientific Workshop K's (e-mail kswork@office.email.ne.jp)までお願いいたします。 |