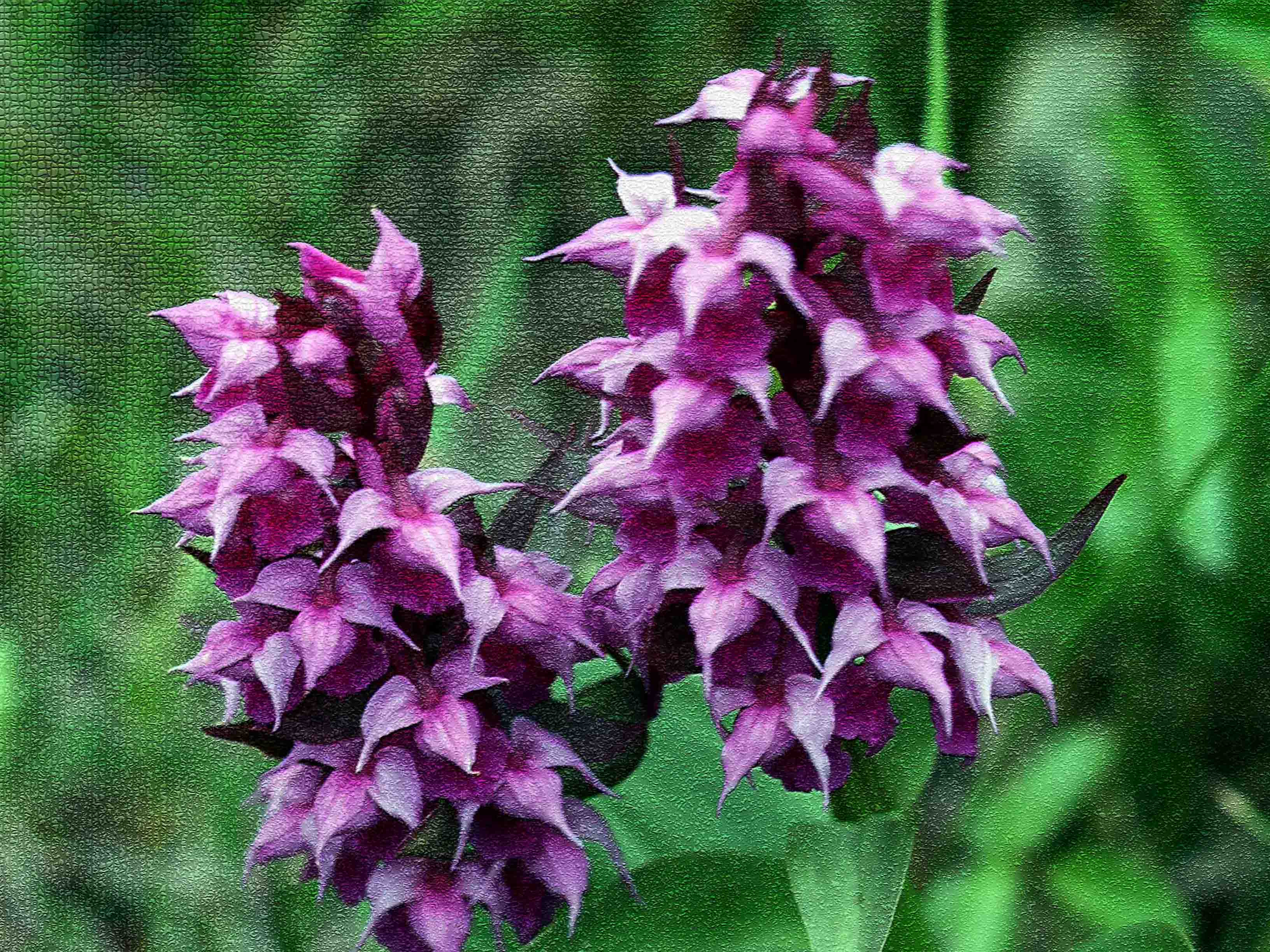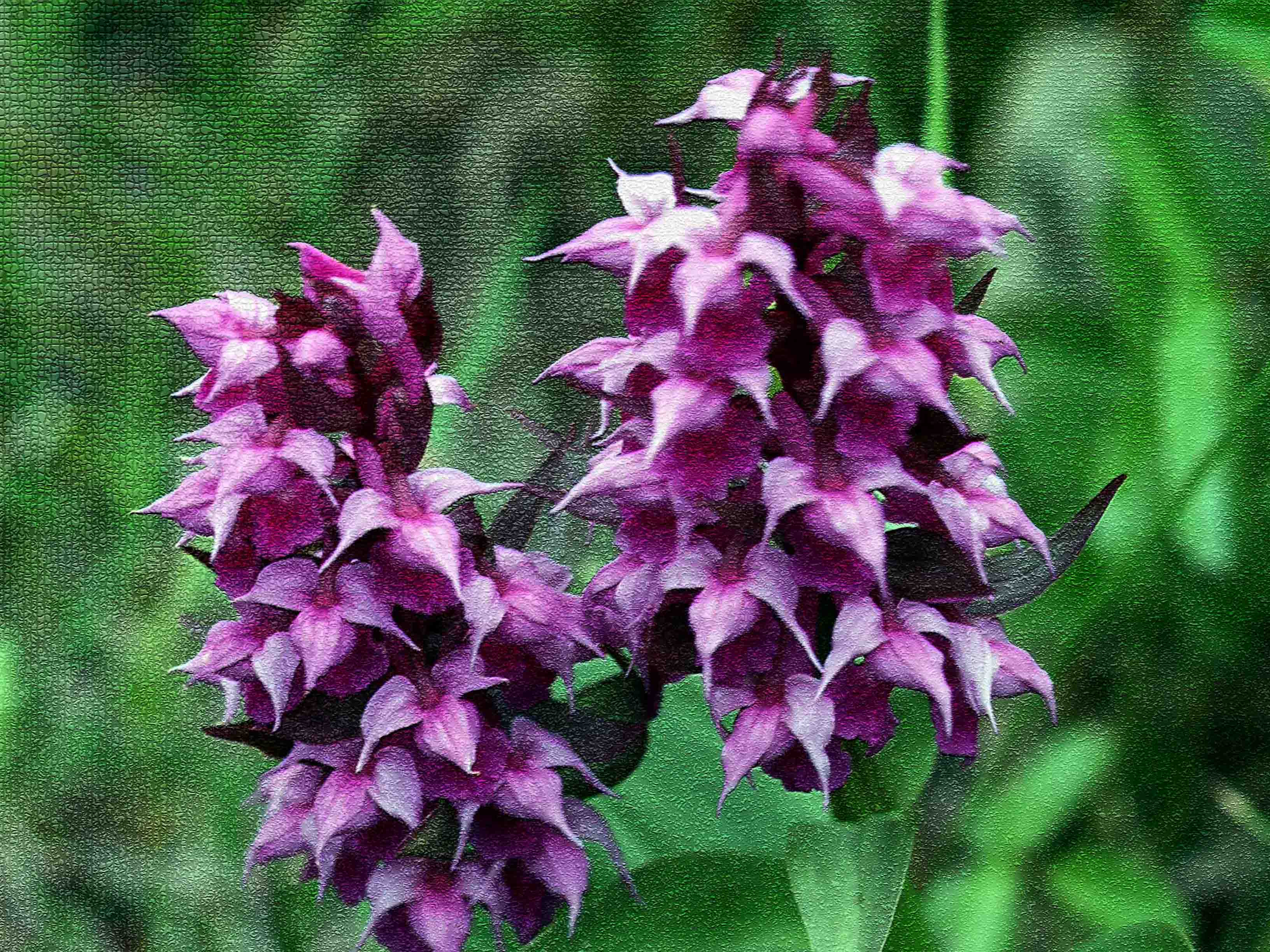
鑑賞御礼
小生の俳句は俳句のボリシーがない。その時々の感性で作句している状態です。しかし、皆さんに鑑賞して頂き、感謝して居ります。まだ、句評を頂いたものもありますが、正確に記憶しておらず、記録があるものを載せて見ました。句評をして頂いた方々の敬称は失礼ですが除かせて頂きました。
鹿寄するホルーン音色ト長調
芳彦
令和7年2月「「天心粲花(1)」
これが、ジャジャジャジャーンのハ長調だったら、鹿じゃなく鷹が鋭い嘴と爪で攻撃してきそうだ。だが、同じベートーヴェンでも、ト長調ならば、メヌエットやロマンスなど、優しく穏やかな曲ばかりだ。優しい目をした鹿が寄ってきそうである。
(古明地祐人)
この芽立ち山に谺の能舞台
芳彦
令和6年3月「天為」東京例会、日原傅主宰特選句
屋外の能舞台、佐渡などが有名ですがそういう所に行かれ、ちょうど季節としてはこの芽が出る頃、屋外の舞台なので声は山の方に響いていく。舞台の広々とした感じが見えてきます。
(日原傅主宰)
水澄むや仁淀川の青い石
芳彦
令和6年4月「天心粲花(2)」
石鎚山を源流とする仁淀川は、高知県のほぼ中央を流れる一級河川である。第五十三代天皇である平城天皇の第三皇子として知られる高丘親王が、京都の淀川に擬えて名付けたとの説もあるようだ。近年この仁淀川は、その良質な水質から、水面が青く見えることでも有名である、より青が際立って見えるのは、川床に白色や薄緑色の石が多い地点だそうだが、揚句も水がよく澄んだ秋の日に、美しい渓流を捉えた景であろう、実際には白っぽい石なのだろうが、水澄むの季語が、詩の世界の現実として、青い石を現前させているように感じられる。
(秋谷三春)
海石榴市の八十の衢に古典菊
芳彦
令和6年4月「天心粲花(1)」
奈良県の桜井市にあった古代の一大中心地。日本書紀や万葉集に「海石榴市(つばいち)の衢(ちまた・巷)」とある。
(大澤久子)
海石榴市の八十の衢に古典菊
芳彦
令和5年10月「天為」東京例会、日原傅主宰特選句
海石榴市は奈良県の桜井辺りである。昔、その辺りで市が立ったという古くからある固有名詞である。この俳句は「海石榴市」「八十の衢」雅な言葉を上手く入れた句である。今、歴史のあるこの場所で古典菊が咲いているのを見た。或いは、昔のことを思ったというようにも詠める。固有名詞が上手く入った句である。
(日原傅主宰)
伊吹野は銀河のほとり姫蛍
芳彦
令和5年6月「天為」東京例会、日原傅主宰特選句
伊吹野は琵琶湖の東、伊吹山の麓をいうのでしょう。そこは夜たくさんの星が見える場所のようです。その地に今日は蛍が舞っている。「伊吹野」「銀河」「姫蛍」という美しい言葉を並べて統一感のある世界が描かれました。
(日原傅主宰)
凍て星の一つ随ふ月の舟
芳彦
令和4年5月「天為」東京例会、日原傅主宰特選句
青いシリウスと三日月の繰り広げる天体ショーは、感動的で美しい。コロナ禍の楽しみの一つで会った。星になられた師を思いながら・・。
(永 伊予人)
母の忌の母の日傘の影の中
芳彦
令和4年1月 「天心粲花(1)」(選句)
母の命日に思い出された事であろう。子供のころ、母の日傘で強い日差しから守ってもらった。今も、この時と変わらず、母の愛情に包まれているとしみじみと感じた。
(梶 倶認)
夕暮れの月上元に鳰の群
芳彦
令和2年2月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
夕暮れの月上元がいいです。ちょうどいまごろで真ん丸になる。旧暦の一月十五日の満月です。元句の「上弦」では三日月のようになるから、「上元」にしました。このほうが正月らしくていいです。とても美しい句だと思います。
(有馬朗人)
潮満つるモンサンミシュル鳥渡る
芳彦
令和元年10月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
元の句は「雁渡る」となっているが、本当に雁が渡っていたのかい。あそこには雁はいないと思います。雁は大体東アジアの方にいます。行った経験があるのだと思いますが、本当に見たことを言いましょう。「鳥渡る」ならいいと思います。モンサンミシェルを持ってきたことはいいですよ。潮満つるもいいと思います。
(有馬朗人)
星月夜アララト山のターコイズ
芳彦
令和元年9月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
ターコイズはトルコ石。アララト山はノアの方舟の着いたところ。そこにトルコ石があり、星月夜にピカピカ光っていたというところがこの句の命。
(有馬朗人)
リュート弾くアルハンブラに後の月
芳彦
令和元年9月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
スペインのグラナダにあるアルハンブラは十世紀から十二世紀に掛けてこの地を支配したイスラムの作った宮殿。金色で右から書くコーランの字などがある美しい宮殿。とてもよい庭がある。そこでリュートを弾いているところがよい。
(有馬朗人)
クリオネの海の群青春浅し
芳彦
平成30年7月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
クリオネが今、たぶん北海道の海に浮かんでいるだろう。そのクリオネの海が群青であって、まだ春が浅いと言ったところが良いと思います。
(有馬朗人)
吟遊の白夜詩人の古リュート
芳彦
平成30年7月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
中世ヨーロッパ、自作の詩を朗読した吟遊詩人がマンドリンに似たリュートを演奏した。その古き伝統の楽器を見付けた処がよい。
(有馬朗人)
ヴァイキング丘陵涼しルーン文字
芳彦
平成30年2月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
ヴァイキングは八世紀後半から二百数十年、西ヨーロッパ沿海部に侵攻したゲルマン族。ルーン文字は、ゲルマン人の用いた古い文字体系。今この丘のルーム銘文に吹く風が涼しい。
(有馬朗人)
尼寺の筧音消ゆる村時雨
芳彦
平成30年1月 「天為」蒐玉抄
筧はそもそも静かに水を通す。それも尼寺のものと言えばやさしい幽玄なものであろう。その尼寺の筧が静かな音で水を流している所へ、村時雨が降って来た。その瞬間筧の音が消えてしまったのである。村時雨は普通と違って短い時間に急に強く降って通り過ぎる雨である。この句は尼寺の優美な筧の音の特徴と、村時雨という烈しい雨の降り方を結びつけて描いたところが巧みである。
(有馬朗人)
知と行の寒山拾得新樹光
芳彦
平成29年8月 「天為」課題入選句
賢者でありかつ隠遁者である寒山拾得。奇行に毀誉褒貶があったとされるが、作者は彼らの何物にもとらわれない純粋さに新樹光を重ね合わせている。現代の寒山拾得を待望するかのようである。
(西村我尼吾)
リー将軍刻む岩山星の降る
芳彦
平成28年9月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
リー将軍は独立戦争の南軍で負けてしまったけれども、殺されず、ワシントン大学の先生になる。軍人であり、学問もできて学長になった人です。その姿が岩山に刻まれている。その様子が見えて来て、よいと思いました。珍しい素材なので取りました。
(有馬朗人)
中庸を説く器に灌ぐ秋の水
芳彦
平成28年9月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
私も一緒に夏季鍛錬句会の足利学校でこれを見た。水を入れてないと傾いていて、水を入れるとちょうど水が平衡になった感じがするんですが、入れ過ぎるとばたっと水が零れてしまう。入れ過ぎてもいけないし、入れなくてもいけないという風にして中庸を説いたおもちゃみたいなものであり、秋の水を灌ぎ、そこを詠ったところがよいと思う。
(有馬朗人)
屈原の緑陰留む汨羅江
芳彦
平成28年5月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
自分は行かないけれど中国の句が出るだろうと考えて出した句でしょう。汨羅に、屈原が飛び込んで亡くなってしまう。入水の前に、「滄波の水清まば以て吾が纓(冠の紐)を濯うべし、水濁らば以て吾が足を濯うべし」というその汨羅江を見てきて屈原のことを思い出した。屈原がそこで涼んだであろう緑陰が残っていたというところが面白いと思います。
(有馬朗人)
早春の空の細波重力波
芳彦
平成28年4月 「天為」課題入選句
早春の空の発する細波を心に感ずる時、それは生の実感を手にしているときでもある。何がそれをもたらしてくているのかは明確に説明できないが、芭蕉が造化と呼んだ何者かの恩顧を感ずる時である。それは神の数式で物理学者たちがその存在を求めた重力波の存在の確信のようなものと通ずるところがあると作者は述べる。今年になってついに重力波の計測に成功したとのニュースが流れた。詩的洞察が科学的洞察により裏付けられた。なかなか深い作品である。
(西村我尼吾)
風邪の身のトレドに深く風の中
芳彦
平成28年3月 「天為」課題入選句
スペインの古都トレドを旅している。夕暮れになるとなじみの酒場に老人がワインを傾けている、そんなどこかなつかしい路地。入り組んだ坂道に風が吹く。過ぎゆく時間の迷路に迷い込んだかのような風邪の身である。
(西村我尼吾)
初茜パドヴァ劇場解剖図
芳彦
平成28年1月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
イタリアのパドヴァを訪れたのだろう。パドヴァ大学ではかつてガリレオが教えた。わたしも客員で呼ばれたことがある。この大学では、教会の反対をものとせず、世界初の人体解剖が行われた。階段教室の下が狭い部屋になっていて、そこから献体が上にもち上げられる。急のときは蓋をあけて献体を海に流す。
(有馬朗人)
越前の紙漉き唄や水の音
芳彦
平成27年12月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
越前、福井県の辺りでしょうか。このところ紙漉きが世界遺産になりました。その紙漉きの村に行ってみたら紙漉きの唄が聞えて来た。そして水の音が聞えて来るというところが美しくてうまいと思いました。
(有馬朗人)
月煌々少彦名も芋煮会
芳彦
平成27年10月 「天為ネット俳句」特選句
大国主命とともに日本の国造りをした少彦名と芋煮会という取り合わせが面白い。
芋煮会は昼間行われるので月夜の設定もおかしいことになるが、月を見ながら神話を
楽しんでいるということだろう。芋煮会の世界が広がった。
(対馬 康子)
風紋に影ひく駱駝なごり月
芳彦
平成27年10月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
砂漠に行って来られた。ゴビ砂漠に駱駝が影をひいているところがよい。そこまでは当たり前であるが、なごり月と持ってきたところがよいと思いました。
(有馬朗人)
星に星降る古都の夜に別れ霜
芳彦
平成27年5月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
どこの古都かわかりませんが、星がよく出てはれた古都に別れ霜となった。古都と星、春の終りの晴れた天の写生がよく、正確に詠っているとともに美しさが出ていると思います。
(有馬朗人)
塞翁が逃がした馬は仔馬連れ
芳彦
平成27年5月 「課題句」入選
作者は故事を踏まえ、それに新しい解釈を加えて、写生するという独自性を持っている。逃げた馬が仔馬を釣れて逃げたから、駿馬となって親子ともども帰ってきた時に幸運がもたらされたと感じた。しかし、その馬が落馬事故を引き起こし、不幸をもたらしたが、その傷のために戦争での死をまねがれるという運命の連鎖の起点となったのは親馬か仔馬かの意味を問うている。塞翁が馬と言う時の馬とは、逃げた馬でなく、この仔馬のことであると解釈して強調しているところが面白い。
(西村我尼吾)
春本を食らふや紙魚の懺悔文字
芳彦
平成26年8月 「天為ネット句会、互選句」
こうあってほしいと願う作者の観察願望がみえるおもしろい句です。
(原 豊)
嬋娟の花櫛に舞ふ落し文
芳彦
平成26年7月 「天為ネット句会、互選句」
艶やかで美しい女性の花櫛と恋の予感の落し文。
(小橋柳絮)
編鍾の旋律恋ふる楷若葉
芳彦
平成26年6月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句」
孔子の好きな楷の若葉が編鍾の旋律を恋うている。その昔、孔子も編鍾を叩いて心を慰めた。その編鍾の旋律を恋うるところが楷若葉らしいですね。
(有馬朗人)
妖精があまたケルトの夕菖蒲
芳彦
平成26年5月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句」
ケルトに妖精が沢山いたというところがよいと思う。ケルトはアイルランドですがアイルランドからスコットランドですが昔妖精が沢山いたという話と夕菖蒲の美しさを表現したところがよいと思う。
(有馬朗人)
クリスマス酢漬け鰊は魔女隠す
芳彦
平成26年2月 「課題句」
スウェーデンではクリスマスの後、イースターの祭の時に魔女が集まって話し合いしたそうである。その祭には、酢漬け鰊や羊を食べる習慣があるらしい。その時のためにクリスマスでは、魔女は酢漬け鰊を隠したのかもしれない。クリスマスという祭の原点に由来する人々の生活を北欧の伝説とを踏まえて、楽しい幻想の世界に遊んでいるところがよい。
(西村我尼吾)
ドナウ凍つ漁夫の砦に塔二つ
芳彦
平成25年12月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句」
ドナウ凍つ、と言ったところが新しくていいと思います。川の一景にそういう砦があって塔が二つあるところが面白い。
(有馬朗人)
水澄むや平安よりの掬ひ湯葉
芳彦
平成25年10月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句」
それは「きれいな句です。平安から湯葉は掬って食べるものだ、水が澄んでいる、いかにも湯葉のきれいな様子が見えてきます。湯葉の字は湯波・油皮・豆腐皮のどれがよいか考えて下さい。」
(有馬朗人)
水澄むや天平よりの機の音
芳彦
平成25年9月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句」
これは綺麗な句です。水澄んで天平時代からの機の音が聞こえて来
る。会津八一の「いかるがの さとのをとめは よもすがら きぬはた おれり あきちかみかも」の光景を詠っているのでしょう。まだ斑鳩の里には機織りが残っているのでしょう。
(有馬朗人)
杜鵑声の宝石拾ひけり
芳彦
平成25年7月 「天為ネット句会、互選句」
「声の宝石」音波を固体にして扱い、しっかりした詩が素晴らしい。
(菅野 強)
ほととぎすの声を宝石に喩えた所がすばらしい、「拾いけり」もお見事。
(浅井貞郎)
ゲルニカも丸木の図にも蛍舞ふ
芳彦
平成25年7月 「天為ネット句会、互選句」
人類の退化に対する警鐘句。
(伊是名白蜂)
我が家のゲルニカの絵の中に蛍を探すが見つけられ無かった。丸木夫妻もピカソも反戦の図、かって20代のころ奥様の丸木俊様と反戦と女の問題でパネラーとして同席した事を想いだしました。きっと蛍は死者の言葉〜。
(江原文)
初詣ヴァチカンの空澄み渡り
芳彦
平成23年6月 「課題句」
元旦に初詣としてバチカンにゆく人々がいる。日本人の得意とする見立ての美学ともいえるものである。日本の風景とは異なってもローマ法王の法話を聞くのも国際化の世の中では初詣と言えよう。
(西村我尼吾)
春近きギリシャ劇場碧き海
芳彦
平成25年2月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句」
原句「春近し」でしたがそこが切れてしまうので「春近き」としました。イタリアのシチリヤ島の光景を思い出しました。碧い海に面したギリシャ劇に春が近づいている。
(有馬朗人)
尼寺の丸窓開かず白薊
芳彦
平成24年8月 「天為ネット句会、互選句」
ひっそりと戒を守り白薊が美しい。
(關根文彦)
初日の出着衣輝くゴヤのマハ
芳彦
平成24年2月 「天為ネット句会、互選句」
スペインの宮廷画家ゴヤ。着衣のマハのシルクの輝は見事である。マハとは小粋な女ほどの意味。
(小橋柳絮)
昨年現地で見てまいりました。初日の出がいいですね。
(蛭川晶代)
天高く塞翁が馬肥ゆるなり
芳彦
平成23年11月 「課題句」
天高く馬が肥える。しかしその馬は塞翁が馬。人生万事塞翁が馬。これから何かが起こる。幸運な出来事が起こるのである。
(西村我尼吾)
空蝉やカラカラカーンと自鳴琴
芳彦
平成23年9月 「天為ネット句会、互選句」
空蝉が落ちてくるのに、カラカラカーンとオルゴールのような音がしたのかしら?童話の世界かな。
(蛭川晶代)
街角で天使が覗く夕薄暑
芳彦
平成23年7月 「天為ネット句会、互選句」
賑やかな街をそっとそっと天使が見ている、なんとも微笑ましい俳句です、 銀座四丁目和光近くに天使が路地を見ている像を思い出します.。
(齊藤昭信)
古寺の風の色濃しカンパニュラ
芳彦
平成23年7月 「天為ネット句会、互選句」
古寺に対してカンパニュラの洒落た花の名が利いている。
(安西佐和)
古寺に大陸偲ぶ韮の株
芳彦
平成23年6月 「課題句」
韮はユーラシア大陸が原産といわれている。しかしヨーロッパではあまり広がらず。紀元前後、中国で栽培が始まった。ここで読まれている大陸を中国と考えるのが普通だと思うが、更にユーラシアの面影が残っているとみるのも面白い。遥かシルクロードをこえてやってきた韮の株にはヘレニズム文化の趣が当然中国大陸を超えて届けられているからである。
(西村我尼吾)
裁ち板の母の箆あと梅匂ふ
芳彦
平成23年3月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句」
使わなくなって久しい裁ち板。梅匂うが句に奥行きを加えています。
(安光せつ)
アレッポ春黒き松種襤褸市に
芳彦
平成23年2月 「天為ネット句会」
素敵な句ですね、旅がしたくなりました。
(杉 美春)
雨井戸に白く光れり木の実落つ
芳彦
平成23年1月 「課題句」
この木の実には牧歌性をこえた超現実の美しさがある。現実を歌いながらそれを超えて詩的な、その言葉によって作り出される世界に読者を誘う。白く光って暗闇に落ちてゆく木の実に一瞬の中の永遠を見るようである。
(西村我尼吾)
雪兎淋しき夜には空を舞ふ
芳彦
平成22年12月 「天為ネット句会」
幻想的な白い姿が浮かびます。
(岡崎美代子)
詩情がありますね。
(朱 月英)
コスモスの夕日を集めサキソフォン
芳彦
平成22年9月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
サキソフォンでコスモスの夕日集めている。詩があってよい。
(有馬朗人)
三伏や遷都節目の奈良の塔
芳彦
平成22年8月 「天為ネット句会」
有馬先生はNHK俳句王国で塔の反りの美しさを翼と詠まれていましたが・・・・・。掲句からは遷都1300年のあつい奈良が感じられる句。出雲にも奈良へと続く天平古道があり、4月に夫婦で奈良を訪れ嬉しく思った。
(宮本よしえ)
ガウディの蜥蜴吐く水掬ひあげ
芳彦
平成22年8月 「天為ネット句会」
異才の建築家ガウディ。蜥蜴の吐く水はどんな味・・・・。私も飲んでみたくなった。
(宮本壮太郎)
未完成の神聖家族聖堂が浮かびあがる。
(蛭川晶代)
水去りし塩湖に水の蜃気楼
芳彦
平成22年5月 「天為ネット句会」
南米ポリビアのウユニ塩湖か。直径100キロメートル以上もある巨大なウユニ塩湖は最高地点が富士山より高いところにある。眼前に在るのは果てしない水のない塩湖と青空のみ。雲の上歩くような夏の塩湖の、捉えどころがない程の雄大な景観を「蜃気楼」という語があますところなく表現している。「水」を繰りかえし遣ったことも効果的。通りを歩く。
(熊谷かをるこ)
アンデスには何百キロと続く真白の塩湖がある。水の蜃気楼が立つのかよく分からないが、そうあってほしいという気もする。ちなみに、最近は、リチュームをとるために、塩湖が注目されている。
(荒尾保一)
鶯や礁に落す餌の毛鉤
芳彦
平成22年4月 「天為ネット句会」
鶯というと山と思われがちだが、意外に海辺にもいるのだ。それを詠んだのはめずらしいのではないか。
(土屋 尚)
カルタゴの軍港遺跡虎落笛
芳彦
平成22年3月 「天為ネット句会」
哀愁一入、U−ボートの基地も見えてくるのは何故だろう。
(三宮隆宏)
柳絮舞ふ鮮緑青なる偽刀貨
芳彦
平成22年2月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
中国では刀の形のお金を造っていたはずです。それを今売っている。偽であることは明らかであるけれども、柳絮が舞う中でその刀貨を見ると美しく感じた。緑青がとても美しいといったところが、良いと思います。
(有馬朗人)
仲見世の裏歩く癖切山椒
芳彦
平成22年2月 「天為ネット句会」
一年中、観光客で溢れている仲見世通りをさけて、土地っ子や浅草に詳しい者は裏通りを歩く。裏通りは浅草寺とは別の古刹も多くあり喧騒とは程遠い。この時期にしかない切山椒の淡い色彩と味がたのしみで老舗の和菓子屋に立ち寄り忘れずに買って帰ります。
(熊谷かをるこ)
仲見世は子供の頃からの遊び場だったのでしょう。仲見世の裏を歩いていると素の自分に戻れる作者の気持ちが伝わってきました。
(土屋香誉子)
雪蛍蘇州胡琴の律に舞ふ
芳彦
平成22年1月 「天為ネット句会」
雪蛍が胡弓の音律に乗って舞う”と言われて素直に納得。
(滝澤たける)
あたかも胡琴の上を雪蛍が舞っているようです。
(須田真弓)
フラメンコ終りて路地の朧月
芳彦
平成21年7月 「蒐玉抄」
フラメンコは今は日本でもアメリカでも見られる。私は東京でも、アメリカのサンタ・フェでも見た。カスタネットを鳴らし情熱的に躍りまわる。でもやはり本場のスペインそれも南部のアンダルシアで見るのが一番良い。私はグラナダの郊外の路地の奥の穴蔵のゆな所で見た。この句の舞台も路地であるからスペインの街であろう。フラメンコが終ったときは、空には朧月が掛っていたのである。フラメンコはジプシーに由来し東方音楽の要素が大きい。そしてアンダルシアにはムーア人が支配していた頃のイスラム文化の匂いがある。この句にもそのような雰囲気がある。
(有馬朗人)
ガウヂィの窓に下垂る浅き春
芳彦
平成21年3月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
スペイン。バルセロナにガウヂィの塔とか住居がある。そのガウヂィの作った不思議な家があって、その窓が溶ける様な格好に浅き春が下垂った。ガウヂィの溶ける様な建物の感じをうまく使っていて佳いと思う。
(有馬朗人)
クリオネのあそべる海の藍深し
芳彦
平成21年2月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
クリオネが季語になるかという問題ですが。クリオネは流氷とともにくるので有季定型として採りました。
(有馬朗人)
西行の碑石掌に触れ悴めり
芳彦
平成21年4月 「課題句」
西行という歌人の業績をたたえる碑文にさわった時、その石の冷たさに詩人の困難な道のりを実感した。そこに諧謔がある。
(西村我尼吾)
楼蘭の泉細し女玉響に
芳彦
平成20年11月 「課題句」
古語を駆使して泉を表現した。オアシスの都、楼蘭。女性のミイラも発見されている。シルクロードに繁栄し滅びた都市の泉。それを表現するのに万葉語の細し女や玉響という言葉をつかった。それぞれ美しい。玉の響くもどのはかないという意味。課題をこなすための努力を多としたい。
(西村我尼吾)
インヴァネス崩れし城や秋深し
芳彦
平成20年10月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
インヴァネスを作ったスコットランドの北部の地です。ネス湖が近くにあり、インヴァネス城も崩れて寂れた町になり秋も深いと思った。インヴァネスは冬の季語ケープ付の男性用外套ですので前書にスコットランドの北部の地とあるとよいと思います。
(有馬朗人)
オペラ座の怪人消えてソーダ水
芳彦
平成20年7月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
本物のパリのオペラ座を見て来たのですね。偉いですね。私は日本劇団四季のオペラ座の怪人を見ているけれど。やれやれ、オペラが終ってここにいた怪人も消え失せた。本当のパリのオペラ座に行かれた。ほっとしたところでソーダ水を飲んでいる。そこに面白さがあります。
(有馬朗人)
トレド初夏聖体祭の偽信者
芳彦
平成20年7月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
トレドの初夏、とてもよい所です。エル・グレコが最後に居た所です。聖体祭に紛れて、明るいお堂の中に入って行った偽信者が自分であるところがユーモアがあってよいと思います。
(有馬朗人)
メドッサの首石なるも余寒あり
芳彦
平成20年6月 「課題句」
メドッサの首石見れば石になる。石にならなかったが「ゾッ」とした余寒の実感がのこった。
(西村我尼吾)
筍や場所柄知らぬお前もか
芳彦
平成20年5月 「天為ネット句会」
突然顔を出す筍と 自称、気侭な私を並べた所が独創的。
(大山由美子)
円柱のトロイヤ遥か春の星
芳彦
平成20年3月 「天為」東京例会、有馬主宰特選句
有名なトロイ戦争の地トロイアに、円柱が建っていた。今、遺跡に円柱の跡が残っている。そのトロイアを遥かに望んで春の星を見ている。あるいは日本で春の星を見たときに、昔行ったあの円柱のトロイアは遠くだなと思ったのかもしれません。
(有馬朗人)