 |
 |
 |
生まれて初めてミヤマクワガタを採った!!いや、見たのはたしか 小学校低学年の時でした。父親の実家の岡谷へ帰省した時、 叔父が外灯下を歩くミヤマクワガタを拾い上げ 「お!クワガタムシがこんなとこ歩いている、ほれ!」 と見せてくれたのが初めてだったと思います。 当時の私は、クワガタムシと言えばノコギリクワガタの事で 足が長く、イガツイ体は逆に抵抗があり、触るのがとても怖く いまいち好きになれなかった記憶があります。 しかしながらどこでどう間違ったのか、ミヤマクワガタは 今現在私の一番好きなクワガタムシなのです。 |
| あきる野市 | |
| ここからは東京のミヤマクワガタについてお話したいと思います。私がホームページを立ち上げてからメールをいただくなかで 一番多い問い合わせ?質問?は、ミヤマクワガタはどこで採れますか?と言ったような内容のメールをたくさん頂きます。 たしかに市街地に住んでいるとそのへんの雑木林で普通にお目にかかれるようなクワガタムシではありません。 現に私もこの年になって再びクワガタムシにはまるまでは、ミヤマクワガタは、山地の外灯下の道路を歩いている以外は 採集したことがありませんでした。 「なんとかミヤマクワガタを樹液採集したい!」という思いが、この道にますますはまるきっかけになった理由の1つ でもあると自分では思ってます。話がそれましたが、ミヤマクワガタは、市街地住民の憧れのクワガタムシで あることは間違いない事実でしょう。 |
|
|
|
|
 |
私自身あまり興味はないのですが、ミヤマクワガタというと、呼び名を 大顎の形などで分類を3つに分けて呼んでいます。 世間一般では基本型、エゾ型、フジ型とか呼ばれております。 東京で私がよく見るのは、第一内歯が長いタイプです。 分類でいうとフジ型と呼ばれるタイプで大型種は、大抵この型です。 そのほかに基本型も見かけます。 東京でエゾ型は、まだ見たことがありません。 標高や生息環境に影響されているのかもしれません。 みなさんもミヤマを捕まえたら一度顎の形をよく見て見ては? |
| Lucanus maculifemoratus | |
|
|
|
 |
一度ミヤマクワガタを飼育してみるとわかりますが、コクワや ヒラタ、オオクワなどと違い、乾燥と高温に弱く、油断すると すぐに死んでしまいます。深山(ミヤマ)という名前からしても、 避暑地のような環境を好むクワガタムシというのがわかると おもいます。そんなイメージを東京にあてはめてみると 自然が豊富な多摩地区というのが頭に浮かんでくることでしょう。 山地・湖畔または丘陵の川がそばにあるような、高湿度の広葉樹林 まさしく多摩地区はミヤマの生息環境に近い自然がまだまだ多く 残っています。 下の図は、東京ミヤマ生息マップです。 |
| 青梅市のミヤマクワガタ | |
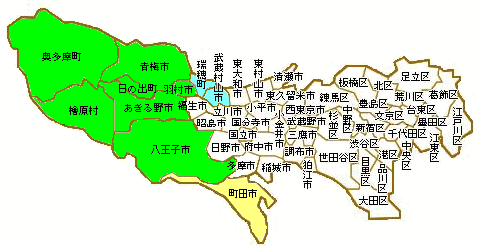 |
|
| 緑色は生息、水色はわずかに生息、黄色は私自身確かめてませんが生息していると教えていただいた市。 多摩市や日野市あたりもいそうな気もしますが確認がとれていません。 |
|
| 色塗りをみてもわかるように多摩地区に生息しており、奥多摩のようなブナやミズナラなどの山岳地帯や 青梅、あきる野、八王子のような低山地の里山のような高湿度を保った場所に生息してます。 |
|
|
|
|
 |
6月から西多摩地区の各地域で発生していると思われますが、 6月の上旬頃から奥多摩の外灯下で見ることができます。 奥多摩で採れるなら青梅、八王子のほうがもっと早く 見られるような気がしますが、都市部公園のクヌギ、コナラと 違い、ミヤマが好む里山の道沿いの木々は、樹液の出が 遅いため、6下旬ごろにならないとなかなか見ることがきません。 どうしても上旬頃から採集したいのであれば、丘陵地帯の ミズナラ、ハンノキ、カエデなどの細木を見て歩くか、樹液を 噴きだしてるコナラなどを探すとよいでしょう。 よくいわれるヤナギの木の採集は、東京の山岳、丘陵地帯周辺に おいてヤナギがあまりないためとても大変です。 私の考えですが、灯下の方がミヤマが早く見られるのは、たぶん 羽化したあと樹液を探してるうちに明かりが目に入り、そちらに 間違っていってしまったためではないかと思います。 東京で樹液採集をしたいのであれば、 早くても木々の樹液が出始める6月の下旬頃から7月まで。 また灯下採集であれば6月の上旬頃から9月上旬。 樹液採集において7月までとしたのは、樹液酒場の拮抗種である カブトムシが大量に発生してくると次第にミヤマクワガタは、影を ひそめ繁華街の飲み屋からマニアックな路地裏の飲み屋に 移動しているため見つけにくくなってしまいます。 好戦的なミヤマクワガタとはいえ、やはり王者カブトムシには 一歩譲らざるをえないのでしょう。 |
| 奥多摩灯火飛来のミヤマクワガタ | |
 |
 |
| 里山沿いのクヌギ・コナラ | 樹液酒場近くのサクラの木で様子をうかがっているミヤマ |
|
|
|
 |
奥多摩方面は道も険しく、有名なヤナギの木もほとんどないため 昼間林道沿いの木々を見て歩くような採集はあまり向いてません。 東京では、昼間の採集よりも外灯採集のほうがおすすめです。 奥多摩街道、周遊道、吉野街道、秋川街道、陣馬街道、高尾街道 甲州街道、日原街道、旧甲州街道、檜原街道、柚木街道など、 多摩地区を通っている街道の特定の場所において見つけられて います。(灯火採集の項を参考に) 樹液採集を楽しむには、昼間でも直射日光があたらない森の 湿度がある程度保たれている里山的なポイントのクヌギの木を 見つけておきましょう。樹液が出始めれば可能性大。 もし樹液酒場をカブトムシが占領していたらその木の周りの 樹液が出てない木なども探してみましょう。 ミヤマクワガタは隙あらば!と待機してるかのように木に 張り付いていることがあります。 (親子で楽しむ昆虫採集の項を参考に) |
| 林道のミヤマ採集の風景(私のお気に入りのショット) | |