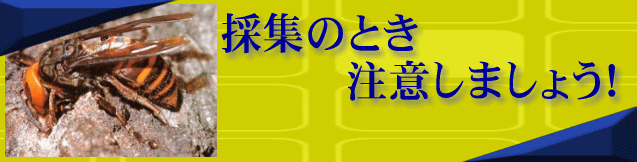 |
|
| クワガタムシ、カブトムシ採集でやっかいなのが、スズメバチと毒ヘビです。 ひとつ間違えると命に関わる危険があります。 |
|
 |
採集で一番多く出くわすのが、カブトムシ・クワガタムシと 仲良く蜜をすすっている黄色と黒のストライプ。 とにかくこいつを見かけたら怒らせない!おどかさない!立ち寄らない! とくに秋口の冬眠越冬前のスズメバチはとくに敏感になってますので きをつけましょう! 一般的に1回のハチさされで重いショック症状が生ずることは少ないと いわれてます。 (しかしながら初めてさされた場合によっても刺された部位などによっては まれにおきることがあるといわれています。) |
| ハチに刺されたときの症状は、ハチの毒そのものの薬理作用によるものと、 ハチの毒に対するアレルギー反応の2つがあり、局所症状と全身症状として現れます。 局所症状は、経験のある人ならわかると思いますが、赤く熱をもってはれ、痛みをともないます。 全身症状は、ショック反応です。 過去にハチにさされ、既に体のなかでIgE抗体が産生されている場合に、 もう一度刺されることによってアナフィラキシーが生ずるといわれてます。 (全身の蕁麻疹、呼吸困難、動悸、腹痛、発熱、血圧低下)等の症状を呈し、 ショックによって死に至ることもあります。 刺されたところ以外にかゆみが広がる、息切れがする、喘鳴がある、冷や汗が出る 意識が遠のくなどの症状があらわれたらとにかく受診してください。 夏の終わりから秋にかけては特にハチに刺される事故が多いです。 アナフィラキシーをもっとよく知りたい方は、こちらのHPを参考にしてください。 ハチ毒を持つものとしてはアシナガバチ、スズメバチ、ミツバチ、マルハナバチ等がおり、 このうち2つの主要なグループとして,ミツバチ類(ミツバチ,マルハナバチ)と スズメバチ類(ジガバチ,スズメバチなど)に分けられます。 ミツバチ類は従順で,通常は刺激しない限り刺すことはあまりないと言われてます。 ミツバチの針には複数のさかとげがあり,通常は刺した後に分離します。 スズメバチ類はさかとげをほとんどもたず,何回も刺すことができます。 中でもスズメバチの毒力が強く、アナフィラキシーショックの危険性が高いといわれております。 昆虫採集の最中にとにかくハチにさされたら刺入された毒針を取り除き、石けんと水で患部をよく洗って冷やします。 (ミツバチの場合は針に鉤があるため皮膚に残らないように気をつける。) 従来慣用されてきたアンモニア水の使用は、理論的には効果が期待できません。 (まちがってもオシッコなどかけないように・・・) 仕事柄よく蜂に刺された方のお話を聞くことが多く、大抵の人はアシナガバチの仲間に刺されているようです。 庭いじりしてたら突然チクッっとしたとか、ベランダで布団ほしてたら刺された。という話を聞きます。 実際、これにやられました!!などと見せてくれる人もいます。 ショック症状がなかったり、よほどひどくない限りは、ステロイド含有の軟膏が処方され様子を見ます。 虫にさされた時に毒を吸引する商品も販売されているので昆虫採集のときに持参しているといいでしょう。 「インセクトポイズンリム−バ−(デンマ−ク製)定価1000円」 「エクストラクタ−ポイズンリム−バ−(フランス製)定価3500円」 プラスチック製の注射器型で、先端のカップを虫に刺された患部に あてレバ−を引くとカップ内の皮膚が吸引されて中の毒を吸い出す。 エクストラクタ−のほうが吸引時の空気の流速が早いので刺されたあとの針を抜く毒虫などに有効です。 毒の吸引はさされてからすぐでないと効果が薄いのであくまでも応急処置程度で使用してください。 |
|
 |
林業などのお仕事をしている人は職業がらハチに刺されることが多く、 アナフィラキシーショックによる死亡事故が年間数例おきてます。 最近、蜂毒に起因するアナフィラキシー反応に対する補助治療薬でアナフィラキシーの 既往のある人またはアナフィラキシーを発現する危険性の高い人に限って使用できる 携帯用注射が発売されました。 誰でも処方してもらえるわけではなく、医療機関での使い方の指導などの教育を受け 医師の判断のもとに同意を得て処方してもらう注射器です。 使用法は、蜂にさされアナフィラキシ−症状などがでたと思ったら(衣服の上からも可) 太ももの前外側に注射します。1回限りの使い捨てです。 あくまでもアナフィラキシーに伴う症状を軽減させる効果だけなので使用後は、 必ず医療機関にかかってください。 |
|
|
|
| 私が勤めていた救急病院でも最近はあまり毒ヘビにかまれた−!という話はほとんど聞かなくなりました。 でもクワガタ・カブトムシ採りにちょっと雑木林のしげみの中に入ったりするとヘビを見かけることがあります。 とくに河川敷などの採集の時には十分注意しましょう! 私自身、ヘビの種類に詳しくないものですから見かけたら逃げる!とにかく立ち向かおうなんて気にはなりません。 もし、運悪くかまれたりした場合、毒蛇のかみきずは(マムシ、ヤマカガシなどの場合) 通常一対の牙痕が認められ、かまれた部分の疼痛、浮腫、時に皮下出血が認められます。 牙痕からの出血が止まりにくいなどの症状がある場合は毒蛇の可能性が高いといわれてます。 応急措置として テレビや本などでも見たことがあると思いますが 毒蛇にかまれた場合では咬傷部より中枢側を軽く緊縛します。毒素の拡散を防止するためです。 口で毒を吸い取ろうとしないでください。まちがって飲むこともありますし虫歯などから毒がまわることも考えられます。 ポイズンリムーバーを携帯してたら使用しましょう! 次に創部の清浄化 咬傷・刺傷ともにいえる事ではありますが、創部を水道水で充分に洗浄し、消毒液が手持ちにあれば消毒します。 抗毒素血清の投与は、受傷後6時間以内に投与するのが望ましいとされているのでただちに病院に受診します。 病院によってはその場に置いてない場合があるので、かまれたらすぐ受診することが第一! (血清を取り寄せる時間がかかるため) そのときできれば、ヘビの特徴を覚えておくとよいでしょう!(カラフルな色してたとか・・) かまれたときにアナフィラキシ−ショックを起こすこともあるので、昆虫採集の時は、 できるだけ2人以上で行動をするのがよいと思われる。(1人だと対処できない) といいつつもクワ馬鹿な私は、1人で行動をおこしてしまうんだよなぁ−。 |
|