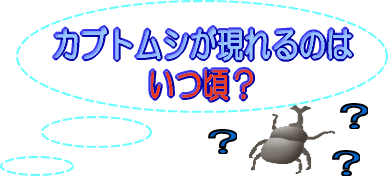
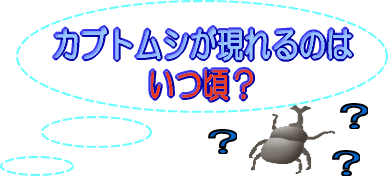
| 毎年、5月の連休がくると今年はいつ頃からカブトムシが見られるのかとっても気になりませんか? (そんなことが気になるのは私のような一部のマニアだけでしょうtが・・・。) 実際、出現日が予測できたらこんなに楽なことはないのですが・・・。 |
| スギ花粉の飛散開始日は1日の最高気温を1月1日から加算した数字(積算温度)で おおよそ予測できると言われています。(積算温度は関東以西で350〜400℃) ではカブトムシの出現時期も積算温度で予想することはできないだろうか? |
|
|
|
|
| 毎年データ収集を行っている青梅市のとある林 | |
 |
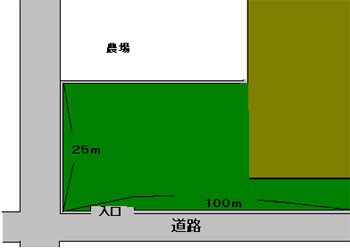 bbbbbgv bbbbbgv |
| 下草もほとんどなく整備されているふつうの林(近所の農業の堆肥作りなどに利用されている) 夏休みともなるとものすごい採集圧(たくさんの人がくる)のポイント 個体・・・・・・コクワガタが圧倒的に多く、ついでカブトムシ、ノコギリクワガタが少々見うけられる 緑色・・・コナラ・他落葉樹などでクヌギはない。黄土色・・・赤松主体でコナラは数本 道路沿いは日当たりもよく早い時期から樹液が出始める。 観測時間帯・・・・・5月GW明けの雨の日をのぞく7時頃から9時ぐらいの間での見回り なぜ青梅市かというと気象庁の東京での観測点に青梅市計測があるため |
|
| 青梅市のデータ 年度 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| かぶとむし出現日 | 5/26 | 5/10 | 5/28 | 5/25 | 5/19 | 5/21 | 5/27 | 5/3 | 5/11 | 5/17 | 5/16 | データ無 |
| 4月の夏日日数 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 4月に最高気温が10(℃)以下の日数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 4月の平均温度 | 13.3 | 14.3 | 13.2 | 14.2 | 13.2 | 11.8 | 11.7 | 13.2 | 13.7 | 10.9 | 12.6 | |
| 1月〜4月までの積算温度 | 1463.1 | 1613.8 | 1419.4 | 1671.3 | 1454.3 | 1429.3 | 1588.5 | 1439.6 | 1604.3 | |||
| 4月の日照時間 | 213.4 | 156.6 | 164.2 | 227.4 | 210 | 134.4 | 154.1 | 146.5 | 214.7 | 137.1 | 185.6 | |
| 約30度を最初に超した日 | 無 | 4/15 | 無 | 4/22 29.9 |
4/28 | 5/1 | 無 | 無 | 5/10 | 無 | 無 | |
| 5月の最高気温の日 | 5/20 | 5/5 | 5/7 | 5/30 | 5/19 | 5/20 | 5/23、27 | 10,20 | 5/21 | 5/21 | ||
| 4月の降水量 | 34.0 | 63.0 | 106.0 | 38.0 | 50.0 | 91.0 | 138 | 263 | 118 | 170 | 56 | |
| 5月から夜、昆虫採集する人はあまりいないという前提のデータ | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 青梅市のデータ 年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| かぶとむし出現日 | 5/10 | 6/4 | 5/15 | 5/13 | 5/19 | 5/6 | 5/23 | 5/24 | 5/17 | 5/18 | ||
| 積算温度でかぶとむしの出現は早いか遅いかぐらいは、簡単に判断できるだろうぐらいに私は思ってました。 ところが5年間のデータではまったく予想できませんでした。 2002年は、サクラの開花が異様に早く、本来なら入学式あたりに咲くのが卒業式にはすでに満開。 積算温度も高く、5/10に出現という納得のいく結果でした。ところが2004年は、2002年よりも4月までの 積算温度は高かったのになぜか5月の終わり頃までカブトムシを見ることができませんでした。 (たまたま見過ごしただけなのかもしれませんが他のポイントでもみられませんでした) 最初の1匹を見つけただけでデータをとるのはおかしいんじゃないかと思うかもしれませんが、不思議なもので 1匹見つけると各方面の林ででも、カブトムシに遭遇することができるのです。 なので何かしらのきっかけで早とちりのカブトムシは地上にでる時期を決めているのはたしかだと私は思います。 本来ならこのあと、日を追うごとにゾロゾロ出てきてもおかしくないのですが、これまた自然の摂理というか 不思議なものでカブトムシは6月の中旬すぎ頃にならないと一気に増えてこないのです。 このあたりの謎が積算温度に関わってきているような気がします。 |
| 5年間のデータをもとに2006年度は、5/20という予想をたててみました。 カブトムシは、サナギから成虫になるのに約20日平均かかりますので出現日から逆算すると必然的に 幼虫から蛹に変身する日がだいたい決まります。なのでその日あたりの気温を見てみますと 30度近くの最高気温を記録していたり、急に暑くなったりしているというのが読み取れました。 とくに2005年は、4/28.29と連日の30度超えの日々が続き、5月19日の暖かかった日の出現 というほぼデータとおりの結果となりました。 よって一部の早とちりのカブトムシは4月から5月にかけて気温が急に上がったりしたときに、体の中で まず蛹になるスイッチが入り、約20日間で成虫の準備をし、次に気温が高くなったりしたときに羽化し 地上にでてくるのではないかと思われます。 2006年は、5/1に急に暑くなりました。その暑さにつられて雑木林ではコクワガタもちらほら顔を だしていました。仮説からするとその20日後の5/20が出現予定日という事になります。 実際5/20は、午前中はよく晴れ「これは間違いないかな」と思うぐらい暑くなりましたが、夕方にかけて すごい雷雨となってしまい結果、夜見回ってみても発見できずじまいでした。 しかし翌5/21には、なんとか数匹のメスの確認がとれました。雷雨で1日ずれましたが はやとちりのカブトムシの出現予想としては、まずまずの結果だったとおもいます。 |
| 2008年5/3の出現は異常に早かったですが、ここ10年を見る限りだいたい5月中旬ごろの蒸した夜に 出現します。数はほんとに1匹〜数匹ぐらい。 最初の出現から毎日徐々に増えるかと思いきやそうではなく、数日の間見られなくなることがあります。 当たり前ですが本当の出現は、やはり6月に入ってからが本番なんでしょう! |