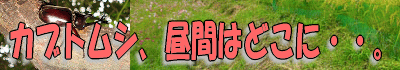 |
||
|
|
||
|
|
||
| なかなか夜、かぶとむし採集にでられなかった子どもの頃は、捕まえに行くと言ったらもっぱら昼間の公園や近所の林でした。 子どもの頃の知識というと、友達や学校の先生、親からの情報だけで 1.ゴツゴツした木にいる。2.蜜を出す木にいる。3.昼は土の中にもぐっている。ぐらいでした。 今思うとよくこんな知識だけで林に出かけてたなと思います。(でも運が良いとたまに捕まえられる事もありました。) 今は、昔と違いインターネットで探したり昆虫図鑑や雑誌も豊富で捕まえ方の情報は今よりもずっと多いと思います。 でも昼間の採集の説明に関しては、ちゃんと説明している本はまだまだ少なく、「かぶとむしは、夜行性で昼間は、木の根元や枯葉、土の中にもぐっている。」 というような感じで書かれている事が多いです。そのせいか公園などにある木の根元は、あたりかまわず掘られ根がむきだし状態なんて事があります。 木が傷まないようにちゃんと埋め戻しておいてくれればいいのですが大抵はそのままの状態です。 そういう私も子どもの頃は、木の根元を掘った記憶がありますが、その時捕まえたという記憶はありません。では、日中はどこを探せばよいのでしょう |
||
|
|
||
| 私が観察している限りでは、カブトムシは周りが明るくなってきたから「さあ隠れよう」とは思ってないように思えます。なぜかというと 6月頃夜、樹液場でイエローマーカーを付けたカブトムシは翌朝見に行っても大抵そのまま樹液を吸っています。 (カブトムシの数がまだ少ない時期、夜10時頃観察したカブトは翌朝7時過ぎてもその場で蜜を吸っています。) その夜、再度見に行った時はすでにイエローカブトの姿はなく他のカブトが占拠してました。その2日後の夜には再びイエローカブトは樹液場にいました。 カブトムシは夜行性ですが、ある程度お腹がいっぱいになるまでは樹液場にいて、お腹がふくれて「ハッ」と気がつく頃には周りも明るくなり気温も上昇し 「こりゃまずいぞ!」というようにあわてて隠れるのではないのでしょうか? 行動の優先順位として1.まず食事、2.交尾、3.隠れる(休憩) という事なのかも知れません・・。 |
||
|
|
||
 |
日中彼らが休んでいる場所は、樹が生い茂った枝の間、草むらの中、 枯葉の下、樹液が出ている木の根元などで暗くて涼しい場所に好んでいます。 でもそれは、全部のカブトムシに言えるわけではなく、7月の後半に入ると 樹液場のあちらこちらで日中からカブトムシが群がっている光景を目にします。 数が増え始めるカブトムシ甲虫類たちの需要と樹液を出す樹木の供給の バランスが崩れる頃から段々と昼間から彼らを見ることが出来るようになります。 私の考えですが、樹液を出す木はある程度数は限られています。 5.6月頃までは樹液酒場と甲虫の数は、なんとかバランスがとれており 夜の営業の時間だけで、ほぼすべての甲虫がなんとかお腹いっぱい食事がとれ 明るくなる頃には休む場所を求めて帰っていく。 そのため昼間からカブトムシ・クワガタムシを見る事があまりないと考えます。 ところが7月頃から甲虫たちが増え始めると夜の樹液酒場は常に満席状態。 場所取りで戦いに敗れたカブトムシ達は、勝者が消え去った後に一杯やるため 朝方、時には日中までも樹液酒場にとどまることになってしまうことになるのでは ないでしょうか。 |
|
| 奥深い森とかにある木ではなく、小学校の隣にある林のコナラです。 | ||
 |
 |
|
| 7〜8月の樹液酒場は常に戦闘状態 | 戦いに負け振り落とされたカブトムシたち | |
|
|
||
| 樹液酒場でたっぷり食事を取ったカブトムシたちは、樹液酒場からそう離れていない場所に外敵から身を守るように隠れます。 一番多いカクレ場所は、 1.沢山の葉に被われた木の枝につかまっている。 2.落ち葉に潜る、堆肥などの土の中で休む。 と個人的には考えております。 「木の根元などに隠れている」という表現は的確ではなく、雑誌・本などにこのように書かれているせいか 公園、ちょっとした空き地の林などの木の根元は、ザックリ掘られているという事が多々あります。 これは樹木にとってはいい迷惑です。根元に潜っている木は、大抵決まってます。 |
||
 |
 |
|
| カブトムシが根元にもぐる木は、根元近くに樹液がでています。樹液もでてない電柱クヌギやコナラなどの根元には、まずいる事はありません。 ただ、根元近くにウロがある木の場合は、そこに隠れているという事はあります。その場合でも樹液酒場から離れていない木に限られます。 |
||
|
|
||
 |
今年、神社のシラカシの大木の樹液酒場の前に折りたたみのイスを置き 夕方から夜にかけてじっと観察してたことがあります。農作業を終えた人や 神社に来た人から見ればとても変な男に思われたと思います。 夕方涼しくなる頃カブトムシ達は、どこからともなく飛んで来るとばかり思ってました。 ところがずっと観察していると羽音と共に木の上の方から飛びながら少しずつ 降りてくるのです。実は、昼間は木の上の方に隠れており、涼しくなった頃に 1匹また1匹と降りてくるのです。ただ全部が全部でなく一部は、やはり隣の畑の 方から飛んできました。そのカブトは♀で、背中に土が付いていたので羽化したてか もしくは産卵していたのかもしれません。 カブトムシ達は、お腹が満腹になると木の上の茂みの中にひっそりと隠れ また夜が来るのをきっとじっと待つのでしょう。 |
|
| この写真は樹液場から近いクヌギですが、カブトムシ達は、よ−く見ると目立たないようにひっそりと隠れています。 | ||
 |
||
 |
 |
|
| こういう木の茂みにも隠れてます。 | ちょっと草をどけると・・・。 | |
 |
 |
|
| 日中、草の葉裏に捕まって隠れてたりもします。 | 落ち葉の堆肥場の中 メスが比較的多いです | |
| 昼間、樹液が出ている木を見つけ、その木が大木であり葉が鬱蒼と茂っていたらその中に隠れているか、または半径10メートルぐらい内にある茂みを ちょっとかき分けて見ましょう。けっこう見つけられる確率高いですよ。 |
||
|
|
||
 |
左の写真は、目立つところにあるヤナギの木です。 昼間から根元付近でカブトムシが樹液を吸っています。 たまたま目撃したのですが、すぐ横の木でハシブトカラスがあきらかに カブトムシを狙っていました。 あわててカメラを用意したものの一瞬のうちにカラスは、カブトムシを挟み はらわた辺りを食べ飛び去っていきました。実際目の前で見ると何とも言えない 気分でした。 昼間、雑木林で、よくカブトムシのバラバラ死骸を見ますが、このように カラスのような鳥に襲われた痕か、タヌキなどに食べられたのでしょう。 |
|
 |
 |
|
| うえの写真を拡大、カブトムシがちゃんといます。 | 矢印にカブトムシはもういません。 | |
 |
 |
|
| ハシブトカラス | カブトムシの頭が転がりました。 | |