(08/3/16作成)
(08/3/4掲載)
クリティカル・エディション (英):Critical Edition
ちょっとアブない、子供には見せられないような出版物のことではありません(それは「エロティカル・エディション」)。
さるアマチュアオーケストラが、演奏会でドヴォルジャークの交響曲第8番を演奏することになったと思って下さい。パート譜は、以前使ったKalmus版があったので、そのまま使うことにしたのですが、本番の指揮者が来る前に団内の指揮者が使うために、やはり同じKalmus版の大判スコアを入手しました。ところが、練習が始まってみると指揮者のスコアとパート譜の間で細かいところに違いがあることが分かってきたのですよ。スラーやスタッカートがあったりなかったり、表情記号が付いていたり付いていなかったり、という具合です。同じ出版社のスコアから作ったパート譜であるはずなのに、この違いはいったい何なのでしょう。
そこで、いろいろ調べてみると、この出版社の楽譜にはどうやら2種類の版が存在していることが分かりました。そもそもこのKalmusというのは、自分のところで楽譜を作っているわけではなく、他の出版社が出版したものをそのまま印刷するという「リプリント」専門の出版社なのです。中には、まだ権利が生きているのに、正式のライセンスを取らずに出版しているという「海賊版」まがいのものも含まれています。まあ、でも、例えばブルックナーの「ハース版」のように、今では絶版になってしまっているものが容易に入手できるようになってはいるのですから、その辺は大目に見ることにしましょうか。
そこで、この「ドボ8」のケースですが、この曲が最初に出版されたのは1892年のことでした。出版社はそれまで彼の作品をほとんど出版していたドイツのSimrock社ではなく、イギリスのNovello社だったため、この曲は長いこと「イギリス」という愛称で呼ばれることになります(現在では、そんな無意味なタイトルを使う人は誰もいませんが)。この楽譜が、それ以後オーケストラでのライブラリーとしてスコア、パート譜とも広く使われることになるのです。ちなみに、その時点で彼の「1番」から「4番」までの交響曲は出版されてはいませんでしたから、この曲は「6番」、「7番」、「5番」(!)に続いて出版された交響曲ということで「交響曲第4番」という番号を与えられます。そして、この楽譜をおそらくKalmusは「リプリント」したのでしょう。
確かに、このオーケストラで使っていたパート譜にはこのように「No.4」の文字がありますね。
1956年に、現在のSupraphonというチェコの出版社から、作曲者の自筆稿をもう一度見直して、出版された楽譜のまちがいを正し、作曲者の意図が可能な限り反映された楽譜が出版されました。その作業には多くの音楽学者が参加し、自筆稿以外の資料も検討して最も正しいと思われる楽譜を作っていったのです。そのようにしてできた楽譜が、「クリティカル・エディション」と呼ばれるものです。日本語では「批判校訂版」、あるいは「原典版」と呼ばれます。
そして、この楽譜も、Kalmusがリプリントするところとなりました。こうして、同じ「Kalmus版」と言っても、複数のものが存在することになったのです。
批判校訂という作業の中では、必ずしも自筆稿のすべての音符を正しいものだとはとらえず、明らかに間違っていると思われるものは校訂者の裁量で別な形に直されます。そして、その課程を「校訂報告」というもので逐一報告してあるのです。それによると、例えば第4楽章の256小節目のチェロの4番目の音は、「Novello版では『h』、自筆稿では『c』となっているが、ここはNovello版の方を解決策とする」といったようなことが述べられています。
現在では自筆稿もファクシミリとして世に出回っています。ですから、この部分について、あくまで自筆稿にこだわって演奏している指揮者もあります(実は、自筆稿ではなくとも、例えば全音のポケットスコアなどでは、この部分が『c』になっています)。古くは1958年のコンスタンティン・シルヴェストリとロンドン・フィルとの録音(EMI)、そして最近では1998年の、ニコラウス・アーノンクールとロイヤル・コンセルトヘボウ管(TELDEC)や、2005年のチャールズ・マッケラスとプラハ響との録音(SUPRAPHON)でそれを確認することができます。さらに、あの下野竜也さんも、この「自筆稿版」を信奉されているお一人です。ただ、同じ校訂報告に259小節目の前半の三連符が、自筆稿では「十六分音符、十六分音符、八分音符」だとも述べられているのですが、そこまでやっている人はいないようです。
 |
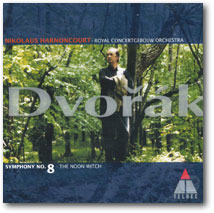 |
 |
| シルヴェストリ盤 | アーノンクール盤 | マッケラス盤 |
こんな風に、どの楽譜(資料)が最も作曲者の意志に近いものであるかの判断には、かなりの主観が入ってくる場合があります。従って、別な人が校訂を行えば、別な結果が出てくることもあり得るわけです。現に、2004年にはEulenburg社から新しいクリティカル・エディションが出版されましたが、それは多くの点でSupraphon版とは異なっているそうです。
今までは、そんな批判校訂の資料となっていたものは、紙に書かれた、あるいは印刷された楽譜だけでした。昔から楽譜といえば作曲家が五線紙にペンや鉛筆で書いたものと決まっていました。そして、それを印刷するときには、出版社の担当者はその手書きの楽譜を見て印刷用の原板(版下)を作ることになります。その版下は、それこそ大昔の銅板に直接刻み込むようなものから始まって、ごく最近までは烏口を使って紙に五線を書き、その上に音符をハンコのように押しつけていくというような、気の遠くなるような根気の伴う仕事によって作られていました。
ところが、そんな楽譜の事情も、最近では、コンピューターを使った楽譜浄書のシステムが確立され、それが印刷現場でも広く用いられるようになってくることによって、大幅に変わらざるを得なくなっています。中には、作曲の段階からすでに手書きではなく電子データによって楽譜を作る人も増えていますので、必然的に紙に印刷された物ではなくデータとして楽譜を見る機会も多くなっているのです。
それに伴い、将来は批判校訂の現場でもデータによる楽譜について検討を加える、という作業が出てくることになるのかもしれませんね。いつのことになるのかは分かりませんが、もしそのようなことが行われるような時代になったときに、もしかしたら起こるかもしれないある「事件」を実際に体験したものですから、それをご紹介させて下さい。
先日、さる合唱団で、武満徹の「小さな空」という曲を演奏することになりました。この楽譜はSCHOTT JAPANから出版されていますので、当初はそれを使っていましたが、それが演奏されるコンサートの構成上、その曲が歌われるステージの曲を一緒にまとめて1冊の楽譜集として印刷することになったのです。その演奏会のためにわざわざ編曲したものも多くありますし、なによりも200人近い合唱のメンバーのためにも、きちんとした楽譜になっていた方が扱いやすいからです。そこで、この武満の曲も、そのままコピーするのではなく、楽譜浄書ソフトで新たに作ったものを掲載することになりました。元の楽譜は繰り返しや最後のコーダなど、ちょっと使いづらいところもありましたし(もちろん、著作権の認可はきちんととりました)。その際に使われたのは、「KAWAIスコアメーカーFXII Pro」という、最新のヴァージョンのソフトでした。ご覧のように、小節の構成は変わりましたが、楽譜自体は元のもの(上)と全く同じものが出来ました。
しかし、これが印刷されてメンバーの手に渡ったときに、なぜかこのように、表情記号の一部が変わってしまっていたのです。
それは、歌詞が出てくる2小節前に付けられた2種類の記号です。まず、「<>」という、小さなクレッシェンドとディミヌエンドが組み合わされた特殊なアクセント記号です。非常に微妙なニュアンスを伝えるときに用いられる記号で、三善晃という作曲家が好んで使っていたことから俗に「三善アクセント」と呼ばれるものです。これは、「KAWAIスコアメーカーFXII Pro」でもきちんと「三善」という名前で登録されています。しかし、実際に印刷されたものでは、それがごく普通のアクセント「>」に変わってしまっています。それは、製本の際に他の曲で用いられていた同じメーカーの少し前のヴァージョンの「スコアメーカーFX」と印刷方法を統一するために、ヴァージョンダウンしたものにデータをエクスポートした際に発生した問題でした。古いヴァージョンではその「三善」がサポートされていなかったので、代用として普通のアクセントに変わってしまったのです。
同じことが、「mfp」だったものが「sfp」に変わってしまう、という、やはりサポートされていないものを代用のものに置き換えるという結果となって現れてきています。
どうです。電子データという形で保存してあったものが、それを楽譜として再現する際にソフトのヴァージョンが違っていただけで、これだけの違いとなって現れてしまうのです。これは、例えばシューベルトの自筆稿におけるディミヌエンドとアクセントの読み間違い以上に深刻な問題にはなっては来ないでしょうか。何十年か先には、もしかしたらこんなことが音楽学者の悩みの種になっているかもしれませんね。本当に「批判校訂」などというのは大変な仕事です。