
寶抸尰応丂俀侽侽侽擭俈寧俀俋擔乮壓抧崌斅揬傝姰椆乯

寶抸尰応丂俀侽侽侽擭俈寧俀俋擔乮壓抧崌斅揬傝姰椆乯
丂
7寧6擔偵抐擬嵽偺廩揢傪廔傢傝婥枾僔乕僩揬傝傪偼偠傔傑偟偨丅摴撿偵埵抲偡傞嬵儢妜嶳榌偺彫偝側嶳彫壆偱嶐擭偺墇搤傪宱尡偟傑偟偨丅偙偙偼敓娰巗撪偐傜30Km偔傜偄偟偐棧傟偰偄側偄偺偱偡偑敓娰抧曽偲偟偰梊曬偝傟傞壏搙傛傝傕彮偟掅偄傛偆偱楇壓20搙傪挻偊傞偙偲偑偁傝傑偟偨丅偲塢偆偙偲偱抔朳偑寚偐偣傑偣傫偑丄岠棪揑側抔朳偲壏搙嵎偵傛傞寢業傪峫偊傞偲偒崅抐擬丄崅婥枾偲寁夋姺婥偼愨懳忦審偱偡丅抧媴忋偺暔幙偱偁傞尷傝擬揱摫偼旔偗傜傟偢丄憢丄暻丄揤堜丄彴摍傪峔惉偡傞嵽椏傪捠偟偰幐傢傟傞擬検偼奜婥偲偺壏搙嵎傪僷儔儊乕僞乕偲偟偰擬娧棳棪偐傜寁嶼偡傞偙偲偑弌棃傑偡丅婥枾偵晄旛偑偁傞偲梊婜偟側偄擬偺弌擖傝偑惗偠寁夋捠傝偺姺婥丄抔朳偑擄偟偔側傝傑偡丅偙偺壠偱偼擬検偵偍偗傞僉儖僸儂僢僼偺朄懃偑寁嶼弌棃傞偙偲傪栚昗偵峫偊傑偟偨丅偙偺壠偺憤擬懝幐學悢偼147.86kcal/h亷偱偡丅奜婥壏偑-10亷偺帪偵幒壏傪20亷偵曐偮偨傔偵昁梫側擬検丄偡側傢偪寶暔傪峔惉偡傞嵽椏傪捠偟偰幐傢傟傞擬検偼奜婥壏偲偺壏搙嵎30傪偐偗傞偲栺5,000Kcal/h偑昁梫偱偡丅偙傟偼彫宆偺億僢僩幃摂桘僗僩乕僽偱傕廫暘側偼偢偱偡丅 |
|
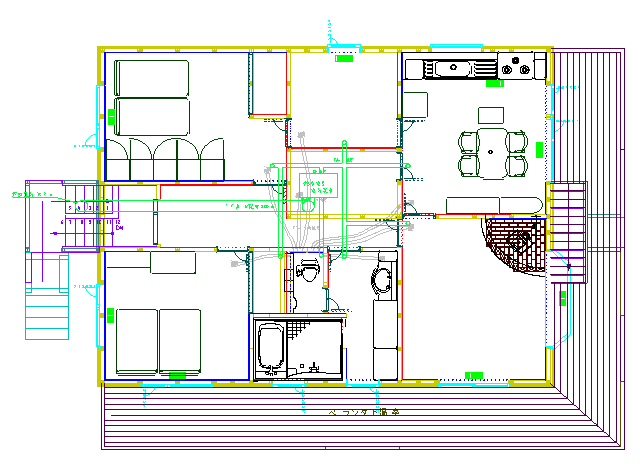 |
|---|
姺婥抔朳宯摑恾 |
崱傑偱偺岺掱偱偼揤堜偺攔婥僌儕儖丄攔婥娗儖乕僩偍傛傃僩僀儗棤偺娧捠僟僋僩偵捠偠傞僠儍儞僶乕傑偱姰惉偟偨丅屄暿攝娗傕100冇偲偟偨偐偭偨偺偩偑彫壆棤偺WBS偲偺擺傑傝偑偆傑偔偄偐側偄偺偱50冇偱懨嫤偟偨丅惷埑偺栤戣偑偁傞偐傕偟傟側偄偑丄廤傔傜傟偨娧捠僟僋僩傗姺婥憰抲偺攔婥媧擖岥偺懢偝偑100冇側偺偩偐傜7杮偵暘婒偝傟偨偲偙傠偑50冇偱傕偄偄偺偱偼丄偲偐偭偰偵峫偊偰偄傞丅 |
|
||
 |
 |
 |
|---|---|---|
2000擭7寧15乣20擔 壓弨旛 WBS偺傒側傜偢懠偺岺朄偱傕敪惗偡傞偺偩偑擖嬿晹暘偵偼僔乕僩傗崌斅傪棷傔傞偲偙傠偑柍偔側傞丅WBS岺朄偱偼崱夞揤堜埵抲傪WBS僽儘僢僋偺拞娫偵攝抲偟偨偨傔暻柺偵傕擖傝嬿傪峔惉偡傞摲墢傪30噊妏嵽偱捛壛偟側偗傟偽側傜側偐偭偨丅 |
2000擭7寧15乣20擔 僔乕僕儞僌僥乕僾揬傝 擖傝嬿偱婥枾僔乕僩摨巑傑偨偼僔乕僩偲峔憿梡崌斅偑傇偮偐傞偲偙傠偵偼僔乕僕儞僌僥乕僾偱栚挘傝傪擖傟偨丅僔乕僕儞僌僥乕僾偼50噊嬓丄堦姫偒20m偺僾僠僽儖宯偺嫮椡擲拝僥乕僾偱偁傞丅擲拝懁偵棸巁巻偑揬偭偰偁傝丄偦傟傪攳偑偟側偑傜揬傝晅偗傞偺偩偑堦搙揬傝晅偄偰偟傑偆偲攳偑偡偺偼帄擄偺嬈偩丅摿偵擖傝嬿晹暘偼擄偟偄丅偼偠傔偼條巕偑暘偐傜偢50噊嬓傪偦偺傑傑巊偄幐攕偟偨丅幐攕偺強嶻偲偟偰偁傒偩偟偨傗傝曽偼丄傑偢偼僥乕僾傪敿暘偺25噊嬓偵偡傞丅擖傝嬿偵偼棸巁巻傪晅偗偨傑傑偱嵶偄僪儔僀僶乕傪摉偰偰妏偵墴偟崬傒側偑傜棤懁偺棸巁巻傪壓懁偵堷偭挘傞偲偆傑偔捈妏偵揬傝晅偗傞偙偲偑弌棃傞丅偙偺曽朄偼20m姫偒1,000墌傕偡傞僥乕僾偺愡栺偵傕側傞偺偱堦嫇椉摼偱偁傞偑庤娫偑偐偐傞丅偦傟偱傕偙偺壠慡懱偺僔乕僩揬傝偱9姫丄9,000墌偺弌旓偲側偭偨丅 |
2000擭7寧15乣20擔 婥枾僔乕僩揬傝偺姰惉 嶌嬈偵柌拞偱搑拞宱夁傪幨恀偵廂傔傞偙偲偑擄偟偄偺偱傎偲傫偳偑堦抜棊偟偨抜奒偺幨恀偲側偭偰偟傑偆丅嶌嬈拞偼3抜偺媟棫偺忋偵懌応斅傪抲偒嶌嬈傪偡傞丅忋偺幨恀偼嫃娫偺搶撿偵岦偐偭偰嶣偭偨傕偺偩偑慜柺乮撿懁乯傪2枃偺僔乕僩偱揬偭偨屻丄堷偒屗榞偵増偭偰僇僢僞乕僫僀僼偱價僯乕儖傪僇僢僩偟偰奐偗傞丅偮偄偱揤堜偐傜搶懁偺暻偼堦枃偱堦嫇偵揬傝丄摨偠偔搶懁偺弌憢晹暘傪偔傝偸偄偰丄僔乕僩偺愙崌晹偵僥乕僾張棟傪巤偟偰偄傞丅尯恖偺傗傝曽偲偼堘偆偐傕偟傟側偄偑婡枾惈偼枩慡偲帺晧偟偰偄傞丅 |
|
||
 |
 |
 |
|---|---|---|
7寧21乣29擔 揤堜儀僯儎揬傝 揤堜儀僯儎傪揬傞偲偒偵偼偄傠偄傠弨旛偑偄傞丅傑偢偼揤堜崻懢偵偁傢偣偰僇僢僩偟偨儀僯儎偑偄傞丅5.5噊側偺偱栄堷偒偱傕愗傟傞偑帪娫偑偐偐傞偺偱夞揮僲僐傪巊偭偨丅掅偄媟棫偺忋偵懌応斅傪嵹偣丄塃庤偺撏偔斖埻偵崅偄媟棫傪攝抲偟丄偦偺嵟忋晹偵揃懪偪婡傪抲偄偰偍偔丅儀僯儎偺慜曽傪傒備偒偑枩嵨傪偡傞宍偱墴偝偊丄屻傠懁偐傜埵抲寛傔偲妏傊墴偟偮偗傞椡傪壛偊側偑傜偢傟側偄偆偪偵慺憗偔揃懪偪婡偱屌掕偡傞丅揃懪偪婡偺揃偼50噊偱僗僋儕儏乕偑擖偭偰偄傞偺偱堦搙懪偪崬傓偲儀僯儎傪攋傜側偄偲揃傪敳偔偙偲偑弌棃側偄丅堦枃堦枃側偐側偐崪偺愜傟傞嶌嬈偩偭偨丅 |
7寧21乣29擔 愇峱儃乕僪揬傝 愇峱儃乕僪偼儚乕僪儘乕僽偺棤偲僗僩乕僽偺儗儞僈慻偺攚柺偵巊偭偨丅摉弶偼慡晹峔憿梡崌斅偱暻揬傝傪偡傞偮傕傝偱崌斅傪梡堄偟偨偺偩偑丄嵽栘壆偝傫偑偪傚傠偭偲儃乕僪偺抣抜傪岥偵偟丄偦傟偑偁傑傝偵傕埨偄偺偱傎偲傫偳怗傟傞昁梫偺側偄晹暘偵巊偭偰傒傞偙偲偵偟偨丅崌斅偼9噊丄愇峱儃乕僪偼9.5噊岤偱偁傞偑揬傝廔傢偭偰傒傞偲傎偲傫偳晄棨偼婲偙傜側偐偭偨丅 |
7寧21乣29擔 揤堜仌暻壓抧崌斅揬傝偺姰椆 揤堜偲暻壓抧偑弌棃忋偑傞偲晹壆傜偟偔側偭偰偒偨丅 |
|
||
 |
 |
 |
|---|---|---|
7寧30乣7寧31擔 攔婥娗偺愝抲 奺晹壆偺僐乕僫乕偺攔婥僌儕儖偐傜僩僀儗棤忋晹偺僠儍儞僶乕傑偱偱偁傞丅揤堜棤偼僽儘乕僀儞僌300噊傪梊掕偟偰偄傞偺偱偦偺拞偵偍偝傑傞傛偆偵丄妿偮丄弌棃傞偩偗嬋偑傝偑弌棃側偄傛偆偵攝娗偟偨丅忋偺幨恀偱偼5杮偺攝娗偑幨偭偰偄傞偑僠儍儞僶乕偺嵍塃偵傕偆堦杮偯偮丄寁7杮偱偁傞丅 |
7寧30乣7寧31擔 攔婥僌儕儖偺庢晅 攔婥僌儕儖偲抐擬僄儖儃傪慻傒崌傢偣偰愙懕偡傞丅攔婥僌儕儖偺奐岥晹偼130噊妏偱偁傝丄偙傟偼帯嬶傪嶌偭偰偍偒丄偦傟傪摉偰側偑傜僩儕儅乕偱寠傪偁偗偨丅攔婥僌儕儖偼奺晹壆偺僐乕僫乕300噊晅嬤偵攝抲偟偨偄偺偩偑丄僄儖儃偺愙懕岥偑偁傑傝偵傕暻偵嬤偔側偭偰偟傑偄攔婥娗偑偆傑偔偍偝傑傜側偄丅傗傓側偔WBS偺墶榞偵70噊偺寠傪奐偗偨丅偙偺偨傔偵杮奿揑側70噊偺儂乕儖僜僂乮17,000墌乯傪峸擖偟偨丅 |
8寧2擔 攔婥僠儍儞僶乕 僩僀儗棤偵偼偼偠傔偐傜GF-1F偺娧捠岥傪奐偗偰偁傞丅摉弶偼CS乮働乕僽儖僔儍僼僩乯偺偮傕傝偱揹婥宯摑摍偺娧捠岥偲偟偰懡栚揑偵巊偆偮傕傝偩偭偨偑丄婡枾偺栤戣偑偁傞偨傔丄寢嬊偼僩僀儗梡攝娗偲姺婥儖乕僩偩偗偵巊梡偡傞偙偲偲側偭偨丅僩僀儗偺揤堜晹暘偵攔婥娗傪廤傔傞僠儍儞僶乕傪嶌傝丄偦偙偵攔婥娗傪廤傔偨丅忋偺幨恀偼庤慜偲忋偺晹暘偑傑偩傆偝偑傟偰偄側偄忬懺偱偁傞丅偙偙偵廤傔傜傟偨攔婥偼GF傊捠偠偰擬岎姺宆姺婥憰抲傊愙懕偝傟傞丅 |