
建築現場 11月17日(土台&GFのコンクリート完成)

建築現場 11月17日(土台&GFのコンクリート完成)
すでに11月11日(木)から家の組立に入っており、同上は木枠を取り去って、GFのコンクリート部分の形が見えるようになった時の写真す。従って、1Fスラブ上にはすでに家の骨格部分(WBS)が一段分組み上がっています。WBSの詳細は本レポートのメインですので次回に詳細の報告します。 |
基礎及びGFのコンクリートの製作工程
|
||
 |
 |
 |
|---|---|---|
10月22日(金) GF土台スラブの鉄筋配置完了 |
10月23日(土) GFスラブコンクリート流し |
10月24日(日) GFスラブ完了 |
25日から腰壁用の木枠を取り付ける作業に入った。鉄筋はすべてダブルで150㎜厚である。開口部には木枠を挿入したのでアルミサッシはねじ留めで取り付けることが出来る。この作業はほとんど家を建てる作業と同じで天井スラブまで木枠が全部出来たところで一挙に生コンを流し込むのことで一体化し強度を出している。 |
||
 |
 |
 |
|---|---|---|
10月26日(火) 腰壁の配筋 |
10月27日(水) 開口部への木枠挿入 |
10月30日(土) 梁および腰壁枠完了 |
本宅の内部 |
|
GFと1Fは熱的に完全分離するため、使い勝手を犠牲にして内部に階段を設けなかった。このため、面倒でも1FからGFへ行くには玄関から風除室経由で駐車場への階段を下りるか、東側のベランダから木製の階段でベランダ下温室へ入り工作室へ行くルートしかない。 |
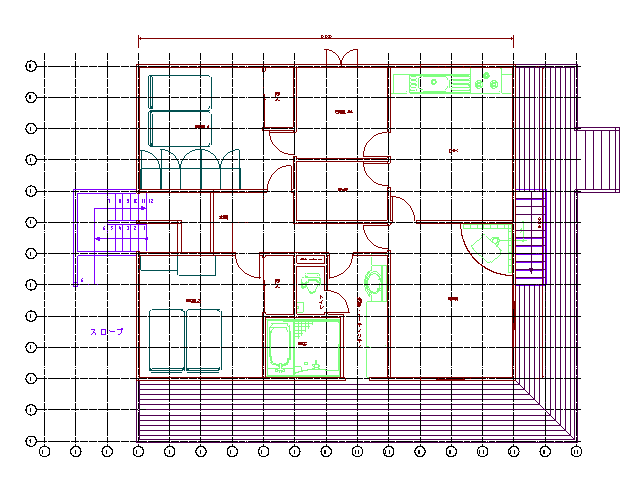 |
|---|---|
GFは冬や雨天の時の活動拠点を確保することと、1Fの居住空間をサポートするために使われる。電気および調整空気を作り1Fの居住空間を快適な状態に保つと同時に居住空間の廃熱を利用して、GF部分も暖めることにより温度差を無くすように北側のコンクリート壁は半分を盛り土すること、南および東の一角はベランダ下温室を作りコンクリート壁からの直接的に熱が逃げるのを防いでいる。 |
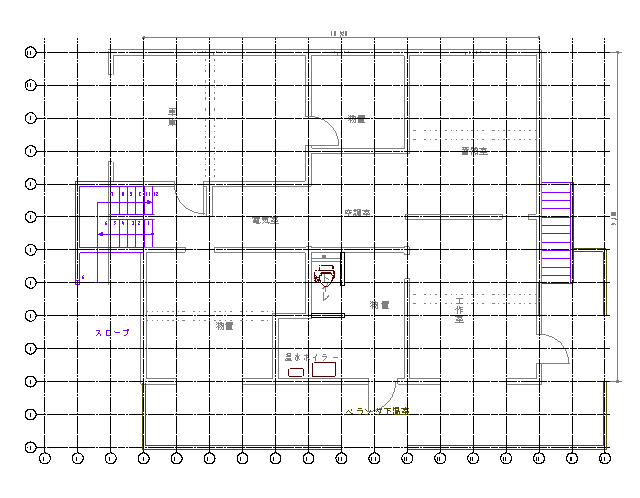 |