| ■連載 |
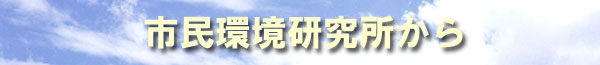
<第11回> 市民とともに活動する研究者の育成に向けて |
(ニュースレター No.19号掲載) |
| 1970年代にふたつの海を、若者を満載して2隻の漁船が走っていた。プロ集団とは比較にならないお粗末な装備で、水を汲み、泥をすくい上げている。ふたつの海と書いたが、ひとつは瀬戸内海であり、ひとつは琵琶湖である。公害が激化し、大学闘争が強力な警察力とモノを考えない大学当局によって鎮圧された大学から、公害の現場に新しい科学を模索しようと出て来た若者たちである。そこには、権力的に振る舞う教授はいない。その代わりに海域、水域の汚れを生業の中で見続けてきた漁師が居る。権力的ではないが、より厳しい目を持って若者を見続け、チェックし、時としては苦言を呈する存在である。港々を渡り、漁師の話を聞き取り、分析試料を採る。集団の名前は「瀬戸内海汚染総合調査団」と「琵琶湖汚染総合調査団」である。それぞれの調査団は多くの成果を社会に発信し続けた。 爾来、30年の歳月が経過し、昨春と今春に両調査団のメンバーの2人が大学を去った。1人は神戸大学を退職した讃岐田訓であり、もう一人は筆者である。讃岐田は播磨灘にこだわり続け、神戸空港反対運動の先頭を務めている。筆者はその後、中央アジアのアラル海にフィールドを移した。十数年後の去年から、2人は「20年目の琵琶湖調査団」に参画して、一緒に琵琶湖を走っている。 公害問題が各地に多発し、被害者住民からの毒性物質などの分析依頼を受けて、被害者とともに環境調査を行う研究者が関西の大学には多数いた。彼らはそのような科学的営為の中から新しい科学を創造する道を開こうとしており、研究室で住民・市民とともに分析作業に明け暮れ、関西の反公害運動の重要な一翼を担っていた。まさに、開かれた大学として彼らの研究室は機能していたのである。そのような研究者が次々と大学を去り、分析拠点として住民が利用できた最後の研究室が讃岐田研究室であったが、残念ながらそのような拠点が消えたのである。 前述した「20年目の琵琶湖調査団」は昨年から始まった、琵琶湖の汚染を総合的に把握するための研究者、学生、市民の合同調査活動である。これに参画する筆者の思いは、もうひとつあった。それは、市民とともに活動する研究者の発掘と育成である。このふたつの目的が達成できたかどうかを世に問う企画が、若手研究者・技術者・市民によって進められている。2004年8月26日から29日までの4日間、滋賀県湖北町尾上の漁業会館で開催される「琵琶湖市民大学」である。本誌読者諸氏にもぜひ参加いただきたい。市民とともに、現代社会の矛盾に立ち向かう研究こそが「開かれた大学」である。残念ながら、国立大学の独立法人化はまったく別の方向へと大学を導いている。そこには、市民の依頼で働く研究者を育成する雰囲気はない。調査団に参加した若い研究者を励まし、育てるためにもぜひ参加・支援をお願いしたい。 (石田紀郎) ※20年目の琵琶湖調査団のホームページを見てください。 http://hesl.xuu.jp/20biwa00.html |
Copyright (C ) 2004 地域・アソシエーション研究所 All Rights Reserved.