| ■連載 |
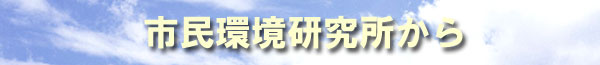
<第8回> きびしい生業の中での百姓の実践こそ突破口 |
(ニュースレター No.29号掲載) |
| 我が国の農業が厳しい社会的、経済的状況下にあることは今さら書くまでもないことで、前号で話題とした省農薬ミカン園もその埒外にあるわけではない。このミカン農家は老夫婦2人で約1.3町歩を栽培しており、70才を越えた2人ではこれが上限の栽培面積である。木の本数は1300本で、収穫したミカンの全量20トンを、私が理事長をしている生協(エル・コープ)と、京大農薬ゼミでさばいている。ありがたいことに毎年完売しているから、少々生産量が低い省農薬ミカン栽培であるが、農家としての経営はまずまず成り立ってきた。 ところが、この園は1970年代に開いた園で、当時としては普通の栽植密度で木が植えられているから、木と木の間が1.5間しかない。30年も経ち、成長も著しく、壮年期に入った木々は隣の木の枝と絡み合っている。この混み合った木の間をぬって肥料を運んだり、収穫したミカンを運び出すのは、若者でもそうとうきつい仕事である。腰をかがめて、枝に遮られながら、斜面を上り下りしなければならない。まして、70才を越えた老夫婦には過酷すぎる。16才からミカン一筋に生きてきた百姓だからこそできるのだが、ここらでもう少し楽な農業へと転換しなければ、この先やっていけるだろうか、と不安を覚えたのは数年前である。 本数を減らすため間伐し、木と木の間を広くすれば歩き易くなるが、それでは収穫量が減ってしまう。小さな区画で実験的に間伐を実施し、収量の変化の観察もした。木に勢いのあるうちに間伐をして、残った木を大きくし、日当たりと風通しを良くすれば、病害虫も減少するだろう。「どうや、思い切って間伐しませんか」と去年の暮れに尋ねてみたら、「早うやってや」と答が返ってきた。 毎年、秋の収穫時には、実ったミカンの一つたりとも地面に捨てることができないのが、百姓の心情である。まして、30年も育てた木を切り倒すのは、つらくないわけがない。しかし、80才まではミカン栽培を続けるという目標を達成するためには、農作業が可能な環境を作らねばならない。 2月末にまず100本を切り倒す。農家の生計を左右しかねない決断である。農業とは、土地の風土と農業者の種々の条件がかみ合って成し遂げられる生業である。限定された条件の中で、環境と生産物を汚染しない省農薬農業を目指してきたこのミカン園は、農薬問題の先駆的存在である。今やろうとしている間伐は、農業者の高齢化という日本農業が当面している課題の先送りにしか過ぎないかもしれないが、この園での省農薬の取り組みが全国のミカン栽培に拡がるまでは止めるわけにはいかない、というこの百姓の意気込みなのである。「地球にやさしい」とか「環境にやさしい」とか、環境問題を口にすれば「良い人」のような社会風潮が蔓延しているが、きびしい生業の中でのこの百姓の実践こそが環境問題解決の突破口になるだろう。 (石田紀郎) |
Copyright (C ) 2004 地域・アソシエーション研究所 All Rights Reserved.