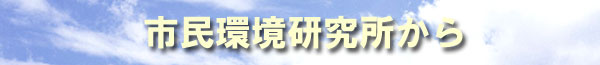|
暖冬に慣れてしまって、少し寒気がやってくると肩をすぼめて、情けない格好で歩いてしまう。40年前の京都はもっと寒かったが、我が貧乏学生の下宿部屋には暖房器具などまったくなかった。同じ下宿屋に4人が住んでいたが、電気ゴタツを持っていたのはたった1人で、どうしようもなく寒い夜は彼の部屋に4人が集まった。4人が集まると当然のように麻雀が始まる。背中にコートを肩掛けにしてすきま風に耐えながらの夜更かしである。最近の学生達が麻雀をやらなくなったのは、非科学的な結論であるが、彼らが暖かい個室を確保しており、寄り添って寒い冬の夜を耐えていないからだと思う。
前号で和歌山のミカン山に調査に出かけていたことを書いた。和歌山県海草郡下津町大窪のミカン専業農家と協同して、「省農薬ミカン栽培」を25年間継続している。我が国の農業全体が農薬一辺倒になっていた1970年代に始めた「省農薬の試み」である。爾来25年、このミカン園での病害虫発生や収量に関する調査を、京大農薬ゼミという自主グループで継続してきた。
始めた頃は、農薬全盛期であり、省農薬などは社会から歯牙にもかけられず、研究者からも農民からも非常識と非難されたものである。しかし、30年が経過した今では、当時の非常識は省農薬や無農薬が主流とはいかないが常識になりつつある。非難し罵倒した当時の研究者たちは、長年の主張のように農薬多用を戒める発言をしているのだから、研究者ほど信用できない者はない。しかし、市場はまだまだ旧態依然である。省農薬ミカンは残念ながらと言うか、当然のこととして、外観・見栄えは悪い。きれいな物がおいしい物と錯覚してしまった(錯覚させられたと言うべきかもしれないが)消費者は、見栄えのしない物を買ってはくれない。だから、市場の大勢はきれいなミカンだけである。きれいなミカンを収穫するには、農薬を十数回散布しなければならない。
この省農薬ミカンをいかに販売するかは、農家にとっての大問題である。そこで、農薬ゼミが全量販売することにしている。1町歩のミカン山からは毎年15トンの収穫があるから、10キログラム箱で1500箱を売りさばかなければならない。販売に関しては素人集団であるが、20年の経験の蓄積から、相当手際よく売りさばいてきた。15トンもさばく小売店は京都市内でも少ないだろうと自負している。
ところで、このミカン販売の大敵は暖冬である。10月から注文を取り出すが、11月下旬になっても寒さが来ないと注文は伸びない。どうしようかと悩んでいるところに、寒波がやってきてくれ、どこの家でもコタツを出し始めると、注文がやってくるようになる。コタツに入りながら、ミカンを食べる。このセットが日本の冬の家庭風景なのである。コタツとミカン。かくして、ありがたいことに今年も省農薬ミカンを完売した。オール電化・暖房の時代になり、家庭からコタツが消えたら、我が国のミカン消費動向はまた変わるのだろうか。
(石田紀郎)
|