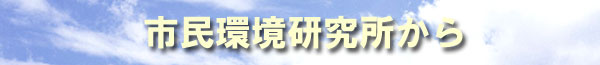市民環境研究所は京都の東大路通りに面したビルの3階にある。大路を走る車の多さと騒音にうんざりするが、「やかましい」と思う時は、仕事が嫌な時か、仕事に集中していないからである。ところが、この数日前からは、気分に関係なく「やかましい」。いよいよ総選挙である。ここ京都2区は自民、民主、共産党の3名が争う。ビルの前に共産党候補の選挙事務所があり、朝昼晩とその挨拶を聞くことになる。あとの2名は、スーパーマーケット形式になった公設市場の前で街頭演説をする。それぞれの党の主張が、嫌でも耳に入ってくる。どの候補者も国家財政を中心演題としており、いまだに環境問題を重視した演説には出くわさない。選挙の争点とならないのは、市民の関心も思いのほか低いということか。
前号で、沙漠の国、カザフスタンの水のことを書いた。沙漠にある、世界第4番目の大きさを有した湖・アラル海は、縮小に縮小を重ねて、あと数年で干上がってしまう状況にある。旧ソ連邦政府が進めた大規模な潅漑農業の開拓で流入河川から大量に取水したために、アラル海への流入量が激減した。1960年代以降のことである。そして、わずか30年の間に、アラル海は消滅寸前となった。
その影響の詳細は割愛するとして、このアラル海に漁業を生業として暮らしていた20万人ほどの漁民は、職を失うことになった。彼らは牧畜に移行するか、遠くの町に移住した。700軒近くあった漁村は、今では200軒足らずにまで減っている。いまだ全貌が掴めない地域環境変化のもとで、人々は経済的にも苦しい日々を送っているが、カザフスタン政府もウズベキスタン政府も確たるアラル海再生計画を示さなかった。首都から2000キロも離れた沙漠の民は、捨て置かれたままである。それでいながら、両国政府とも国際会議では、アラル海問題は世界の問題であり、人類史上最悪の環境破壊であると主張する。
まさに、アラルの悲劇は政府が海外援助を引き出すための口実にだけ使われているのである。その現実の中で、被害者は切り捨てられていく。水俣病の患者がそうであったように、我が国だって例外ではない。まさに、棄民である。つまり、アラル海は4度死んでいく。まず、水溜まりとしての死、ついで、生き物達の死、漁民の死があり、最後には地域の死が訪れる。最後の死こそがもっとも残酷な死ではないだろうか。
日本とて、深刻な環境破壊の時代から脱出できない現状である。時間をかけ、経費をかけて社会構造、産業構造を変えない限り、現在の環境問題は解決しない。誰がこの国の環境問題に取り組んでいく力と知恵と気概を持っているのだろうか。しばらくは、「やかましい」通りを眺め、演説に聞き耳を立てながら、考えて見ることにしよう。
(石田紀郎)
|