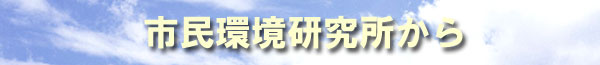「金は天下のまわりもの」と言われるが、とうの昔に、これはウソであることは分かっている。貧乏人が自分を慰めるために使っていることばである。金持ちは自分のところにたっぷり貯めていて、余所には回すはずもない。かくして、富は偏在するのである。 さて、「水は天下のまわりもの」なることばがあるかどうかは知らないが、これは当たっている。地球上の水は天下を回り、留まることはない。水循環は、地域規模でも地球規模でも、年間を通じて動き続ける。しかし、天下を回っているが、これもまた、貧富の差を地球規模的に発生させている。「水の不平等」は、自然の摂理として地球上に厳然と存在する。
年間降水量が1800ミリもある日本は、先進国の中でもダントツに雨の多い国である。先進国首脳会議(G7)に集まってくる国々で、年間降水量が1000ミリを越えるのは日本とイギリスだけである。ただし、国土が狭ければ、利用できる総水量は少なくなるから、水資源が余るほどあるというわけではないが、水資源が豊富であることにはかわりがない。熱帯雨林が発達した地域ではさらに大量の雨が降り、大陸内部の乾燥地域では年間でわずか50ミリしか降らないところもある。水は地球を回っているが、「水の不平等」はいかんともしがたく存在する。さらに、大陸のいくつもの国を流れる河川(国際河川)では、上流と下流で、その不平等はさらに拡大していく。農業は水に支えられているので、水の不平等は食糧の不平等となり、富の偏在を発生させる。水もまた厳密には天下の回りものではない。
この夏、中央アジアのカザフスタン共和国の沙漠の村で生活してきた。旅行の目的などは割愛するが、調査のための基地としている大都市から、目的の村までの距離は1500キロである。2台の車に分乗して、山麓から平原を通過し、沙漠の中を4日間かけてその村に到着した。2台の車の内、1台には乗車人数を減らして、食糧とガソリンと水を満載した。食糧は行く先々で購入できるから量を減らすことはできるが、ガソリンと水だけはどうしようもない。とくに、水は2種類の水を用意しなければならない。ひとつは飲料水のミネラルウォーターであり、ひとつは炊事用の水である。連日、気温が45度の中で過ごすのであるから、飲用する水をケチるわけにはいかない。炊事用はタンクに詰めて運んでいくが、10日くらいが使用に耐える限度である。現地の水は外国人にとっては水質面で危険である。かくして、如何にして少量の水で毎日を快適に過ごすかの知恵がいる。土地の人は、土地の僅かの水をうまく利用して生活している。その知恵を見ていると、天下をめぐって来ない水と上手につき合ってきた歴史を見ることができる。
しかし、現在このような少雨乾燥地帯の少量の水さえも横取りし、水の不平等をさらに助長する動きが世界各地で発生している。地球という自然が決めた不平等にうまく合わせて培ってきたそれぞれの地域文化を根こそぎ破壊するような「水戦争」を阻止しなくてはならない。そのために私たちは多くの英知を獲得しなれば、と思う。
(石田紀郎)
|