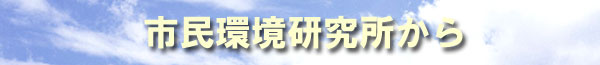祭りの後はさわやかさと寂しさが入り組んだ雰囲気が街中にも人々の心の中にも残り、漂っているものである。京都に在住40余年にして、初めて祇園祭りの山鉾巡行を見た。友人の好意で、4階と9階の2室を借用でき、稚児や囃子方と同じ高さの4階と数基の鉾や山を同時に俯瞰できる9階を行ったり来たりしながらの、贅沢な見物であった。祭りが終わり、浴衣がけの男女学生と例年になく涼しい鴨川を渡って帰った。耳に残る祇園囃子を楽しみながら。
遡って3月中旬に10日間ほど京都で開催された「世界水フォーラム」は国際的祭りであったが、さわやかさと寂しさの両方とも残さずに終わっていったように思われる。海外から人が来たな、えらい人も来たな、なんだか水は大事だと京都市も京都府も言っていたな、イベントはいっぱいあったな、マスメディアも水・水・水とにぎやかに紙面と画面を毎日送ってきたな、と思い出しはするが、さて何が残ったのだろうと考えると、思い浮かぶものがない。1日参加で7000円のチケットを購入しなければならず、とうてい庶民が数日参加などできない料金設定であった。筆者も、関係した「アラル海ワークショップ」当日のみの参加だけであった。「水はみんなのもの」とお題目は立派であるが、国際機関が多くのセッションを牛耳り、それぞれの機関が今後の発言権を確保しようと、勢力誇示を展開した。
主催した日本側もお粗末の限りであり、各省庁からの出向チームが自分たちの仲間内でイベントを組み、各省間の合同企画もなく、事務局は各省ごとにデスクを構えており、横の連絡・連携など望むべくもない状況であった。「期間中の会場は用意したし、プログラムをパンフレットにして広報はやります。あとは知りません」と、丸投げ方式である。そこには、日本も世界もが抱えている深刻な水問題とは正反対のノホホン状態である。
かくして、総額は知らないが、莫大な経費が使われて、祭りは終わった。主開催地の京都の市民に何が残ったかを調査する必要もない。なぜなら、京都市民の中で、「世界水フォーラム」なる祭りがこの3月にあったことを記憶している人さえ極めて少ないのである。京都市と京都府の罪は大きい。
また、市民参加を標榜して開催されたこの会議に出席した人たちの多くは、「水」を大事な課題として日常的に取り組んでいる人達よりも、「世界フォーラム」が好きで参加しているに過ぎないようであった。だから、祭りが終わり、何も残らなかったのも当然である。
祇園祭りは町衆の祭りと言われる。官製で虚構と策謀の祭りでない祭りを見られたのが、この夏のなぐさめである。
(石田紀郎) |