| ■連載 |
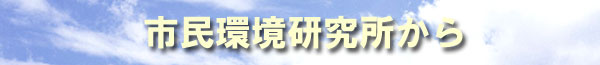
<第2回> 水・越境--20年目の琵琶湖調査団 |
(ニュースレター No.17号掲載) |
| 本格的な梅雨を過ごすのは久しぶりである。我が家の屋根にはこの春に設置した太陽光発電装置があり、毎朝、発電量を記録しているが、この1ヵ月はその数値は低迷したままである。農業を営んでいる友人からは、野菜や果菜の病気が日に日にひどくなると悲鳴が届く。太陽光発電も作物も太陽光のエネルギーによって動いているのであるから、この長期間の雨天・曇天はこたえる。 「水はその地形の中で、いちばん低い所を流れます。だから、その地形の上で人間がどんな生活をするかを色濃く映します。いちばん低い水の中から見れば、人間の生き方のあり様が見えてくると思うのです」―この文章は20年近く前に、「飲み水、捨て水、かえり水」という本を住民運動の成果として出版した際、その購入者に頼まれて表紙裏に書いた文で、大学退官記念文集に収録してくれた。琵琶湖・淀川水系調査に走り回っていたころを思い出した。20年という月日が経過したが、この水系の水環境は回復の兆しさえ見せていない。環境問題に社会の関心が向きだしたとは言え、社会全体、すなわち陸上の人間の生き方・社会全体が改善されていないのであるから、水系がよくなる訳がない。 そんなことを考えている時、20年前に琵琶湖調査を共にした漁師から、もう一度、一緒に琵琶湖調査をやろうと声がかかってきた。この間、彼も琵琶湖浄化の運動を必死でやってきたが、琵琶湖はますます悪くなる。20年前とどこが違ってきたのかを明らかにしようというのである。琵琶湖とともに生きてきた漁師から声をかけられたのだから、イヤという訳にはいかない。そして、「20年目の琵琶湖調査団」を結成し、この春から活動を開始した。 この20年の間に、琵琶湖には24時間の水質モニタリング装置が何基も建設された。水質調査も自治体や研究機関でずいぶんやられているのに、何を今更、琵琶湖専門家でない集団が調査などやるのか、といぶかる声も聞いた。調査経費の工面も大変である。何を酔狂にと思うこともあるが、何か、駆り立てるものがある。それは、環境問題は総合して考えなければならないと、学際的でないと、上流から下流までの流域で考えないと駄目だといわれながら、あいも変わらず、行政機関の調査は縦割りと地域割りの調査しかしていない。研究機関も専門分野別の調査に終始している。生活者の目からみた環境政策が必要だと強調されてもきた。お題目はできているが、実行されているといい難い。我が調査団は、滋賀県から京都、大阪までの市民・住民と研究者が、地域を越えて、専門性を越えて琵琶湖・淀川流域を捉えようとしている。人間が線引きした境を越えて流れる水を知るには、我々もまた、越境しあうことを前提とした作業であるべきだろう。 (石田紀郎) |
Copyright (C ) 2003 地域・アソシエーション研究所 All Rights Reserved.