| ■新連載スタート! |
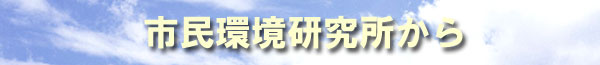
<第1回> まずは連載にあたっての自己紹介です。 |
(ニュースレター No.15号掲載) |
| 今月から環境問題に関する雑感を連載させていただくことになった。まず、何者が連載するのかを知っていただくために、少しばかり自己紹介をしたい。1959年に京大農学部に入学して、今春定年で退職するまでの45年間を大学という特殊な社会に身を置いてきた。この間に、1960年の反安保闘争や1969年の大学闘争を経験したが、それらに対して私なりに主体的に関係し、大学という特殊な社会で営まれる科学的営為の社会性を考えてきたつもりである。その過程で、70年代当時の公害問題が、科学と社会との最大の矛盾を表す現象であり、公害問題に真っ正面から向き合わない限り、次の時代、次の社会が見えてこないだろうと思うようになった。とにかく、多くの公害現場を歩いた。そうしながら、自分の科学的営為とは何をすることかを模索してきた。しかし、悲しいかな納得できる地点まで行き着く前に定年となってしまった。まあ、自己の人生が定年で終わってしまうわけでもないから、場所が変わって肩書きが変わっても、模索をつづけていこうと思っている。 1970年代に公害問題を研究課題とすることは、大学からも、仲間内の研究者からも異端視されたものである。公害は単に「あくどい企業があくどい儲けをするために犯した罪のようなものである」から科学の対象になるものではない、というのが大方の見方であった。つまり、自然の摂理を探求する自然科学者が関わらなければならないような問題ではない、というのである。ところが、公害問題が環境問題と呼ばれるようになった今では、「環境」を考えない研究者は研究者ではないかのような風潮が充満し、既存の学問分野の名称の前か後ろに「環境」を付けた研究室が並んでいる。「真理を探究する」科学ほど「現金を探査する」術に長けたところはない。環境問題の部門に多額の金が落ちる昨今、金の流れの道筋に居を構えるためなら平気で名称を変えるのだと思わざるをえない。大学には環境を冠した部局がいっぱいできたのであるから、地域の、あるいは地球の環境問題は迅速に解決できるだろうと市民に期待を抱かせているようだが、研究内容がそれ以前と変わるとは限らないので、あまり期待しすぎない方がよい。税金を使って人を欺くとは罪なことである。 大学という環境を離れ、4月から京大の近くに部屋を借りて、学生や市民と一緒に環境問題を考える場を作った。さて、名称をどうするかといろいろ迷ったが、若い感覚を取り入れようと学生諸君に任せてみた。彼らがつけてくれたのが、「市民環境研究所」である。私の考えた名称は却下され、これに決まった。環境を冠した研究室は眉唾ものが多いと言ってきた手前、心して活動内容で勝負しなければと思っている。 (石田紀郎) |
Copyright (C ) 2003 地域・アソシエーション研究所 All Rights Reserved.