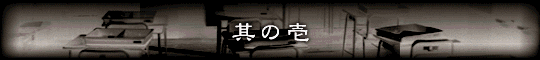
| 第八十一話 踏み切り |
|
N子さんの家の近く、JRのH駅とM駅の間に踏み切りがあった。 ある日午後、N子さんはその踏み切りで電車の通過を待っていたという。 電車が近づいてきたとき、N子さんは背後から突き飛ばされた。思わず手をついて倒れこんだとき、N子さんの顔に風を叩き付けて電車が通過したそうである。 N子さんは驚いて後を振り返った。自転車に乗ったおばさんがびっくりした顔をしていただけだったそうである。 N子さんの背中には、はっきりと両手で押された感覚が残っていた。 N子さんはこの踏み切りで事故が多い理由がわかったという。 現在この踏み切りは廃止され、小さな地下道になっているそうである。 |
| 第八十二話 水滴 |
|
M君の話である。 ある日アパートに帰ると、玄関を入ってすぐのところに水滴が落ちていた。直径は1センチ程であったという。 水漏れかと天井を見上げたが、しみのようなものも見当たらなかったそうである。変だなあ、と感じたものの、顔を洗ったときの水滴が落ちたのかも知れない、と、水滴を拭きとってそれ以上気にも止めなかった。 翌日帰宅すると、今度はワンルームの入り口に水滴が落ちていた。 それから時々、どこかしらに水滴があるようになったという。テーブルの上や、テレビの上にたれていたこともあったという。あるときなど、水滴を指でこすったように、廊下に筋がついていたこともあったそうである。 その現象は、ひと月ほどでおさまってしまったそうである。 |
| 第八十三話 心霊写真 |
|
Bさんが大学時代の話。大学の友人が心霊写真を撮って、大騒ぎになったそうである。 Bさんもその写真を見たという。 それは、配線になった線路を撮ったもので、枯れすすきの平原に伸びる線路の写真だったそうである。その線路の脇に、使われなくなった信号機がぽつんと立っている。 その信号機の周りに、びっしりと人の顔が写っていたそうである。 「思い出しても、ぞっとするよ」 私は彼に、よくある心霊写真と言われているような、3点あれば人の顔に見える類のものじゃないの?と、聞いて見た。 Bさんは首を振って、 「あれは見た人じゃないとわかんないよ」と、鳥肌のたった腕をさすった。 |
| 第八十四話 倉庫 |
|
Bさんが友人から聞いた話である。 彼は、福岡の某デパートの倉庫でバイトしたという。似たようなバイトに比べ、1割りほど高かったそうだ。そのバイトを紹介してくれたのは大学の先輩で、卒業にあたって彼にそのバイトを譲ってくれたのだという。ただ、「面白い経験ができるよ」と笑ったのを、後になって思い出したという。 ある日、倉庫で独り、在庫チェックをしていると、笑い声が聞こえたという。彼は辺りを見回したが、山積みになったダンボールで倉庫は見渡すことができなかった。 どこかの声が反響したんだろう、と思い、再びチェックを再開すると、目の端を小さな女の子が通りすぎた。パタパタという足音もはっきり聞こえたという。 はっと顔をあげたが、誰もいなかった。一旦チェックを止めて倉庫を見回り、女の子を探したが、どこにもいなかったという。その時、担当者が来たので、 「女の子が入り込んでいるみたいなんですが」と言うと、 「なんだ、聞いてないのか」と顔をしかめたという。 上司によると、その倉庫には昔から幽霊が出るそうで、ほとんどの社員やバイトが何らかの怪現象に遭遇しているという。ただ、問題視する程の危害を加えるわけではないので、「気にするな」ということだった。 結局、彼は2年間、そのバイトを続けたという。 笑い声や足音、女の子らしき人影はしょっちゅう見たそうだ。ダンボールの影から、小さな赤いスニーカーの先が覗いているのが見えたこともあったという。 後日、彼が先輩にあったとき、その話をした。 その先輩は「なんだそれだけか。俺はもっとすごい体験をしたぞ」と笑ったそうである。 「どんなことですか?」と先輩に言うと、すこし真顔になって、「聞かないほうがいいよ」と言ったそうである。 |
| 第八十五話 線香臭い |
|
都内にあるN公園のベンチで、夕方、Fが休んでいたときのこと。辺りはそろそろ暗くなりかけていたという。 隣のベンチにはOLらしき2人連れがいた。そのうちのひとりがトイレかどこかに立った時のことである。 しばらくすると、ふいに線香の臭いが漂ったのだという。なんだろうと見回すと、隣のベンチのOLとちょっと目が合ったそうである。その時、OLの連れが戻ってきた。 彼女は立ち上がり、2人はFの前を通りすぎていった。 彼女たちの会話が聞こえた。 「○○がいない時、すごく気持ち悪い人が通ったんだよ」 「どんな?」 「なんか、すっごい痩せた男の人で、ふらふらしてて、幽霊みたいに気持ち悪いの」 「幽霊だったんじゃないの?」 「いや〜!(笑)」 Fは、そんな男をまったく見ていないそうである。 |
| 第八十六話 救急車 |
|
消防署に勤めている方から聞いた話である。 M市に在る某消防署には、2台の救急車があるという。 救急車によってスピードの違いがあるわけもなく、搬送する病院など決まっているわけでもない。 ところが、片方にくらべ、もう片方の救急車で患者を搬送した場合の救命率が、格段に違うそうである。 口性ない署員はその救急車を、「白い霊柩車」と呼んでいるそうである。 |
| 第八十七話 こっくりさん |
|
こっくりさんについての怖い話はどこにでもある。これも、そんな話のひとつの加えていただけたら、と思う。 K子さんは中学生の時、演劇クラブに所属していた。 ある放課後、部室兼小道具部屋で仲間たちと雑談に興じていたそうである。話はいつしか、何年か前に流行った「こっくりさん」の話になっていった。 中のひとりが、盤面を描けるというので、K子さんは他の3人とこっくりさんを始めることになったという。 盤面をマジックで紙に描き、4人で10円に指をあてた。「こっくりさん、こっくりさん。いらっしゃいましたら、『はい』のところにお進み下さい」 何回か言ううちに、10円玉は『はい』と書かれたところに移動したという。 K子さんたちは、きゃあきゃあ言いながらも、好きな男の子のことや勉強のことなど他愛のないことを質問したという。 K子さんによれば、「本当に霊が動かしているなんて、本心、誰も思ってなかったと思う。でも、構わないんだよ、遊びだからね」 さて、もうそろそろ終わりにしようか、ということで、帰ってもらうことにした。 「こっくりさん、こっくりさん、ありがとうございました。お帰りください」 ところが、今まですいすい動いていたのに、10円玉はぴたりと動かなくなった。 K子さんたちはあせったそうである。遊びとはいえ、ルールがある。10円玉が動かない限り、この遊びを終わらせることが出来ないのである。 「早く誰か動かしてよ」とK子さんが思ったとき、何かが10円玉を触るK子さんの手を触った。はっきりと、手を握られる感じがしたという。 友人のひとりが悲鳴をあげ、K子さんたちはパニックになって、我先にと部室を飛び出したそうである。 聞いて見ると、みんなが同じ感触を感じたそうである。ひとりは、壁に子供の人影が見えたといって、泣き出していた。確かに、K子さんたちが感じた手の感触は子供のように小さかった、という。 後におそろおそる見にいくと、誰が片付けたか、盤はくしゃくしゃに丸められてゴミ箱に捨てられていたそうである。 「でも、それだけで終わらなかったの」と、K子さんは続けた。 |
| 第八十八話 演劇 |
|
こっくりさんの霊が帰っていない、という後味の悪さが残ったが、さすがに、またやる気は起こらなかった。 それ以来、部室で独りでいると人影を見たとか、子供の笑い声を聞いたとか噂がたったが、そのうちそう言った話も終息していった。文化祭で発表する劇の練習が忙しくなり、そういったことに構っていられなくなったせいもある。とはいえ、やはり独りきりで部室に行くのは、「正直言って、怖かった」という。 そして、文化祭が来た。K子さんの所属する演劇部の出しものは、『鶴の恩返し』であったという。 劇は順調に進んだが、なぜか場内がざわついている感じがしたという。それでも劇の終わりは盛り上がり、拍手喝采の大成功を修めたそうである。 「K子、よかったよ」部室に戻るK子さんに、同級生が声をかけた。 「ありがと」 「でも、あの木の陰にいた子供は誰なの?」 結局、観客の何人かが、セットの木の陰に立つ子供を見たらしい。話によると、それは小学校2、3年生くらいの女の子で、にこにこしながらK子さんたちの劇を見ていたらしい。 K子さんの友人も、最初は不思議に思ったが、誰かの妹だと思ったという。もちろん、そんな事実はない。 演劇を撮った写真をチェックしたが、友人の言った場所には誰も写っていなかった。ただ、1枚、奇妙な光が感光していた写真があったというが、それが霊のせいなのかどうかわからなかった。 K子さんたちは、自分たちがやったこっくりさんで呼びだした子供の霊かも知れないと思ったそうである。帰ってもらうために、もう一度こっくりさんをした方がいいという話が出、 友人の、いわゆる「心霊に強い子」に頼んで、こっくりさんを行った。 今度はちゃんと帰ってくれたそうである。 |
| 第八十九話 サーチライト |
|
百武彗星が来た時である。O君は友人とともに甲府郊外の山に登り、雲の切れ間から彗星を見ていたという。 その時O君は、山の狭間に、一条の光を見た。光は、雲間にまで没し、ゆっくりと円を描くように動いていたという。 甲府市街には、何本ものサーチライトが立っている。O君は別に気にも留めなかった。 雲が出始めて、結局それ以降彗星を見ることはできなかったそうだ。帰ることにしたとき、先ほどのサーチライトの方に目をやったが、すでに消えていたそうである。 市街が見えるところまで降りると、いくつかのサーチライトが伸びて雲に円を描いていた。そのとき、O君は山の上で見かけた光とサーチライトが違うことに気付いたという。 O君が見た光は、雲の上方を基点として動いていたそうである。 |
| 第九十話 幼馴染み |
|
F美さんが友人からこんな話を聞いた。 その友人が実家に帰省していた時、自分の子供の頃の話になったという。 母親が、弟のお嫁さんに言ったそうである。 「この娘は、独りで遊ぶのが好きでね。しょっちゅう、独りでままごとしてたのよ」 F美さんの友人は、それを聞いて首を傾げたそうである。彼女は独りでままごと遊びをした記憶がない。ままごと遊びは、いつも隣のチエちゃんという子としていたはずである。 そう考えていると、ふと、チエちゃんはどこの子だったのか、顔すらも思い出せなかった。 いつの間に遊ばなくなってしまったのか、それどころか、あれほど仲良く遊んだチエちゃんのことを、今まで一度たりとも思い出さなかったことをひどく不思議に思ったそうである。 なんだか、少し気味が悪くなったF美さんの友人は、反論することも出来ず、母親にチエちゃんのことを聞くこともためらってしまったそうである。 「私の記憶違いなのかしら」 ただ、チエちゃんがいつも同じ赤いストライプのシャツを着ていたことだけは、はっきりと覚えているそうである。 |
| 第九十一話 落書き |
|
Wさんが大学時代の話。 その日は論文の提出を控え、学校の図書館で遅くまで勉強していたそうである。 Wさんは、後の棚にある資料を取りに机を離れた。場所はわかっていたので、ほんの20秒ほどのことだったという。 Wさんが戻ってくると、ノートに落書きがあった。 「カオリ」と、ギクシャクした文字で書かれており、「リ」のすぐ下にシャープペンシルが置いてあった。 誰のいたづらか、とWさんは見回したが、知り合いは見当たらない。 思いきって、低い隔壁で遮られている前の女子学生に、今、誰か来なかったか聞いてみた。 女子学生は怪訝な顔をして、誰も来なかったと思う、と答えたそうである。 |
| 第九十二話 天井 |
|
夜中、Wさんはバンっという大きな音で目を覚ました。 時計を見ると、まだ4時前だった。寝ぼけていたものの、天井の方で聞こえたのはわかったので、どうせ上の階の住人が何かしたのだろうと、すぐに寝入ってしまったそうである。 翌日の夜、寝ようと思い布団に入って天井を眺めた時、Wさんは天井に汚れがついているのに気がついた。 それは、炭で汚れた手で触ったような、くっきりとした手形だったという。 |
| 第九十三話 ロケーション |
|
E社があるビデオ作品のため、都内のI公園でロケを行った。役者を使ってのイメージシーンの撮影である。 撮影も無事終わり、帰社した監督のHさんが撮影済みのテープをチェックしていると、何か変な感じがした。Hさんが巻き戻してみると、カットとカットの間に1フレームだけ異質な画が入っていたという。 その画は、ピントもぼけており、露出も暗かったという。しかし、雰囲気から見て、間違いなくI公園の池が写っているようである。その前に、眼鏡をかけ、背広を着た男が、ぽつんと立っているというものだったそうである。 カメラマンを始めスタッフに聞いてみたが、そんな男性の記憶は誰にもなかった。それよりもなによりも、前後のカットは役者の演技によるテイク違いなので、その間にカメラを動かすことは決してない。絶対に入るはずのない映像だった。 Hさんは長年映像にたずさわっているが、唯一の不可思議な体験だという。 |
| 第九十四話 温泉 |
|
信じてもらえないと思うけど、と、前置きして、M君が語ってくれた話である。 2年前、彼は独りで、信州の温泉に行ったという。丁度、女性用の旅行雑誌にも温泉がよく取り上げられ始めた頃だったという。 その旅館には、24時間入浴できる、混浴の露天風呂があった。 M君は、夜中の2時近くに、その露天に向かったという。若い娘も、深夜なら他に誰も入って来ないだろうと油断して混浴風呂に来るのではないか、という下心があった。 脱衣所に入ったM君はがっかりした。どの篭も空だったからである。とはいえ、そのまま帰るのもなんなので、風呂に入ることにした。 湯船はかなり広く、両側は岩で遮られている。昼間ならきれいであろう前方の闇に沈んだ景色を見つめ、ぼんやりとしていた。 乳白色の湯は、ややぬるめだったので長湯もできそうだったが、やはり誰も入って来ない。期待があらばこそだったが、ひと気のない大きな風呂はどこか薄気味悪い。結局M君は出ることにしたそうである。 脱衣所のガラス戸を開けたとき、ぽちゃんと、背後で音がした。M君は振り返った。 湯船の真ん中、湯煙の中に、人の後頭部があった。多分、女性の頭であった。肩は見えず、長めの細い首から上だけが湯面に突き出ていた。その髪の毛は、今まさに水から出たように濡れて、脱衣所の灯りを反射していたそうである。 まさか、とM君は思ったそうだ。風呂場のどこにも隠れる場所はない。M君がお湯につかっていた15分ほどの間、ずっと潜っているのも不可能だった。 悪寒が走り、温泉あがりのM君の身体は一気に冷えて、鳥肌が立つのがわかったという。 動けずに湯から突き出た後頭部を凝視するM君は、その頭が動いているのに気がついた。湯船のそれは、ゆっくりとではあったが、振り返ろうとしていた。 そう気がついた瞬間、M君は手拭い一本きりで、脱兎の如く逃げ出したそうである。 それからM君は、電気をつけっぱなしにした部屋の隅で布団にくるまったままで震えて夜を過ごし、翌朝早々に旅館を引き払ったそうである。 M君が脱衣所に残した下着は、まだその旅館に保管されているのだろうか。 |
| 第九十五話 毒気 |
|
Sさんの大学時代の知り合いに、F子さんという霊感のある同級生がいたという。ぽっちゃりしてたが、性格も明るく、普段はそんなことをおくびにも出さなかった。 ある日クラスの仲間で喫茶店に行ったときのことである。10人ほどいたので、大テーブルを占領した。 ひとりの先輩が外で携帯をかけていたので、席がひとつ空いていた。 何を注文しようかと迷っていると、隣に座っていたF子さんが、その席を指差して、Sさんに耳打ちしたという。 「あれ、見える?」 Sさんは何を言っているかわからなかったそうである。 「幽霊が座ってるよ。水が置いてあるでしょ。覗き込んでる」 その時、遅れて来た先輩が入ってきて、その席に座った。 「あ〜あ、座っちゃった」 先輩は、座るやいなや、水を飲んだ。そして、顔を歪めて、 「まじいっ! おまえ、なんか入れただろ!」と隣の友人に食ってかかった。 それを見ていて、Sさんはぞっとしたという。 「大丈夫なの?」とF子さんに聞くと、「2、3日、調子悪くなるくらいよ」と笑ってパフェを注文したそうである。 |
| 第九十六話 帽子 |
|
同じくF子さんにまつわる話である。 SさんがF子さんと一緒にショッピングをし、S駅に在る古着屋に行った時の話。 Sさんはそこで、気にいった帽子を見つけたのだという。被って鏡で見てみると、自分のことながら、なかなか似合っていたそうだ。 Sさんは、洋服を見ていたF子さんを呼んで聞いてみた。 F子さんは「その帽子は止めた方がいいよ」と、顔をしかめたという。 「なんで? 似合ってないかなあ」と、納得いかないSさんに、 「そういうことじゃなくって、、、」と言ったという。 Sさんは、その言い方を察し、買うのをやめたという。 店を出てSさんは、F子さんに何が見えたのか聞いてみたそうだ。 F子さんが言うには、すでに被っている人がいたのだという。それは首だけで、顔は見えなかったが、Sさんが帽子を動かす度に、ばさばさと髪の毛が揺れていたのだそうだ。 「あたし、かぶっちゃったよ!」Sさんは思わず叫んでしまったという。 「そうだね」とF子さんは苦笑いしたそうである。 聞かなきゃ良かった、とSさんは思ったそうだ。 |
| 第九十七話 騒々しい |
|
Kが知人のOさんから聞いた話だという。 Oさんは、N区にあるアパートに、大学2年から、3年ほど住んでいたことがある。 そのアパートは4部屋しかなく、古びた木造であったが、その分家賃は安めだったという。 就職したばかりで金のないOさんは、大学を卒業してもそこに居続けたのだそうだ。もっとも、プロダクションに入ったOさんは仕事が忙しく、夜半過ぎに帰宅して寝るだけだったから、別に古かろうが構わなかったそうである。 ある夜、帰宅して寝ていると、なんだかうるさくて目が覚めた。 決して厚いとはいえない壁を通して、隣の部屋のざわめきが聞こえた。しかし、疲れていたので、布団を被って寝てしまったという。 何日か後、再び夜中に目が覚めた。また隣が騒がしい。Oさんは腹が立って、思いきり、壁を蹴ったという。声はふいに途切れ、Oさんは翌朝まで眠れたそうだ。 そんなことが何回かあったものの、ひと月程が経ち、その日曜日は、Oさんにとって久しぶりの休みだった。 夜、ヘッドホンでCDを聞いていたOさんは、もう寝ようかとヘッドホンをはずした瞬間、わっという感じで、隣の騒ぎ声が聞こえたという。 それはまるで潮騒のように、大きくなったり小さくなったりしていたという。 窓をあけて隣を覗くと、室内の灯りでカーテンに何人もの人影が見える。Oさんは部屋を飛び出すと、隣の部屋のドアを叩こうとした。 ところが、部屋の前に立つと、電気が消えているのに気付いた。あれだけ騒々しかった声も、聞こえなくなっていた。 それでも、Oさんはノックしてみたという。しかし、返事はない。しばらくOさんはドアの前で耳をひそめていたが、その部屋に居るはずの人々は息を殺しているのか、物音ひとつしなかったそうである。 翌朝、Oさんは「夜中は静かにしろ」との貼紙を隣の部屋にして、仕事に出かけたという。 その日帰宅したとき、電気が消えていた。覗いてみると、貼紙もそのままだ。どこかに出かけたのかも知れないと、ほっとしたそうである。 ところが、明け方に再び、騒々しさに目が覚めた。 今度は下の部屋から、大きなラジオの声が聞こえる。しかも、ちゃんと周波数が合わせてないような、雑然とした音だったという。 Oさんは、寝たまま思いきり畳を蹴飛ばした。どん、とアパートが揺れるほどの衝撃とともに、ぴたりとラジオの音が消えた。 その瞬間、隣の部屋から笑い声が聞こえ、後はしんと静まり返ったそうである。 翌日、朝一番にOさんはアパートを管理している不動産屋に行った。 Oさんの苦情を聞いた不動産屋は、顔をしかめた。 「どこだって?」 「○○町の、N荘です」 首を傾げながら、帳簿を開いた不動産屋は言ったそうである。 「あんたんとこ以外は、誰も住んでないよ」 不動産屋によれば、ひと月以上前に、他の住人は全て越していたという。 Oさんは「そんなわけはない」と食い下がったが、不動産屋は「鍵はつけ換えてるし、勝手に人が入り込むことはない」と、ひどく厭な顔をしたという。 「でも、ちゃんと、電気がついているのも見てるんだぜ」 Kにこの話を語り終えたOさんは、割り切れない顔をしていたという。 ちなみにOさんは、不動産屋に行ったその日から友人の家に泊り込み、すぐに引っ越したそうである。 |
| 第九十八話 生き物 |
|
A君が中学の時、兵庫県のH郡で見たものだという。 夏の昼下がり、プールからの家路で、田舎道を歩いていたときのこと。 それは、A君の右手のカヤのやぶから現われたという。 バレーボールくらいの大きさの、黒いものだったそうである。全体がぬらっと濡れていた。 太くて黒い、ヒルのような質感のものが絡み合っているようだったという。 それは回転しながら、太い触手をべちゃべちゃと歩道に打ちつけながら、A君の前をよぎって行ったという。 その何かは、道路を横切ると、ぼちゃんと水飛沫を上げて用水路の中に落ちてしまった。A君は用水路を覗き込んだが、濁った水で何も見えなかったそうである。 夢でない証拠に、それが横切った舗装道路には、濡れた痕がついていたという。 A君は、「今だにあれがなんだったのか、わからない」と首を傾げた。 |
| 第九十九話 百物語 |
|
百の怪談話を一気に聞くと、怪異な現象が起こるとされている。皆さんはここまで、一気に読んでこられましたか? Kたち物好き連中とともに、百物語をしたときのことだ。 百の物語りはとうに越えて、時間は午前4時。うっすらと夜が明け始める「彼は誰」時になっていた。 「なんにも起こらなかったなあ」そう言って、笑っていたときである。 がたがたがた、と背後にある本棚が揺れた。 もちろん地震ではない。本棚だけが、細かく振動したのだ。 皆があっけにとられる中、 「オチがついたから、お開きだね」とJが言った。 |
| 第百話 梅 |
|
最後の話は、いわゆる「霊異」とは言えないかも知れない。 友人の母が亡くなった。私は、縁あって、友人の家で執り行われた告別式に参列させていただいた。 天気の良い日で、庭には梅が咲き誇っていた。その梅は、友人の亡くなったお母さんが大事にしていたもので、その梅の花を見ることなく逝ってしまわれた。 お坊さんが、お母さんの戒名を言った。 その瞬間、庭から一陣の突風が吹き込んできた。 「ああ、こんなこともあるんだなあ」 私はそう思いながら、風が運んできた梅の花びらが祭壇に舞い踊るのを眺めていた。 |
|
|
|
|