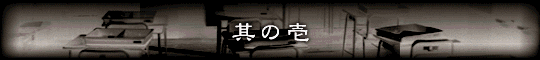
| 第四十一話 ムジナ |
|
Mさんが子供の頃の話である。 夜、母親とともに家路についていた時、前方から男の人が運転する自転車が近づいてきた。 明るいライトのせいで顔はよく見えなかった。 通りすぎる瞬間、Mさんがその男の顔を見ると、なんとのっぺらぼうだったという。 びっくりして振り返ると、自転車はあっと言う間に暗闇に吸い込まれて、見えなくなってしまったそうだ。 「おかあさん、今の男の人、顔がなかった!」 Mさんがそう言うと、母親はびっくりして、 「誰も通ってないじゃない」と言ったという。 |
| 第四十二話 アベック |
|
N子さんの地元には、鬱蒼とした木々の茂る公園があり、夏の真昼間でもひんやりとして薄暗かったという。 N子さんが中学生の時。その公園通りを歩いていると、むこうからアベックがやってきた。女が抱きつくように男にしなだれかかっていて、N子さんは目のやり場に困ったものの、好奇心から盗み見るように、ちらちら眺めていたという。 だんだんと近づくアベックを見ているうちに、N子さんは異様な感じがしたという。 三十くらいの背広を着た男は、しなだれかかる女のことなど気にもせず、顔をあげることなく目線を落として歩いている。一方、女性の方は首を左右にがくがくさせながら、長い舌をだらんと突き出して、笑いながら男の顔をねめつけていた。 すれ違う時、その女は一瞬、N子さんを睨みつけたという。 ぞっとして振り返ると、女の姿は無く、男の後姿だけだった。 厭なもの見た、と思ったそうである。 |
| 第四十三話 自動ドア |
|
Kが以前勤めていた、世田谷にある会社の話である。 その会社の自動ドアは、誰もいないのに開閉することがよくあった。感度が良すぎるのでは、と修理を依頼してみたものの、相変わらず開閉してしまうそうである。 そのドアの近くに、Gさんという総務職の中年の社員がいた。もの静かな人で穏和そうであったが、どこか暗く、ドアが自然に開閉する度に「女の人だ」とか「事故にあった子供が来た」とかつぶやくので、女子社員から毛嫌いされていたという。 Kは、「どうせいい加減なことを言っているに違いない」と相手にしなかったそうである。 ある日の午後、社員が出払ってしまい、KとGさんの2人きりになってしまったという。 しばらく仕事に集中していたが、Gさんがぶつぶつ言う声に顔をあげた。Gさんは入り口のドアを見つめ、独り言を言っていたそうだ。 「考えてるな。入ってくるかな。どうする。そうそう。ああ、入って来た」 その瞬間、誰もいない入り口のドアが開いたそうである。 驚いてGさんを見たが、Gさんは何事もなかったように仕事に戻っていたそうである。 |
| 第四十四話 間違った写真 |
|
R氏から聞いた話。 その日R氏はある写真店で、社員旅行で撮った写真のプリントを受け取って帰宅したそうである。 封を開けて、何か違うことに気がついた。ざっと眺めると、自分の知らない写真ばかりである。あわてて封の名前を確認すると、姓は同じだが、他の人の写真であった。 R氏は舌打ちしたものの、その写真が女子大生かOLと思われる若い女性たちの旅行の写真であったために、思わず1枚1枚丹念に見てしまったのだと言う。 写真に写っている女性たちは3人連れのグループで、行き先は神戸近辺のようであった。 そのうちの1枚が温泉旅館の一室で撮られた記念写真であった。浴衣姿の若い女性3人が、楽しげに写っていたので、タイマーで撮られたものに違いなかった。 R氏によれば、楽しげな彼女たちの様子とは裏腹に、その写真を見た瞬間、ひどく厭な感じがしたという。 彼女たちは窓際に座ってふざけあっている。外は真っ暗で、ガラスにストロボの青い光が反射していた。真ん中で、その青白い光の前で大きく笑っている女性の首元に、他の女の子の手がかかっていた。 首を締めてるみたいだな。R氏がそう思った瞬間、あることに気付いて愕然とした。 「1、2、3、、、7」 手が7本写っていたのである。 R氏はできうる限り可能性を考えたそうだが、どうしても真ん中の女性の首元にかかる手の持ち主がわからなかった。 翌朝、R氏は早々に写真を交換してもらいに写真店を訪れた。店主は恐縮していたが、R氏は自分の写真を受け取ると、足早に写真店を後にしたそうだ。 あの写真の女性に何か悪い事が起こらなかったか、R氏はずっと気になっているという。 |
| 第四十五話 洗濯機 |
|
Aの友人の話。 彼女は学生時代、静岡の大学に通っていた。彼女は下宿が狭いこともあって、近くのコインランドリーを利用していたそうであるが、引っ越しにともない、リサイクルショップで洗濯機を3千円で購入した。 最初にスイッチを入れた時、なんて楽なんだろうと、思ったそうである。重い洗濯物を持って往復する必要も無く、不審者の心配をする必要も無い。いい買い物をした、と満足だったそうである。ところが、、、。 2槽式だったので、洗濯物を脱水槽に入れ替えていると、シャツに絡まる黒い繊維を見つけた。なんだろうと思ってよく見ると、髪の毛の塊だったそうである。 気持ち悪くなったが、中古品なので、前に使っていた人のゴミがどこかにひっかかっていたんだろうと思ったそうだ。 一旦洗濯物を出し、水だけを大量に入れて回し、洗濯槽内を掃除した。 ところが、再び洗濯をすると、また髪の毛が絡み付く。先ほどの髪の毛と合わせると、かなりの量になったそうである。 さすがに気味が悪くなって、コインランドリーに向かったという。 その後彼女は無理をして新品の洗濯機を購入したそうである。髪の毛の絡まる洗濯機はどうしたかというと、髪の毛のことは内緒にして3千円で後輩に売りつけてしまったそうだ。 「ひどいよなあ」と、私にこの話をしてくれたAは笑った。 もっとも彼女の話によれば、 「後でそれとなく聞いてみたけど、別になんの問題もないって言うし、相手も喜んでたんだから、いいじゃない」と言うことだそうである。 |
| 第四十六話 まとわり憑く影 |
|
Hさんが結婚式のビデオ撮影をしていた時のことである。 撮影も順調に終わり、早速編集作業にはいったそうである。しばらくすると編集していた部下のKさんが青い顔をして、Hさんを呼びにきた。 「あの、昨日撮った結婚式のテープなんですが、、、」 「なんや、ミスっとんのか」 「いや、あの、、、」 しどろもどろのKさんの様子に業を煮やして、Hさんは編集室に向かった。 Hさんが見る中、Kさんはビデオを再生した。 別に問題ない、Hさんはそう思ったそうである。主賓の祝辞が始まる。カメラは客なめで主賓を捉えていた。Hさんは、画面の左下隅に黒いもやの様なものがあるのに気付いた。 なんだろうと、思っていると、カメラがゆっくりズームバックを始めた。黒いもやが画面の中にはいってきた。 「なんや、これ?」 ひとりの来賓の顔を隠す様に、黒い円型のもやが写っていた。 「他はどうなんや?」 Kさんは早送りし、別なシーンで再生を始めた。そこにも、同じもやがあった。恰幅から同じ人物であることは明白だった。花嫁の親族だったそうである。結局、彼の写っているカットは、どのアングルでも全て気味の悪い黒いもやに顔が覆われていたという。技術的ミスではない。 頭を抱えたHさんは、結婚式場に相談したそうである。式場の担当者にもビデオを見てもらったそうだ。担当者は絶句していたという。 最終的には、使えるカットをメインにし、どうしようもないシーンはエフェクトを使ってごまかしたそうである。いつもとは毛色の変わった、予算もかなりオーバーした作品になってしまったが、なんとか納品できたそうである。 そのかいもあって、その式場からはかなりごひいきにされたとのことであった。 |
| 第四十七話 双眼鏡 |
|
ある晴れた春の日の日曜日、Tは家族とともに、東京郊外にあるT山にピクニックに行ったそうである。春霞もなく、T山の展望台からは、都心までがくっきりと見渡せたという。 5才になる息子が双眼鏡を覗きたいというので、Tはお金を入れてやった。 小さな子供は重い双眼鏡をふらふらと操作していたが、やがて空の方に向けてしまったという。 「それじゃ、何にも見えないだろ」 Tは笑ったが、子供はじっと空を見ている。その内に手を振り出したそうである。 Tは飛行機でも飛んでるのかと思い空を見上げたが、雲ひとつない空が拡がっていただけだったという。 「何が見える?」そう子供に聞いたが、息子は空に双眼鏡を向け、笑いなが手を振り続けていた。そのうち、時間がきてがしゃんという音がした。 息子に向かい、Tはもう一度聞いてみたと言う。「何が見えた?」 満足そうな息子は、Tにこう言ったそうである。 「おばちゃんが、手ぇ振ってた」 |
| 第四十八話 河童 |
|
Nの大学時代の友人の話である。高知あたりの出身だった彼が、中学生1年の夏休み、家族とともに近くにある湖畔のバンガローに泊まった時のことらしい。 夜中、彼はトイレに行きたくなったのだそうである。トイレはバンガローの棟が並ぶ敷地のはずれにある。彼は兄を叩き起こして哀願し、文句を言う兄とともにトイレに向かったそうである。 兄はあれほど文句を言っていたくせに、トイレに着くと「ついでだ」と言って、大の方に入ってしまったと言う。独りで帰ることも出来ず、彼はトイレの前でふるえていたそうだ。 トイレからは湖が見えた。その時、暗い湖面に、月灯りに浮かぶ異様なものを見た。 それは、水の上に目から上を出した河童だったという。暗くてよく見えなかったものの、彼は自分が河童に睨まれているのが、はっきりわかったという。 動くことも逃げ出すことも出来ず、1分くらい対峙してたそうであるが、兄がトイレから出て来て目を離した瞬間、それは波紋も残さずに消えてしまったそうである。 話を聞いたNたちは、具体的に河童の姿を聞いたそうであるが、どう考えても、河童というより普通の人間のようだったと言う。 するとNの友人は「幽霊より、河童と思った方が怖くない」と、言ったそうである。 |
| 第四十九話 高架下の声 |
|
大学時代の話。 どうしても、その夜中に仕上げなくてはならない映画実習課題があり、私は迷惑も顧みず、夜中の3時に先輩のHさんの家に器材を借りにむかった。 私は甲州街道沿いに歩いていた。甲州街道とはいえ、高尾の夜中の3時にもなれば車の通りもまばらだ。車も途切れ、あたりがしんと静まり返ることも、まれではない。 そんな時、私は、国鉄C本線が甲州街道をまたぐ高架にさしかかった。 ふいに、どこからか歌うような声が聞こえてきた。私はどきりとして、立ち止まり、耳をすませた。 どこからともなく、歌うような、うめくような、かぼそい声が断続的に聞こえてくる。あきらかに女性の声である。 気味が悪くなり、私は足早に歩き出した。反射の関係か、高架の下あたりで最も良く聞こえたが、そこから離れるにつれ、次第に声は聞こえなくなっていった。 Hさんの家に着いて、そのことを話すと、 「あそこは事故が多いから」とのことであった。 帰りもそこを通らねばならなかったが、幸い、声は聞こえなかった。 |
| 第五十話 迫りくるもの |
|
Kの知人が大学時代に聞いた話だという。 その知人は、神奈川のF市に住んでいた。そこに有名な幽霊貸家があったそうである。平屋ではあるが一軒屋で、6畳ひと間のアパートなみの破格の安さなのに、その家を借りるものは誰もいなかったという。 同級生にUというのがいた。彼は貧乏だが豪胆だったそうである。彼は、安いのならと、その家に引っ越ししたそうである。その上、不動産屋と交渉し、更に値引きさせたという。 引っ越ししたUによれば、確かに変なことが起こるということであった。 煙草を吸わないのに煙が漂ったり、トイレの戸や押し入れがいつの間にか開いているのは、日常茶飯事だということである。 最初のうちは、物好きな友人たちが泊まりに行き、人影を見たとか、うめき声を聞いたなどと盛り上がっていたが、そのうち興も冷めてしまったそうである。 それから3か月ほど後のこと。その日は課題の提出日だったそうである。ところがUが来ない。どうしたんだろうと思っているうちに、一週間ほど過ぎて、ようやくUが大学に顔を出したのだという。 Uは心持ち憔悴しているようであった。 どうしたと聞く友人に、Uは幽霊貸家から引っ越ししたと言い、顛末を語ったそうである。 その夜、Uは課題のため、明け方近くまで机に向かっていたという。 背後で、きい、という音がした。Uが机を置いていた部屋は、玄関から伸びる廊下のつきあたりにある。振り返ると、開け放した扉から、玄関までが見える。Uが見たのは、ゆっくりと開きつつあるトイレのドアだったという。 Uは、またか、と思って立ち上がり、トイレのドアを閉め、居間のドアも閉めて再び机に向かったそうである。ところが、いつもと違って、妙な感じがする。誰かに凝視されている感じがしたのだという。 Uが振り返ると、先ほど閉めたはずの居間の戸も、玄関脇のトイレの戸も全開していた。 そして、トイレの、床から1メートルくらいの高さのところから、首をねじ曲げるように顔を突き出してUを睨みつける男と、目が合ってしまったのだそうだ。 「思い出すと今でも汗が出る」そう言ったUの額には、本当に脂汗がにじんでいたと言う。 いつもと違う恐怖にUが思わず立ち上がろうとした時、トイレの男が飛び出してきたのだそうである。 手足や身体は異様な角度でギクシャクと激しくうねらせているのに、顔だけは微動だにせずUを凝視していた。そして、バタバタと床を打ち鳴らす激しい音をたてて、4つん這いのまま、猛スピードで廊下を駆け抜けて迫ってきたのだという。 Uはそこで気を失ったそうである。 翌日、目が覚めた後、Uはすぐに引っ越ししたのだという。 |
| 第五十一話 青いヤッケの男 |
|
Mさんの話である。 夜中、Mさんは犬の散歩に出たそうである。普段は昼間に散歩するのだが、その日は用事で散歩することができず、夜になっても犬があまりに出たがるので仕方なく深夜の散歩になってしまったという。 夜中とはいえ、コースはいつも通り。その途中に小さな公園があるという。 ところが公園に入ると、犬の様子が変であることに気がついた。いつもなら公園ではしゃぐ犬が、身を地面につけ、「ほふく」の様に歩いていたのだという。 どうしたんだろう、と思いながら、ふと見ると、青いヤッケを着た男がぶらんこを漕いでいるのが見えた。 どきっとしたものの、「なんでこんな夜中に」「雨でもないのにヤッケなんて、浮浪者だろうか、、、」と思いつつ、なるべくその男を見ないように足早に通りすぎようとしたそうである。 ところが、犬がぐいと引っぱるので、Mさんは思わず振り返ってしまったらしい。 青いヤッケ男の姿はなかったそうである。 |
| 第五十二話 ヒダルガミ |
|
Nの登山仲間のWさんの話である。高校生の時、叔父とともに岐阜県のO山に登った時のことだそうである。 その日Wさんは、快調に登山を楽しんでいたという。 ところが、夕方になり山小屋までもう少しという頃になって、ふいに背中の辺りが重く感じだした。そのうち、足取りも重くなってきて、足を一歩出すのもままならぬようになってきたという。 とうとう、Wさんは昏倒してしまったそうである。 Wさんが気付くと、叔父さんがWさんの口に何かを押し込んでいるところだった。思わず吐き出すと、ご飯粒だったそうである。 叔父さんの話では、山にはヒダルガミというのが居て、登山者を歩けなくしてしまうそうである。その時には、飯ひと粒でもいいから口にすれば、元に戻るのだということであった。 実際、Wさんの体調は、嘘のように回復していたそうである。 それ以来、Wさんはご飯を少し残すようにして、ヒダルガミに備えているのだそうである。 |
| 第五十三話 コンビニ |
|
コンビニと言うのは、24時間煌々と電気がついていて明るい割りには、幽霊話が多いようである。もしかすると、逆に賑やかさに引かれて集まってくるのかも知れないが。 S子さんもコンビニのバイトをした時に、奇妙な体験をしたという。 風も無いのに、入り口のスゥイングドアが独りでに開いたりすることが、よくあったそうである。 レジで後をむいている時に、ドアが開いてチャイムが鳴り、目の隅でお客が入ってくるのを捉えているのに、振り返ると誰もいないということもあったという。 ある深夜、下段の商品の在庫のチェックをしていると、商品越しに、棚の向こう側に立っているジーンズを履いた男の足が見えた。いつの間に来たのだろう、と思って立ち上がって見ると、誰もいなかったそうである。 |
| 第五十四話 顔 |
|
代々木公園に程近いY社では、しばしば奇妙な現象が起こっていた。 自動ドアが独りでに開閉するのは日常茶飯事だし、よぎる人影を見かけることも少なくなかった。 ある夜、地下の試写室で仮眠をとっていたN氏が、悲鳴をあげて上がってきた。 一階で残業をしていた社員たちが、何事かとN氏に問いただすした。 N氏はひどく怯えた様子で、寝返りをうったところ、目の前に顔があったのだと言う。 「どんな、顔?」「男か、女か」という社員の質問に、 「あまりに近すぎて、わからなかった」と答えたそうである。 ちなみに、私も、深夜3時頃、独りで地下で残業しているときに、もの凄い男の悲鳴を聞いた事がある。 |
| 第五十五話 覗き |
|
J子さんが、仕事で千葉のホテルに泊まったときのこと。 シャワーを浴びて出ると、数センチ程開いたカーテンの隙間から、室内を覗き込む男のと目が合った。 J子さんはびっくりして、フロントに電話をしようと受話器を手にとった。その時、自分が8階に泊まっているのを思い出したと言う。 振り返ると、もう男の姿はなかった。 ガラスに写った自分の姿かとも思い、確認してみたが、男を見た場所からでは自分の姿を見ることができなかった。 翌朝、明るくなって調べて見たところ、10センチほどの張りだしはあるものの、どうやってもそこまで来る方法は考えられなかったという。 |
| 第五十六話 何を見たの? |
|
F美さんが1才になった子供を連れて里帰りしたときのこと。 夕涼みがてら子供を抱いて、近くの公園に行ったそうである。すると、赤ん坊が火がついたように泣き出したのだと言う。 顔をしっかりF美さんに押し付けて、おしっこともお乳とも違う、初めて見せるような泣き方だったそうである。 どうやら、そこにある大きな木の方を見て、怯えているようだった。 F美さんは、早々にその公園を立ち去ったが、公園を離れると子供は泣き止んでしまったと言う。 子供が何を見たのかわからないが、F美さんが高校生の時、その木で自殺した人がいたそうである。 |
| 第五十七話 パーティ |
|
F美さんが知人に聞いた話だという。 その知人の勤める会社で、顧客を招いて、あるパーティが行われた。 その顧客の中に、知人の同僚のOさんが好意を抱いている女性が来ていたそうである。 パーティがかなり進行した頃、Oさんは会場の端に独りでいる彼女を見つけたのだという。彼はチャンスだと思い、その女性に近づいていったそうだ。 近づくにつれ、彼女の様子が少しおかしいことに気が付いた。酔っているのだろうか、独りでいるくせに、やけに楽しげである。しかも、独り言まで言っている。 一瞬、Oさんは躊躇してしまったそうである。立ち止まって見ていると、その女性は何もない空間におじぎをするように軽く頭を下げたそうである。 Oさんがびっくりしていると、彼女の方がOさんに気付き、近寄ってきたそうである。 挨拶をかわし、彼女は今日のパーティの盛況ぶりなどを褒めてくれたが、彼はほとんど上の空で返事をしていたと言う。 会話が止まって、なんとなく白々しい雰囲気になった時、彼女が切り出したそうである。 「さきほどの方は、どなたですか?」 「はい?」 「Oさんがいらっしゃる前に、話していた人です。お名前を聞きそびれてしまって」 Oさんは、大勢出入りしているものでわからない、と、ごまかしたそうである。 Oさんがその女性からなんとか聞き出した特徴から、2年前に病気で亡くなった経理のNさんではないかというのが、社内でのもっぱらの噂であるという。 |
| 第五十八話 水溜まり |
|
Sから聞いた話。小学生の時の話だという。 ある雨の日の下校途中、道に出来た水溜まりから、ぬっと手が出て来たという。 その時一緒にいた友達2人も見たそうである。 あわてて逃げ出して、後でみんなでもう一度見に行ったが、何もなかったそうである。 |
| 第五十九話 古本 |
|
この話は他の話と違って、話の主人公に仮名を用いている。その理由は読んでいただければわかるはずである。 なお、もしこの仮名と同姓同名の方がいらしたならご容赦いただきたい。 これはK氏が、知人のTさんから聞いたもので、その人の彼女が山村由子さんだった。 Tさんと山村由子さんが同棲していた時の話である。 ある夜。夕食も終え、山村由子さんはソファに座り、仕事帰りに古本屋で買ってきた文庫本を読んでいたという。由子さんは本が好きだったが、書籍代を浮かすために古本屋を度々利用していたそうだ。 一方、Tさんは寝転んでテレビを観ていた。その時、突然由子さんが悲鳴を上げたのだそうである。 Tさんが驚いて振り返ると、由子さんは本を投げ出し、震えていた。「何があった」と問う彼に、由子さんは答えることなく泣き出してしまったと言う。 Tさんは、由子さんが投げ出した本を拾い、ぱらぱらとめくったそうである。すると、あるページが目に飛び込んできて、Tさんは呆然とした。 そこには黒黒と筆で書かれた『怨 山村由子』の文字があったのだという。 だが、よく見ると、違っていたのである。そこには『由子』ではなく『申子』と書かれていたのである。 由子さんにそう言ったものの、すでにパニックに陥っていて、なすすべが無かったという。 「それはそうだろうなあ。一字違いだろうが、気持ち悪いよ。ノブコって読むのかなあ。それに、その文字がね、ゆっくり念を込めて書いたみたいに、細かく震えてたんだよね」 Tさんは、すぐさま本を捨てたそうである。 由子さんは一週間程後遺症を引きずっていたが、やがて元に戻ったそうである。しかし、それ以来、Tさんが知る限り、由子さんが古本を買ってくることは無かったそうである。 Tさんと由子さんはそのあと2年ほどで別れてしまったので、その後の彼女のことは知らないそうである。 |
| 第六十話 峠の少女 |
|
Gさんが、深夜1時頃、埼玉から東京へ抜ける道を車で走っていた時のことだそうである。 その道は東京の西の方にあり、曲がりくねった峠道であった。 車が丁度峠にさしかかった頃、ふいに目の前に左から飛び出してきたものが、車のライトで白く浮き上がったそうである。 Gさんは、あわてて急ブレーキを踏んだ。 車はスピンして、対向車線で止まったそうである。幸い対向車がいなかったことと、後の車との車間距離があったことで大事故は免れたという。 後から来た車の青年が心配して出て来てくれて、一緒に車や周辺を調べてみたが、何かにぶつけた様子はなかったそうである。 Gさんは言う。「間違いない。あれは女の子だった」 その子は小学校の3、4年生くらいで、赤っぽいTシャツに短パンをはいていたと言う。 |
|
|
|
|