| 千と千尋の神隠し | 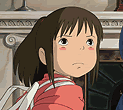 |
オフィシャル・サイト 「監督解説」も「作品解説」も少し説明しすぎでは? 考える余地がたくさんある映画だが、そうした種々の点について非常に詳しく解説されてしまっている。でも、監督があまりに饒舌すぎると、映画自体から直接楽しむという楽しみが減弱してしまうような・・・。 |
| テーマをどう描くか 正直言って私は宮崎駿アニメが大嫌いである。その映像の素晴らしさは評価するが、テーマ性という意味で、過去の宮崎作品は受け入れられない。これがテーマですみたいな感じが、偽善的であり、非常に嫌味である。 私にとって宮崎駿といえば、「風と谷のナウシカ」の原作コミックである。クアトロやクシャナの苦悩に満ちた人間描写、一見悪役だがその裏に広がる深い苦悩とリアルな人物設定。結局、「風と谷のナウシカ」でスタートとした宮崎駿は、その後、子供たちにもわかりやさいキャラクターということで、非常に単純明快な人物ばかりを生み出してきた。そして、明確なテーマ性。そう言うと響きは良いが、私には偽善的プロパガンダにしか見えなかった。 『千と千尋』はテーマがはっきりしないという批判があるが、私はここが非常にいいと思う。過去の作品があまりにもテーマを打ち出しすぎている。すなわち、テーマが明らか過ぎて考える余地見たいのが残されていないわけだ。『もののけ姫』くらいなると、多少考える余地を残しているけども、「自然の大切さ」のテーマは小学生にも伝わるであろう。 『千と千尋』では、「これがテーマです」みたいな一本柱のテーマが、はっきりと打ち出されていない(過去の宮崎作品ほどはっきりとは)。 「お金より大切なものって何だろう?」 「人は見かけで判断しちゃいけないね」 「お父さんとお母さんが急ににいなくなったらどうする?」 「助けて欲しいときに、誰も助けてくれなかったらどうしよう」 「青い空ってきれいだね」 「カオナシって、何だか寂しそう」 |
| 『千と千尋』を見終わった後、子供と一緒にいろいろなことを考えることができる、いろいろなエピソードが詰まっている。さりげないテーマが、さりげなくてくさんちりばめられているのが、『千と千尋』である。そういうさりげないエピソードが、ボディ・ブローのように効いてくるというか、少しずつ心に染みてくる。 過去の宮崎作品に比べて力みが抜けているところが凄く良いと思う。歳をとると勢いがなくなってダメになる映画監督が多い中、良い意味で非常に力が抜けて、宮崎駿は老成したという感じだ。 『千と千尋』を感動大作のように宣伝するテレビCMは、莫大な興行収入と引き換えに、多くの観客に誤った先入観と失望 |
|
| を与えた。『千と千尋』は「心に染みるいい話」という感じであって、宮崎駿も観客を感動させようと思ってこの作品は作っていないだろう。 我々観客は、テレビCMや映画の予告編が、映画の本質と何ら関係がないということを、そろそろ勉強してもいいように思える。 |
| 物語断片の集合体 『千と千尋』は、いろいろな物語の断片の集合体である。オクサレ様は『風の谷のナウシカ』のオームであったり、湯屋に集まる神々は『隣のトトロ』に出てきそうなキャラであったりね実際ススワタリが再登場したり、ハクとの滑空シーンは『天空の城ラピュタ』であったり、他に列挙していくとキリがない。 そうした宮崎作品の断片という他に、多くの民話や寓話からアイデアを得ている。 少女が不思議の世界に迷い込むというくだりは「不思議の国のアリス」、あるいは「雀のお宿」や「鼠の御殿」である。 千尋の両親が豚になるというエピソードは、ディズニーの『ピノキオ』から来ているのだろう。『ピノキオ』の遊園地で遊び過ぎた子供たちが、ロバにされて売り飛ばされるというエピソードである。 オクサレ様が実は格の高い河の神様で、それを助けた千尋が不思議な力を持つ泥団子をもらうというエピソード。人助けをして予期せぬ宝物をもらうというのは、典型的な日本の民話のプロットである。 過去の宮崎作品を含む、いろいろな映画のオマージュ。あるいは、古今東西の民話や寓話、童話のエッセンスが詰め込まれている。このストーリーメイキングの方法というのは、実はスターウォーズと全く同じである。スターウォーズは民話ではなく、神話に題材を得ているが、黒澤映画を中心とした種々の映画作品、神話の断片から構成されている。スター・ウォーズは「現代の神話」を目指しているが、『千と千尋』は「現代の民話」を目指していたのかもしれない。宮崎の表現を借りれば「10代の少女に必要な物語」が、それと同様のことを意味しているのだろう。 現代日本を舞台にする意味 |
|
| なぜ、『隣のトトロ』は現代の日本を舞台にせずに、昔の日本を舞台にしたのか。そこが非常に気に食わなかった。それはささいな問題に思えるかもしれないが、映画の根幹にかかわる重要な問題である。 なぜなら、昔を舞台にすることで、「昔の日本はこんなに自然が豊かだったんだよ」というテーマ、裏返せば「今の日本には自然もないし、トトロなんかいないんだよ」ということになってしまうからだ。結局、『隣のトトロ』は、昔懐かしい風景(例えば三輪トラックなど)を映像化したいという悪しきレトロ主義が支配する、イヤミな映画になってしまった。 『隣のトトロ』も『千と千尋』も、都会の少女が田舎に引っ越すシーンから始まる。『千と千尋』のファースト・シーンを、『隣のトトロ』につけても全くいいはずだ。すなわち、現代日本の都会の少女が、田舎に来て、自然の豊かさに触れ合い、トトロやミコバスといった不思議な神々、精霊(?)に出会うという話でも全くよかったはずなのに、宮崎は映画の舞台をかなり昔の日本に設定してしまった。 私の批判が宮崎に届いたわけではないだろうが、私が想定したベストのオープニングを持った作品『千と千尋』を、ようやく宮崎は作ってくれた。 『隣のトトロ』などを見ると、その視点は「現実逃避」の様にも見えるが、ようやく現実を見据え、現実にいそうな普通の少女を主人公にした。『千と千尋』はファンタジー世界を描きながら、現実を直面させる映画である。カオナシがコミュニケーション不全に陥った現代人を現していることも、それを裏付けよう。 実は「風の谷のナウシカ」(原作コミック)は、極めて現実的(リアル)な物語あったわけだが、宮崎は老成しつつ原点に回帰したのかという安堵の感もある。 ハクが多重人格的に描かれていることに対し、違和感を抱いた人もいるだろうが、これこそがリアルな人物描写というものだ。いつも同じ表情しかみせない、ステレオタイプの紋切り型キャラクター(リアリティを持たない、映画の中にしか存在しない人物像)を見慣れてしまっている、我々観客の悲しさであるし、宮崎がいままでわかりやすい単純なキャラクター・メイキングをしてきたことの弊害でもある。 心ややさい人間は、いつでも優しい表情や態度をとりつづけるのか。現実の世界ではそんなことはありえないだろう。疲れたり悩み事を抱えていれば、誰だってイライラしたり、怒りっぽくなるだろう。ハクがセンに対して冷たい態度をとるシーン。このシーンが入ることによって、人物描写のリアリティが格段に増しているにもかかわらず、それを逆に不自然感じてしまう人は、非常に寂しいと思う。人間、喜怒哀楽があって当たり前なわけでしょ。やさしいときもあるし、怒るときもある。そんな当たり前のことを、実は我々は結構忘れてしまっている。そういう現代日本に埋もれてしまったものに対する再発見の視点が、『千と千尋』にはちりばめられていて、非常におもしろいのである。 |
|
不思議体験に入っていく前に、千尋は一つのカルチャーショックを受ける。木々がおい茂る森の中の祠と石像。大きな好奇心とともに、体験したことのないものに対する畏怖、これは偉大なる自然、あるいは自然とともにある八百万神に対する畏怖であろうか。旧友の別れに悲嘆する少女。その不安定な状態の少女が、未体験の生の自然と接することで、不思議な神々の世界に入っていくというくだりが、妙な説得力を持っている。 |